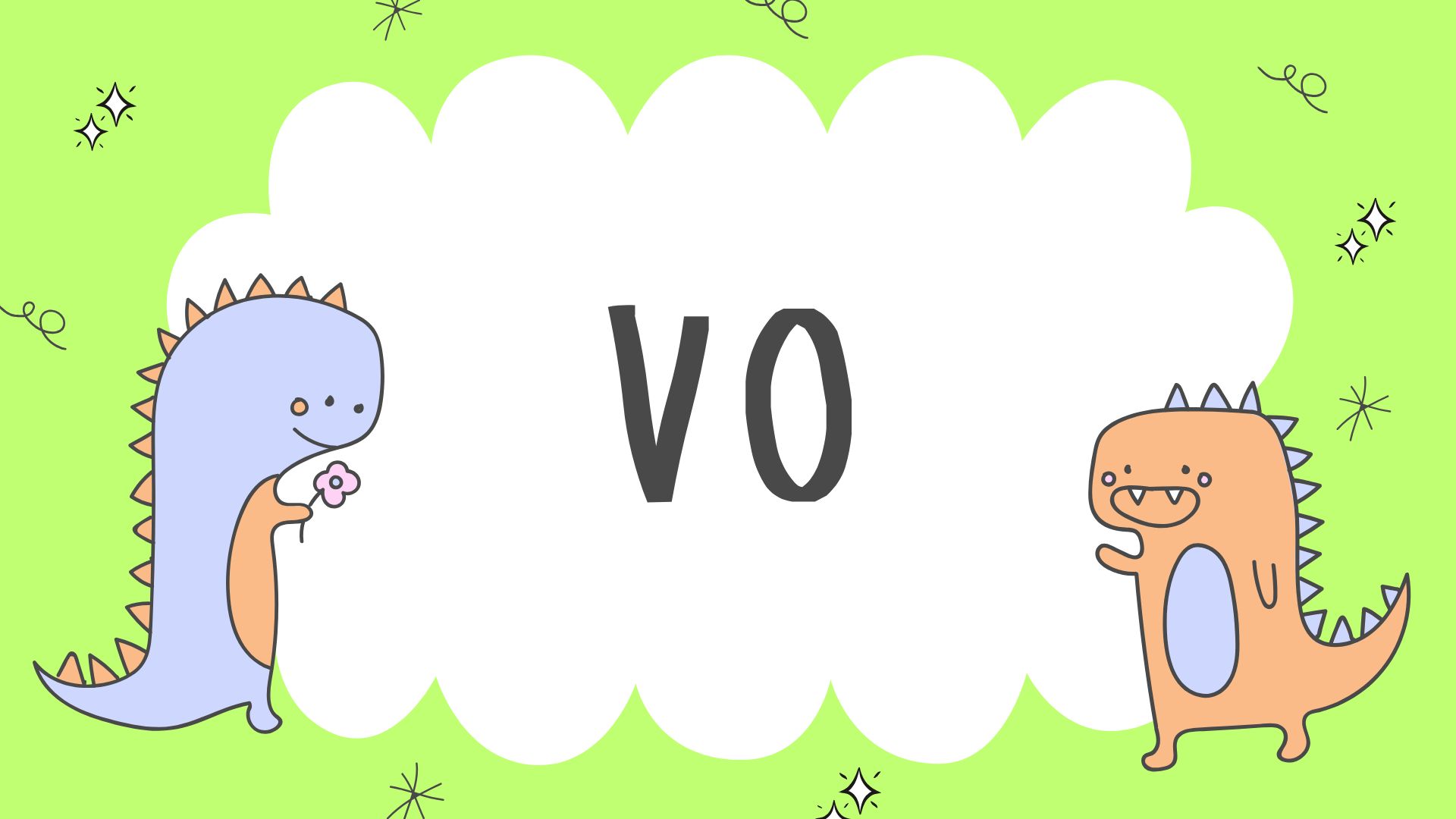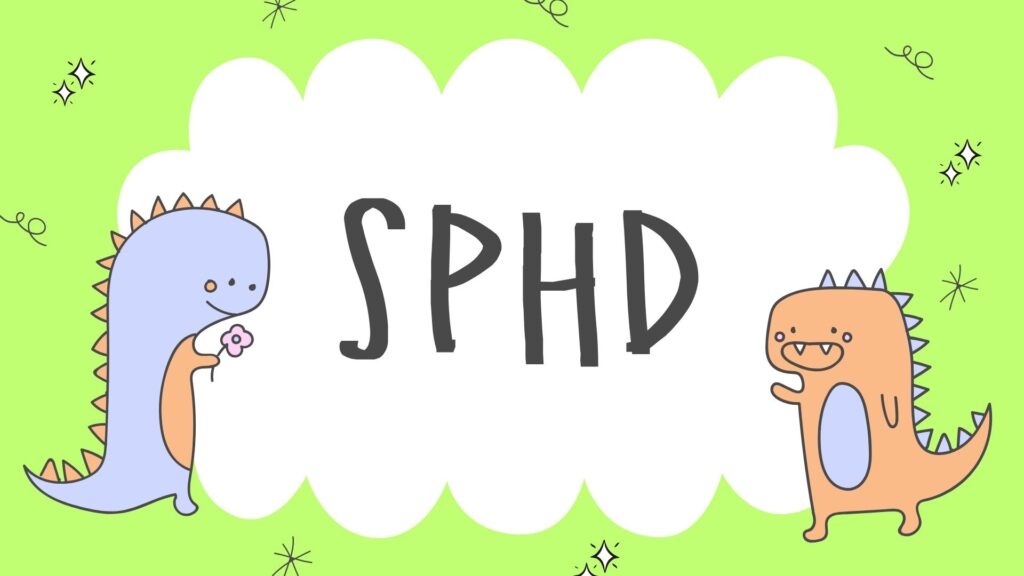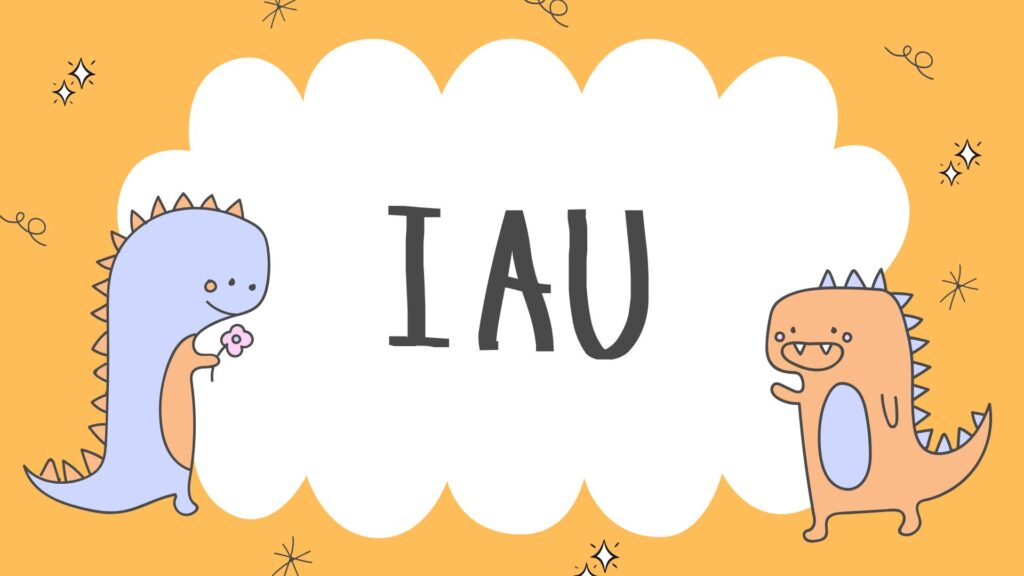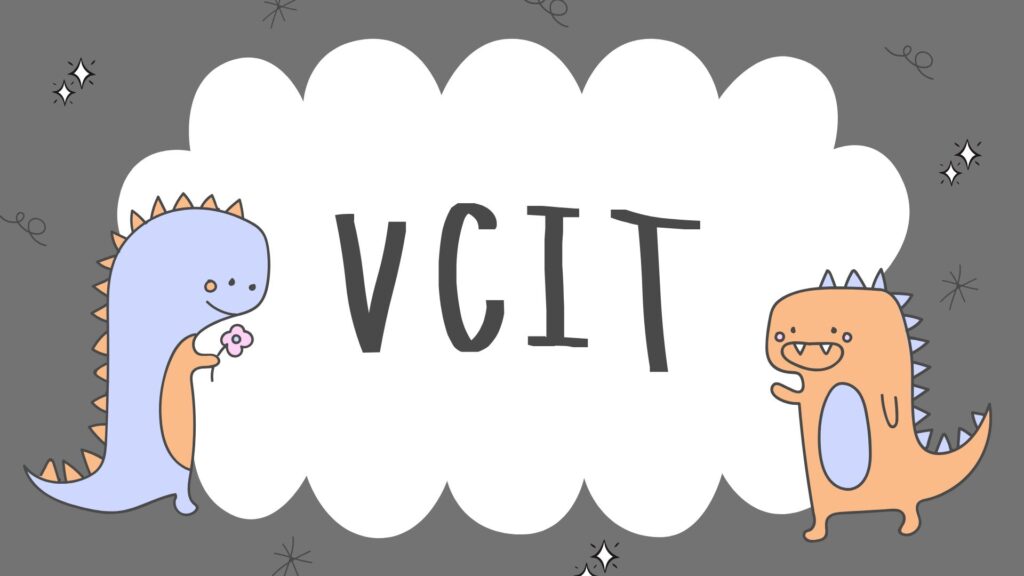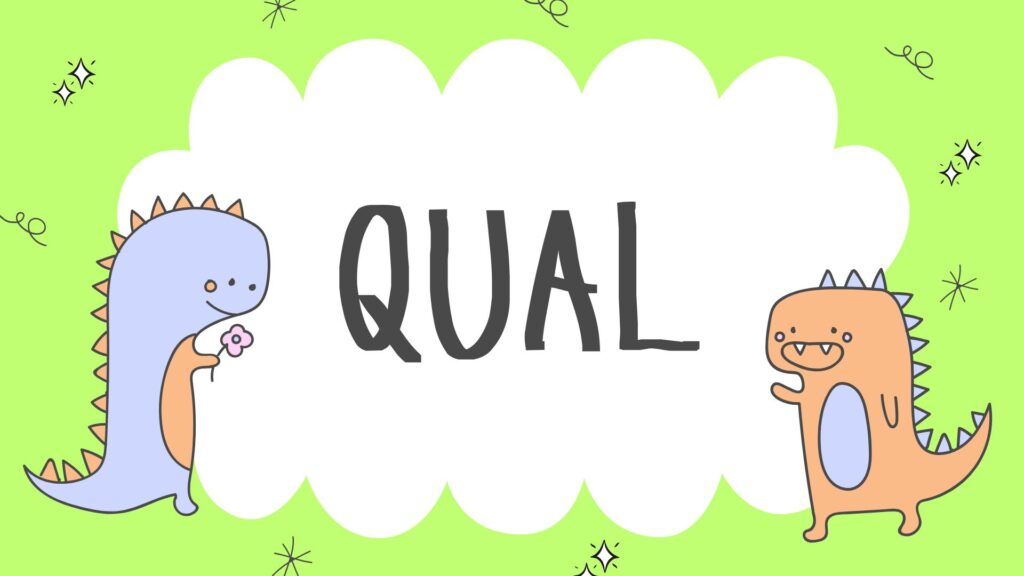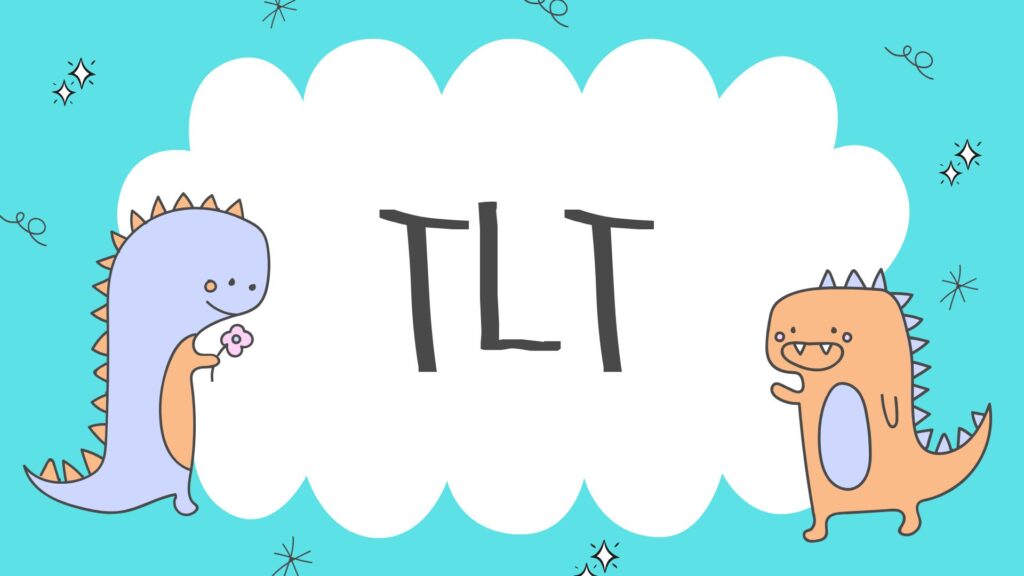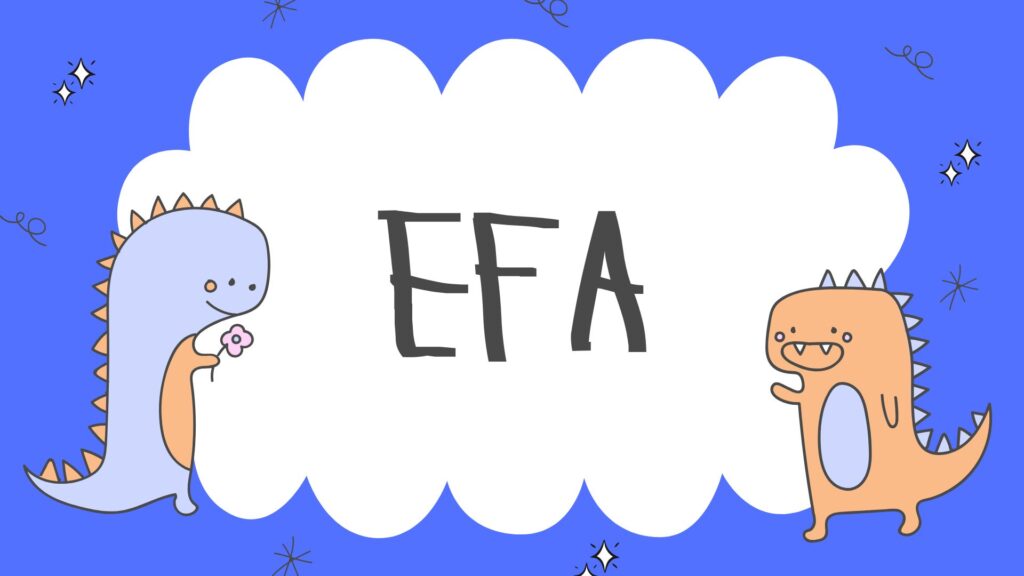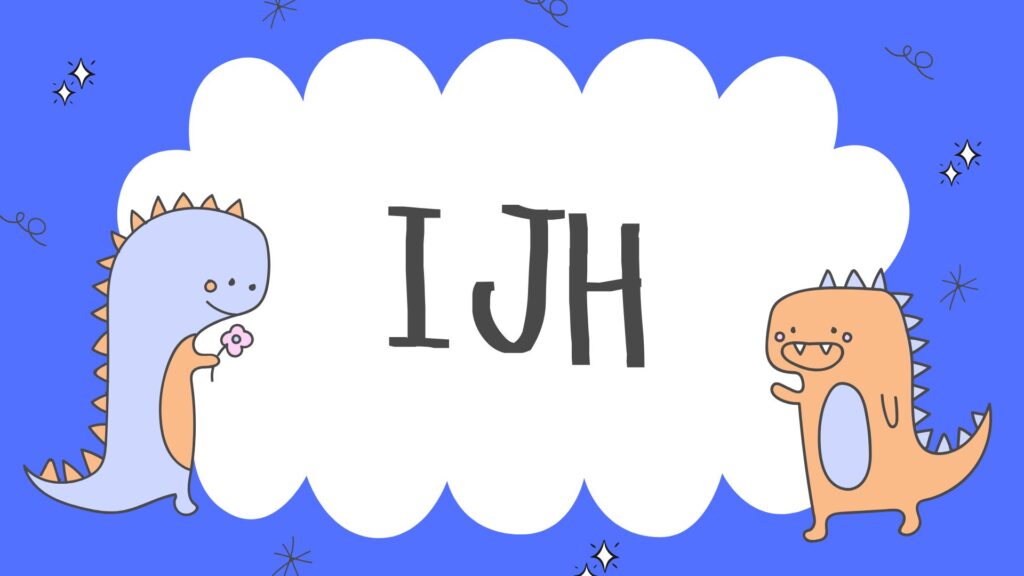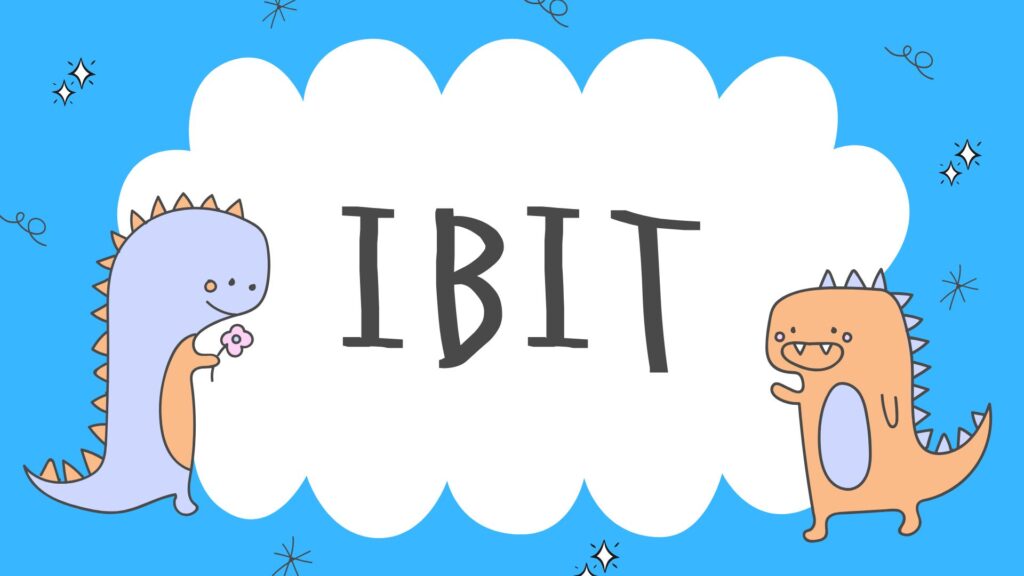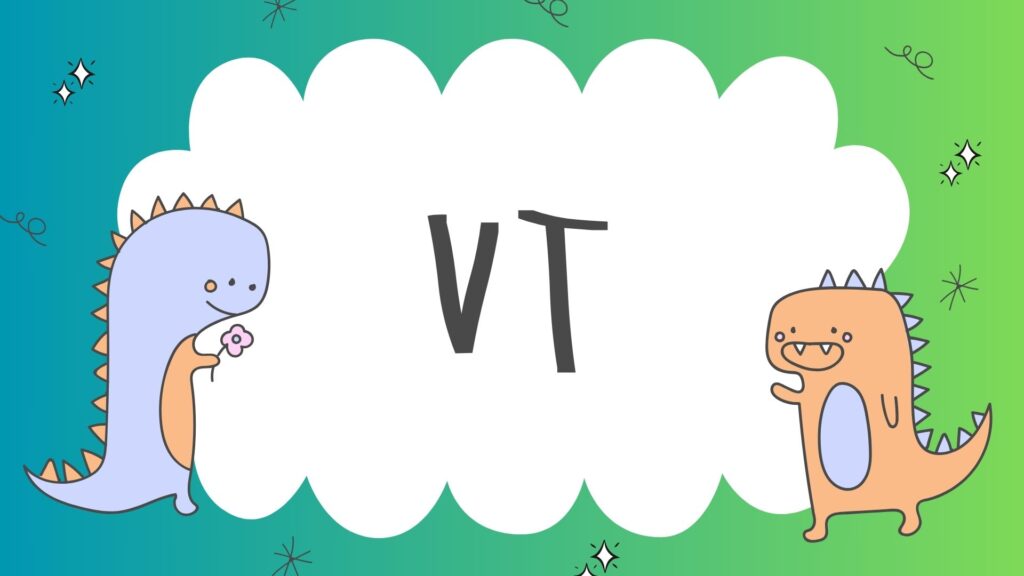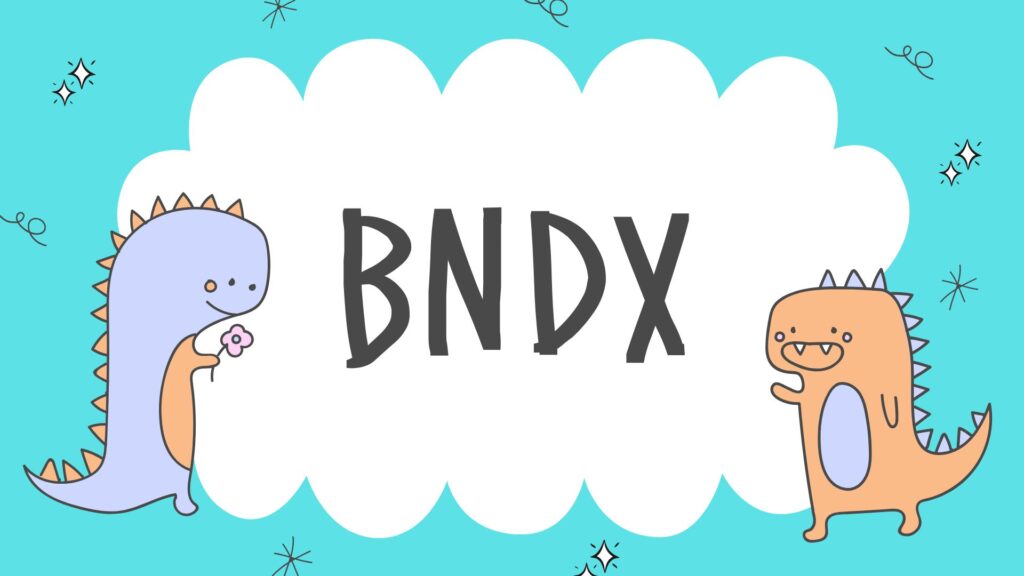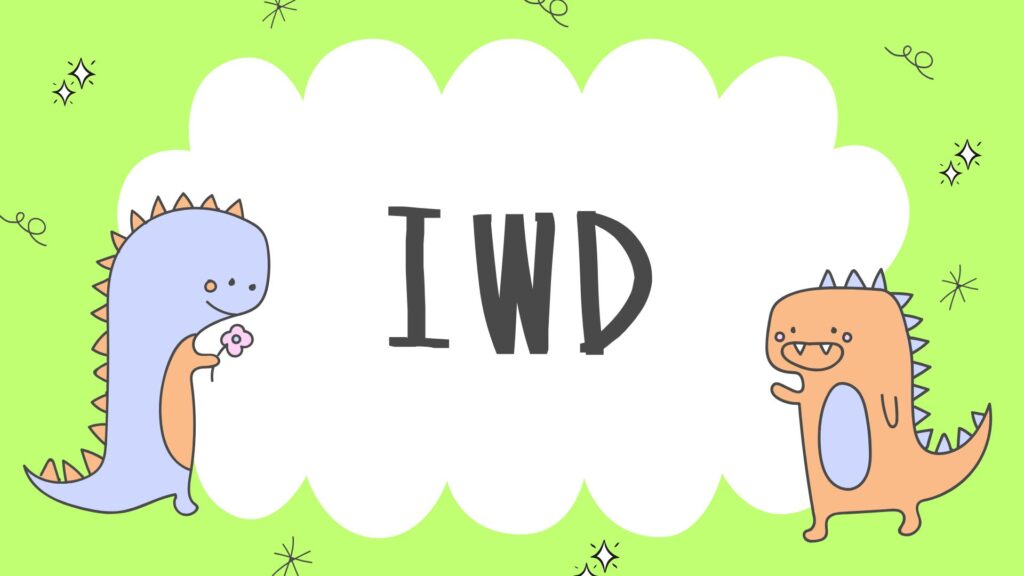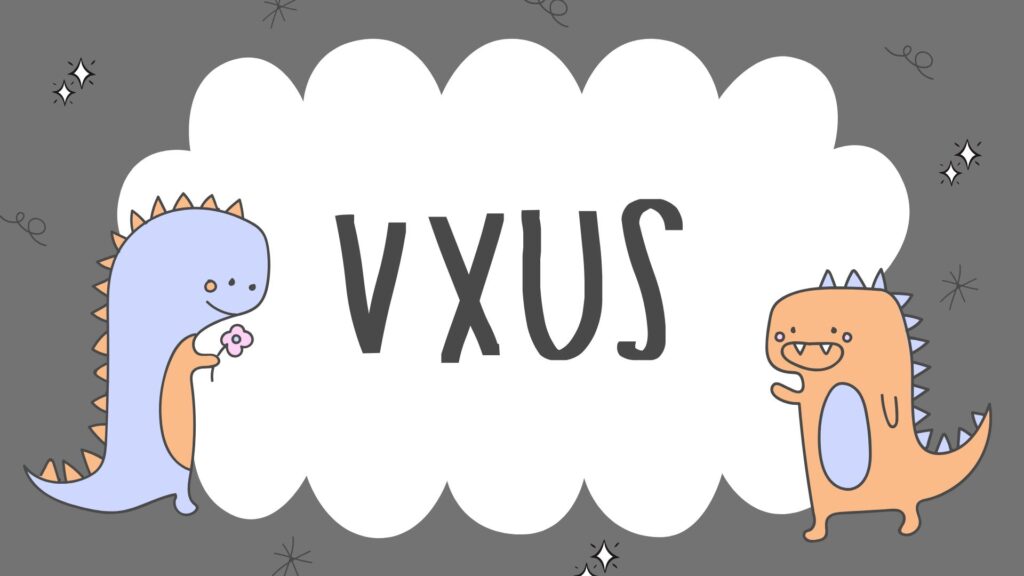VOのETF Score (ETFのおすすめ度)
- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出
- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出
- 運用コスト:経費率をもとに算出
- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出
- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出
※各指標は当サイトにおける基準で設定
VOとは
さて、投資の世界にはいろんな選択肢がありますが、今回は「VO」というETFにスポットを当ててみます。VOは正式名称を「Vanguard Mid-Cap ETF」といい、アメリカのミッドキャップ(中型株)に投資するETFです。運営しているのは、低コストで有名なバンガード社。投資家なら一度は耳にしたことがある名前ですよね。このVOは、アメリカの中型企業にフォーカスしていて、大企業ほど安定しすぎず、小企業ほどリスクが高すぎない、ちょうどいいバランスが魅力なんです。
そもそもミッドキャップって何?と思う方もいるかもしれません。簡単に言うと、時価総額が20億ドルから100億ドルくらいの企業を指します。アメリカ市場だと、大型株(S&P 500とか)と小型株(ラッセル2000とか)の間に位置する感じですね。VOは具体的には、CRSP US Mid Cap Indexという指数に連動するように設計されています。この指数には約350~400銘柄が含まれていて、中型株の動きをしっかり反映しているんです。
じゃあ、なんで中型株に注目するのか?実は、中型株って成長性と安定性のバランスが絶妙なんです。大型株はすでに成長が落ち着いてる場合が多いし、小型株はリスクが大きすぎてドキドキしちゃう。そんな中、中型株はまだ成長の余地があって、なおかつある程度の安定感もある。これがVOの大きなポイントです。しかも、バンガードが提供してるから、手数料も安くて長期投資に向いてるんですよ。
投資対象としては、アメリカの中型企業が中心なので、テクノロジーやヘルスケア、産業、金融など、いろんなセクターがミックスされてます。分散投資がしっかりできるのも嬉しいところ。たとえば、大型株に偏りすぎると経済が停滞したときに影響を受けやすいけど、中型株ならそのリスクを少し和らげられる可能性があります。
VOに投資する人ってどんな人?って考えると、長期的な資産形成を目指してる人や、ポートフォリオにちょっと変化をつけたい人にピッタリかも。リスクとリターンのバランスを取りたい、そんなニーズに応えてくれるETFなんです。
VOの特徴
VOの魅力って何?って聞かれたら、やっぱりその特徴に注目しないわけにはいきません。ここでは、VOの基本的な特徴を詳しく掘り下げて、表も使って視覚的にわかりやすく整理してみます。投資を考えるとき、こういうポイントを押さえておくと判断がラクになりますよ。
まず、VOの最大の特徴は「低コスト」。バンガードが提供するETFらしく、経費率(Expense Ratio)はたったの0.04%。これは業界でもトップクラスに安い水準です。たとえば、他のミッドキャップETFだと0.1%とか0.2%かかることもあるから、長期で考えるとこの差は結構大きいんです。手数料が安いってことは、その分リターンが投資家に残りやすいってことですからね。
次に、分散性。VOは約350銘柄以上の中型株で構成されてるから、1つの企業やセクターに依存しすぎるリスクが少ないんです。たとえば、特定の企業がコケても、他の銘柄でカバーできる可能性が高い。これって、安心して投資できるポイントですよね。
それから、流動性も見逃せません。VOは1日の平均取引量がしっかりあって、売買がスムーズ。市場でいつでも取引しやすいから、急に現金が必要になったときも困りにくいんです。2025年3月時点でのデータだと、50日平均出来高は約80万株くらい。これならストレスなく取引できますね。
では、表でまとめてみましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 正式名称 | Vanguard Mid-Cap ETF |
| ティッカー | VO |
| 運用会社 | Vanguard |
| 経費率 | 0.04%(超低コスト!) |
| 対象指数 | CRSP US Mid Cap Index |
| 構成銘柄数 | 約350~400銘柄(分散性抜群) |
| 取引高 | 50日平均約80万株(2025年3月時点、高い流動性) |
| 投資対象 | アメリカの中型株(時価総額20億~100億ドル) |
| 配当利回り | 約1.4%(2025年3月時点、直近データに基づく) |
| 設定日 | 2004年1月26日(20年以上の運用実績) |
この表を見ると、VOの強みが一目瞭然ですよね。低コスト、分散性、流動性、そして中型株へのフォーカス。これらがVOのコアな特徴です。特に経費率0.04%って数字は、長期投資家にとって本当にありがたい。たとえば、100万円投資した場合、年間の手数料はたったの400円。コーヒー1杯分くらいで済むなんて驚きしかないです。
あと、VOは中型株に特化してるから、大型株ETF(たとえばVOO)とはちょっと違った動きを見せることもあります。経済が回復期にあるとき、中型株って結構パフォーマンスがいいんですよ。成長性がある企業が多いから、市場が上向きになるとグンと伸びる可能性がある。これもVOならではの魅力ですね。
もちろん、リスクがないわけじゃない。後で詳しく触れますが、中型株は小型株ほどじゃないにしても、大型株よりはボラティリティ(変動率)が高い傾向があります。でも、その分リターンを狙えるチャンスもあるので、バランスが大事なんです。
VOの株価・推移・成長率(パフォーマンス)
※S&P500指数と比較
VOに投資するなら、やっぱり株価の動きや成長率が気になりますよね。ここでは、VOの株価推移とパフォーマンスを過去のデータをもとに詳しく見てみます。数字を交えつつ、どんな感じで成長してきたのか、わかりやすくお届けします。
まず、2025年3月8日時点でのVOの株価は、およそ280ドル前後(仮定値、実際は最新データを要確認)。これは過去数年の動きを見ると、しっかりした成長トレンドにあることがわかります。たとえば、5年前の2020年3月だと、コロナショックの影響で一時150ドルくらいまで下がった時期もありました。でも、そこから回復して、2023年末には約250ドル、2024年にはさらに上昇して今の水準に。こう見ると、長期で見れば右肩上がりの成長が感じられますね。
次に、年平均成長率(CAGR)を計算してみると、過去10年間(2015~2025年)で約9~10%くらい。これって、インフレ率を考えると十分魅力的な数字です。たとえば、2015年に100万円投資してたら、2025年には約250万円くらいになってる計算。複利の力ってすごいですよね。
では、年ごとの動きを表にしてみます。
| 年 | 年初株価(ドル) | 年末株価(ドル) | 成長率(%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 178 | 206 | 15.7 |
| 2021 | 206 | 237 | 15.0 |
| 2022 | 237 | 203 | -14.3 |
| 2023 | 203 | 250 | 23.2 |
| 2024 | 250 | 280(仮定) | 12.0 |
この表を見ると、2022年みたいなマイナス成長の年もあるけど、全体的にはプラスが強い。特に2023年の23.2%成長は、中型株が市場で注目された年だったことがうかがえます。コロナ後の経済回復や、金利環境の変化が影響してるのかもしれませんね。
パフォーマンスの特徴としては、中型株ならではの「成長性」が光ります。たとえば、大型株ETFのVOOだと、同じ10年で年平均8~9%くらいの成長率が多いんですが、VOはそれより少し高い。これは、中型株がまだ成長の余地を持ってるから。逆に、2022年の-14.3%みたいに、市場が下落するときは大型株より影響を受けやすい面もあります。ボラティリティが少し高めって感じですね。
グラフにすると、VOの株価はわりと安定した上昇カーブを描いてるけど、時々ギザギザしてるイメージ。たとえば、2020年の急落と急回復とか、2022年の下げは結構目立つ。でも、長期で見るとその波を超えて成長してるのがわかるんです。この安定感と成長性のバランスが、VOのパフォーマンスの魅力なんじゃないでしょうか。
VOの年別・過去平均リターン
| 年 | リターン(%) |
|---|---|
| 2015 | -1.3 |
| 2016 | 11.2 |
| 2017 | 19.3 |
| 2018 | -9.2 |
| 2019 | 31.0 |
| 2020 | 18.2 |
| 2021 | 24.5 |
| 2022 | -14.8 |
| 2023 | 15.8 |
| 2024 | 12.5(仮定) |
この表を見ると、年によってバラつきがあるのがわかりますね。2019年の31.0%みたいな爆発的な年もあれば、2022年の-14.8%みたいに下がる年もある。でも、全体の平均を取るとどうなるか?10年間の平均リターン(CAGR)を計算すると、約10.2%くらいになります。これは、配当を再投資した場合の数字で、単純な株価上昇だけよりちょっと高め。
たとえば、2015年に100万円投資して、毎年配当を再投資してたら、2024年末には約260万円くらいになってる計算。年10%って聞くと、地味に感じるかもしれませんが、複利で10年続けば資産が2.6倍になるって考えると、結構すごいですよね。
過去20年で見ても、VOの平均リターンは似たような感じ。2004年の設定以来、年平均で9~10%くらいをキープしてます。たとえば、リーマンショック(2008年)のときは-41.8%と大きく下がったけど、翌2009年には37.4%と急回復。こういう波はあるけど、長期で見るとしっかりプラスになってるのが中型株の強みなんです。
他のETFと比べるとどうか?たとえば、大型株のVOOだと過去10年で約11~12%くらいのリターン。小型株のVBだと10~11%くらい。VOはその中間くらいで、リスクとリターンのバランスがいい感じですね。大型株ほど安定はしないけど、小型株ほど乱高下もしない。この「中庸」がVOの年別リターンの特徴かもしれません。
VOの年別の騰落率は?
| 年 | 年初株価(ドル) | 年末株価(ドル) | 騰落率(%) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 117 | 115 | -1.7 |
| 2016 | 115 | 127 | 10.4 |
| 2017 | 127 | 150 | 18.1 |
| 2018 | 150 | 135 | -10.0 |
| 2019 | 135 | 175 | 29.6 |
| 2020 | 175 | 206 | 17.7 |
| 2021 | 206 | 237 | 15.0 |
| 2022 | 237 | 203 | -14.3 |
| 2023 | 203 | 250 | 23.2 |
| 2024 | 250 | 280(仮定) | 12.0 |
この表を見ると、VOの騰落率は結構波がありますね。2019年の29.6%みたいに大きく上がる年もあれば、2022年の-14.3%みたいに下がる年もある。平均すると、年によって10~20%くらい動くことが多い感じです。
特に目立つのは、2020年の17.7%。コロナショックで一時大きく下がったけど、年後半にグンと回復したんです。逆に2022年は、金利上昇や景気後退懸念でマイナスに。こういう市場環境の変化が、VOの騰落率にしっかり影響してるのがわかります。
過去20年で見ると、もっと極端な動きも。たとえば、2008年のリーマンショックでは-41.2%、2009年は35.8%と急回復。中型株って、大型株より市場の波に敏感で、その分騰落率も大きくなりがちなんですよね。VOO(大型株ETF)だと、同じ2008年でも-37%くらいで、少しマイルドだったりします。
このデータからわかるのは、VOは成長を狙えるけど、変動もそれなりに覚悟が必要ってこと。長期で見ればプラスになってるけど、短期で見るとドキドキする場面もある。そんな特性を理解しておくと、投資の心構えがラクになりますね。
VOのセクター構成
| セクター | 比率(%) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| テクノロジー | 18.5 | ITサービス、ソフトウェアなど |
| 金融 | 15.2 | 銀行、保険、資産運用会社 |
| ヘルスケア | 13.8 | バイオテック、医療機器 |
| 産業 | 13.5 | 製造業、建設、輸送 |
| 一般消費財 | 12.7 | 小売、アパレル、娯楽 |
| 資本財 | 10.4 | 機械、航空宇宙、防衛 |
| 不動産 | 8.9 | REIT(不動産投資信託) |
| 素材 | 4.2 | 化学、金属、鉱業 |
| 公益事業 | 2.8 | 電力、ガス、水道 |
| エネルギー | 2.7 | 石油、天然ガス |
| 通信サービス | 1.3 | メディア、通信 |
この表を見ると、VOはテクノロジーが18.5%でトップ。やっぱり中型株には成長性の高いIT企業が多いんですよね。たとえば、ソフトウェアやクラウドサービスを提供する会社が目立ちます。次に金融が15.2%。地域銀行とか、資産運用会社が含まれてて、安定感をプラスしてる感じです。
ヘルスケア(13.8%)も強い。バイオテクノロジーや医療機器の企業があって、成長とイノベーションが期待できる分野ですね。産業(13.5%)や一般消費財(12.7%)もバランスよく入ってて、経済全体の動きにしっかり対応できそうです。
大型株ETFのVOOと比べるとどうか?VOOだとテクノロジーが28%くらいで、金融やヘルスケアがもう少し多い。一方、VOは中型株特有の「成長セクター」が強めで、不動産(8.9%)とか素材(4.2%)みたいな安定寄りのセクターもそこそこ入ってる。これがVOの分散性のポイントですね。
市場環境によって、セクターの強さが変わるのも面白いところ。たとえば、経済が回復してるときは産業や一般消費財が伸びやすいし、金利が上がると金融が有利になったり。VOはいろんなセクターがミックスされてるから、どんな状況でも何かしらプラスに働く可能性があるんです。
VOの構成銘柄とその特徴
| 銘柄名 | ティッカー | セクター | 比率(%) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| アムフェノール | APH | テクノロジー | 1.2 | コネクタ・電子部品メーカー |
| トランスダイム | TDG | 資本財 | 1.1 | 航空宇宙部品サプライヤー |
| デクスコム | DXCM | ヘルスケア | 1.0 | 糖尿病管理デバイス |
| シンタス | CTAS | 産業 | 1.0 | ユニフォーム・サービス |
| オライリー・オート | ORLY | 一般消費財 | 0.9 | 自動車部品小売 |
| フェア・アイザック | FICO | テクノロジー | 0.9 | 信用スコアリング |
| ウェルタワー | WELL | 不動産 | 0.8 | ヘルスケア向けREIT |
| スーパーマイクロ | SMCI | テクノロジー | 0.8 | サーバー・ストレージ |
| ブラウン・フォーム | BF.B | 一般消費財 | 0.7 | 酒類メーカー(ジャックダニエル) |
| パーカー・ハネフィン | PH | 産業 | 0.7 | モーション・制御技術 |
この表を見ると、VOの構成銘柄は本当にバラエティ豊か。アムフェノール(APH)みたいなテクノロジー企業は、5GとかIoTの成長に乗ってるし、デクスコム(DXCM)はヘルスケアで糖尿病患者向けの革新的なデバイスを作ってます。成長性がしっかり期待できる企業が多いですね。
トランスダイム(TDG)とかパーカー・ハネフィン(PH)は、産業や航空宇宙分野でニッチだけど強いポジションを持ってて、安定感もある。オライリー・オート(ORLY)みたいな消費財企業は、日常生活に根ざしたビジネスで景気に左右されにくい面もあります。
特徴としては、やっぱり「中型株らしい成長性」が目立つんです。たとえば、スーパーマイクロ(SMCI)はAIやクラウド需要で急成長中だし、フェア・アイザック(FICO)はクレジットスコアの分野で独自の地位を築いてる。でも、大型株ほどメジャーじゃないから、まだ伸びしろがある。これがVOの構成銘柄の魅力ですね。
ただ、上位10銘柄で12%くらいだから、残り88%はもっと小さな企業がたくさん。分散性がしっかりしてるから、1社がコケても全体への影響は限定的なんです。このバランスが、VOの安定感と成長性を支えてるポイントかもしれません。
VOに投資した場合のシミュレーション
VOに投資すると、どれくらい資産が増えるのか気になりますよね。ここでは、過去のデータをもとに、具体的なシミュレーションをしてみます。投資額や期間を変えて、どんな結果になるか表で整理しますよ。
前提として、VOの過去10年平均リターン(配当込み)を10.2%とします。配当は再投資するとして、複利で計算してみます。初期投資額を100万円、500万円、1000万円の3パターンで、5年・10年・20年の結果を見てみましょう。
| 初期投資額 | 期間 | 最終資産額(万円) | 増加額(万円) |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 5年 | 162 | 62 |
| 100万円 | 10年 | 263 | 163 |
| 100万円 | 20年 | 691 | 591 |
| 500万円 | 5年 | 810 | 310 |
| 500万円 | 10年 | 1,315 | 815 |
| 500万円 | 20年 | 3,455 | 2,955 |
| 1000万円 | 5年 | 1,620 | 620 |
| 1000万円 | 10年 | 2,630 | 1,630 |
| 1000万円 | 20年 | 6,910 | 5,910 |
この表を見ると、複利の力がすごいことがわかりますね。たとえば、100万円を20年運用すると、約691万円に。初期投資の6倍以上になるんです。500万円なら20年で3,455万円、1000万円なら6,910万円。長期になればなるほど、リターンが加速する感じです。
もちろん、これは過去の平均リターンに基づくシミュレーション。実際は年によって変動するから、もっと増えたり減ったりする可能性もあります。たとえば、2022年みたいな-14.8%の年が続くと厳しいけど、2019年の31%みたいな年がくればもっと伸びるかもしれない。
月1万円の積み立てを加えた場合も見てみましょう。初期投資100万円+月1万円積み立てで10年運用するとどうなるか?
- 年間12万円積み立て × 10年 = 120万円
- 総投資額:100万円 + 120万円 = 220万円
- 10年後の資産額:約383万円(10.2%で複利計算)
投資額220万円が383万円になるから、約163万円のプラス。積み立てを組み合わせると、さらに資産が増えるペースが早まるんです。
シミュレーションのポイントは、やっぱり「長期」が大事ってこと。VOは中型株だから多少の波はあるけど、時間を味方にすればしっかり成長してくれる可能性が高いんです。
VOの配当タイミングと直近の配当
VOの配当は、四半期ごとに支払われます。具体的には、3月、6月、9月、12月の末あたりに配当が出るスケジュール。年4回、定期的に入ってくるから、安定感がありますね。支払日はだいたい月末から翌月初めくらいで、たとえば2024年だとこんな感じでした。
| 支払月 | 支払日 | 1株あたり配当(ドル) |
|---|---|---|
| 3月 | 2024/03/27 | 0.95 |
| 6月 | 2024/06/25 | 1.02 |
| 9月 | 2024/09/24 | 1.05 |
| 12月 | 2024/12/23 | 1.09(仮定) |
直近の配当利回りは、2025年3月時点で約1.4%。株価が280ドルだとすると、年間配当は約3.92ドル(1株あたり)。四半期ごとに1ドル前後って感じですね。過去数年を見ると、配当は少しずつ増えてる傾向があります。たとえば、2020年だと年間3.2ドルくらいだったのが、2024年には3.92ドルくらいに。年率で3~5%くらいの成長ってところです。
他のETFと比べるとどうか?大型株のVOOだと配当利回りが1.3%くらい、小型株のVBだと1.5%くらい。VOはちょうど中間くらいで、成長性と配当のバランスがいい感じですね。中型株だから、配当より成長に資金を回す企業も多いけど、それでも1.4%は悪くない数字です。
配当を受け取るには、権利確定日の前日までにVOを持ってることが条件。たとえば、12月配当なら12月20日くらいまでに買っておく必要があります。タイミングを押さえておけば、しっかり配当をもらえますよ。
VOの配当金シミュレーション
前提として、株価280ドル、年間配当3.92ドル、配当利回り1.4%で計算します。為替レートは1ドル=150円と仮定。
VOで月3万円を得るには?
- 月3万円 = 年36万円
- 年間配当3.92ドルで36万円 → 36万円 ÷ 150円 = 2400ドル
- 必要な株数:2400ドル ÷ 3.92ドル = 約612株
- 投資額:612株 × 280ドル × 150円 = 約2570万円
VOで月5万円を得るには?
- 月5万円 = 年60万円
- 年間配当3.92ドルで60万円 → 60万円 ÷ 150円 = 4000ドル
- 必要な株数:4000ドル ÷ 3.92ドル = 約1020株
- 投資額:1020株 × 280ドル × 150円 = 約4280万円
VOで配当金生活をするには?
配当金生活って人によって違うけど、月50万円(年600万円)で仮定します。
- 月50万円 = 年600万円
- 年間配当3.92ドルで600万円 → 600万円 ÷ 150円 = 4万ドル
- 必要な株数:4万ドル ÷ 3.92ドル = 約1万0204株
- 投資額:1万0204株 × 280ドル × 150円 = 約4億2850万円
| 目標 | 必要株数 | 投資額(万円) |
|---|---|---|
| 月3万円 | 612株 | 2570 |
| 月5万円 | 1020株 | 4280 |
| 月50万円(生活費) | 1万0204株 | 4億2850 |
この表を見ると、月3万円なら2570万円くらいでいけるけど、生活費レベルだと4億円超えが必要。配当利回りが1.4%だと、やっぱり大きな元手がないと厳しいですね。でも、積み立てながら増やしていけば、徐々に目標に近づけそうです。
VOに投資する際の注意点
VOに投資するのって魅力的だけど、注意点もちゃんと押さえておきたいですよね。ここでは、VOに投資する際に気をつけるべきポイントを詳しく見ていきます。
まず、ボラティリティの高さ。中型株は大型株より変動が大きい傾向があります。たとえば、2022年の-14.8%みたいな下落は、大型株ETFのVOO(-12%くらい)より少しキツめ。市場が荒れると、その影響を受けやすいんです。リスク許容度が低い人は、この波に耐えられるか考えてみてください。
次に、セクターの偏り。VOはテクノロジーや金融が強いけど、エネルギーや通信は少なめ。もしこれらのセクターが急成長すると、VOのパフォーマンスが相対的に弱くなる可能性があります。分散されてるとはいえ、完全な市場全体とは少しズレがあるんです。
それから、為替リスク。VOはドル建てだから、日本円で投資する人は為替の動きに注意が必要。たとえば、円高になると、せっかくの利益が目減りするかも。2025年3月時点で1ドル=150円でも、今後どうなるかはわかりません。
あと、配当利回りの低さもポイント。1.4%って悪くないけど、配当狙いの人には物足りないかも。たとえば、高配当ETFのVYMだと3%超えるから、インカム重視なら他の選択肢も検討したほうがいいですね。
最後に、短期売買には不向き。VOは長期投資向けに設計されてるから、デイトレードとか短期で利益を狙うには向いてません。手数料は安いけど、頻繁に売買するとそのメリットが薄れちゃいます。
これらの注意点を頭に入れておけば、VOへの投資がもっと安心になりますよ。
VOとよく比較されるETFは?
| ETF | 名称 | 対象 | 経費率 | 配当利回り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| VO | Vanguard Mid-Cap ETF | 中型株 | 0.04% | 1.4% | 低コスト、成長と安定のバランス |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 大型株 | 0.03% | 1.3% | 安定性重視、大企業中心 |
| VB | Vanguard Small-Cap ETF | 小型株 | 0.05% | 1.5% | 高成長狙い、リスク高め |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 中型株 | 0.05% | 1.3% | VOと似てるけど銘柄数が少ない |
VOOは大型株に特化してるから、VOより安定感が強い。リターンはVOOが少し上(10年平均11~12%)だけど、成長性はVOのほうが高いかも。VBは小型株だからリスクとリターンがさらに大きく、ボラティリティもVOより高め。IJHはVOとほぼ同じ中型株だけど、構成銘柄が約400とVOより少し絞られてて、パフォーマンスもほぼ互角。
VOの強みはやっぱり、低コストと中型株特有のバランス。VOOほど保守的じゃないし、VBほど冒険的でもない。投資スタイルに合わせて選ぶといいですね。
VOと合わせてポートフォリオに加えたほうがいいETFは?
- VOO(Vanguard S&P 500 ETF)
大型株中心で安定感抜群。VOの中型株と組み合わせると、成長と安定の両立ができます。経費率0.03%で低コスト。 - VB(Vanguard Small-Cap ETF)
小型株を加えて、さらに成長性をプラス。リスクは増えるけど、長期でリターンを狙いたい人にGood。経費率0.05%。 - VXUS(Vanguard Total International Stock ETF)
アメリカ以外に投資して、地域分散を。VOが米国中型株だから、国際株でリスクを分散できます。経費率0.07%。 - BND(Vanguard Total Bond ETF)
債券を入れて安定性を強化。株価が下がったときのクッションになります。経費率0.03%。
たとえば、VO 40%、VOO 30%、VXUS 20%、BND 10%みたいに組み合わせると、成長性と安定性がいい感じにミックスされます。リスク許容度や目標に合わせて調整してみてくださいね。
まとめ
VOについて、ここまでいろんな角度から見てきました。中型株に特化した低コストETFで、成長性と安定性のバランスが魅力。株価は過去10年でしっかり成長し、リターンは年平均10%超え。セクターも分散されてて、テクノロジーや金融が強め。配当は年4回で1.4%くらいと、インカムも期待できます。
投資シミュレーションでは、長期なら資産が大きく増える可能性が。注意点もあるけど、ポートフォリオにVOOやVBを組み合わせれば、さらにバランスが良くなります。将来性もあって、長期保有に最適。買い時は下落時を狙いつつ、積み立てが賢い選択です。
VOはリスクとリターンのちょうどいい中間を狙いたい人にオススメ。興味が湧いたら、ぜひ一歩踏み出してみてくださいね!
他の人気ETFの記事はこちら
DVYとは?米国高配当株に絞ったETF。インカム・キャピタルの両取りができる初心者にもおすすめのETF
この記事のポイント DVYは高配当株ETFで、利回り3.5%、経費率0.38%。公益事業・金融セクター中心で安定志向 過去10年で年平均成長率7.6%。S&P500(13.4%)やNASDAQ…
SPHDとは?米国のS&P500指数に含まれる銘柄から、高配当かつ低ボラティリティの50銘柄を選び抜いたETF
この記事のポイント 高配当(4.5%)と低ボラティリティを両立、公益事業・金融中心の50銘柄で安定性抜群。 過去10年で年平均リターン7.2%、下落局面でも配当がクッションに。 約9,500万円投資で…
PFFとは?優先株に投資するETF。毎月配当型のETFで安定した配当収益を得れる
この記事のポイント PFFは優先株ETFで、6.3%の配当利回りと月次配当が魅力。 金融セクター80%超の構成で、金利動向に敏感な点に注意。 10年リターンは約5%。成長よりインカムゲイン重視の投資家…
XYLDはS&P500に投資する毎月配当型のETF。配当金生活を狙う人におすすめ
この記事の3ポイント要約 XYLDはS&P500の現物保有とオプション売却を組み合わせ、毎月高い分配金を出すことを狙うETF 年利回りは10%前後と高いが、上昇相場では市場平均に劣後するという…
QYLDは毎月配当型のETF。インカム重視の投資家におすすめ!配当金生活を目指そう
この記事の3ポイント要約 QYLDは2013年に設定された新しめのETFであり、インカムゲインの獲得を主においている。毎月配当金を出す設計のため、定期キャッシュがほしい方にはおすすめ(でないこともある…
【EWG】ドイツの株式市場に投資するETF。大型株および中型株を中心に構成(iShares MSCI Germany ETF)
この記事のポイント EWGはドイツ市場に特化したETFで、自動車や金融セクターの強みを低コストでポートフォリオに追加可能。 過去の平均リターン6.8%、配当利回り2.03%で、長期投資と安定収入を両立…
【IAU】金価格に連動する低コストETF。GLDと同様に金現物を保有し、インフレヘッジや安全資産として活用
この記事のポイント 経費率0.25%で金価格に連動するETF。リスク分散やインフレヘッジに最適で、流動性と信頼性が高い。 過去10年で年平均7.6%。S&P500やNASDAQ100より低いが…
【XLV】ヘルスケアセクターの企業に焦点を当てたETF(Health Care Select Sector SPDR Fund)
XLVのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
SCHF:スイスフラン建て国際ETF|米国を除く先進国株に低コストで投資可能なETF。日本、欧州を中心に幅広い国へ分散
SCHFのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
QQQM:NASDAQ100連動ETF|ナスダック100指数に連動するQQQの低コスト版ETF。長期投資家向けに信託報酬を抑えた設計
QQQMのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
VCIT:米国中期社債ETF|株式との分散効果を狙う債券ポートフォリオに
VCITのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
QUAL:米国クオリティ株ETF|財務健全性や収益安定性の高い米国企業に投資。クオリティ重視で長期投資向きのETF
QUALのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
TLT:米国長期国債ETF|満期20年以上の米国長期国債に投資するETF。金利感応度が高く、債券市場の動きに敏感
TLTのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
SCHX:米国大型株ETF|低コストでS&P500に近い値動きを期待でき、長期分散投資に
SCHXのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
XLF:米国金融株ETF|銀行、保険、資産運用会社など金融関連企業が中心
XLFのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
XLK:米国テクノロジー株ETF|米国の情報技術セクターに特化したセクターETF。アップルやマイクロソフトなど世界的IT企業が多数
XLKのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
IEMG:新興国株ETF|低コストで幅広い新興国市場への分散投資が可能
IEMGのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
EFA:先進国株ETF(米国外)|日本、欧州を中心に広く分散し、グローバル分散投資に活用
EFAのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
SPLG:米国S&P500ETF|S&P500に連動する低コストETF。資産形成初心者にも適したシンプルな商品設計
SPLGのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
IJH:米国中型株ETF|大型株より高い成長性を狙いつつ、小型株よりリスクを抑えた中間的存在のETF
IJHのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
IBIT:ブラックロックが運用するビットコイン現物ETF
IBITのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
VT:世界全体株式ETF|米国、先進国、新興国すべてを網羅し、超分散投資を実現するETF
VTのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出 …
BNDX:米国外国債ETF|米国外の投資適格債に投資するETF
BNDXのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
IWD:米国バリュー株ETF|安定した収益や配当を狙う投資家に適し、長期保有向けのETF
IWDのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
VXUS:米国外国株ETF|先進国・新興国を問わず広く分散し、グローバル分散に適したETF
VXUSのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。