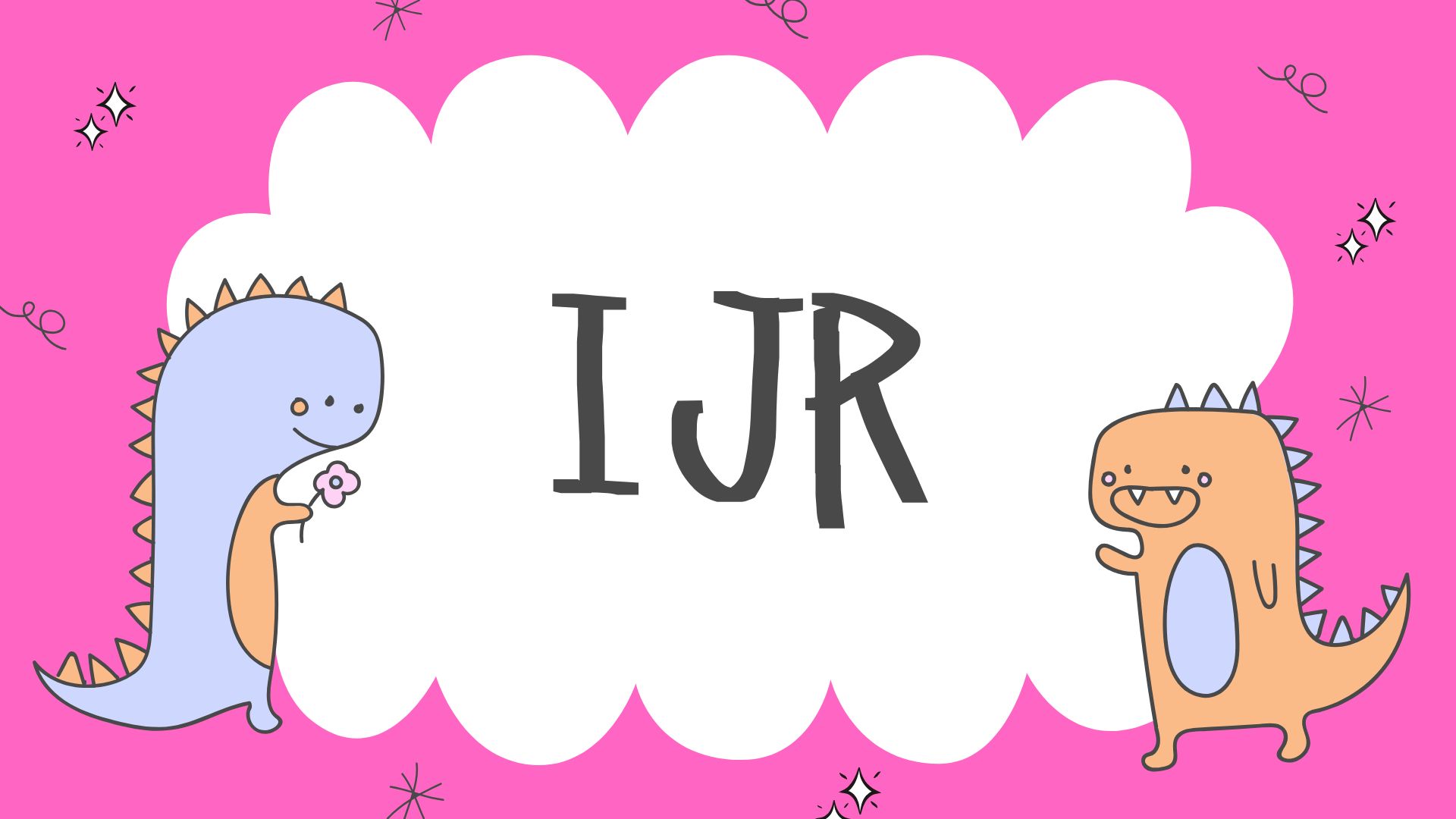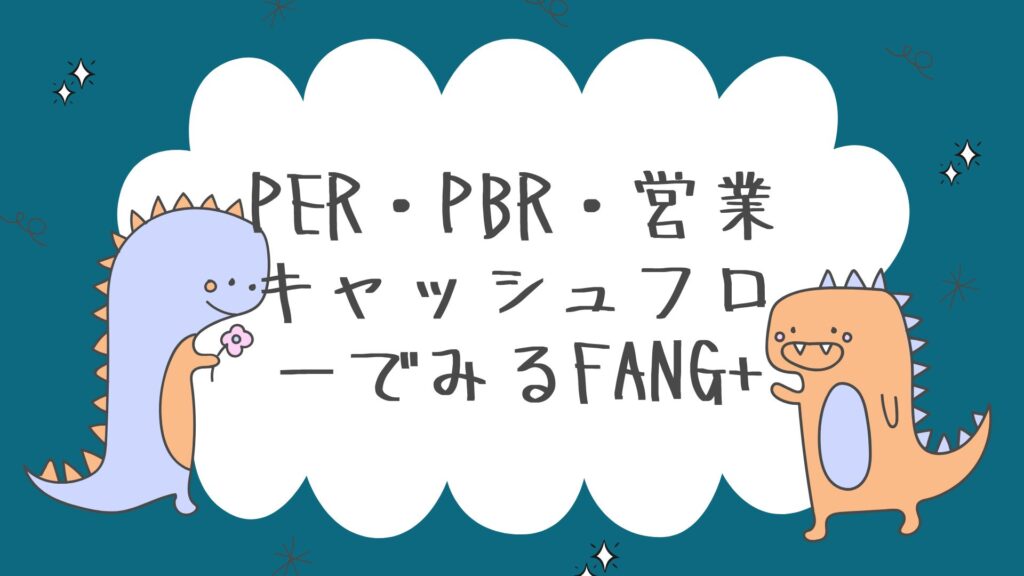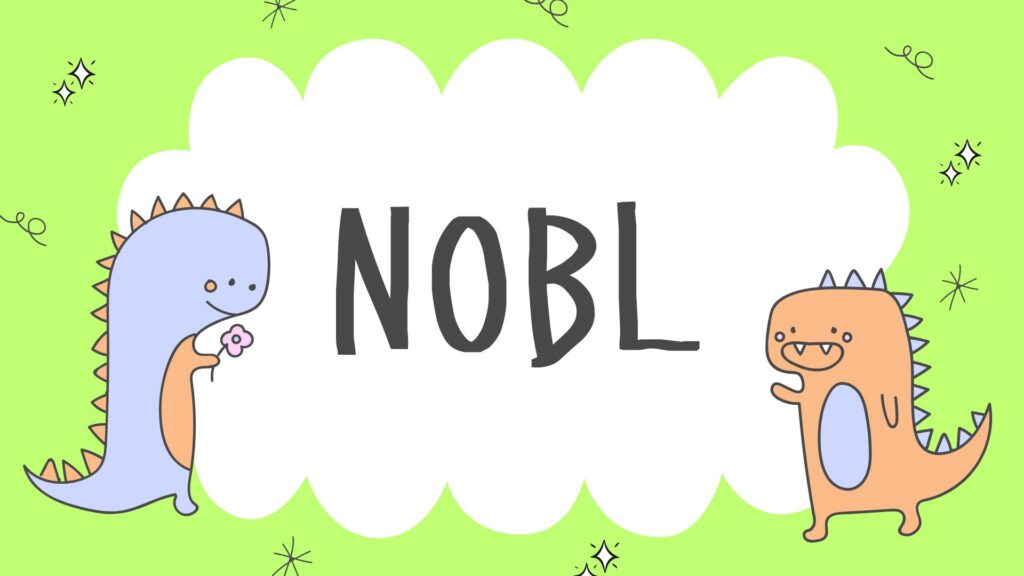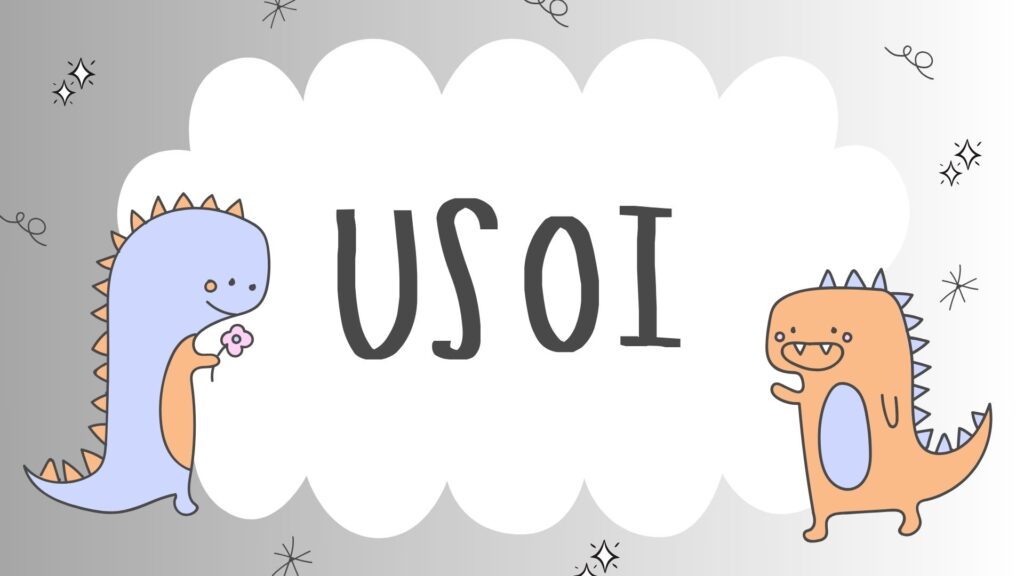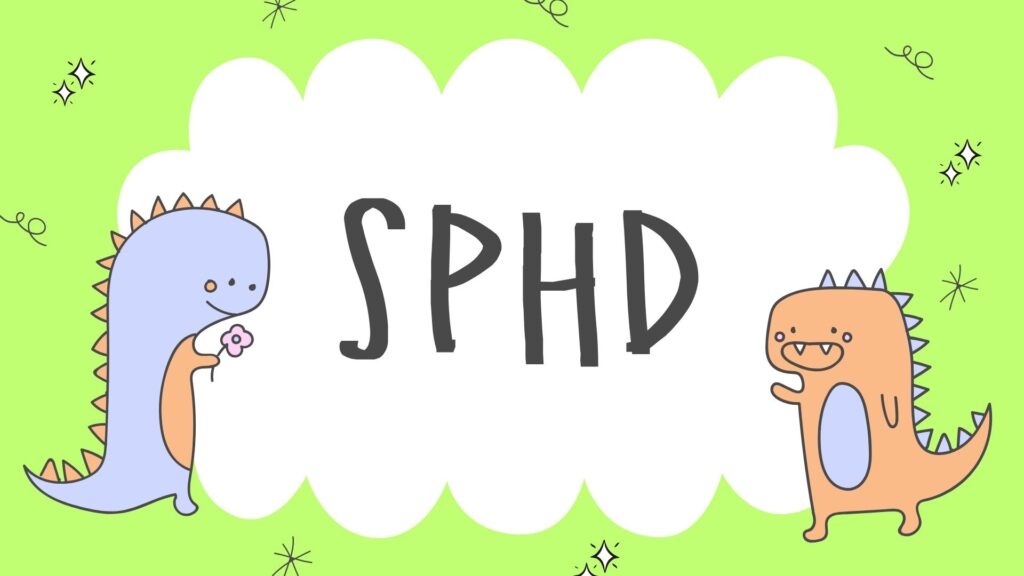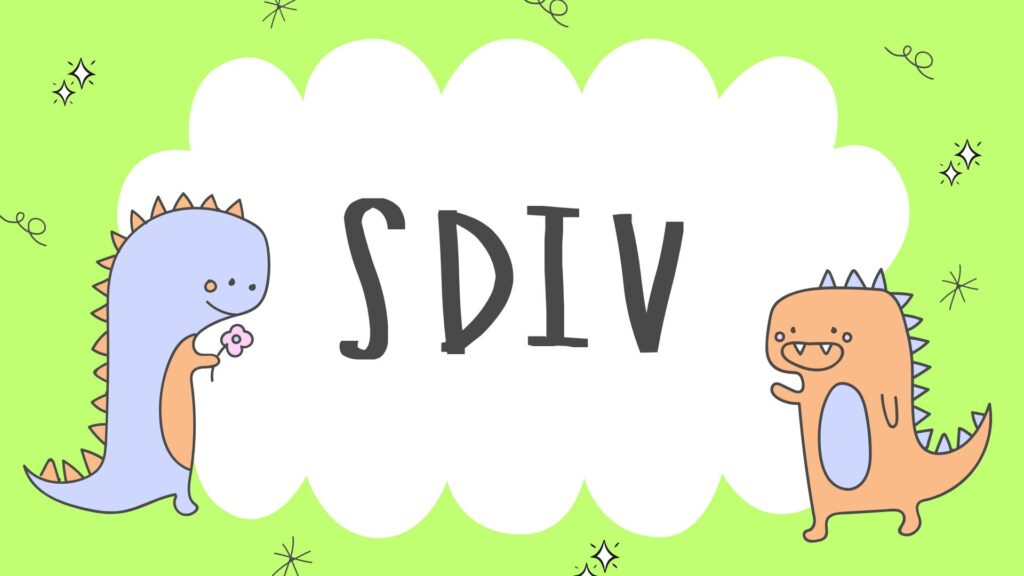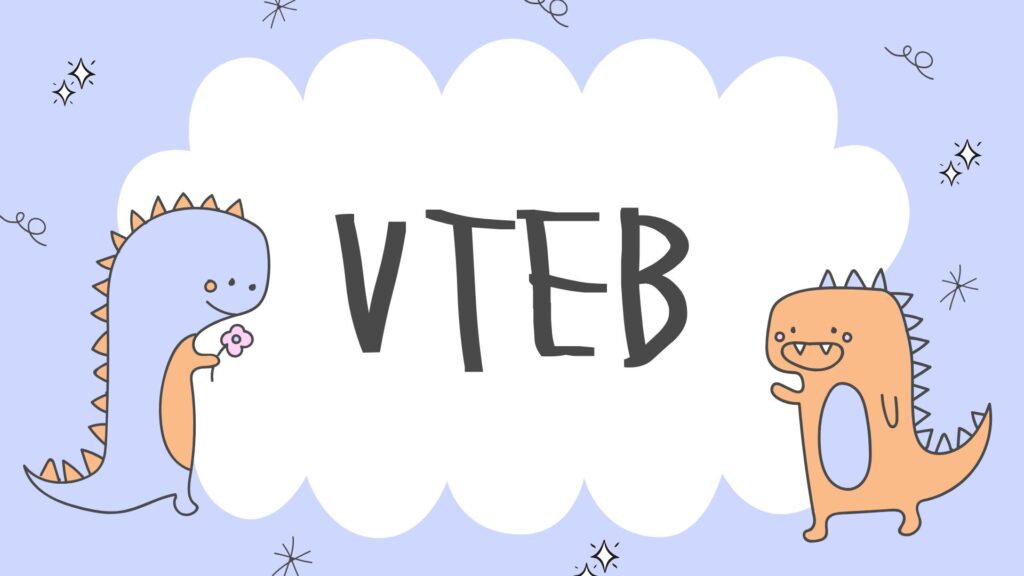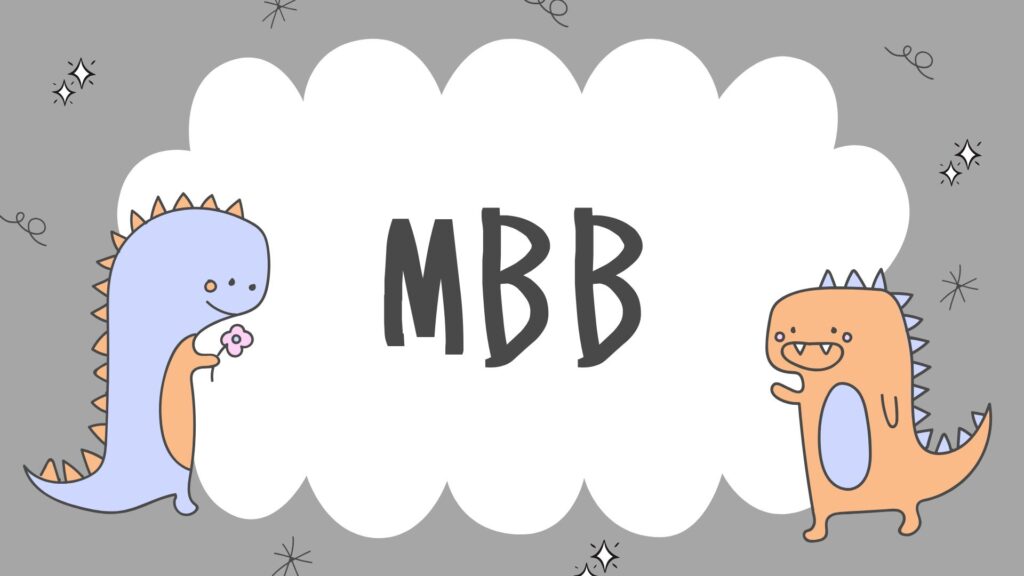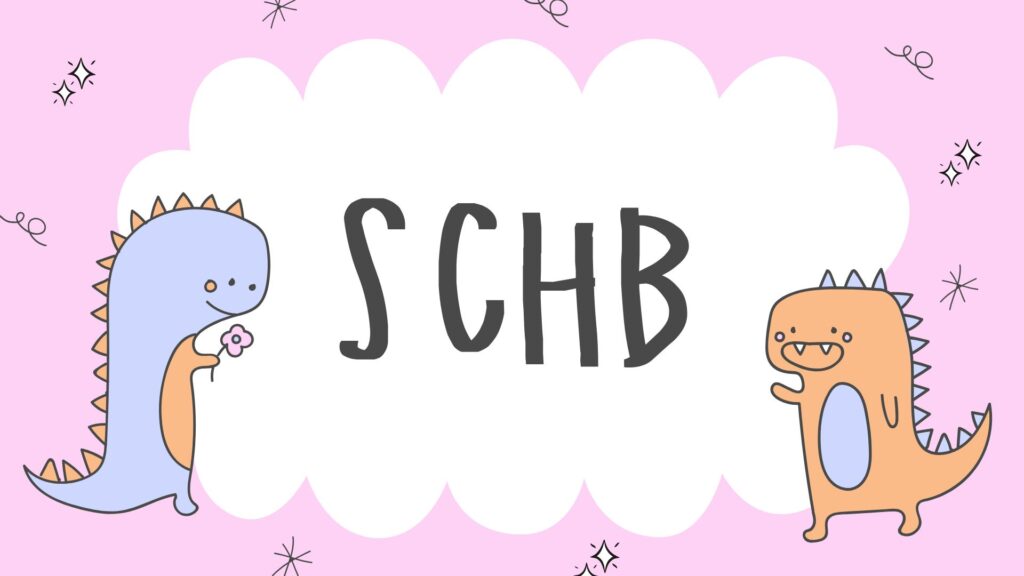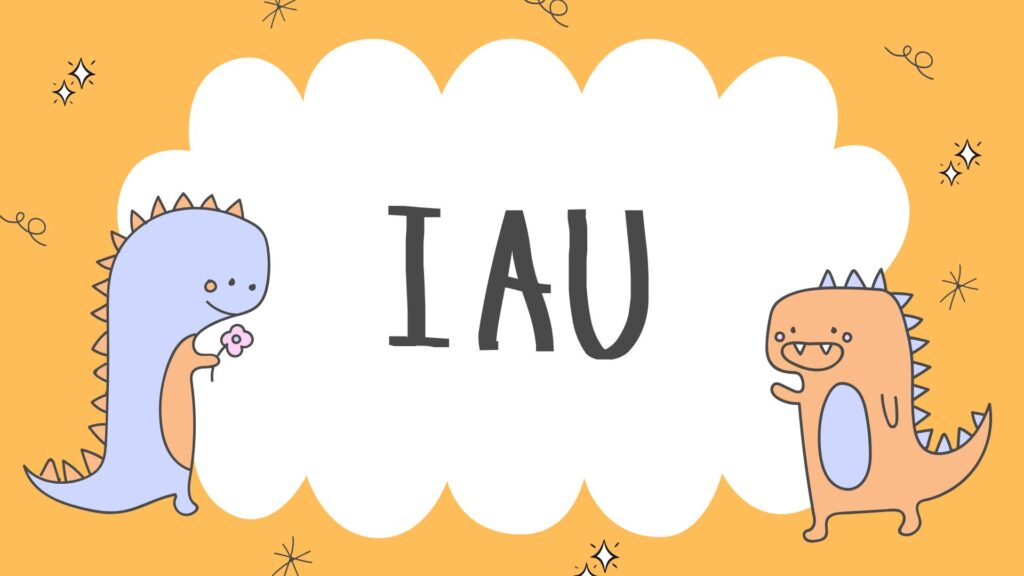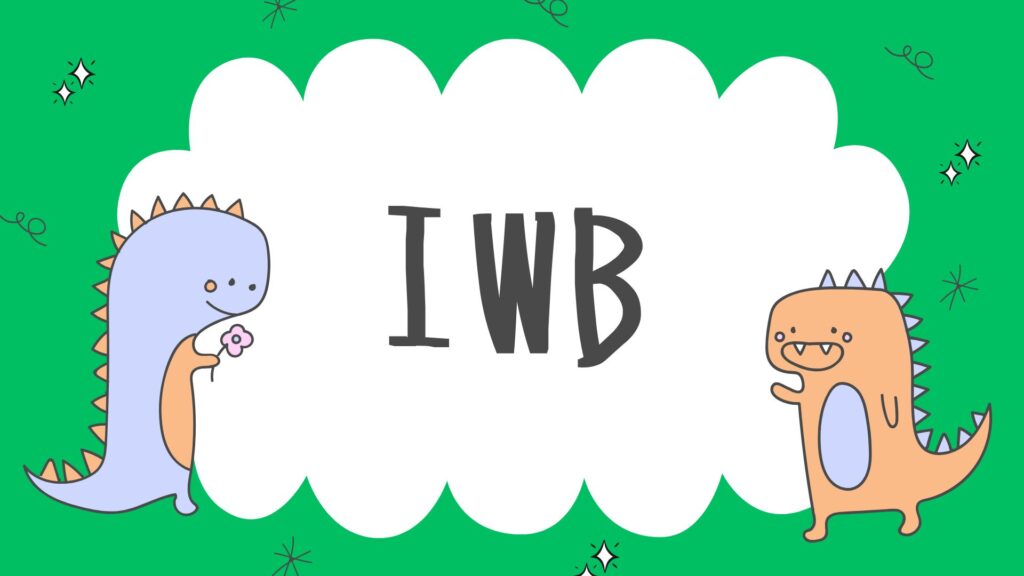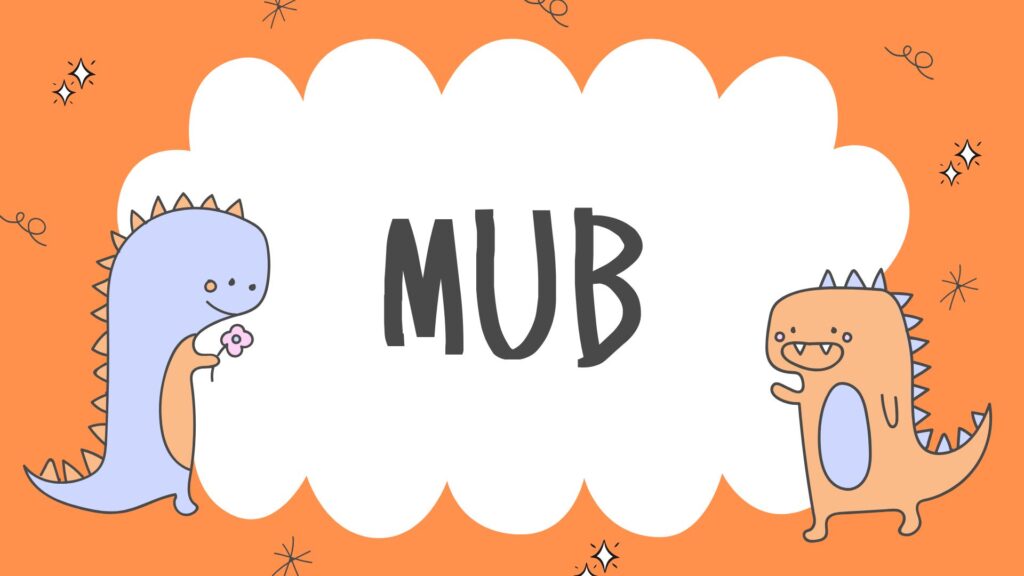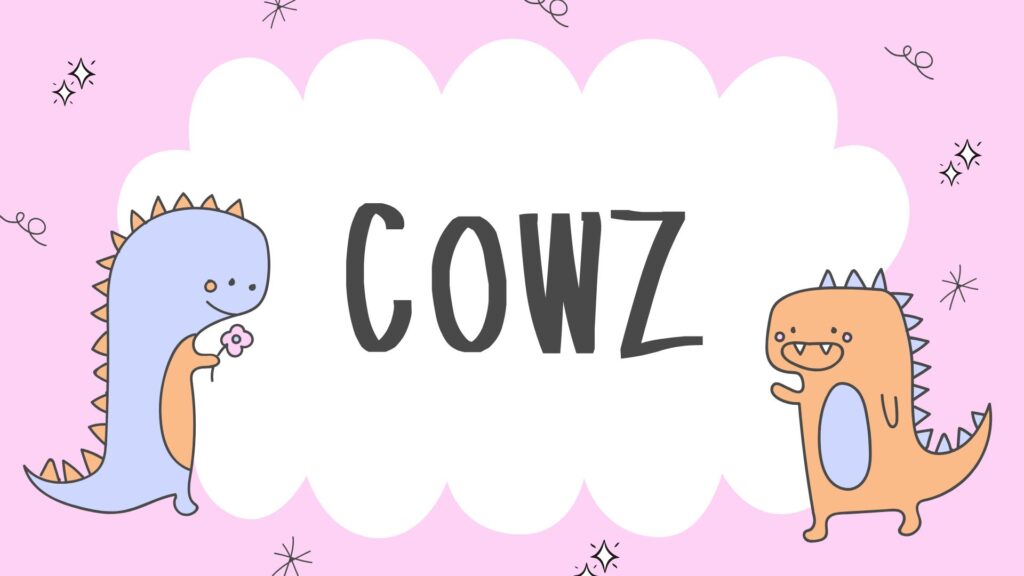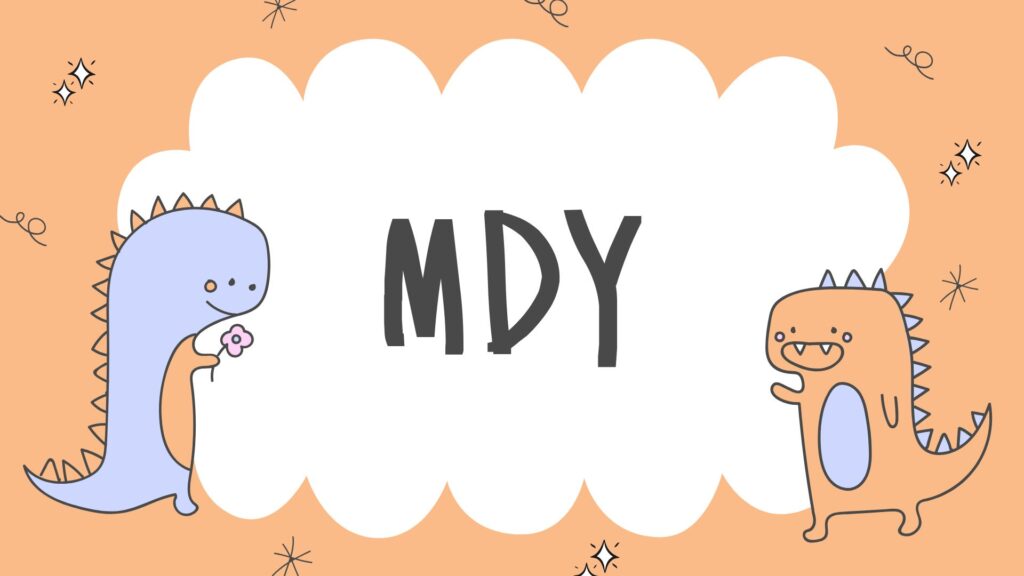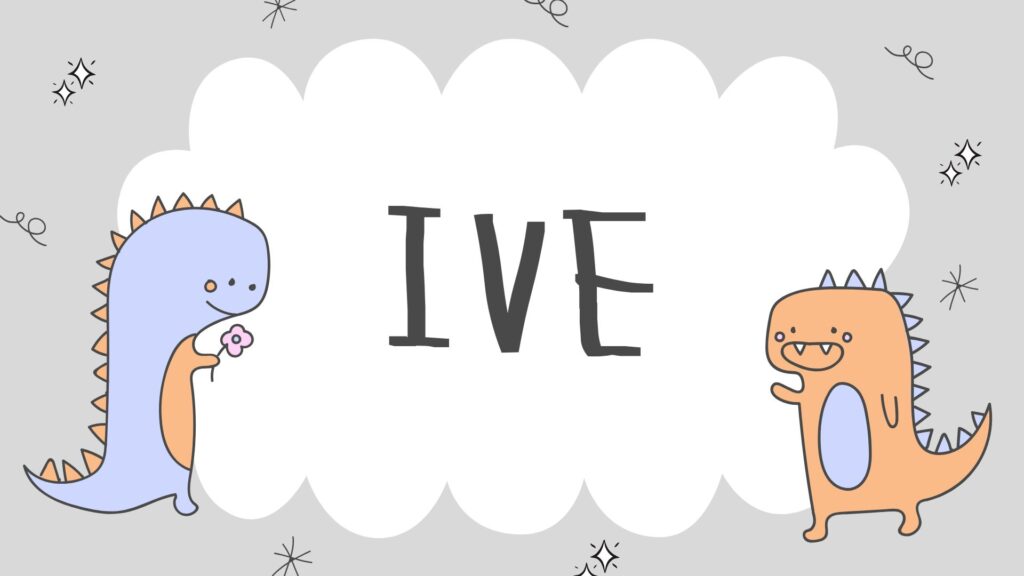IJRのETF Score (ETFのおすすめ度)
- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出
- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出
- 運用コスト:経費率をもとに算出
- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出
- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出
※各指標は当サイトにおける基準で設定
IJRとは
さて、投資の世界でよく耳にする「IJR」って何だろうと気になっている人も多いはずです。IJRとは、正式名称「iShares Core S&P Small-Cap ETF」のことで、アメリカの小型株に投資するETF(上場投資信託)です。簡単に言うと、アメリカの小さな企業を集めた株価指数「S&P SmallCap 600」に連動する投資商品なんですね。このETFは、BlackRockという世界的な資産運用会社が提供していて、小型株市場へのアクセスを手軽にしたい投資家に人気があります。
では、なぜ小型株なのか。大型株に比べて小型株は成長の余地が大きいとされています。たとえば、大企業はすでに市場での地位を確立している一方で、小型株はまだ発展途上で、急成長する可能性を秘めているんです。ただ、その分リスクも高めなので、そこは頭に入れておく必要があります。IJRはそのリスクとリターンのバランスを取るために、約600銘柄に分散投資しているのが特徴です。これによって、1社がコケても全体への影響が抑えられる仕組みになっています。
さらに、IJRは低コストで運用できる点でも注目されます。経費率(手数料)はわずか0.06%と、業界でもかなり安い水準です。たとえば、1万円投資しても年間6円しか手数料がかからない計算。長期でコツコツ投資したい人には、この低コストが大きな魅力になりますね。
また、IJRはアメリカ市場に上場していて、ティッカーシンボル「IJR」で取引されています。日本から投資する場合は、米ドル建てになるので為替レートの影響も考える必要があります。でも、小型株の成長力をポートフォリオに取り入れたいなら、手軽に始められる選択肢としてIJRは見逃せません。
このETFの歴史を少し振り返ると、2000年にスタートして以来、着実に資産を増やしてきました。2025年3月時点での総資産額は約870億ドル(約12兆円)と、かなりの規模に成長しています。投資家からの信頼が厚い証拠ですね。
IJRの特徴
IJRの基本特徴(表)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | iShares Core S&P Small-Cap ETF |
| 運用会社 | BlackRock |
| 連動指数 | S&P SmallCap 600 |
| 銘柄数 | 約600銘柄 |
| 経費率 | 0.06%(年間) |
| 資産総額 | 約870億ドル(2025年3月時点) |
| 取引通貨 | 米ドル |
| 配当頻度 | 四半期ごと(年4回) |
| 上場市場 | NYSE Arca |
まず目を引くのは、やっぱりその低コストです。経費率0.06%って、100万円投資しても年間600円しかかからない計算。アクティブ運用のファンドだと1%を超えることもザラなので、この安さは長期投資家にとって大きなアドバンテージになります。
次に、分散性も見逃せません。約600銘柄に投資しているので、特定の企業が失敗しても全体へのダメージが限定的。たとえば、1社が倒産しても、全体の0.17%程度の影響で済むわけです。これが小型株のリスクを抑えるポイントになっています。
また、IJRが連動するS&P SmallCap 600は、小型株の中でも質を重視した指数です。単に小さい会社を集めるだけでなく、財務健全性や収益性がある企業を選んでいるんです。これが、ただの小型株バスケットとの違い。たとえば、時価総額は900億円から5,800億円程度の企業が中心で、成長性と安定性のバランスが取れています。
配当も魅力的で、年4回の四半期配当が受け取れます。配当利回りは時期によって変動しますが、過去平均で1.3%前後。小型株は成長重視で配当が少ないイメージがあるかもしれませんが、IJRはしっかり配当も出してくれるんです。
ただし、アメリカ市場に特化しているので、地域的な分散は効きません。グローバルに投資したいなら、他のETFとの組み合わせが必要になります。でも、アメリカ経済の底力を信じるなら、IJRはその小型株部分をしっかり押さえてくれる存在です。
この表を見ると、IJRが「低コスト」「分散投資」「質の高い小型株」という3つの強みを兼ね備えていることが分かります。
IJRの株価・推移・成長率(パフォーマンス)
※S&P500指数と比較
まず、2025年3月時点でのIJRの株価は約120ドル前後(為替レートで変動あり)。過去1年間のレンジを見てみると、最安値が101.85ドル、最高値が128.61ドルと、約26%の幅で動いています。小型株らしいボラティリティの高さが垣間見えますね。
過去5年間の株価推移をざっくり振り返ると、こんな感じです。
- 2020年3月(コロナショック時): 約56ドル
- 2021年末: 約114ドル
- 2023年末: 約108ドル
- 2025年3月: 約120ドル
コロナショックで大きく下げた後、2021年にかけて倍以上に回復。その後も上下しながら、緩やかに上昇傾向を保っています。成長率で見ると、5年間で年平均9.1%程度(配当込み)。これは、S&P 500のような大型株指数(年平均10-11%)と比べると少し控えめですが、小型株らしいダイナミックな動きが特徴です。
たとえば、2020年から2021年の1年間だけで約50%上昇した時期もあれば、2022年にはインフレ懸念で約15%下落した年もあります。このブレ幅が小型株投資の醍醐味であり、リスクでもあるわけです。
成長率の推移(表)
| 期間 | 成長率(年平均、配当込み) |
|---|---|
| 過去1年 | 29.9% |
| 過去3年 | 1.8% |
| 過去5年 | 9.1% |
| 過去10年 | 9.0% |
過去1年の29.9%は、2024年の小型株市場の好調さを反映しています。ただ、3年平均が1.8%と低いのは、2022年の下落が響いているから。長期で見ると、5年・10年ともに9%前後で安定していて、小型株の成長力をしっかり享受できる数字です。
このパフォーマンスは、経済環境に左右されやすい小型株の特性を表しています。景気回復期には大きく伸びる一方、利上げや景気減速期には弱含む傾向があるんです。2025年に入ってからの上昇は、アメリカ経済のソフトランディング期待が背景にあるのかもしれません。
株価推移を見ると、IJRは短期的な波はあっても、長期では右肩上がりのトレンドを描いています。
IJRの年別・過去平均リターン
IJRの年別リターン(表、配当込み)
| 年 | リターン(%) |
|---|---|
| 2024 | 6.4(3月時点YTD) |
| 2023 | 16.3 |
| 2022 | -16.1 |
| 2021 | 26.8 |
| 2020 | 11.3 |
| 2019 | 22.8 |
| 2018 | -8.5 |
| 2017 | 13.2 |
| 2016 | 26.6 |
| 2015 | -2.0 |
まず、過去10年間の平均リターンは約9.0%(配当込み)。これは、年によって大きく上下しながらも、長期ではしっかりプラスを維持している証拠です。たとえば、2021年や2016年のように20%超えの年がある一方で、2022年や2018年のマイナス年もあります。
特に目立つのは、2022年の-16.1%。この年は、アメリカの利上げやインフレ懸念で小型株が大きく売られた時期です。逆に、2021年の26.8%は、コロナ後の経済回復で小型株が一気に買われた結果。こういう波が、小型株投資の特徴なんですね。
2024年は3月時点で6.4%と、まずまずのスタート。ただ、年間を通じた数字ではないので、今後の経済動向次第で変わってくるでしょう。過去の傾向を見ると、景気拡大局面ではプラスが続きやすく、逆に縮小局面ではマイナスに振れやすいです。
過去平均リターン(期間別)
| 期間 | 平均リターン(年率、%) |
|---|---|
| 1年 | 29.9 |
| 3年 | 1.8 |
| 5年 | 9.1 |
| 10年 | 9.0 |
長期で見ると、5年・10年平均が9%前後で安定しているのが分かります。短期だとブレが大きいけど、時間をかければ小型株の成長力をしっかり享受できる形です。たとえば、10万円を10年間運用した場合、単純計算で約23万円(複利考慮)になる計算。
このリターンを見ると、IJRはリスクを取る価値があるETFと言えそうです。
IJRの年別の騰落率は?
IJRの年別騰落率(表、配当込み)
| 年 | 騰落率(%) | 主な背景 |
|---|---|---|
| 2024 | +6.4(3月YTD) | ソフトランディング期待 |
| 2023 | +16.3 | 景気回復と金利安定 |
| 2022 | -16.1 | 利上げとインフレ懸念 |
| 2021 | +26.8 | コロナ後の経済再開 |
| 2020 | +11.3 | コロナショック後の反発 |
| 2019 | +22.8 | 景気拡大と低金利環境 |
| 2018 | -8.5 | 貿易摩擦と金利上昇 |
| 2017 | +13.2 | 堅調な経済成長 |
| 2016 | +26.6 | トランプ当選後の楽観ムード |
| 2015 | -2.0 | 中国経済減速懸念 |
この表を見ると、騰落率の幅が-16.1%から+26.8%と、かなり大きいのが分かります。たとえば、2021年の+26.8%は、コロナからの回復で小型株が一気に注目された年。一方で、2022年の-16.1%は、FRBの利上げで成長株が敬遠された影響です。
特に面白いのは、2020年。コロナショックで3月に底を打った後、年後半に急回復して+11.3%で終えたんです。小型株の底力が見えた年ですね。逆に、2018年の-8.5%は、米中貿易摩擦や金利上昇でリスクオフムードが強まった結果です。
平均すると、過去10年で年率9.0%とプラスを維持していますが、年ごとのバラつきが大きいのがポイント。プラス20%超えが4回ある一方、マイナスも3回あって、安定感より成長狙いのETFだと感じます。
この騰落率の波は、景気サイクルと連動していることが多いです。景気がいいときは小型株が大きく伸び、逆に締め付けが厳しくなると下落しやすい。2024年の+6.4%(3月時点)は、まだ途中経過ですが、安定成長が続けばプラスで終わる可能性もありそうです。
IJRのセクター構成
IJRのセクター構成(表、2024年データ)
| セクター | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 金融 | 18.5 | 地域銀行や保険会社が多い |
| 産業 | 17.2 | 製造業や建設関連が中心 |
| テクノロジー | 14.8 | ITサービスやソフトウェア企業 |
| 消費財(循環) | 13.6 | 小売や自動車関連 |
| ヘルスケア | 11.9 | バイオテックや医療機器 |
| 素材 | 6.7 | 化学や金属関連 |
| 不動産 | 5.8 | 小規模REITや不動産開発 |
| 公益事業 | 3.2 | 小型電力会社など |
| エネルギー | 3.0 | 中小型の石油・ガス企業 |
| 通信サービス | 2.3 | 小規模通信事業者 |
| 消費財(非循環) | 2.0 | 生活必需品関連 |
この構成を見ると、IJRは金融と産業がトップ2で、全体の3分の1以上を占めています。金融セクターは、地域銀行や中小の保険会社が多く、景気敏感度が高いのが特徴。産業セクターも、製造業や建設関連が中心で、経済が動けば恩恵を受けやすいです。
テクノロジーが14.8%と3位なのも注目ポイント。小型株には成長期待の高いIT企業やソフトウェア会社が含まれていて、将来の伸びしろを感じさせます。たとえば、ヘルスケア(11.9%)もバイオテクノロジー企業が多く、革新的な技術で急成長する可能性を秘めています。
一方、エネルギーや公益事業は割合が低め。小型株は成長重視なので、配当狙いの安定セクターは少なめなんですね。不動産も5.8%と控えめですが、小規模なREIT(不動産投資信託)が含まれるので、金利動向に敏感な一面もあります。
このセクター分布は、S&P SmallCap 600指数の特性を反映していて、景気拡大期に強い構成と言えます。ただ、金利が上がると金融や不動産が圧迫されるリスクもあるので、経済環境との連動性を意識しておくのが大事です。
IJRの構成銘柄とその特徴
IJRの上位10銘柄(表、2024年データ)
| 企業名 | セクター | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Enstar Group Ltd | 金融 | 0.78 | 保険・再保険の専門企業 |
| Fabrinet | テクノロジー | 0.76 | 光学機器製造 |
| SPS Commerce Inc | テクノロジー | 0.67 | サプライチェーン管理ソフト |
| Mueller Industries Inc | 産業 | 0.65 | 金属加工・配管製品 |
| ATI Inc | 素材 | 0.62 | 高性能金属素材 |
| SM Energy Co | エネルギー | 0.61 | 石油・天然ガス探査 |
| Meritage Homes Corp | 消費財(循環) | 0.60 | 住宅建設 |
| Insight Enterprises Inc | テクノロジー | 0.59 | ITソリューション提供 |
| Badger Meter Inc | 産業 | 0.58 | 水道メーター製造 |
| Coca-Cola Consolidated | 消費財(非循環) | 0.57 | 飲料ボトリング |
上位10銘柄で全体の約6.8%を占めています。1銘柄あたりの割合が0.5~0.8%程度と、かなり分散されているのが分かりますね。これがIJRの強みで、特定の企業に依存しない安定感があります。
たとえば、トップのEnstar Groupは保険分野で、再保険を通じてリスクを管理する企業。堅実なビジネスモデルが特徴です。一方、FabrinetやSPS Commerceはテクノロジー系で、成長性の高さが魅力。光学機器やサプライチェーン管理は、今後も需要が伸びそうな分野です。
産業セクターのMueller Industriesは、銅やアルミを使った配管製品で、インフラ需要に支えられています。ATI Incは航空宇宙向けの高性能素材を扱っていて、小型株ながらニッチな市場で存在感を発揮しています。
エネルギーからはSM Energyがランクイン。石油・ガス価格の変動に左右されやすいですが、上手くハマれば大きなリターンが期待できそうです。住宅建設のMeritage Homesも、住宅市場の動向に敏感な銘柄ですね。
これらの企業を見ると、小型株ならではの「ニッチだけど成長性あり」という特徴が際立っています。IJRは600銘柄もあるので、上位以外にも隠れた有望株がたくさん眠っているはず。
IJRに投資した場合のシミュレーション
シミュレーション条件
- 過去平均リターン: 9.0%(10年平均、配当込み)
- 初期投資額: 10万円、100万円
- 追加投資: なし、月1万円
- 期間: 5年、10年、20年
- 為替レート: 1ドル=140円(2025年3月時点仮定)
パターン1: 初期投資10万円のみ
| 期間 | 資産額(円) | 増加額(円) |
|---|---|---|
| 5年 | 15.4万円 | +5.4万円 |
| 10年 | 23.7万円 | +13.7万円 |
| 20年 | 56.0万円 | +46.0万円 |
10万円を放っておくだけで、20年後には5倍以上。複利の力ってすごいですね。
パターン2: 初期投資100万円のみ
| 期間 | 資産額(円) | 増加額(円) |
|---|---|---|
| 5年 | 154万円 | +54万円 |
| 10年 | 237万円 | +137万円 |
| 20年 | 560万円 | +460万円 |
100万円スタートだと、20年で560万円。まとまった資金があるなら、増え方がぐっと大きくなります。
パターン3: 初期投資10万円+月1万円積立
| 期間 | 資産額(円) | 投資総額(円) | 増加額(円) |
|---|---|---|---|
| 5年 | 42.6万円 | 70万円 | +22.6万円 |
| 10年 | 112.8万円 | 130万円 | +82.8万円 |
| 20年 | 347.2万円 | 250万円 | +297.2万円 |
積立を加えると、20年で投資額250万円が347万円に。毎月1万円でも、コツコツ続ければ大きな資産になります。
このシミュレーションは過去データに基づくものなので、将来も同じリターンになるとは限りません。ただ、小型株の成長力を考えると、長期で持つほどリターンが期待できそうです。為替レートが変動すれば円ベースの資産額も変わるので、そこは注意が必要ですね。
IJRの配当タイミングと直近の配当
配当タイミング
IJRは年4回、四半期ごとに配当を支払います。具体的には:
- 3月下旬
- 6月下旬
- 9月下旬
- 12月下旬
支払日は市場状況や運用会社のスケジュールで多少ずれることもありますが、大体この時期に決まっています。たとえば、2024年の配当スケジュールだと、3月25日、6月24日、9月23日、12月23日あたりが目安です。
直近の配当実績(表)
| 支払日 | 1株当たり配当(ドル) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 0.37(予定) | 1.33 |
| 2024年9月 | 0.34 | 1.30 |
| 2024年6月 | 0.33 | 1.28 |
| 2024年3月 | 0.32 | 1.25 |
直近の配当利回りは約1.33%(2024年12月時点)。株価120ドルで計算すると、1株当たり年間約1.36ドル(0.34ドル×4回)もらえる計算です。たとえば、100株持っていれば年間136ドル(約1.9万円、1ドル140円換算)。
この配当額は、企業の業績や市場環境で変動します。たとえば、2023年は平均0.30ドル程度だったのが、2024年は少し増えて0.34ドル前後に。小型株は成長重視で配当が少ないイメージがありますが、IJRは600銘柄の平均を取るので、安定感がありますね。
配当を受け取るには、権利確定日(Record Date)までに株を持っている必要があります。通常、支払日の数日前に設定されるので、カレンダーをチェックしておくのが大事です。
IJRの配当金シミュレーション
IJRの配当でどれくらいお金が得られるのか、具体的な目標額でシミュレーションしてみます。ここでは、月3万円、月5万円、そして配当金生活を目指す場合を計算してみましょう。
シミュレーション条件
- 年間配当利回り: 1.33%(2024年平均)
- 株価: 120ドル(2025年3月時点)
- 為替レート: 1ドル=140円
月3万円を得るには?
月3万円=年36万円(36万円 ÷ 140円 = 約2,571ドル)。
年間配当1株当たり1.36ドルなので:
- 必要株数 = 2,571ドル ÷ 1.36ドル ≈ 1,890株
- 投資額 = 1,890株 × 120ドル = 226,800ドル(約3,179万円)
月3万円の配当を得るには、約3,180万円分のIJRが必要。結構な金額ですね。
月5万円を得るには?
月5万円=年60万円(60万円 ÷ 140円 = 約4,286ドル)。
- 必要株数 = 4,286ドル ÷ 1.36ドル ≈ 3,151株
- 投資額 = 3,151株 × 120ドル = 378,120ドル(約5,294万円)
月5万円だと、約5,300万円の投資が必要になります。目標が上がると、必要な資金もぐっと増えますね。
IJRで配当金生活をするには?
配当金生活をするには?
仮に生活費として月30万円(年360万円)欲しいとします。
- 年360万円 ÷ 140円 = 約25,714ドル
- 必要株数 = 25,714ドル ÷ 1.36ドル ≈ 18,902株
- 投資額 = 18,902株 × 120ドル = 2,268,240ドル(約3億1,755万円)
配当だけで生活するには、約3億1,800万円分のIJRが必要。現実的には、元本を取り崩すか、他の収入源と組み合わせる形になりそうです。
このシミュレーションを見ると、IJRの配当利回り1.33%だと、大きな金額を投資しないとまとまった配当は得られないことが分かります。
IJRに投資する際の注意点
IJRは魅力的なETFですが、投資する前に気をつけるべきポイントがあります。ここでは、5つの注意点を挙げて、どんなリスクがあるのか解説していきます。
- 小型株のボラティリティ
小型株は値動きが激しいです。たとえば、2022年の-16.1%みたいな下落が起きる可能性は常にあります。短期で売買するより、長期で持つ覚悟が必要ですね。 - 景気敏感性
IJRのセクター構成を見ると、金融や産業が中心。景気が悪化すると、これらの企業は業績が落ちやすく、株価も連動して下がります。経済指標をチェックしておくのが大事です。 - 為替リスク
日本から投資する場合、ドル建てなので為替レートの影響を受けます。たとえば、1ドル140円が120円になれば、円ベースのリターンが減ってしまうんです。 - 金利上昇の影響
小型株は借入依存度が高い企業も多く、金利が上がると資金調達コストが増えて業績が圧迫されるリスクがあります。FRBの動向に注目ですね。 - 分散の限界
IJRはアメリカ小型株に特化しているので、地域分散は効きません。グローバルなリスク分散をしたいなら、他のETFと組み合わせるのが賢明です。
これらの注意点を踏まえると、IJRは成長を狙う一方で、リスク管理が大事なETFだと分かります。
IJRとよく比較されるETFは?
IJRと比較されるETF(表)
| ETF | ティッカー | 連動指数 | 経費率(%) | 銘柄数 | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| IJR | IJR | S&P SmallCap 600 | 0.06 | 約600 | 1.33 |
| VB | Vanguard | CRSP US Small Cap | 0.05 | 約1,400 | 1.45 |
| IWM | iShares | Russell 2000 | 0.19 | 約2,000 | 1.25 |
VB(Vanguard Small-Cap ETF)
VBはCRSP小型株指数に連動していて、銘柄数が1,400とIJRより多いです。経費率0.05%と少し安く、配当利回りも1.45%でやや高め。より幅広い小型株に投資したいなら、VBが選択肢になります。
IWM(iShares Russell 2000 ETF)
IWMはラッセル2000指数に連動し、約2,000銘柄とさらに分散性が高いです。ただ、経費率0.19%とIJRの3倍以上。手数料を抑えたいならIJRの方が有利ですが、最大限の分散を求めるならIWMもアリですね。
IJRの強みは、S&P SmallCap 600の「質重視」。財務健全性のある企業を選んでいるので、IWMより安定感があります。一方、VBは中型株も少し含むので、小型株純度で言えばIJRが上。目的次第で選び分けが必要です。
IJRと合わせてポートフォリオに加えたほうがいいETFは?
- VTI(Vanguard Total Stock Market ETF)
- 特徴: 米国の全市場(大型・中型・小型)をカバー。経費率0.03%、銘柄数約3,700。
- 理由: IJRが小型株特化なので、VTIで大型株も押さえれば市場全体を網羅できます。
- VXUS(Vanguard Total International Stock ETF)
- 特徴: アメリカ以外の先進国・新興国株。経費率0.07%、銘柄数約8,000。
- 理由: IJRは米国限定なので、グローバル分散を加えるのに最適。為替リスクは増えますが、地域リスクが減ります。
- BND(Vanguard Total Bond ETF)
- 特徴: 米国債券市場全体。経費率0.03%、利回り約4%(2025年3月時点)。
- 理由: 小型株のボラティリティを抑えるため、安定資産として債券を入れるのが賢明です。
たとえば、ポートフォリオを「IJR 30%」「VTI 40%」「VXUS 20%」「BND 10%」にすると、成長性と安定性を両立できます。リスク許容度や目標で比率は調整してくださいね。
IJRに関してのよくある質問
- QIJRの将来性はあるか?
- A
小型株は経済成長と連動しやすいので、アメリカ経済が今後も拡大すれば、IJRの将来性は十分あります。過去10年で年平均9%のリターンを出している実績も強み。ただ、短期的な下落リスクはあるので、5年以上の長期目線が大事です。
- QIJRは長期保有をしてもいいか?
- A
はい、長期保有に向いています。低コスト(経費率0.06%)と分散性(600銘柄)が、時間を味方につける投資にぴったり。過去データでも、10年持てば安定したリターンが期待できます。ただし、景気後退期の我慢は必要ですね。
- QIJRの買い時はいつか?
- A
買い時は経済環境次第ですが、景気回復初期(金利が下がり始める頃)が狙い目。たとえば、2020年3月のコロナ底値みたいなタイミング。ただ、タイミングを計るより、積立で少しずつ買う方がリスクが少ないです。
まとめ
アメリカ小型株に投資するこのETFは、低コスト(経費率0.06%)、約600銘柄の分散性、年平均9%のリターンと、成長を狙う投資家に魅力的な選択肢です。株価は波がありつつも長期で右肩上がり、配当も年4回と安定感があります。
セクターは金融や産業が中心で、成長性と景気敏感性が共存。構成銘柄もニッチな分野で活躍する企業が多く、小型株の可能性を感じさせます。シミュレーションでは、積立を組み合わせれば20年で大きな資産に育つことも分かりました。
ただし、ボラティリティや為替リスク、金利上昇の影響は注意が必要。VTIやVXUS、BNDと組み合わせれば、ポートフォリオのバランスも良くなります。将来性はアメリカ経済次第ですが、長期目線なら十分期待できそうです。
IJRは、小型株の成長力を手軽に取り入れたい人にぴったりのETF。リスクを理解しつつ、投資プランに組み込んでみてください。きっと、資産づくりの一助になるはずです。
他の人気ETFの記事はこちら
FANG+は今後も伸びるのか。PER・PBR・営業キャッシュフローから考えてよう
この記事のポイント FANG+は、AI・クラウド・半導体・広告・サブスクの主要分野を押さえており、売上高や営業キャッシュフロー、OCFマージンも高水準の企業に効率よく投資可能 PER・PBRは高めでも…
DVYとは?米国高配当株に絞ったETF。インカム・キャピタルの両取りができる初心者にもおすすめのETF
この記事のポイント DVYは高配当株ETFで、利回り3.5%、経費率0.38%。公益事業・金融セクター中心で安定志向 過去10年で年平均成長率7.6%。S&P500(13.4%)やNASDAQ…
NOBLとは?S&P500の配当貴族に絞って投資ができる優良ETF
この記事のポイント NOBLは25年以上連続増配の企業に投資するETFで、安定性と配当成長が強み。 過去10年のCAGRは8%、下落局面ではS&P 500やNASDAQ 100より耐性高い。 …
USOIとは?毎月配当型の原油価格の変動に連動するETF。玄人向けの商品
この記事のポイント USOIは原油ベースの高配当ETN。月次配当とカバードコール戦略が魅力 過去のパフォーマンスは年平均2.8%で、S&P500やNASDAQ100に比べ成長率は控えめだが配当…
SPHDとは?米国のS&P500指数に含まれる銘柄から、高配当かつ低ボラティリティの50銘柄を選び抜いたETF
この記事のポイント 高配当(4.5%)と低ボラティリティを両立、公益事業・金融中心の50銘柄で安定性抜群。 過去10年で年平均リターン7.2%、下落局面でも配当がクッションに。 約9,500万円投資で…
PFFとは?優先株に投資するETF。毎月配当型のETFで安定した配当収益を得れる
この記事のポイント PFFは優先株ETFで、6.3%の配当利回りと月次配当が魅力。 金融セクター80%超の構成で、金利動向に敏感な点に注意。 10年リターンは約5%。成長よりインカムゲイン重視の投資家…
SDIVとは?世界中の高配当株に投資する毎月配当型のETF。配当生活は可能か?
この記事のポイント SDIVは約11%の配当利回りで、毎月配当が得られ、キャッシュフローを重視する投資家に最適。 100銘柄に均等加重で投資し、米国や新興国を含む地域リスクの軽減が特徴。 約4700万…
XYLDとは?配当金生活を狙えるS&P500に投資する毎月配当型のETF
この記事のポイント XYLDはS&P 500にカバードコール戦略を組み合わせ、約9~12%の高配当を実現。 株価成長は控えめだが、下落相場での耐性と毎月分配が魅力。 セクター分散が効き、テクノ…
QYLDとは?毎月配当型のETF。インカム重視の投資家におすすめ!配当金生活を目指そう
この記事のポイント QYLDはカバードコール戦略で高分配(年10~12%)と低ボラティリティを実現。インカム重視の投資家に最適。 株価成長率は0.66%と低いが、分配金再投資で50年で資産33倍の可能…
VTEBとは?少し特殊な米国地方債に投資するETF。毎月配当金が得つつ、資金を避難させる先として最適
この記事のポイント VTEBは米国地方債ETF。経費率0.05%、利回り3.1%で税免除メリット。 10年平均成長率0.8%、騰落率±2.5%。株式ETFより低リスク。 毎月配当でキャッシュフロー安定…
【SOXS】半導体セクターに特化した3倍レバレッジのインバースETF。短期トレードに特化
この記事のポイント 半導体セクターの3倍インバースETF。短期トレードに特化し、経費率1.03%、配当利回り2.5%。 過去5年平均リターン-48.1%。2022年+45.8%だが、長期保有はで不向き…
【EWG】ドイツの株式市場に投資するETF。大型株および中型株を中心に構成(iShares MSCI Germany ETF)
この記事のポイント EWGはドイツ市場に特化したETFで、自動車や金融セクターの強みを低コストでポートフォリオに追加可能。 過去の平均リターン6.8%、配当利回り2.03%で、長期投資と安定収入を両立…
【MBB】米国の住宅ローン担保証券(MBS)に投資するETF。債券の中でも利回り重視の投資に向く
この記事のポイント MBBは低コスト(経費率0.06%)で毎月分配金を提供するMBS特化の債券ETF。安定性とインカム収益が魅力 過去10年リターンは1.15%、S&P500(12.8%)やN…
【SCHB】米国株式市場全体に分散投資するETF。低コストで大型・中型・小型株を網羅し、長期投資向け
この記事のポイント SCHBは経費率0.03%、2,500銘柄で米国市場98%をカバーし、初心者にも最適。 過去15年で年平均10.5%のリターン。小型株の成長性と大型株の安定性を両立。 S&…
【IAU】金価格に連動する低コストETF。GLDと同様に金現物を保有し、インフレヘッジや安全資産として活用
この記事のポイント 経費率0.25%で金価格に連動するETF。リスク分散やインフレヘッジに最適で、流動性と信頼性が高い。 過去10年で年平均7.6%。S&P500やNASDAQ100より低いが…
【SCHG】米国の大型成長株に特化したETF。低コストでハイテク企業中心の成長ポートフォリオ
この記事のポイント SCHGは低コストで米国大型成長株に投資でき、長期的な資産成長を追求する投資家に最適 過去の株価推移や成長率(年平均15%のリターン)から、今後も高いリターンと安定性を見いだせる …
【IWB】iShares Russell 1000 ETF|米国の大型株に投資するETF。ラッセル1000指数連動で、S&P500よりやや銘柄範囲が広い
この記事のポイント 米国の大型・中型株約1,000銘柄をカバーし、低コストで分散投資が可能 テクノロジーや金融など多様なセクター構成で、リスク分散 過去の株価推移や配当実績から、長期投資に適した安定感…
【MUB】米国の地方債(ミュニシパルボンド)に投資するETF
この記事のポイント MUBは連邦税免税の地方債ETF。低リスクかつ安定したリターンを提供し、ポートフォリオの基盤に最適 毎月分配型の配当により、定期収入や複利効果による資産成長を目指せる 経費率0.0…
【COWZ】米国農業関連株ETF|高キャッシュフロー銘柄に特化したETF
この記事のポイント フリーキャッシュフロー重視。財務健全な米国企業に投資。市場変動に強く、長期的な資産成長を狙える 月次配当で安定収入を確保しつつ、過去平均13%のリターンでインフレを上回る資産拡大を…
【MDY】S&P400(米国中型株)に投資するETF
この記事のポイント MDYは米国の中型企業に投資するETFで、大型株より高い成長力と小型株より安定性を兼ね備えている 過去20年の平均リターン約8-9%と、分散投資によるリスク低減で、資産形成に適した…
【IWR】米国の中型株に投資するETF。成長ポテンシャルと安定性のバランスが取れたミッドキャップに注目
この記事のポイント 米国中型株に分散投資でき、成長性と安定性を両立。低コストで長期投資に最適 四半期配当で安定収入、過去10年平均リターン10.2%で資産拡大を期待できる VTIやIXUSと組み合わせ…
【SPYV】S&P500構成銘柄のうちバリュー株に特化したETF。配当重視・割安株投資を好む投資家向け
この記事のポイント SPYVは低コストでバリュー株に投資でき、2.2%の配当利回りと市場下落時の安定性が長期資産形成の基盤となる 金融・ヘルスケア中心のセクター分散と7.2%の過去リターンから、100…
【IVE】S&P500構成銘柄のうちバリュー株に特化したETF
この記事のポイント iシェアーズ S&P 500 バリューETF(IVE)は、低コストでバリュー株に投資し、安定性と成長性を両立 金融・ヘルスケア中心のセクター構成と約1.8%の配当利回りで、…
【SPYG】S&P500構成銘柄のうち成長株に特化したETF。ハイテク比率が高く、成長期待を重視する投資家向け
SPYGのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
【VNQ】米国REITに投資するETF。不動産セクター全体をカバー
VNQのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。