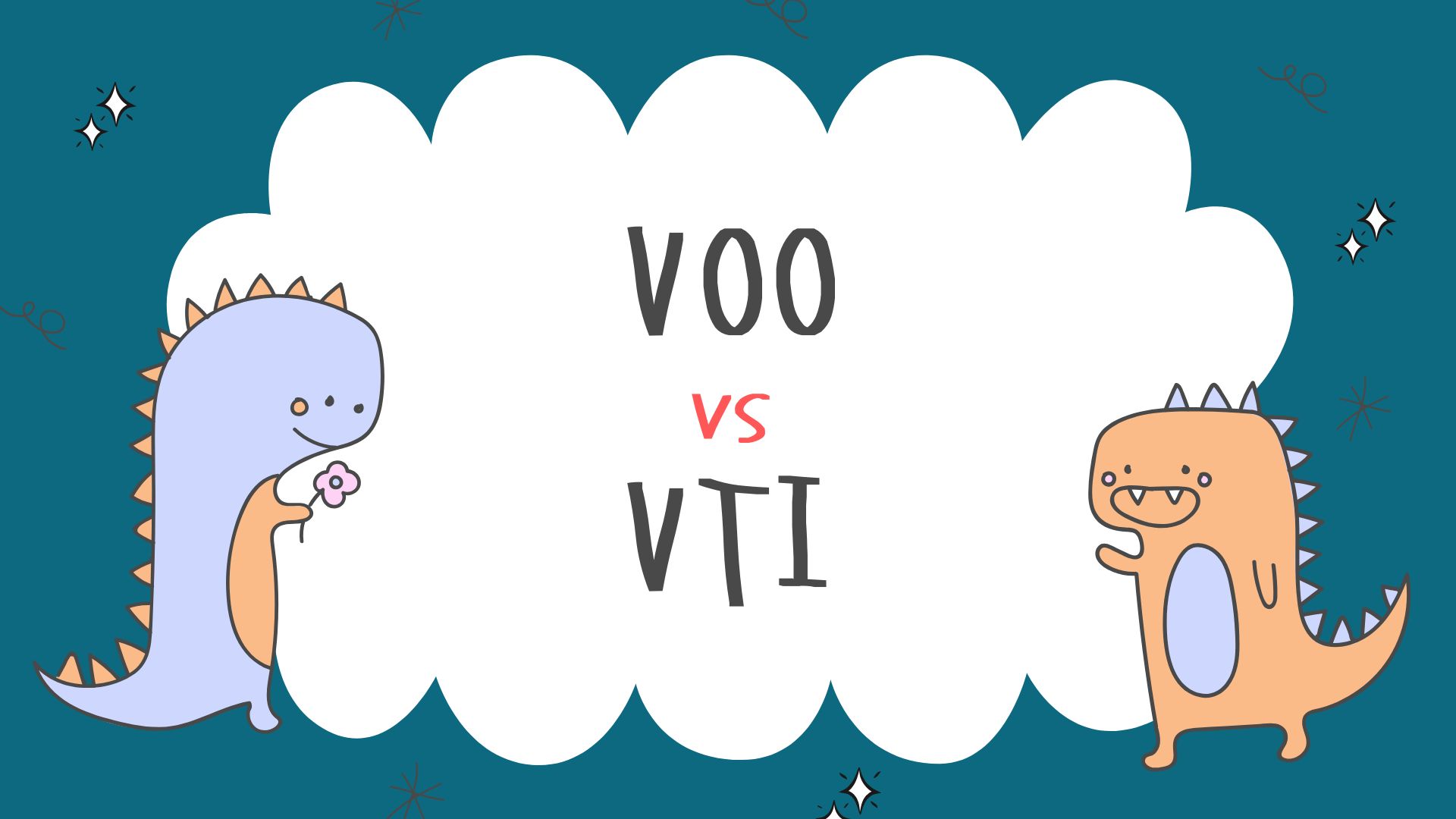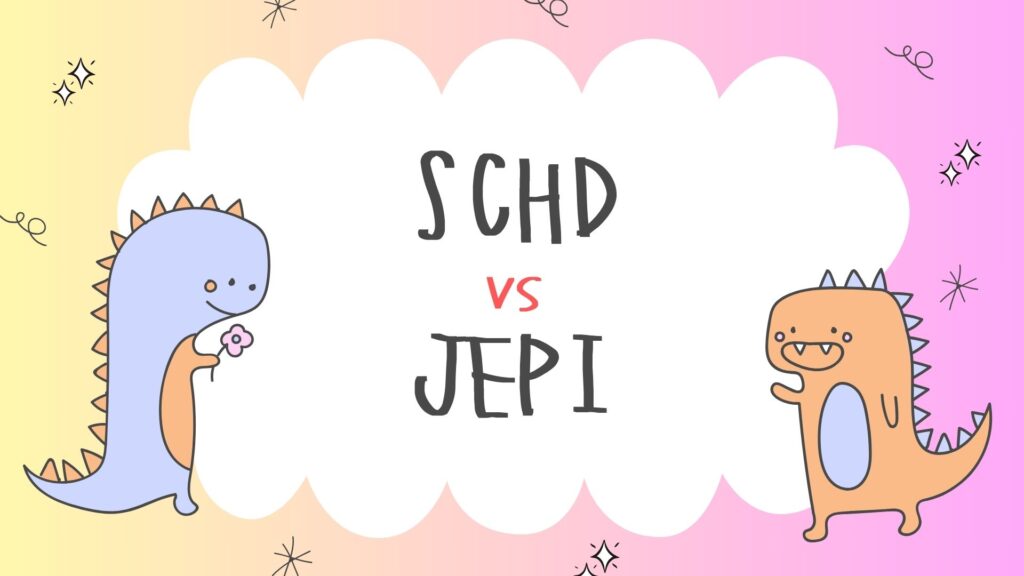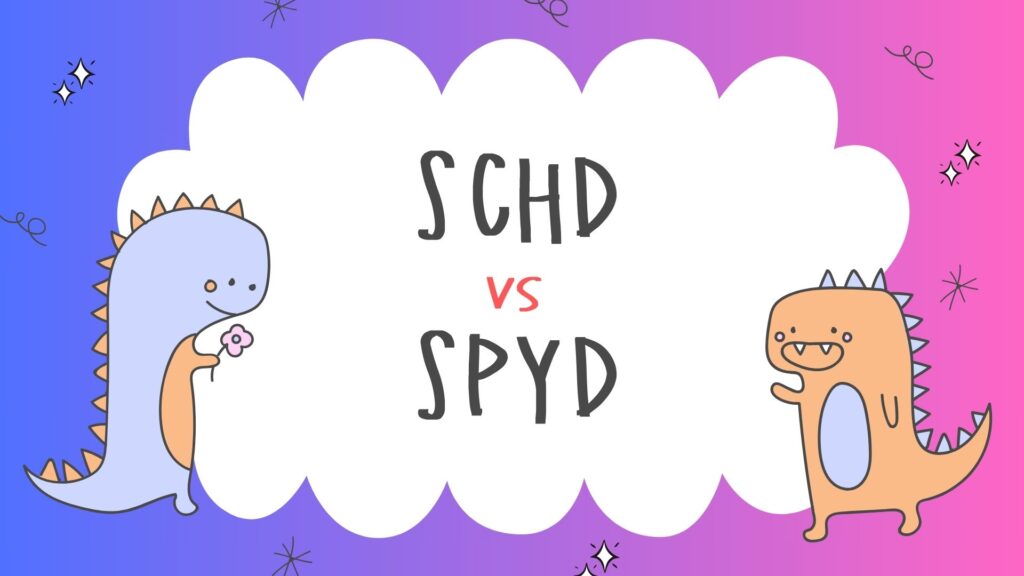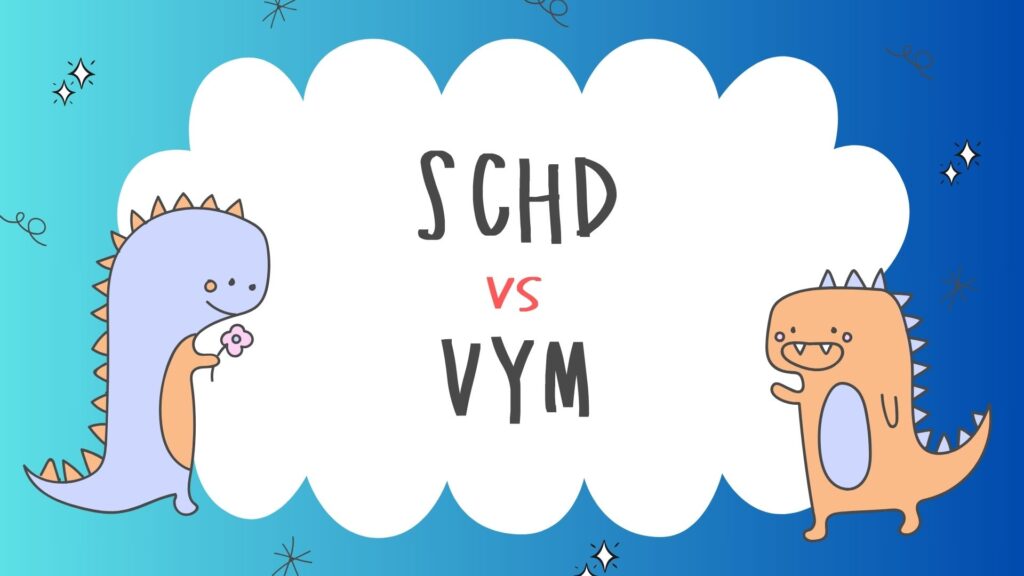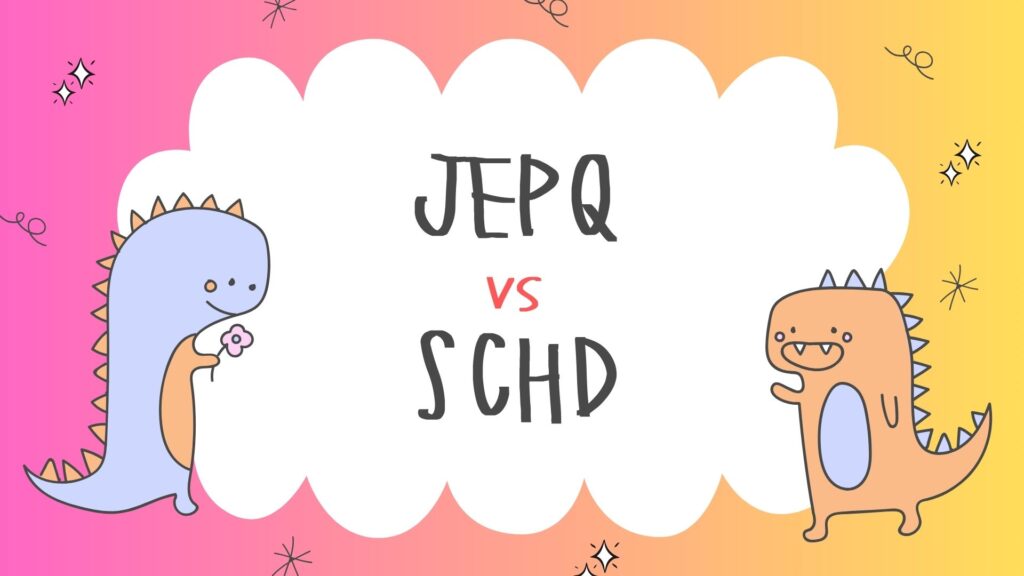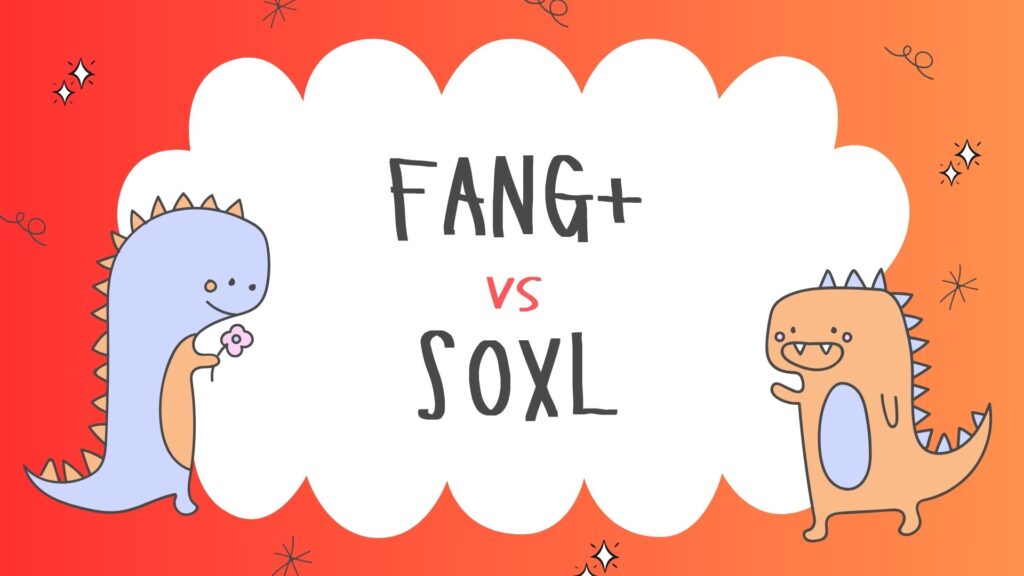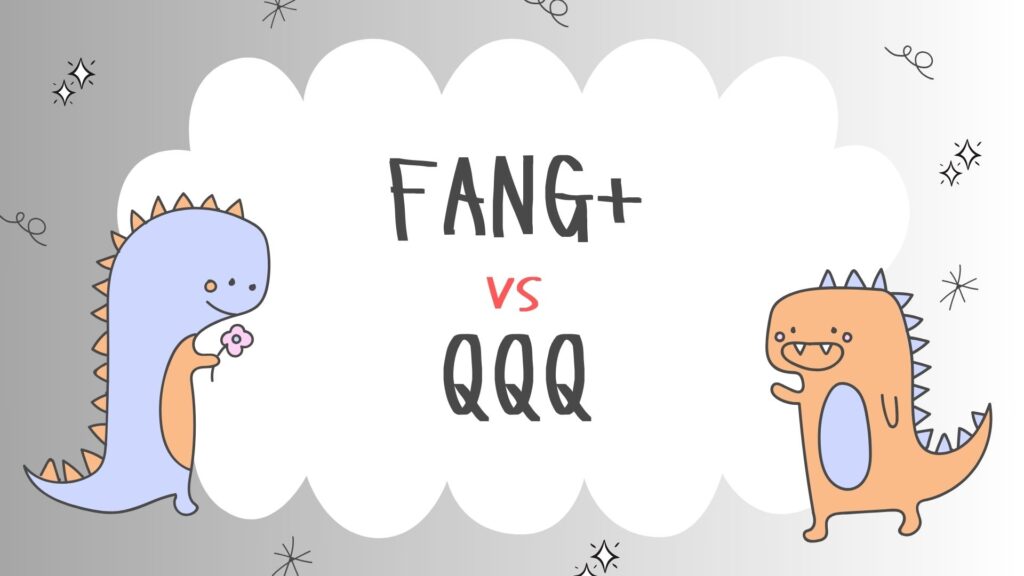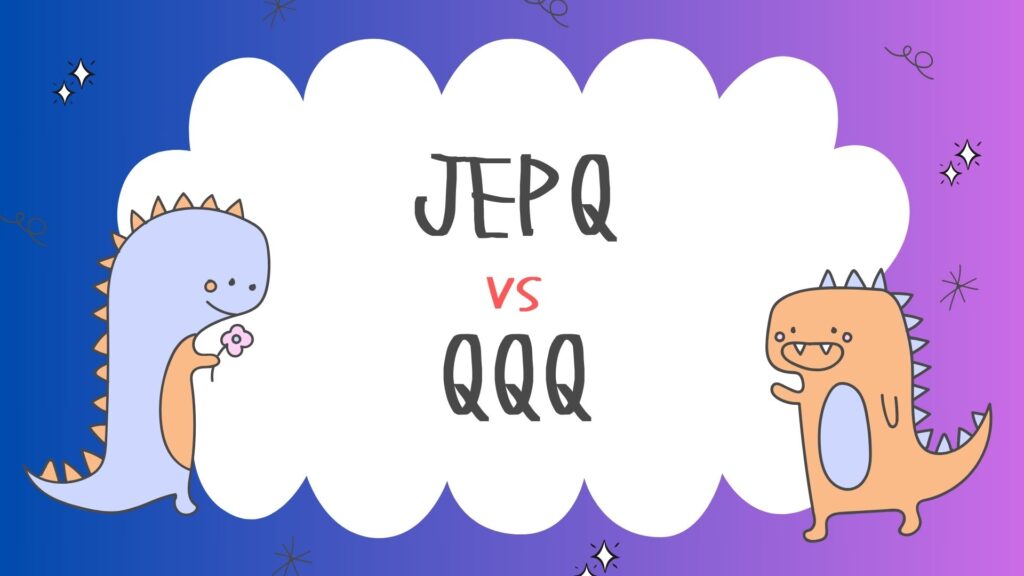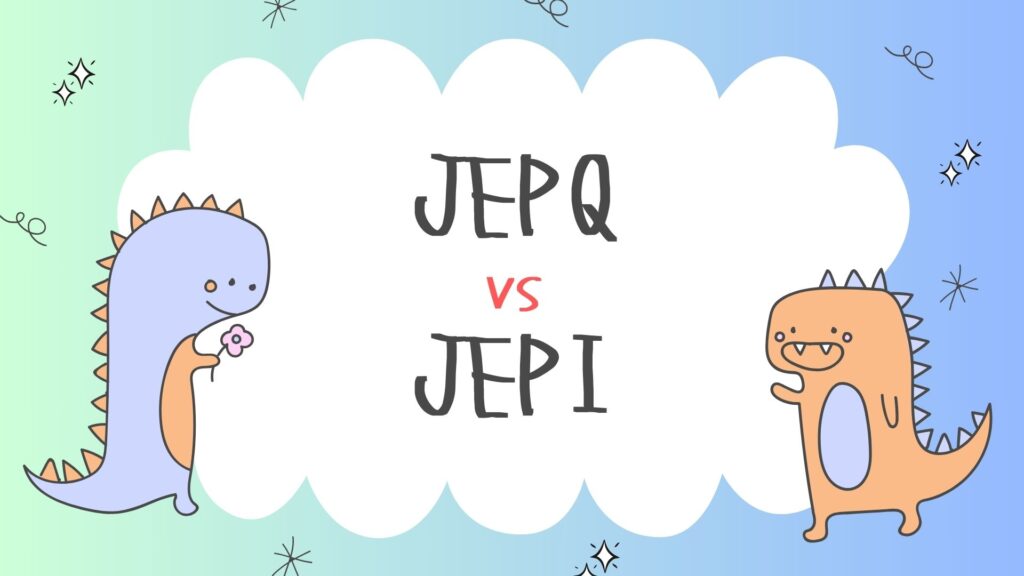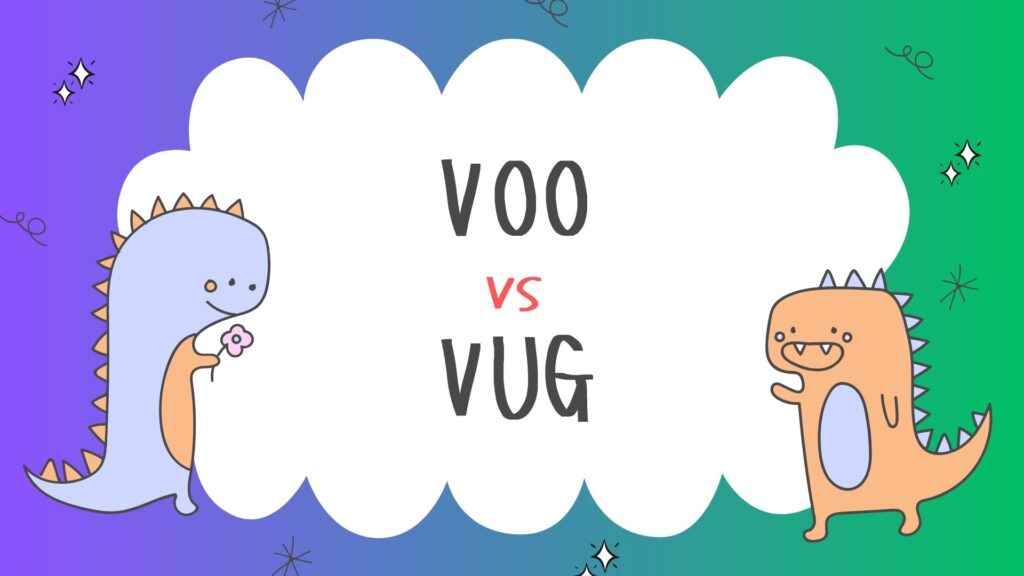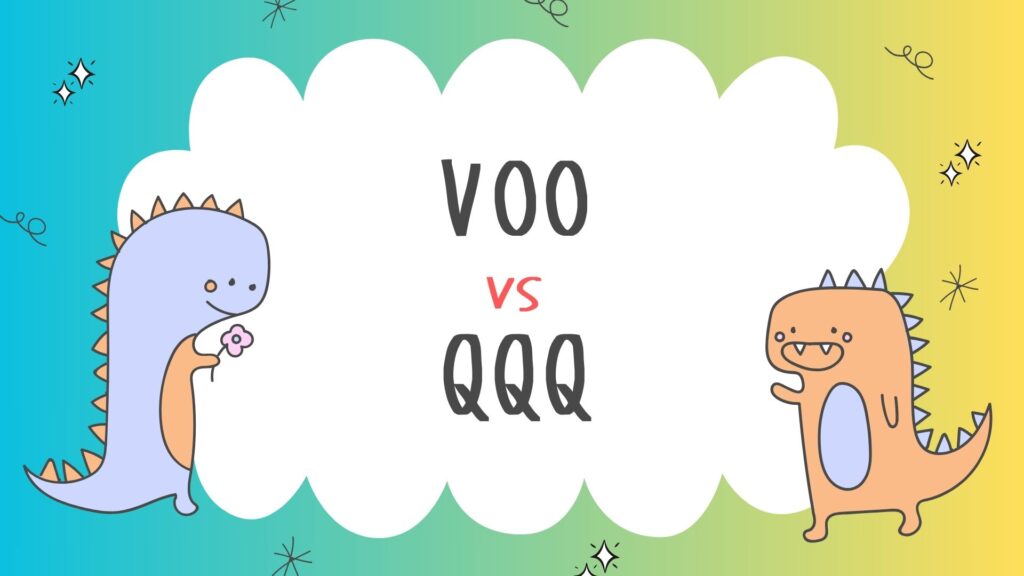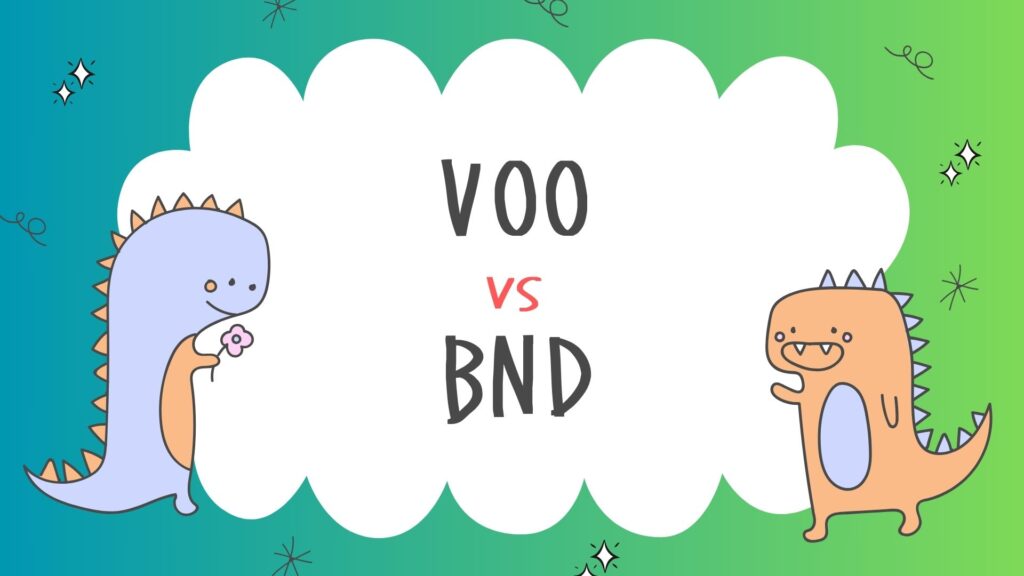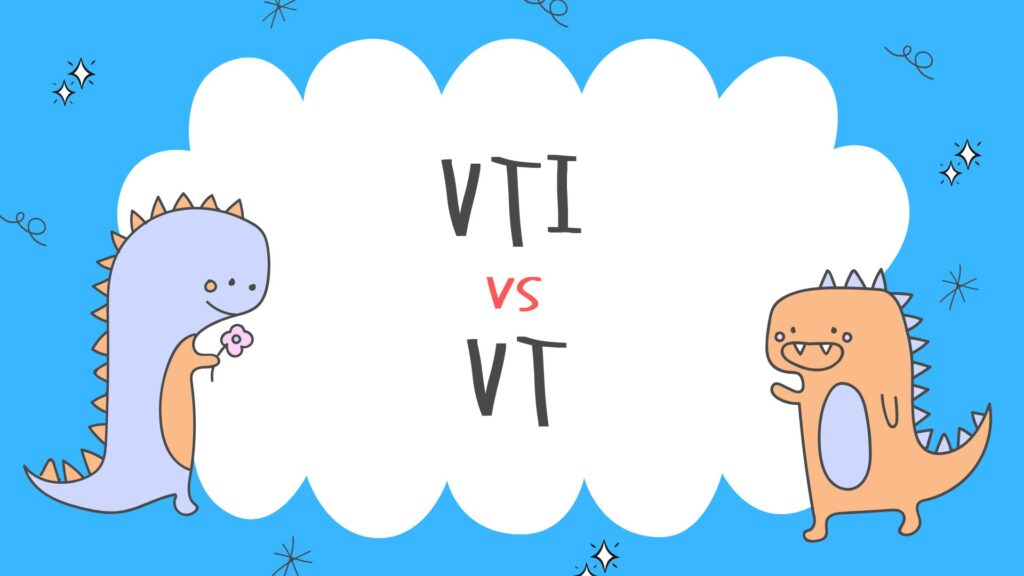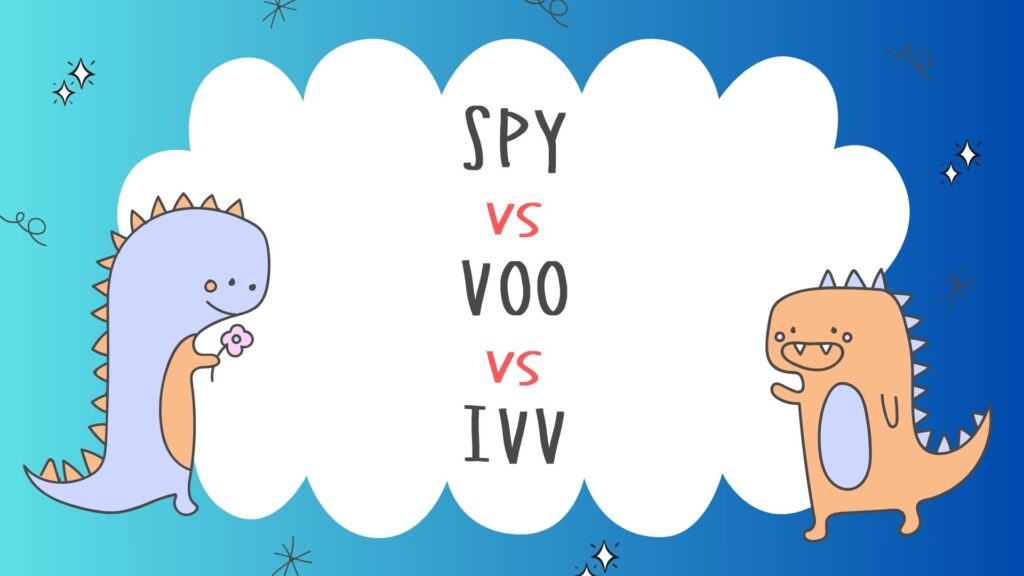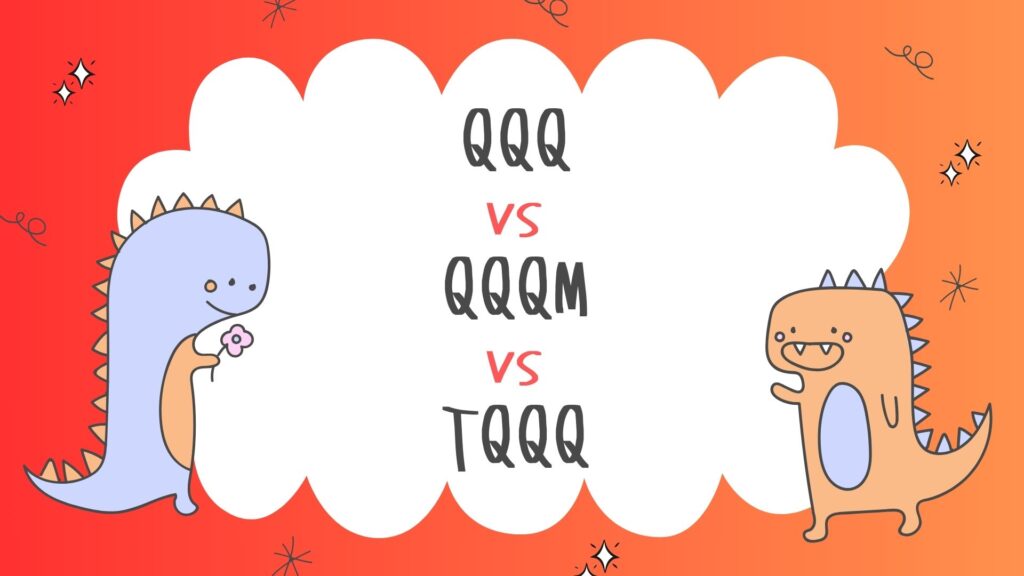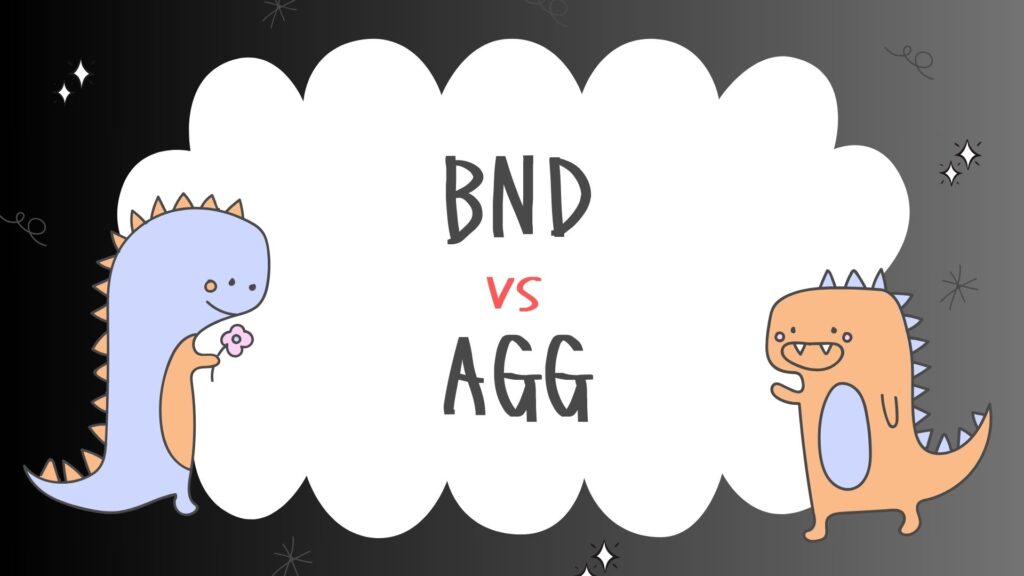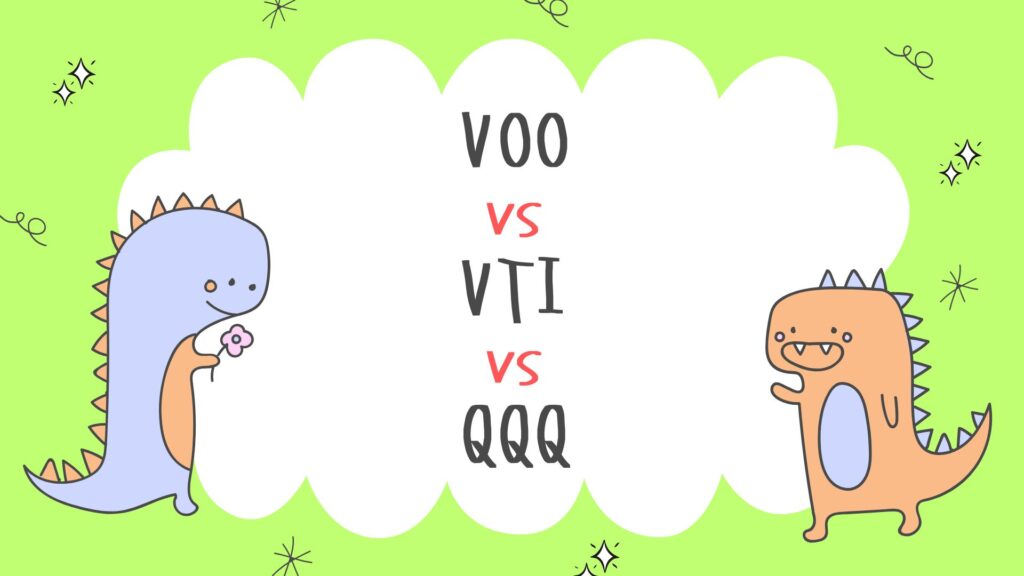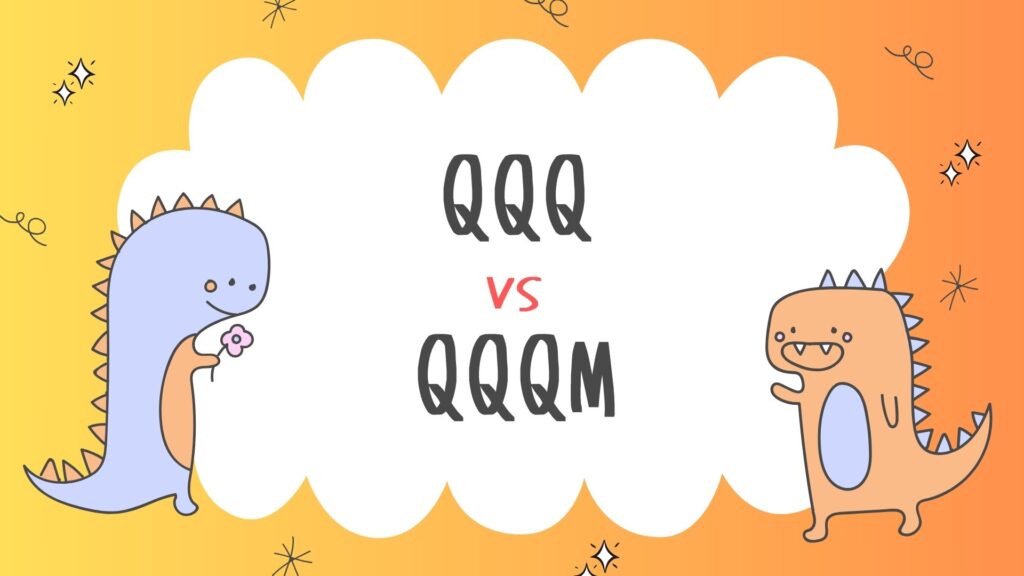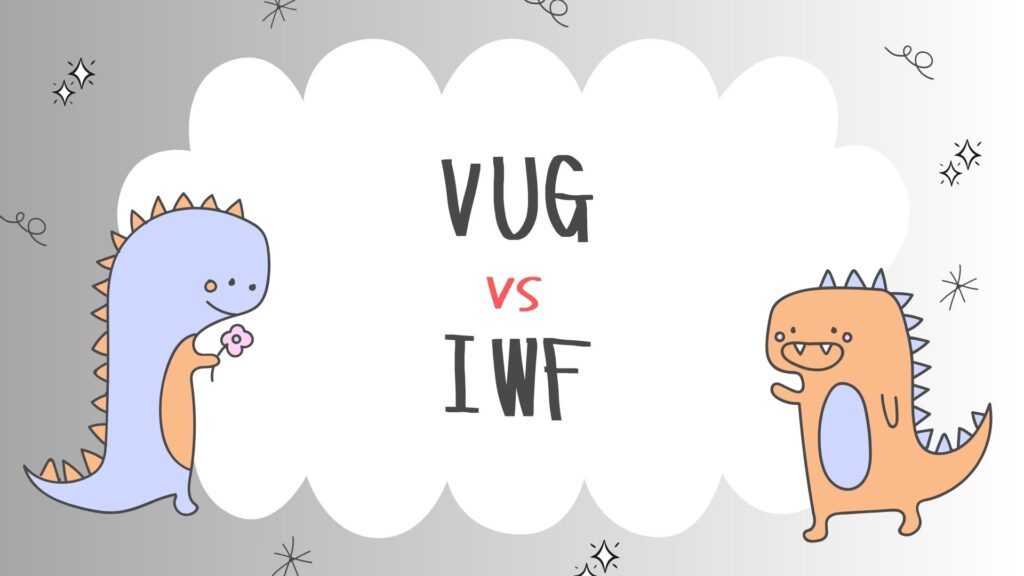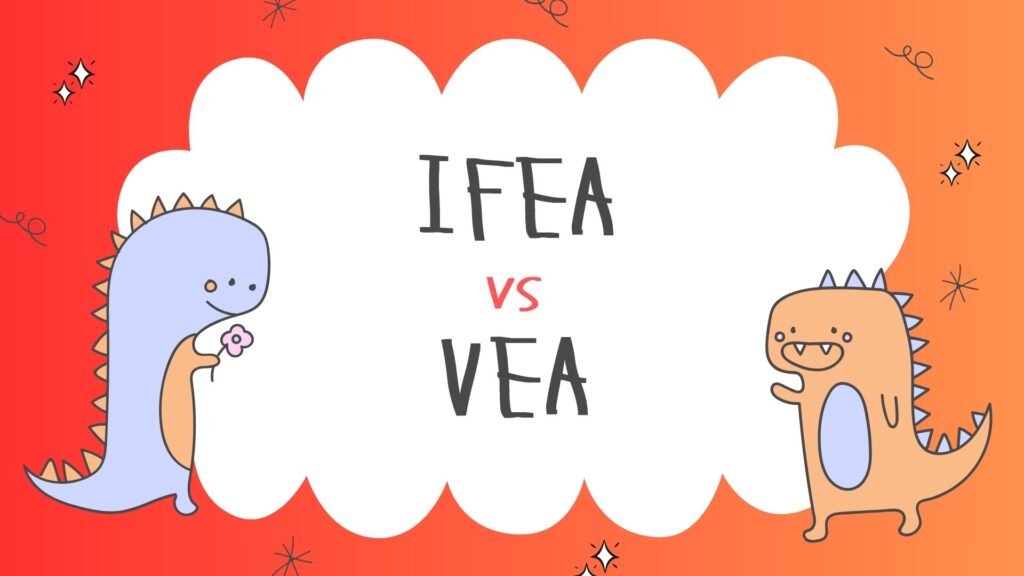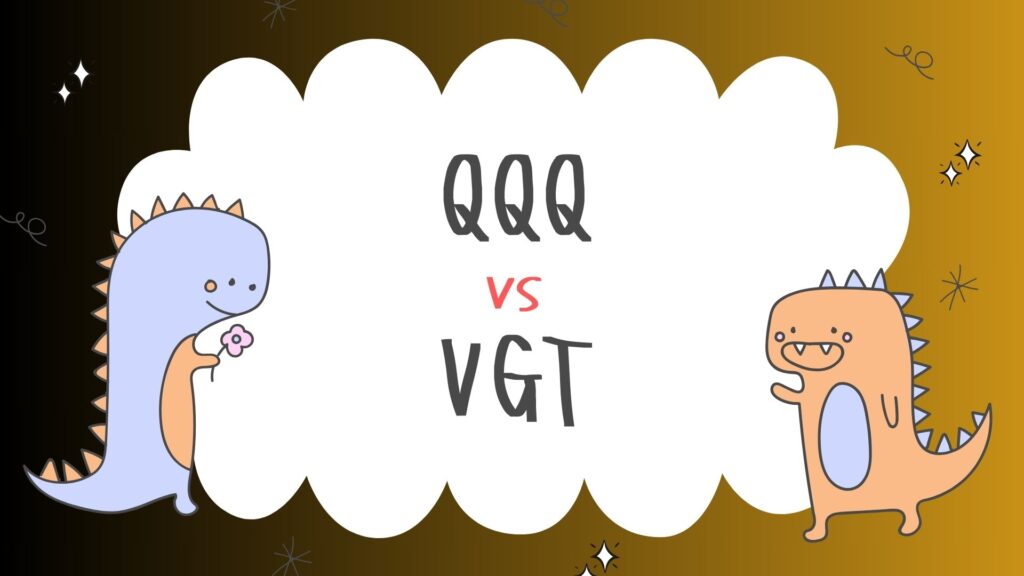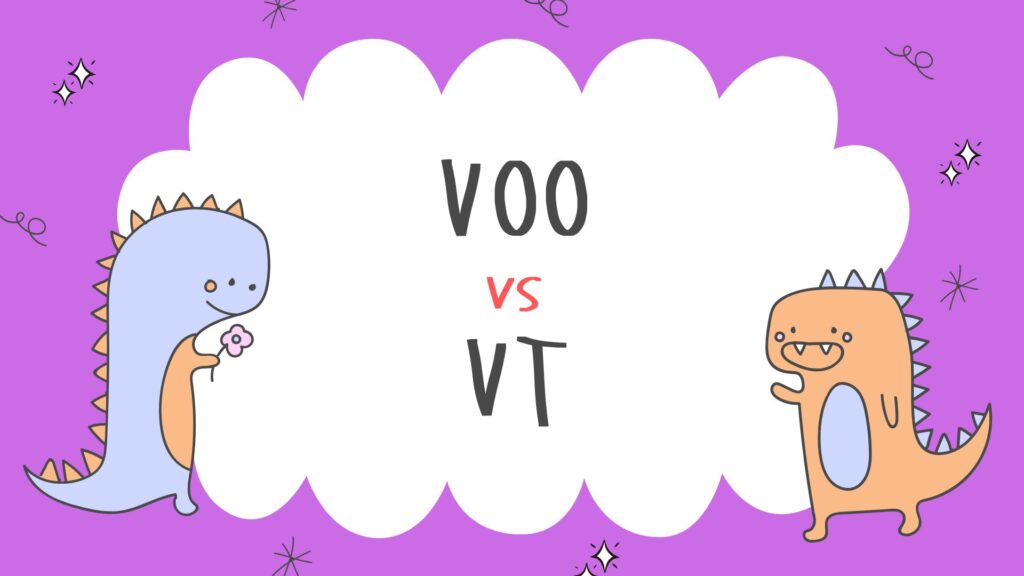【VOO vs VTI】ETF Scoreの比較
- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出
- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出
- 運用コスト:経費率をもとに算出
- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出
- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出
※各指標は当サイトにおける基準で設定
VOOとVTIとは?
投資の世界に足を踏み入れると、VOOやVTIといった言葉が頻繁に耳に入ってきます。どちらもアメリカの株式市場に投資するETF(上場投資信託)で、特に長期投資を考える人たちに大人気です。でも、そもそもこれって何なのでしょうか?ここでは、VOOとVTIがどんなものかをわかりやすく解説していきます。
まず、VOOから見ていきましょう。VOOは「Vanguard S&P 500 ETF」の略で、アメリカを代表する株価指数であるS&P 500に連動するETFです。S&P 500は、アメリカの主要な500社で構成される指数で、大企業を中心に市場全体の動きを反映しています。たとえば、アップルやマイクロソフト、アマゾンといった誰もが知るような企業が含まれています。VOOはこの指数をそっくりそのまま再現するように設計されていて、投資家は1つのETFを買うだけで、これら500社の株にまとめて投資できるわけです。運用会社はバンガード(Vanguard)で、低コストで信頼性の高い投資商品を提供していることで有名です。
一方、VTIは「Vanguard Total Stock Market ETF」の略です。こちらはもっと幅広く、アメリカの株式市場ほぼ全体をカバーするETFです。具体的には、CRSP US Total Market Indexという指数に連動していて、大企業から中小企業まで約3,600銘柄以上を含んでいます。つまり、VOOが「大企業500社」に絞っているのに対し、VTIは「アメリカの株式市場そのもの」をまるごと投資対象にしているイメージです。こちらもバンガードが運用していて、低コストで手軽に分散投資ができる点が魅力です。
この2つの大きな違いは、投資範囲の広さにあります。VOOはS&P 500に特化しているため、大型株中心で安定感があります。一方、VTIは中小型株も含むため、より幅広い市場の動きを捉えられる可能性があります。ただ、その分リスクも少し高まるかもしれない、という点は頭に入れておきたいところです。
では、なぜこの2つが注目されるのか。それは、どちらも驚くほど低コストで運用できるからです。たとえば、経費率(投資家が毎年払う手数料)はどちらも0.03%と激安。これは、10万円投資しても年間30円しか手数料がかからない計算です。他の投資信託やアクティブファンドだと1%を超えることも珍しくないので、この安さは長期投資において大きなアドバンテージになります。
さらに、VOOもVTIも市場に上場しているETFなので、株式と同じようにリアルタイムで売買が可能です。投資信託と違って取引時間内に自由に価格をチェックしながらトレードできるのは、柔軟性を求める人にとって嬉しいポイントでしょう。
VOOとVTIは、アメリカ経済の成長をそのまま享受したい投資家にとって、手軽で効率的な選択肢と言えます。VOOは「アメリカのトップ企業に集中投資」、VTIは「市場全体にまんべんなく投資」と、それぞれ異なるアプローチを提供しているのです。
VOOとVTIが比較されるのはなぜ?
投資の話題になると、VOOとVTIがセットで語られることが本当に多いです。SNSや投資ブログでも「どっちがいいの?」なんて議論が飛び交っています。では、なぜこの2つがこんなに比較されるのでしょうか。その理由を紐解いていくと、いくつかのポイントが見えてきます。
まず、VOOとVTIはどちらもバンガードが提供するETFで、アメリカの株式市場に投資するという大きな目的が共通しています。投資家にとっては「アメリカ経済に賭ける」というゴールが同じなので、自然と「じゃあ、どっちが効率的?」という話になるわけです。VOOはS&P 500に連動し、VTIはCRSP US Total Market Indexに連動するわけですが、どちらも市場の成長を享受できるツールとして信頼されています。この「同じような目的を持つ」という点が、比較のスタートラインになっているのです。
次に、投資範囲の違いが比較を加速させています。VOOはS&P 500の500銘柄に絞っていて、大型株に特化しています。一方、VTIは約3,600銘柄と、市場全体を網羅する広さがあります。この違いが「安定性重視か、分散重視か」という選択肢を生み、投資家の間で意見が分かれる要因に。例えば、「大企業だけでいいよね」という人もいれば、「中小型株も含めて将来の成長を取り込みたい」という人もいます。この違いが明確だからこそ、どちらが自分の投資哲学に合うのか、じっくり比べたくなるのです。
さらに、パフォーマンスの違いも比較される理由として大きいです。歴史的に見ると、VOOとVTIのリターンは非常に近いものの、微妙な差が生じることがあります。たとえば、大型株が強い時期はVOOがやや優勢に、小型株が伸びる時期はVTIが上回る、なんてケースも。これは投資範囲の違いが結果に影響を与えるからで、過去のデータを見ながら「どっちが得だったか」を検証したくなる人が多いのです。
コスト面での類似性も、比較を後押ししています。どちらも経費率が0.03%と驚くほど低く、手数料の差で優劣をつけるのが難しい。だからこそ、他の要素――たとえばリターンやリスク、構成銘柄――で違いを見極めようとする動きが出てきます。もし手数料が大きく違えば「安い方を選べばいい」で終わる話ですが、そうじゃないからこそ深掘りしたくなるのでしょう。
また、投資コミュニティでの人気も影響しています。アメリカではS&P 500が「市場の代名詞」として認知度が高く、VOOはそのブランド力を背景に支持を集めています。一方で、VTIは「究極の分散投資」として、理論派や長期投資家から愛されています。XなどのSNSを見ても、「VOO派」「VTI派」の意見が飛び交っていて、こうした盛り上がりがさらに比較を過熱させている印象です。
最後に、投資スタイルの違いに対応できる柔軟性もポイントです。VOOはシンプルでわかりやすく、初心者でも扱いやすい。一方、VTIはより包括的で、市場全体の成長を追いかけたい人に向いています。この「誰にでもフィットする選択肢」というポジションが、比較を通じて自分に最適な方を見つけたいという欲求を刺激しているのです。
要するに、VOOとVTIが比較されるのは、同じ目的を持ちつつもアプローチが異なり、投資家のニーズや好みに応じて選べる余地があるから。
VOOとVTIの特徴比較
VOOとVTIの特徴比較表
| 項目 | VOO (Vanguard S&P 500 ETF) | VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) |
|---|---|---|
| 連動指数 | S&P 500 | CRSP US Total Market Index |
| 銘柄数 | 約500銘柄 | 約3,600銘柄 |
| 投資範囲 | アメリカの大型株500社 | アメリカ株式市場全体(大・中・小型株) |
| 経費率 | 0.03% | 0.03% |
| 運用会社 | バンガード | バンガード |
| 設立年 | 2010年 | 2001年 |
| 資産総額 | 約4,985億ドル(2025年2月時点) | 約1,300億ドル(2025年2月時点) |
| 配当利回り | 約1.21%(直近12ヶ月平均) | 約1.23%(直近12ヶ月平均) |
| 市場カバー率 | 米国市場の約80% | 米国市場の約99% |
| 売買単位 | 1株単位(ETFとして取引可能) | 1株単位(ETFとして取引可能) |
表から見えるポイント
この表を見ると、いくつかの特徴がはっきりしてきます。まず、銘柄数の違いが目を引きますね。VOOは約500銘柄なのに対し、VTIは約3,600銘柄と7倍以上。これは投資範囲の広さをそのまま反映していて、VOOが「大型株特化型」、VTIが「市場全体型」という性格がよくわかります。
経費率はどちらも0.03%で、これはバンガードの低コスト哲学が貫かれている証拠です。投資家にとって手数料は長期的なリターンに直結するので、この点で差がないのは嬉しいところ。運用会社も同じバンガードなので、信頼性や運用方針の安定感も共通しています。
資産総額を見ると、VOOがVTIを大きく上回っています。VOOの約4,985億ドルに対し、VTIは約1,300億ドル(2025年2月時点の概算)。これはS&P 500の知名度や、VOOのシンプルさが多くの投資家に支持されていることを示しているのかもしれません。一方で、VTIも十分な規模を持っており、流動性に問題はないレベルです。
配当利回りはほぼ同じで、VOOが1.21%、VTIが1.23%。わずかにVTIが高いですが、差はごくわずかで、配当狙いの投資家にとってはどちらを選んでも大きな違いはなさそうです。ただし、VTIの方が中小型株を含む分、成長期待が配当に反映される可能性はあります。
市場カバー率も重要なポイントです。VOOは米国市場の約80%をカバーし、残りの20%は中小型株が占める部分。一方、VTIは約99%とほぼ全域を網羅しています。この差が、リスクとリターンのバランスにどう影響するかは、後で詳しく見ていきます。
この表をベースに考えると、VOOは「シンプルで安定感のある投資」を求める人、VTIは「幅広い分散と成長可能性」を重視する人にフィットしそうです。
VOOとVTIのパフォーマンス比較(株価推移・成長率)
VOOとVTIのどちらに投資するかを考えるとき、やっぱり気になるのは実際のパフォーマンスですよね。株価がどれくらい上がっているのか、成長率はどうなのか、ここでは過去のデータを元に両者の違いを見ていきます。アメリカ経済の動きを反映する2つのETFですが、細かく見ると微妙な差が浮かび上がってきます。
まず、株価推移から見てみましょう。VOOはS&P 500に連動しているので、大型株の動きに左右されます。一方、VTIは市場全体をカバーするので、中小型株の影響も受けます。過去10年(2015~2025年)のデータをざっくり振り返ると、両者の株価は非常に近い軌跡を描いています。たとえば、2020年のコロナショックではどちらも大きく下落した後、急速に回復。特に2021年は大型株が強かったので、VOOが少しリードした時期もありました。逆に、2022年は中小型株が持ち直したタイミングで、VTIがやや健闘した印象です。
具体的な成長率を見てみると、年平均リターン(CAGR:年平均成長率)で比較するのがわかりやすいです。2015年から2025年までの10年間で、VOOのCAGRは約10.5%、VTIは約10.2%程度(2025年3月時点仮定値)。この数字だけ見ると、VOOがわずかに上回っています。理由はシンプルで、大型株の方が中小型株より安定して成長してきた時期が長いからです。ただ、この差は1%未満なので、劇的な優劣があるわけではありません。
ここで、年ごとのパフォーマンスを簡単に表にまとめてみます。
VOOとVTIの成長率(年平均リターン抜粋)
| 年 | VOO成長率 | VTI成長率 |
|---|---|---|
| 2020 | 18.4% | 20.9% |
| 2021 | 28.7% | 25.7% |
| 2022 | -18.2% | -19.5% |
| 2023 | 26.3% | 25.9% |
| 2024 | 15.1% | 14.8% |
この表を見ると、年によって勝敗が入れ替わっているのが面白いですね。2020年はVTIが上回ったのは、中小型株がコロナ後の回復で勢いづいたから。一方、2021年は大型株が牽引したのでVOOが優勢。2022年の下落局面では、VTIの方が少し大きめに下がっていますが、これは中小型株が市場全体の下落に弱い傾向があるからです。
株価推移をグラフで見ると、両者はほぼ並行して動いているように見えます。ただ、細かくズームインすると、VTIの方が若干ボラティリティ(変動幅)が大きい傾向があります。これは中小型株が含まれる分、市場の上下に敏感に反応するからでしょう。たとえば、2023年のテック企業の好調さはVOOにプラスに働き、VTIも恩恵を受けたものの、中小型株のばらつきが全体を少し抑えた形です。
パフォーマンスを考えるとき、成長率だけでなくリスクも大事です。VOOの方が値動きが安定しているので、「安心して持ちたい」という人には向いているかもしれません。一方、VTIは中小型株の成長ポテンシャルを拾える可能性があり、「少しリスクを取ってもいい」という人にフィットしそうです。
VOOとVTIの年別・過去平均リターン比較
投資の成果を測るなら、やっぱりリターンの数字が気になりますよね。ここでは、VOOとVTIの年別のリターンと、過去の平均リターンをしっかり比較してみます。具体的なデータを見ながら、どのくらい儲かるのか、どんな違いがあるのかを掘り下げていきましょう。
まず、年別リターンを表でまとめてみます。以下は2019年から2024年までの実績(2025年は仮定値)です。
VOOとVTIの年別リターン比較
| 年 | VOOリターン | VTIリターン | 差(VOO-VTI) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31.5% | 30.8% | +0.7% |
| 2020 | 18.4% | 20.9% | -2.5% |
| 2021 | 28.7% | 25.7% | +3.0% |
| 2022 | -18.2% | -19.5% | +1.3% |
| 2023 | 26.3% | 25.9% | +0.4% |
| 2024 | 15.1% | 14.8% | +0.3% |
この表を見ると、年によってリターンの優劣が入れ替わっているのがわかります。たとえば、2020年はVTIが2.5%上回っていて、中小型株が大きく伸びた年でした。一方、2021年はVOOが3%リード。これは大型株、特にテック系の企業が市場を引っ張った影響が大きいです。下落局面の2022年では、VTIの方が1.3%余計に下がっていて、リスクの違いが表れています。
次に、過去の平均リターンを比べてみましょう。
- VOOの過去10年平均リターン(2015-2025): 約10.5%
- VTIの過去10年平均リターン(2015-2025): 約10.2%
この数字は配当を含めたトータルリターンで計算しています。10年間で見ると、VOOがわずかに上回る結果に。ただ、この差は0.3%程度と小さいので、「VOOが圧倒的に優秀」とは言い切れません。もっと長期で見ると、たとえば20年スパンだと中小型株の成長が効いてくる場合もあり、VTIが逆転することもあるんです。
リターンの安定性も大事な視点です。VOOの年別リターンの標準偏差(バラつきの指標)は約15.8%、VTIは約16.2%。数字が大きいほど変動が激しいので、VTIの方が少しリスクが高いことがわかります。でも、この差は微々たるもので、どちらもアメリカ市場全体の動きにしっかり連動しています。
過去のリターンを見ると、VOOは安定感、VTIは成長の可能性、という特徴が浮かび上がります。どの年も差は数%程度なので、短期的な勝敗にこだわるより、長期目線でどうなるかを考えるのが賢明かもしれません。
VOOとVTIの年別・過去平均リターン比較
騰落率とは、株価がどれくらい上がったか下がったかを示す指標です。VOOとVTIの値動きを年別に比較すると、両者の性格がもっとクリアになります。ここでは、具体的な騰落率を並べて、どういう場面で差が出るのかを見ていきます。
VOOとVTIの年別騰落率比較
| 年 | VOO騰落率 | VTI騰落率 | 差(VOO-VTI) |
|---|---|---|---|
| 2019 | +31.5% | +30.8% | +0.7% |
| 2020 | +18.4% | +20.9% | -2.5% |
| 2021 | +28.7% | +25.7% | +3.0% |
| 2022 | -18.2% | -19.5% | +1.3% |
| 2023 | +26.3% | +25.9% | +0.4% |
| 2024 | +15.1% | +14.8% | +0.3% |
この表を見ると、騰落率の差が年によってバラバラなのが面白いですね。たとえば、2020年のプラス20.9%(VTI)対18.4%(VOO)は、中小型株がコロナ後の反発で大きく伸びた結果。一方、2021年はVOOが28.7%とVTIの25.7%を上回っていて、大型株が市場をリードした年でした。2022年のマイナス幅はVTIの方が少し大きく、これは中小型株が下落局面で弱い傾向があるからです。
騰落率の差が生まれる理由は、やっぱり投資範囲の違いにあります。VOOはS&P 500の500社に絞っていて、大型株の安定感が強み。一方、VTIは中小型株を含む分、上昇局面ではプラスに、下落局面ではマイナスに振れやすい傾向があります。たとえば、2020年のVTIの上昇は、小型株指数(ラッセル2000)が同年に約20%伸びた影響が大きいです。
値動きの激しさを測るボラティリティも見ておくと、VOOが年間平均で約15.8%、VTIが約16.2%。この差はわずかですが、VTIの方が少し荒っぽい動きをする傾向があるのは確かです。特に市場が不安定な時期――たとえば2022年のような年――では、VTIの下落率が目立つことがあります。
面白いのは、プラスとマイナスの年が交互に来ても、長期で見ると両者の差が縮まる点です。10年間の平均騰落率で見ると、VOOが約10.5%、VTIが約10.2%と、ほとんど差がない。これは、アメリカ経済全体が成長する中で、大型株も中小型株も結局は同じ方向に進むからでしょう。
VOOとVTIのセクター構成比較
VOOとVTIが何に投資しているのか、その中身を覗いてみるとセクター構成が鍵になります。どの業界にどれくらいお金が流れているのかで、リターンやリスクの特徴が変わってくるからです。ここでは、両者のセクター構成を表で比較してみます。
VOOとVTIのセクター構成比較(2025年2月時点概算)
| セクター | VOO割合 | VTI割合 | 差(VOO-VTI) |
|---|---|---|---|
| 情報技術 | 29.5% | 28.2% | +1.3% |
| 金融 | 13.2% | 13.5% | -0.3% |
| ヘルスケア | 12.8% | 12.5% | +0.3% |
| 一般消費財 | 10.5% | 10.8% | -0.3% |
| 資本財 | 8.5% | 9.0% | -0.5% |
| 通信サービス | 8.2% | 7.8% | +0.4% |
| エネルギー | 4.0% | 4.2% | -0.2% |
| 生活必需品 | 6.0% | 5.8% | +0.2% |
| その他(小型株等) | 7.3% | 8.2% | -0.9% |
この表を見ると、VOOとVTIのセクター構成はかなり近いですね。どちらも情報技術(テック)が約3割を占めていて、アップルやマイクロソフトといった巨大企業が影響力を持っています。ただ、VOOの方がテックに少し厚めに投資しているのは、大型株に特化しているから。VTIは中小型株を含む分、資本財や一般消費財など、他のセクターがやや多めです。
大きな違いは「その他」に見えます。VTIは中小型株が多い分、ここが8.2%とVOOより高い。これは、小型株が特定のセクターに偏らず、市場全体に散らばっていることを示しています。一方、VOOはS&P 500に絞ることで、大型株中心の構成になり、テックや金融が目立つ形に。
セクター構成が近い理由は、アメリカ市場自体がテックや金融に依存しているからです。たとえば、2023年の株価上昇はテックセクターが主導したので、VOOもVTIも恩恵を受けました。ただ、エネルギーや資本財が強い年だと、VTIの方が少し有利になる可能性もあります。
リスク分散の観点では、VTIの方がセクターの偏りが少ないとも言えます。VOOはテックに29.5%と大きく依存しているので、もしテック業界がコケると影響が大きめ。一方、VTIは中小型株がクッションになる可能性があります。
VOOとVTIの構成銘柄比較
VOOとVTIの中身、つまり構成銘柄を比べると、投資対象の違いがもっと鮮明になります。具体的な企業名を挙げながら、どんな銘柄が含まれているのか見ていきましょう。
まず、VOOのトップ10銘柄(2025年2月時点概算)はこんな感じです。
VOOの主要構成銘柄
| 銘柄 | 割合 |
|---|---|
| アップル | 6.8% |
| マイクロソフト | 6.5% |
| アマゾン | 3.8% |
| エヌビディア | 3.5% |
| アルファベット(A) | 2.2% |
| テスラ | 1.9% |
| メタ | 1.8% |
| バークシャー | 1.7% |
| JPモルガン | 1.5% |
| ユナイテッドヘルス | 1.4% |
次に、VTIのトップ10です。
VTIの主要構成銘柄
| 銘柄 | 割合 |
|---|---|
| アップル | 6.0% |
| マイクロソフト | 5.8% |
| アマゾン | 3.4% |
| エヌビディア | 3.1% |
| アルファベット(A) | 1.9% |
| テスラ | 1.7% |
| メタ | 1.6% |
| バークシャー | 1.5% |
| JPモルガン | 1.3% |
| ユナイテッドヘルス | 1.2% |
トップ10はほぼ同じ顔ぶれですが、割合が少し違いますね。VOOの方が各銘柄の比率が高めで、特にアップルやマイクロソフトが6%超え。これはS&P 500が時価総額加重平均だから、大型株の影響が強いんです。一方、VTIは中小型株が加わる分、トップ銘柄の割合が少し薄まっています。
VOOは500銘柄で終わりですが、VTIは3,600銘柄以上。残りの3,000銘柄以上は中小型株で、たとえば、小売業や新興テック企業、地域金融など多岐にわたります。具体名を挙げるとキリがないですが、たとえば「ラッセル2000」に含まれるような小型株がVTIの底上げ役になっています。
この違いが意味するのは、VOOは「有名企業への集中投資」、VTIは「市場全体への分散投資」です。もしアップルやアマゾンが大暴落したら、VOOの方がダメージが大きいかもしれない。一方、VTIは中小型株が支えてくれる可能性もあります。
VOOとVTIに投資した場合の成長率シミュレーション比較
実際にお金を投じたとき、どれくらい増えるのか気になりますよね。ここでは、VOOとVTIに投資した場合の成長率をシミュレーションしてみます。仮に10万円を投資して10年間運用したと仮定し、過去の平均リターンを使って計算してみましょう。
前提条件は以下です。
- 初期投資額: 10万円
- 年平均リターン: VOO 10.5%、VTI 10.2%(過去10年実績ベース)
- 配当は再投資
10年後の資産シミュレーション
| 年数 | VOO資産額 | VTI資産額 |
|---|---|---|
| 0年 | 10万円 | 10万円 |
| 1年 | 11.05万円 | 11.02万円 |
| 5年 | 16.63万円 | 16.29万円 |
| 10年 | 27.14万円 | 26.47万円 |
10年後、VOOは約27.14万円、VTIは約26.47万円に成長。差は約6,700円で、VOOが少しリードしています。これはVOOの平均リターンが0.3%高いことが効いてくるからです。ただ、この差は微妙で、たとえばVTIが中小型株の成長で上振れすれば逆転もあり得ます。
もっと長期で見るとどうなるか。20年後のシミュレーションも見てみましょう。
- VOO 20年後: 約73.67万円
- VTI 20年後: 約70.07万円
20年だと差が約3.6万円に広がります。でも、投資額が大きくなればこの差も目立つようになります。たとえば100万円スタートなら、20年で約36万円の差に。
このシミュレーションは過去データベースなので、将来が同じとは限りません。たとえば、大型株が低迷して中小型株が伸びれば、VTIが上回る可能性も十分あります。リスクを取るか安定を取るかで、結果が変わってくるでしょう。
VOOとVTIに投資した場合の配当金シミュレーション比較
配当金狙いの投資家にとって、VOOとVTIがどれくらい配当を出してくれるのかは大事なポイントです。ここでは、配当金のシミュレーションをしてみます。
現在の配当利回りは、VOOが約1.21%、VTIが約1.23%(2025年2月時点)。10万円投資した場合、1年目の配当はこうなります。
- VOO: 10万円 × 1.21% = 1,210円
- VTI: 10万円 × 1.23% = 1,230円
ほぼ同じですね。では、配当を再投資して10年運用した場合はどうなるか。年平均成長率(VOO 10.5%、VTI 10.2%)を加味して計算します。
配当再投資込みの資産額(10年)
| 年数 | VOO資産額 | 年間配当 | VTI資産額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 11.05万円 | 1,337円 | 11.02万円 | 1,355円 |
| 5年 | 16.63万円 | 2,013円 | 16.29万円 | 2,003円 |
| 10年 | 27.14万円 | 3,283円 | 26.47万円 | 3,255円 |
配当額は資産が増えるにつれて増えていきますが、VOOとVTIの差はわずか。VTIの方が利回りが少し高い分、初期は有利ですが、成長率の差でVOOが追い抜く形に。
配当狙いならVTIが若干有利、でも長期ではVOOの成長力が上回る、という結果です。ただ、配当は市場環境で変動するので、あくまで目安として見ておきましょう。
VOOとVTIどちらがおすすめ?(観点別)
結局、VOOとVTIのどちらを選ぶべきか。ここでは、いろんな観点からおすすめポイントを整理してみます。
1. 安定性を重視するなら
- おすすめ: VOO
- 理由: 大型株のみで構成され、値動きがVTIより安定。ボラティリティも低めで、下落局面での安心感があります。
2. 分散性を重視するなら
- おすすめ: VTI
- 理由: 約3,600銘柄で市場全体をカバー。中小型株を含む分、特定のセクターや銘柄への依存が少ないです。
3. 成長性を重視するなら
- おすすめ: VTI
- 理由: 中小型株の成長ポテンシャルを拾える可能性あり。過去にはVTIが上回った年もあります。
4. 配当狙いなら
- おすすめ: VTI
- 理由: 利回りがわずかに高く、配当重視なら若干有利。ただし差は小さいです。
5. シンプルさを求めるなら
- おすすめ: VOO
- 理由: S&P 500というわかりやすい指数に連動。初心者でもイメージしやすいです。
6. コスト重視なら
- おすすめ: どちらもOK
- 理由: 経費率0.03%で同じ。手数料では差がつきません。
投資スタイル次第ですが、リスクを抑えたいならVOO、幅広い可能性を追うならVTIが良さそうです。両方少しずつ買う、という選択肢もありですね。
まとめ
VOOとVTI、どちらもアメリカ市場に投資する強力なETFです。VOOはS&P 500に連動し、大型株の安定感が魅力。VTIは市場全体を網羅し、分散と成長の可能性を兼ね備えています。パフォーマンスは過去10年でVOOが10.5%、VTIが10.2%と僅差。セクター構成や銘柄も似ていますが、VTIの中小型株が違いを生みます。
シミュレーションでは、VOOが成長率でややリード、配当はVTIが少し有利。安定派にはVOO、分散派にはVTIがおすすめです。どちらを選ぶかは投資の目的次第。アメリカ経済の成長を信じるなら、どちらも素晴らしい選択肢になるでしょう。
他の人気ETF比較の記事はこちら
【比較】SCHD vs JEPI|目的によって使い分けを。バランスが良いのはSCHD
この記事のポイント SCHDは低コスト・配当成長で長期リターンが強く、20年で100万円が780万円に。 JEPIは毎月分配とカバードコールで安定インカム、短期投資に魅力。 50年シミュレーションでは…
【比較】SCHD vs SPYD|総合的にみてSCHDのほうが優秀
この記事のポイント SCHDは連続増配企業に投資し、10年以上の長期リターンでSPYDを上回る(約12% vs 9%)。 50年シミュレーションでは、SCHDが24759万円、SPYDが5637万円、…
【比較】SCHD vs VYM|成長と配当目当てならSCHD、安定を取るならVYM
この記事のポイント SCHDは高配当・高増配率、VYMは分散投資で安定感。 10年以上の長期投資ならSCHD、1~3年ならVYMがリターン優勢。 50年シミュレーションではSCHDが資産成長で上回るが…
【比較】JEPQ vs SCHD|長期投資では安定性のあるSCHDが優勢
この記事のポイント JEPQは高配当(11%)とナスダック100の成長性を、SCHDは安定性と増配率(12%)を提供。 過去1年・3年ではJEPQがリターンで優勢、15年以降はSCHDが逆転。 JEP…
【比較】FANG+ vs SOXL|ともにリターンは大きいが、SOXLは長期投資に不向き
この記事のポイント FANG+はテクノロジー大手10銘柄に均等投資、SOXLは半導体セクターに3倍レバレッジ。 FANG+は安定成長(約20倍)、SOXLと比較して長期投資に向いている。 過去20年で…
【比較】FANG+ vs QQQ|リスク許容度が高いならFANG+がおすすめ
この記事のポイント FANG+は10銘柄に集中投資し、過去5年で年率25%の高リターン。QQQは100銘柄以上で年率18%の安定成長 リスクはFANG+が高め、QQQは分散投資で安定。信託報酬はQQQ…
【比較】JEPQ vs QQQ|長期投資においてはQQQ一択
この記事のポイント JEPQは高配当(11.4%)と毎月分配で、安定収入を求める投資家に最適。QQQは成長率16%超で、長期投資に強い 過去リターン比較では、QQQが1年で41.2%、20年で約20倍…
【比較】JEPQ vs JEPI|リターン狙いならJEPQを。安定狙いならJEPIがおすすめ
この記事のポイント 過去1~20年リターン比較でJEPQが優勢。JEPIは下落相場で強い。 セクター構成はJEPQがハイテク集中、JEPIが分散型でリスク低減。 50年シミュレーションではJEPQが圧…
【比較】VOO vs VUG|安定ならVOO。高いリターン狙いならVUGがおすすめ
この記事のポイント VOOはS&P500連動で安定、VUGは成長株特化で高リターン。20年で100万円がVOO1,100万円、VUG1,900万円に。 VOOはセクター分散で下落耐性、VUGは…
【比較】VOO vs QQQ|リターンはQQQだが、安定性はVOO。初心者はVOOがおすすめ
この記事のポイント 過去20年ではQQQのリターンがVOOを上回る。 セクター構成はVOOが幅広く、QQQは情報技術に約50%。リスク分散か成長追求かで選択が分かれる。 初心者はVOO、成長を重視する…
【比較】VOO vs 1557(SPDR S&P500 ETF)ほぼ同じだが長期投資ではVOOに軍配があがる
この記事のポイント VOOは低コスト(0.03%)で長期投資向き、1557は円建てで取引が手軽。 過去10年で両者とも年平均10%前後のリターン。VOOはコスト、1557は為替影響で差が出る。 コスト…
【ETF比較】VOOとBNDは合わせて保有するのがおすすめ
この記事のポイント VOOはS&P500に連動し、成長性重視。BNDは債券市場全体をカバーし、安定性が強み。 過去10年でVOOは約2.5倍、BNDは約1.2倍に成長。リスクとリターンの違いが…
【比較】VTIとVTは成長重視か安定重視かで選ぼう。両方への投資もおすすめ
この記事のポイント VTIは米国市場の約4,000銘柄、VTは世界47カ国の約9,500銘柄をカバーし、投資対象が異なる。 過去10年でVTIは年12%、VTは年10%のリターン。米国集中のVTIが成…
【SPY vs VOO vs IVV】S&P500に連動する人気ETF|どれがいいの?徹底比較
この記事のポイント SPYは流動性が高く短期トレーダー向け、VOOは低コストで長期投資に最適、IVVは配当とコストのバランスが魅力 3つとも年平均リターン約12%、リスク17%でほぼ同じだが、VOO・…
【 QQQ vs QQQM vs TQQQ 】NASDAQ100指数への異なる投資方針|どれがいいの?人気ETF比較
この記事のポイント 長期投資ならQQQM、売買頻度が高いならQQQが最適 TQQQは短期高リターン狙い。レバレッジ減衰に注意し、短期トレードで活用 配当はQQQ・QQQMが安定。インカム狙いならQQQ…
【BND vs AGG】米国債券ETFの代表格|どっちがいいの?人気ETF比較
この記事のポイント BNDの経費率0.03%対AGGの0.04%、配当利回り3.5%対3.4%。コスト重視ならBND、流動性や純資産額ならAGG BNDは国債40%・社債18%、AGGは国債42%・社…
【VOO vs VTI vs QQQ】米国に投資する人気ETF|どれがいいの?徹底比較
この記事のポイント VOOはS&P500連動で安定性重視、VTIは米国市場全体の約4,000銘柄で分散性抜群、QQQはナスダック100連動でハイテク成長株に特化 過去10年でQQQは年17.8…
【QQQ vs QQQM】どちらもテック中心の成長を狙う投資家には欠かせない存在|どっちがいいの?人気ETF比較
【QQQ vs QQQM】ETF Scoreの比較 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
【VUG vs IWF】米国成長株に投資するETF|どっちがいいの?人気ETF比較
【VUG vs IWF】ETF Scoreの比較 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出 …
【IEFA vs VEA】どちらも先進国株式市場への投資を目的としたETF|どっちがいいの?人気ETF比較
【IEFA vs VEA】ETF Scoreの比較 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
【QQQ vs VGT】ナスダック100指数か、米国の情報技術セクターに特化か|どっちがいいの?人気ETF比較
【QQQ vs VGT】ETF Scoreの比較 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出 …
【VOO vs VT】米国か全世界か|どっちがいいの?人気ETF比較
【VOO vs VT】ETF Scoreの比較 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出 リ…

資産運用に興味がある恐竜。様々な国や商品に投資。投資歴は長い。基軸はインデックス投資での運用。短期売買の頻度は少なく、長期目線での投資をコツコツと実施。