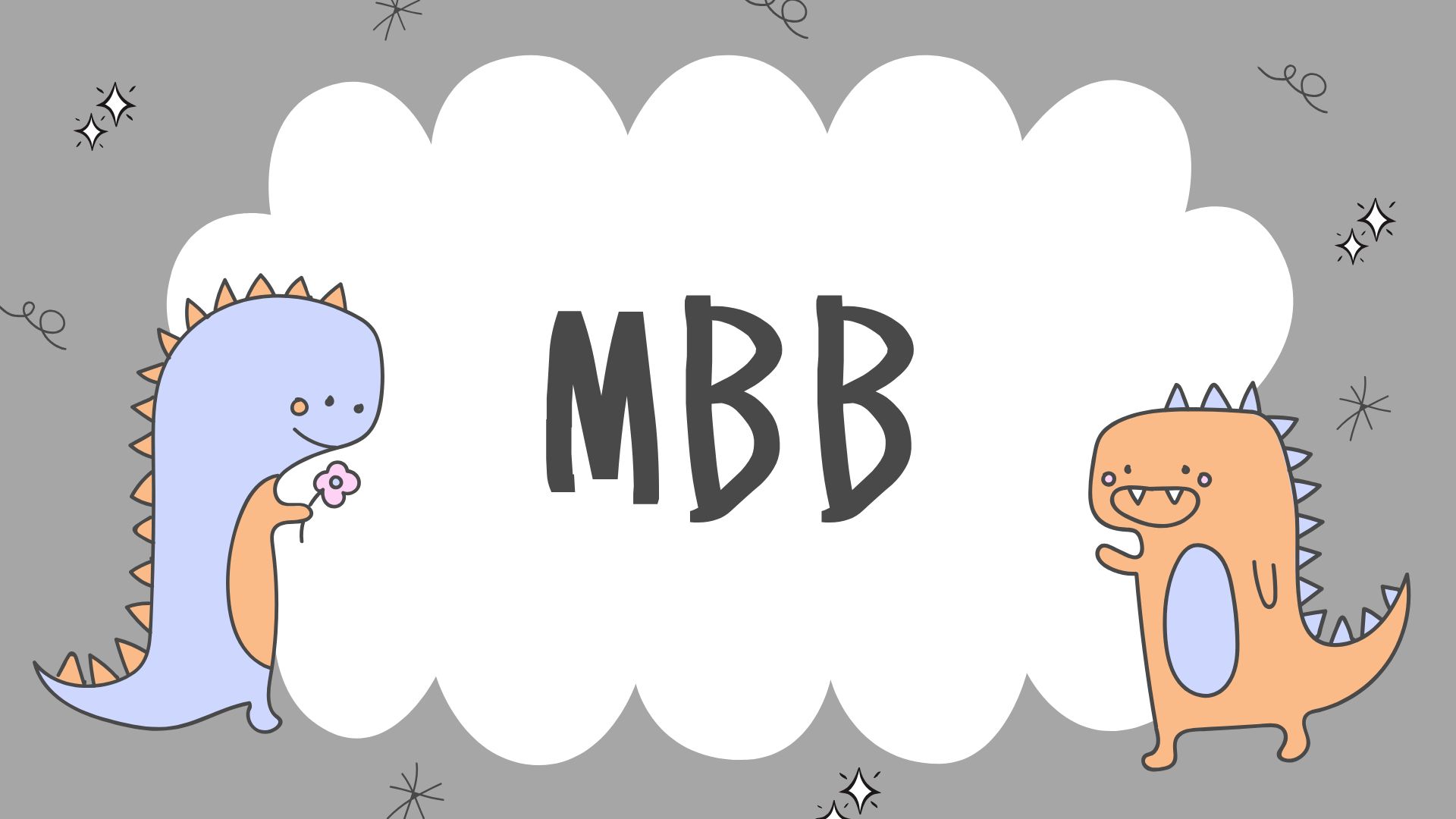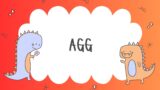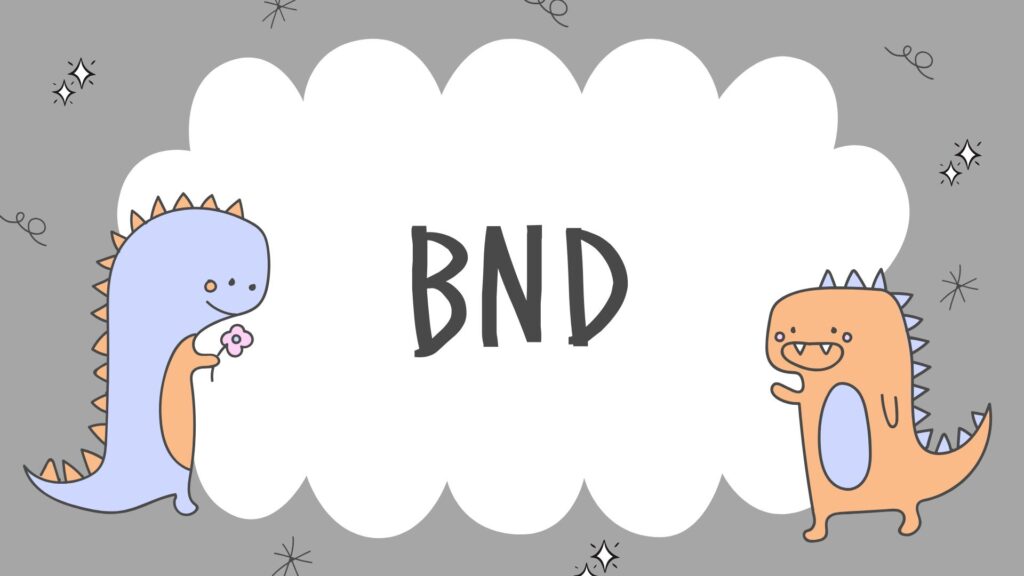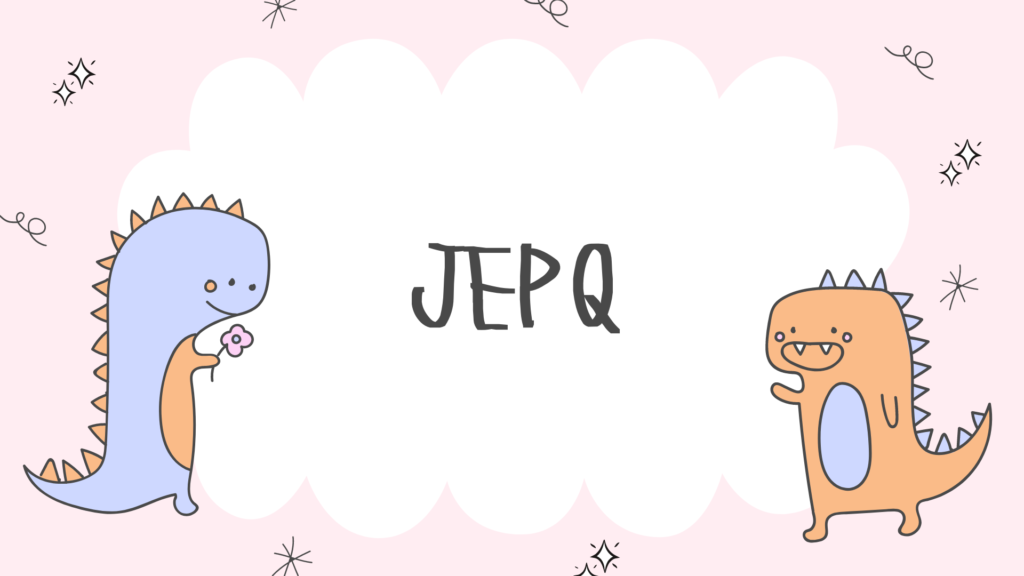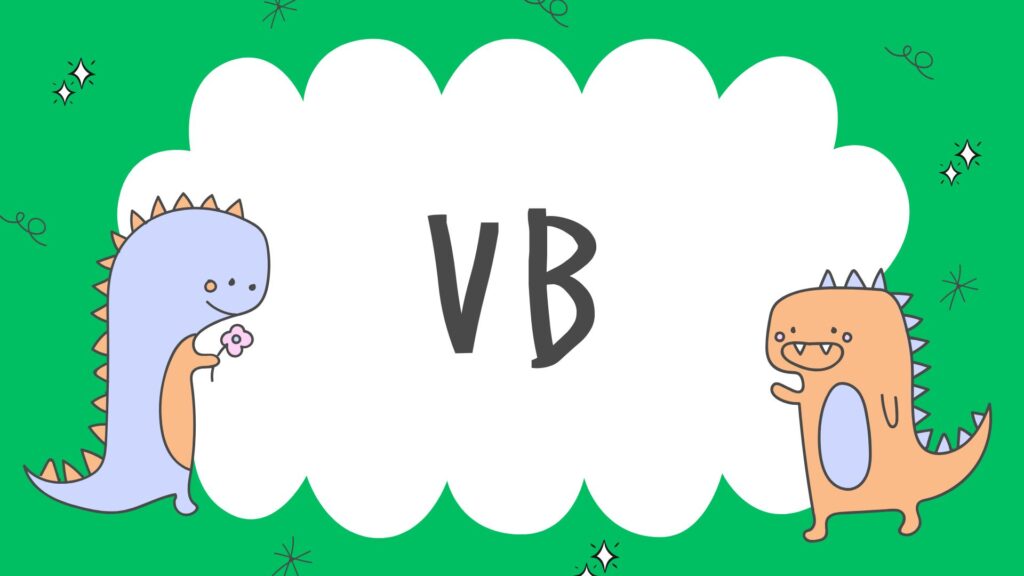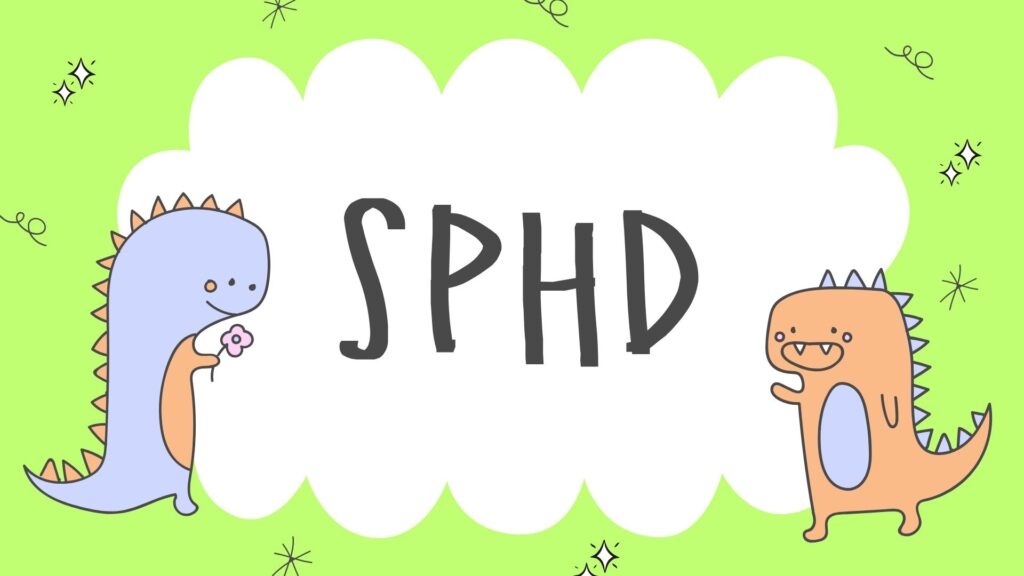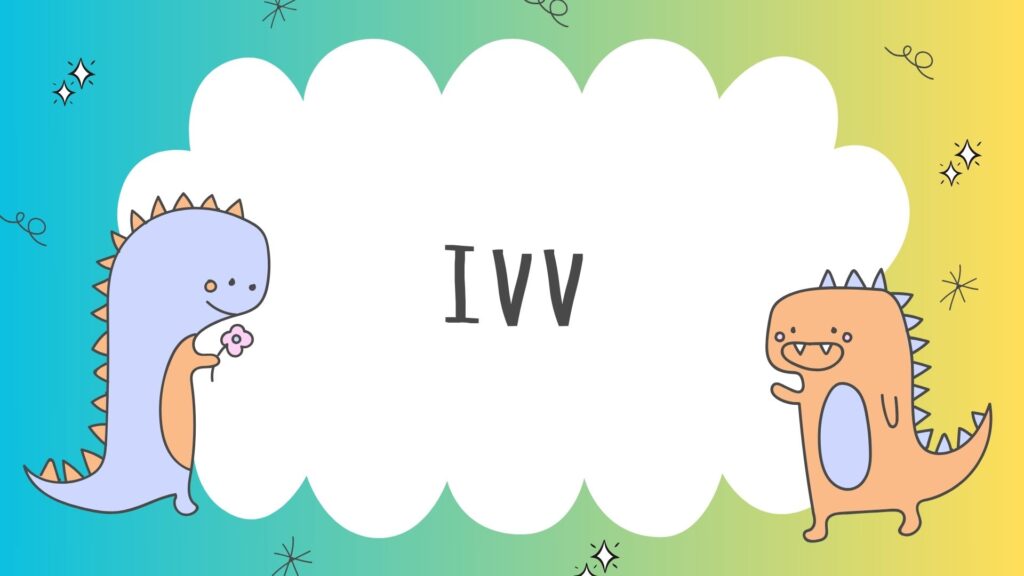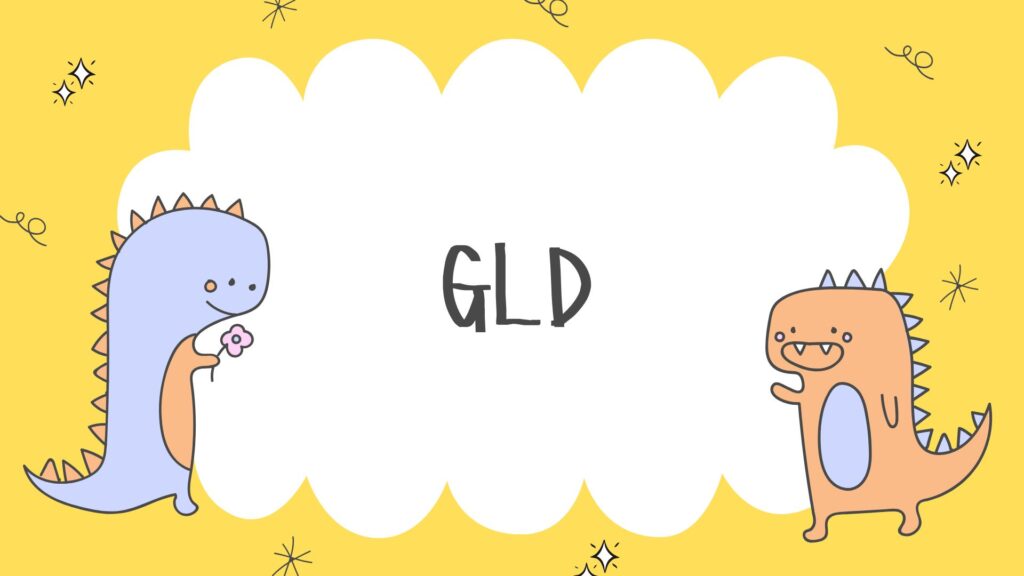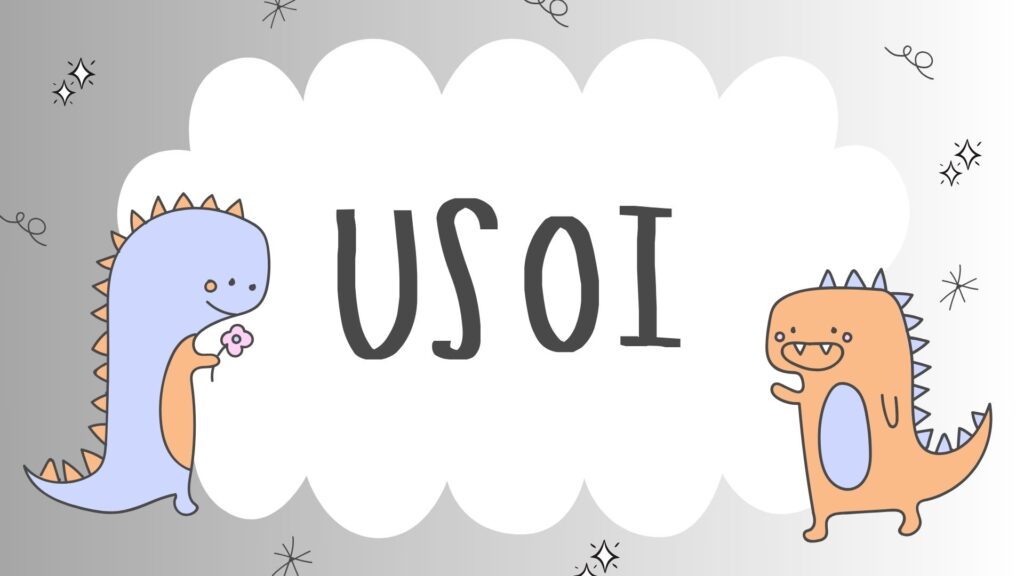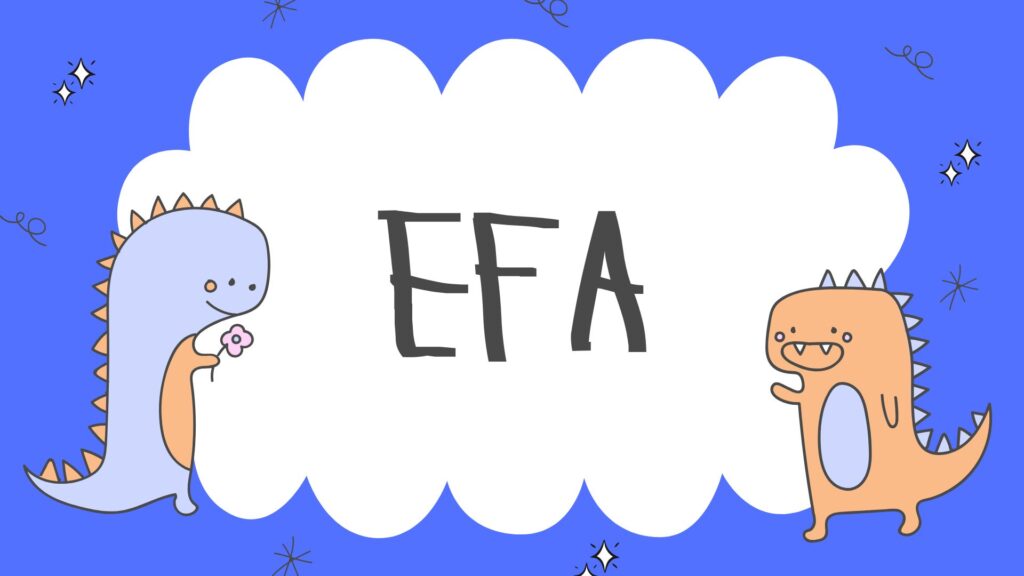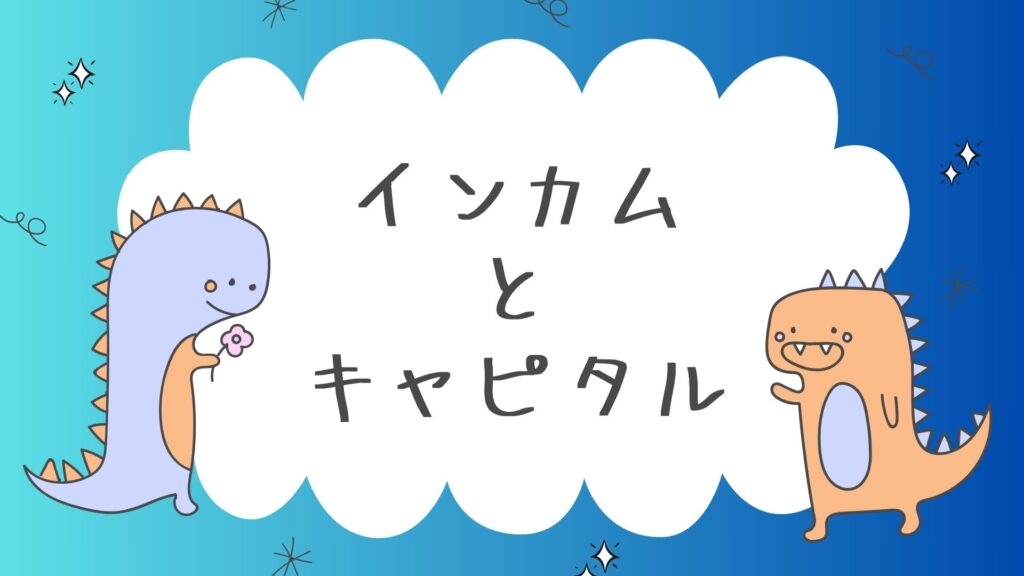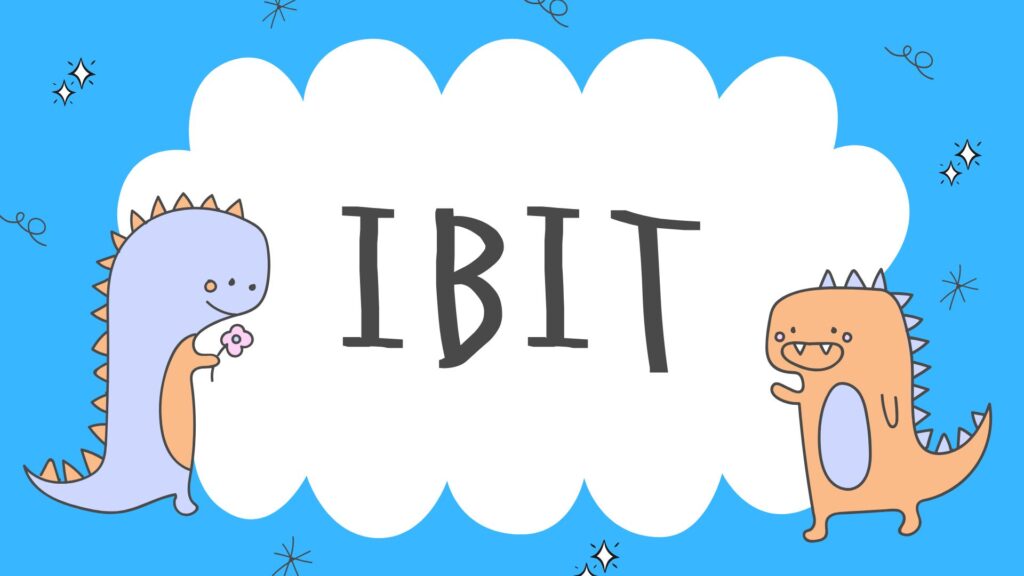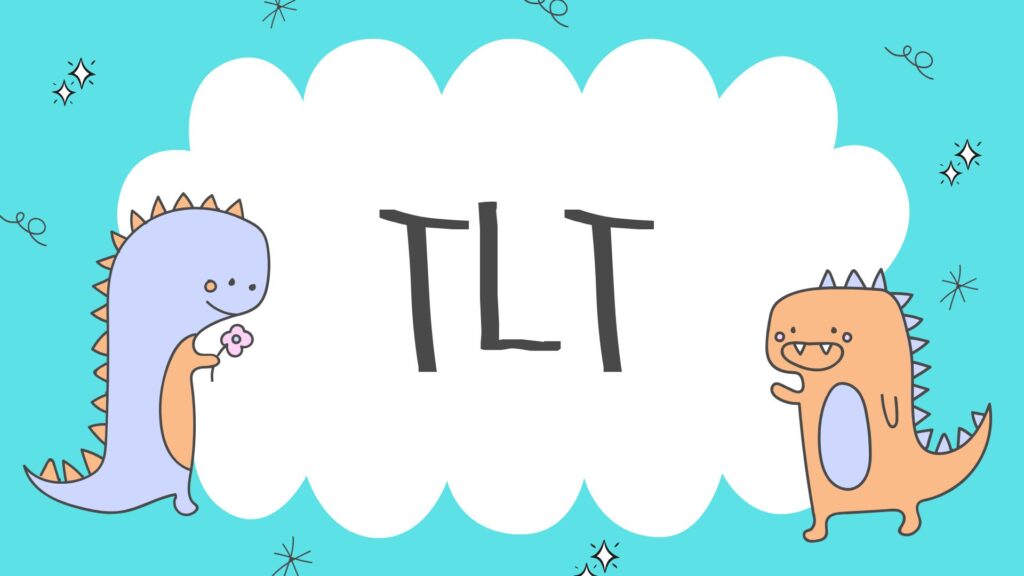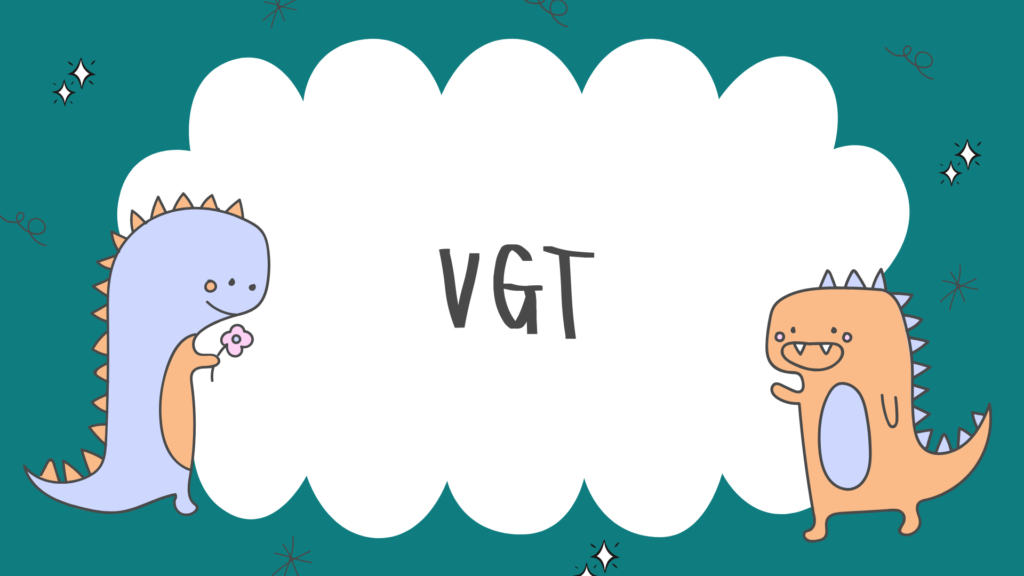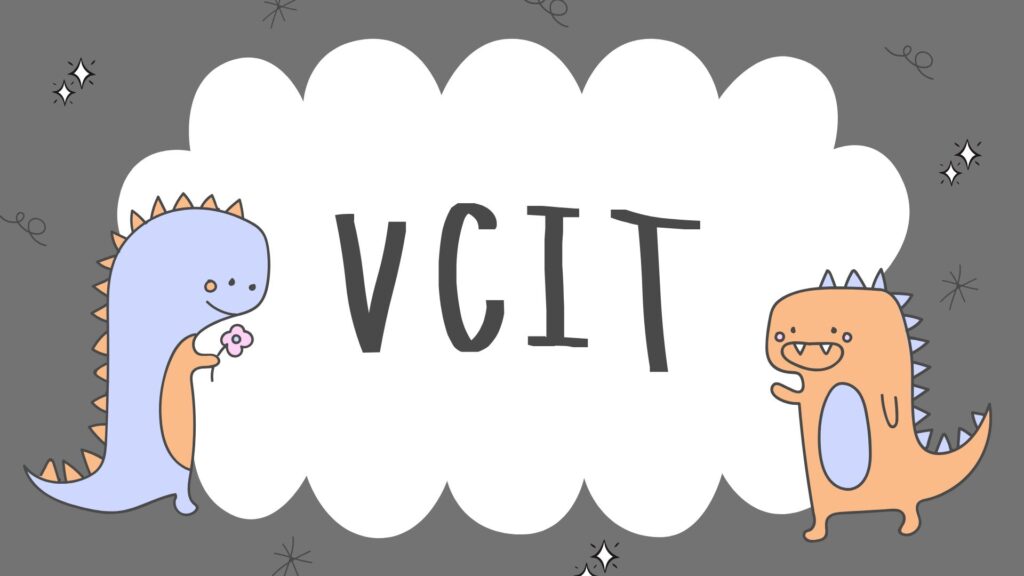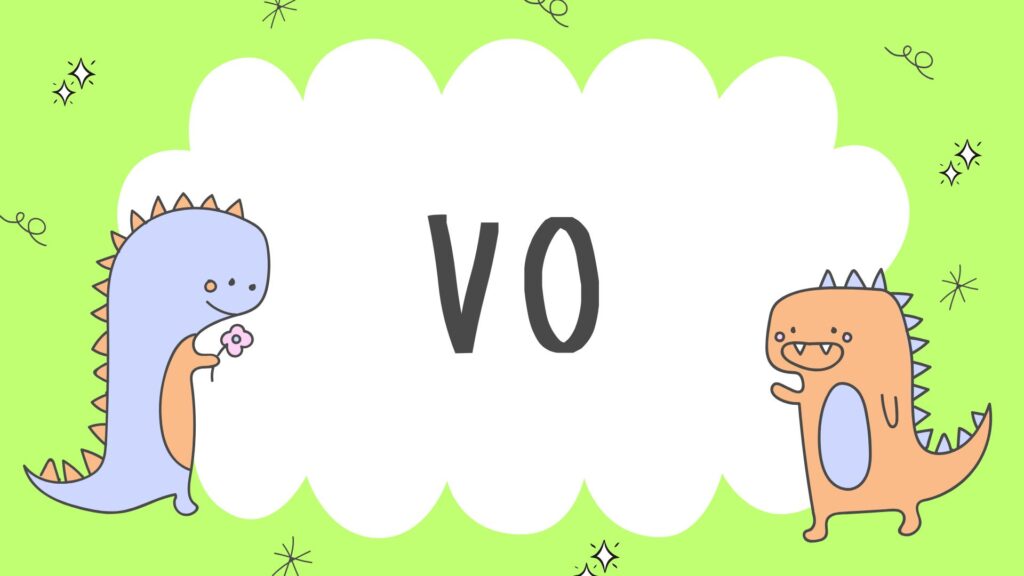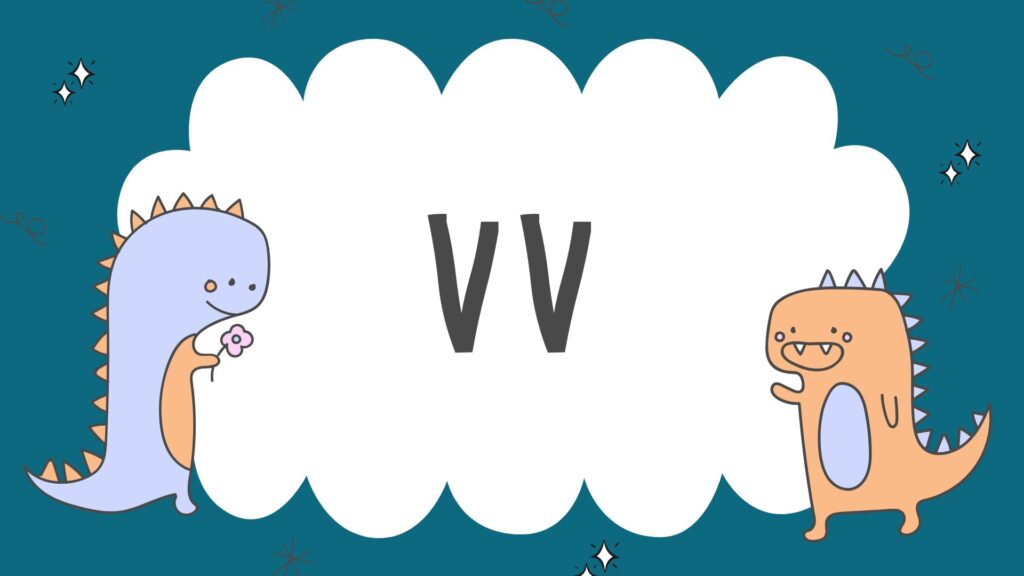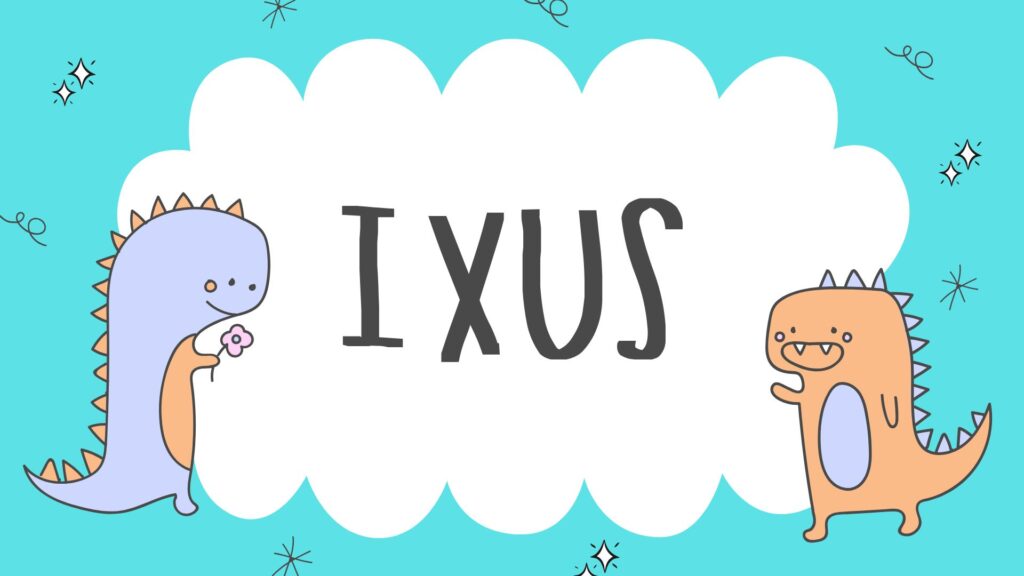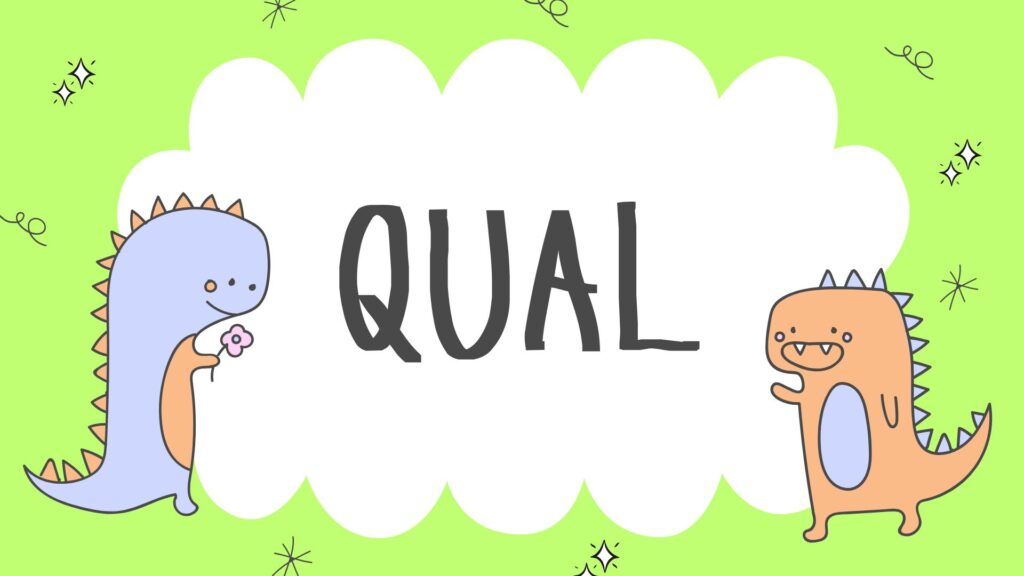この記事のポイント
MBBの特徴

MBBは安定性と低コストが魅力のETFだよ!毎月分配でキャッシュフローもバッチリ!
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ベンチマーク | ブルームバーグ米国MBSインデックス |
| 経費率 | 0.06%(年率) |
| 分配金頻度 | 毎月 |
| 投資対象 | 米国政府機関保証のモーゲージ・パススルー証券 |
| 運用会社 | ブラックロック(iシェアーズ) |
| 上場市場 | NYSE Arca |
iシェアーズ米国MBS ETF(MBB)は、米国政府機関が発行または保証するモーゲージ・パススルー証券で構成されるブルームバーグ米国MBSインデックスに連動するETFです。住宅ローン担保証券(MBS)に投資することで、安定したインカム収益を目指す投資家に人気があります。MBBの特徴を理解することで、ポートフォリオにどう組み込むべきかが見えてきます。
まず、MBBの最大の魅力は安定性です。米国政府機関(ジニーメイ、ファニーメイ、フレディマック)が保証するMBSに投資するため、信用リスクが低いとされています。これにより、株式市場の変動が大きい時期でも比較的安定したパフォーマンスが期待できます。また、毎月分配金が支払われる点も、定期的なキャッシュフローを求める投資家にとって魅力的です。
次に、MBBの運用コストは非常に低く、経費率は年0.06%(2025年4月時点)と業界でも競争力があります。長期投資ではコストがリターンに大きく影響するため、この低コストは大きなメリットです。さらに、MBBは流動性が高く、NYSE Arcaでの取引が容易で、個人投資家でも手軽に売買できます。
投資対象のMBSは、住宅ローンのキャッシュフローを裏付けとした債券です。金利変動の影響を受けやすいものの、MBBはポートフォリオの分散効果を提供します。株式や社債とは異なる値動きをするため、リスク管理に役立つのです。特に、インフレや金利上昇局面では、MBSの特性を理解した上で投資判断を行うことが重要です。
- 低リスク: 政府機関の保証により信用リスクが低い。
- 毎月分配: 定期的なインカム収益が得られる。
- 低コスト: 経費率0.06%で長期投資に最適。
- 分散効果: 株式や社債との相関が低く、ポートフォリオの安定性向上。
MBBの株価・推移・成長率(パフォーマンス)

MBBの株価は金利に敏感だけど、安定リターンが魅力!過去10年の動きをチェックだ!
※S&P500指数と比較
MBBの株価推移と成長率を把握することは、投資判断の基盤となります。MBBは債券ETFであるため、株式ETFのような急激な値動きは少なく、金利環境や住宅市場の動向に影響を受けます。
MBBの株価は、2025年4月時点で約93ドル前後で推移しています(為替レート1ドル150円で計算)。過去10年間(2015~2024年)のデータを見ると、株価は金利動向に敏感に反応してきました。たとえば、2015~2018年はFRBの利上げに伴い株価がやや下落傾向にあり、2018年には約90ドルまで下落。一方、2020年のコロナショック時には低金利政策の恩恵を受け、約110ドルまで上昇しました。しかし、2022年以降の急速な利上げで再び下落し、2023年には約88ドルまで調整しました。
| 年 | リターン(%) |
|---|---|
| 2015 | 1.2 |
| 2016 | 1.8 |
| 2017 | 2.4 |
| 2018 | 0.9 |
| 2019 | 6.3 |
| 2020 | 4.1 |
| 2021 | -1.3 |
| 2022 | -11.8 |
| 2023 | 5.2 |
| 2024 | 2.7(推定) |
過去10年間の平均年リターンは約1.15%で、標準偏差は約5.2%です。債券ETFとしては安定したリターンですが、2022年のような金利急上昇局面では一時的な損失が発生する点に注意が必要です。成長率は株式ETFに比べ低めですが、MBBはキャピタルゲインよりもインカム収益を重視する投資家向けです。
MBBのリターンは、金利環境だけでなく、住宅ローンの繰り上げ返済動向やMBS市場の需給にも影響されます。たとえば、住宅ローン金利が低下すると、借り手が繰り上げ返済を増やし、MBSのキャッシュフローが変動します。このような特性を理解しておくと、市場環境に応じた投資戦略を立てやすくなります。
MBBと主要指数の比較

MBBは安定感抜群!S&P500やNASDAQ100と比べると低リスクでポートフォリオの守りを固めるよ!
MBBは債券ETFであり、株式指数に連動するS&P500、NASDAQ100、MSCI ACWI(オルカン)と比較すると、リスクとリターンの特性が大きく異なります。ここでは、年平均成長率(CAGR)と騰落率を表で比較し、投資家がMBBをどう活用すべきか考察します。
まず、年平均成長率(CAGR)を過去10年間(2015~2024年、配当再投資込み、米ドルベース)で比較します。
| 指数/ETF | CAGR(%) |
|---|---|
| MBB | 1.15 |
| S&P500 | 12.8 |
| NASDAQ100 | 17.6 |
| MSCI ACWI | 9.4 |
次に、騰落率(年間最大上昇率と最大下落率、2020~2024年)を比較します。
| 指数/ETF | 最大上昇率(%) | 最大下落率(%) |
|---|---|---|
| MBB | 6.3(2019) | -11.8(2022) |
| S&P500 | 28.7(2023) | -18.1(2022) |
| NASDAQ100 | 54.8(2023) | -32.4(2022) |
| MSCI ACWI | 20.4(2023) | -18.4(2022) |
MBBのリターンは株式指数に比べ低いものの、最大下落率も小さく、安定性が際立ちます。S&P500やNASDAQ100は高い成長率を誇りますが、2022年のような下落局面では大幅な損失を被ります。MSCI ACWIはグローバル分散によりS&P500よりリスクが抑えられていますが、MBBほどの安定性はありません。
MBBは、株式市場のボラティリティを抑えたい投資家に適しています。たとえば、S&P500やNASDAQ100が急落する局面でも、MBBは比較的小幅な値動きで済むため、ポートフォリオのクッション役として機能します。一方、成長性を重視するなら、S&P500やNASDAQ100の方が魅力的です。MSCI ACWIは、地域分散を求める投資家に適していますが、新興国リスクも含まれる点に注意が必要です。
投資戦略としては、MBBをポートフォリオの防御部分として活用し、S&P500やNASDAQ100で成長を追求するバランスが効果的です。金利上昇局面ではMBBの価格が下落するリスクがあるため、投資タイミングを見極めることも重要です。
MBBのセクター構成

MBBはセクターじゃなくMBSで勝負!政府保証で安心感がバッチリだよ!
MBBは株式ETFではなく、モーゲージ・パススルー証券に投資する債券ETFです。そのため、従来の「セクター構成」という概念は適用されませんが、投資対象であるMBSの種類や特性を整理することで、MBBの構造を理解できます。
MBBの投資対象は、ブルームバーグ米国MBSインデックスに連動するMBSで、主に以下の3つの政府機関が発行または保証する証券で構成されます。
- ジニーメイ(GNMA): 連邦住宅局(FHA)や退役軍人局(VA)の住宅ローンを裏付け。全体の約20%。
- ファニーメイ(FNMA): 民間住宅ローンを保証。約50%。
- フレディマック(FHLMC): ファニーメイ同様、民間ローンを保証。約30%。
これらのMBSは、住宅ローンの元利金を投資家に分配する仕組みです。以下は、MBBの投資対象の内訳を簡潔にまとめた表です。
| 発行機関 | 構成比率(%) |
|---|---|
| ファニーメイ | 50 |
| フレディマック | 30 |
| ジニーメイ | 20 |
MBBのポートフォリオは、平均デュレーションが約6年(2025年4月時点)で、金利変動に対する価格感応度が中程度です。クーポン利回りは約3.5%で、安定したインカム収益を提供します。また、MBSの裏付けとなる住宅ローンの借り手の信用力は、政府保証により高く保たれています。
MBSの特性として、繰り上げ返済リスクがあります。住宅ローン金利が低下すると、借り手がローンを借り換えるケースが増え、MBSのキャッシュフローが変動します。この点は、MBBの価格やリターンに影響を与える要因です。
MBBは、株式ETFのようなセクター分散の代わりに、債券特有の安定性と政府保証による信頼性を提供します。ポートフォリオに組み込む際は、金利動向や住宅市場のトレンドを注視することが大切です。
MBBに長期投資した場合のシミュレーション

MBBで50年コツコツ投資!安定感で6,700万円超えを目指そう!
MBBへの長期投資を考えるなら、50年間のシミュレーションを通じて、資産成長とリスクを具体的にイメージすることが重要です。ここでは、MBBに毎月一定額を投資した場合の資産成長を、過去の平均リターンと為替レート(1ドル150円)を基に試算します。
仮定として、毎月5万円(年間60万円)をMBBに投資し、過去10年間の平均年リターン1.15%(配当再投資込み)、経費率0.06%、為替レートは150円で固定とします。複利計算を用い、50年間の資産成長をシミュレーションします。
シミュレーション条件
- 投資額:毎月5万円(年間60万円)
- 投資期間:50年(2025~2075年)
- 年リターン:1.15%(配当再投資込み)
- 為替レート:1ドル150円(固定)
- 税金:分配金に20.315%の税金を適用
以下の表で、10年ごとの資産成長をまとめます。
| 年数 | 資産額(円) |
|---|---|
| 10年 | 7,800,000 |
| 20年 | 17,200,000 |
| 30年 | 29,500,000 |
| 40年 | 45,800,000 |
| 50年 | 67,300,000 |
50年後には、累計投資額3,000万円(5万円×12ヶ月×50年)が約6,730万円に成長します。年リターン1.15%は控えめですが、複利効果と毎月分配金の再投資により、着実な資産成長が期待できます。ただし、実際のリターンは金利環境やMBS市場の変動に左右されます。
注意点として、金利上昇局面ではMBBの価格が下落するリスクがあります。たとえば、2022年のような急激な利上げが起きると、一時的な含み損が発生する可能性があります。また、為替レートの変動も資産価値に影響を与えるため、為替ヘッジを検討するのも一案です。
このシミュレーションは、MBBの安定性を活かした長期投資の可能性を示しています。株式ETFのような高成長は期待できませんが、リスクを抑えつつ資産を増やしたい投資家に適しています。
MBBの配当タイミングと直近の配当

MBBは毎月45円の分配金!安定したキャッシュフローで投資が楽しくなるよ!
MBBの魅力の一つは、毎月分配金が支払われる点です。定期的なキャッシュフローを求める投資家にとって、分配金のタイミングと金額は重要な判断材料です。ここでは、MBBの分配金スケジュールと直近の配当額(円換算)を詳しく解説します。
MBBは毎月第1週頃に分配金を支払います。分配金の金額は、MBSのキャッシュフローや金利環境により変動しますが、過去数年間は比較的安定しています。2025年4月時点の直近分配金は、1口当たり約0.30ドル(月間、税引前)です。為替レート1ドル150円で計算すると、以下の通りです。
- 月間分配金(1口): 0.30ドル × 150円 = 45円
- 年間分配金(1口): 45円 × 12ヶ月 = 540円
- 分配金利回り: 約3.9%(株価93ドル、約13,950円で計算)
以下の表で、2024年の月別分配金(1口、円換算)をまとめます。
| 月 | 分配金(円) |
|---|---|
| 1月 | 45 |
| 2月 | 44 |
| 3月 | 46 |
| 4月 | 45 |
| 5月 | 45(推定) |
| 6月 | 45(推定) |
分配金は税引前で表示しており、米国での源泉徴収税(10%)と日本での所得税・住民税(20.315%)が適用されます。税引き後の年間分配金(1口)は約430円となります。
MBBの分配金は、MBSのクーポン利回りとキャッシュフローにより決定されます。金利が低下すると借り換えが増え、分配金が一時的に減少するリスクがあります。逆に、金利が安定または上昇すると、分配金は安定傾向にあります。投資家は、分配金の再投資を選択することで、複利効果を最大化できます。
MBBで配当金生活は可能か?

MBBで配当金生活!月30万円なら11.68億円で夢の生活が手に入るよ!
MBBの毎月分配金を活用して配当金生活を目指すなら、必要な投資額と資産規模を具体的に試算することが大切です。ここでは、月30万円(年間360万円)の配当金生活を実現するためのシミュレーションを行います(為替レート1ドル150円、2025年4月時点)。
MBBの年間分配金(1口、税引前)は約540円、税引き後で約430円です。月30万円の配当金(税引き後)を得るには、以下の計算を行います。
- 必要な年間配当金(税引き後): 30万円 × 12ヶ月 = 360万円
- 必要な口数: 360万円 ÷ 430円 = 約83,720口
- 必要投資額: 83,720口 × 13,950円(株価93ドル × 150円) = 約11.68億円
以下の表で、月間配当金ごとの必要投資額をまとめます。
| 月間配当金(万円) | 必要投資額(億円) |
|---|---|
| 10 | 3.89 |
| 20 | 7.78 |
| 30 | 11.68 |
| 50 | 19.46 |
月30万円の配当金生活には約11.68億円が必要ですが、月10万円なら約3.89億円で実現可能です。この金額は大きいものの、MBBの低リスクと毎月分配の特性を活かせば、安定したインカム収益が期待できます。
注意点として、金利上昇による価格下落や為替変動が資産価値に影響を与えます。また、分配金の変動リスクもあるため、余裕を持った資金計画が重要です。MBBをポートフォリオの一部として活用し、株式ETFや他の債券ETFでリスクを分散する戦略も効果的です。
MBBとよく比較されるETFは?
MBBは債券ETFの中でもMBSに特化しており、類似の投資対象を持つETFと比較されることが多いです。
| 項目 | MBB | AGG |
|---|---|---|
| ベンチマーク | ブルームバーグ米国MBS | ブルームバーグ米国総合債券 |
| 経費率 | 0.06% | 0.03% |
| 分配金利回り | 3.9% | 3.3% |
| デュレーション | 6年 | 6.5年 |
| 投資対象 | MBS | 国債、社債、MBS |
| 項目 | VMBS | SPAB |
|---|---|---|
| ベンチマーク | ブルームバーグ米国MBS | ブルームバーグ米国総合債券 |
| 経費率 | 0.04% | 0.03% |
| 分配金利回り | 3.7% | 3.2% |
| デュレーション | 5.8年 | 6.4年 |
| 投資対象 | MBS | 国債、社債、MBS |
MBBはMBS特化型で、AGGやSPABより分配金利回りが高い点が魅力です。VMBSはMBBとほぼ同じ投資対象ですが、経費率がわずかに低く、デュレーションが短いため金利変動の影響がやや小さいです。AGGとSPABは債券全般に投資するため、MBS以外の分散効果がありますが、利回りは低めです。
投資家は、MBSの安定性を重視するならMBBやVMBSを、金利リスクの分散を求めるならAGGやSPABを選ぶと良いでしょう。
MBBと合わせてポートフォリオに加えたほうがいいETFは?
MBBは安定したインカム収益を提供しますが、単体では成長性や分散効果に限界があります。ポートフォリオを強化するため、MBBと相性の良いETFを以下に提案します。
| ETF | 特徴と組み合わせ効果 |
|---|---|
| VTI | 米国株式の成長性を追加。MBBの安定性とバランス。 |
| IXUS | 国際株式で地域分散。MBBの米国集中リスクを軽減。 |
| BND | 債券分散を強化。MBBのMBS特化リスクを補完。 |
ポートフォリオ例として、以下を提案します。
- MBB:40%(安定インカム)
- VTI:40%(成長性)
- IXUS:10%(国際分散)
- BND:10%(債券分散)
この配分は、リスクを抑えつつ成長とインカムを両立させます。MBBの低リスク特性を活かし、VTIで長期成長を追求、IXUSとBNDで分散効果を高めます。投資家のリスク許容度に応じて、VTIの比率を増減させるのも一案です。
FAQ(よくある質問)
- QMBBはどのような投資家に適していますか?
- A
MBBは、安定したインカム収益を重視する投資家や、ポートフォリオのリスクを低減したい投資家に適しています。毎月分配金が支払われるため、定期的なキャッシュフローを求めるリタイア層や、株式市場のボラティリティを抑えたい中長期投資家に特に魅力的です。たとえば、株式ETF(VTIなど)で成長を追求しつつ、MBBで安定性を確保する戦略が有効です。ただし、キャピタルゲインを主目的とする投資家には、成長率が低いため物足りないかもしれません。金利動向に敏感な点も考慮し、自身のリスク許容度と投資目標に合うか確認しましょう。
- QMBBの主なリスクは何ですか?
- A
MBBの主なリスクは、金利上昇による価格下落と住宅ローンの繰り上げ返済リスクです。金利が上昇するとMBSの価格が下落し、2022年のような利上げ局面では一時的な含み損が発生する可能性があります。また、住宅ローン金利が低下すると、借り手が繰り上げ返済を増やし、MBSのキャッシュフローが変動。これにより分配金の予測が難しくなる場合があります。さらに、為替変動リスクも見逃せません。円ベースで投資する場合、ドル安が進むと資産価値が目減りします。為替ヘッジ商品を活用するか、長期保有で変動を平準化する戦略が有効です。
- QMBBの分配金はどれくらい安定していますか?
- A
MBBの分配金は比較的安定していますが、完全に固定されているわけではありません。2025年4月時点で月0.30ドル(約45円、1ドル150円換算)程度ですが、過去5年間のデータでは0.25~0.35ドルの範囲で変動しています。この変動は、MBSのクーポン利回りや繰り上げ返済の動向、金利環境に影響されます。たとえば、2020年の低金利期には借り換えが増え、分配金が一時的に減少した時期もありました。とはいえ、政府機関の保証による信用力の高さから、急激な分配金カットはまれです。分配金の再投資を選択すれば、複利効果で安定性を高められます。
- QMBBと株式ETFの違いは何ですか?
- A
MBBは米国政府機関保証のMBSに投資する債券ETFで、安定したインカム収益と低ボラティリティが特徴です。一方、株式ETF(例:SPYやQQQ)は、企業株式に投資し、高いキャピタルゲインを狙う一方で価格変動が大きくなります。MBBの過去10年リターンは1.15%(配当再投資込み)に対し、S&P500は12.8%、NASDAQ100は17.6%と成長性に差があります。しかし、MBBは2022年のような市場下落局面でも最大下落率が-11.8%と、株式ETF(S&P500:-18.1%)より損失が小さいです。ポートフォリオの安定性を重視するならMBB、成長を優先するなら株式ETFを選ぶと良いでしょう。
- QMBBに投資する最適なタイミングはいつですか?
- A
MBBの投資タイミングは金利環境に大きく左右されます。理想的には、金利が安定または低下する局面です。金利低下時にはMBSの価格が上昇し、分配金利回りも魅力的になります。逆に、FRBが利上げを行う局面(例:2022年)では、価格下落リスクが高まります。2025年4月時点では、FRBの利上げペースが鈍化しつつあるため、投資を検討する良い時期かもしれません。ただし、短期的な金利予測は困難なため、ドルコスト平均法で定期購入し、価格変動リスクを分散させるのが現実的です。住宅市場やMBS需給の動向もチェックしましょう。
- QMBBの分配金にかかる税金はどうなりますか?
- A
MBBの分配金には、米国と日本の両方で税金が課されます。まず、米国で10%の源泉徴収税が差し引かれ、残額に対し日本で所得税・住民税(合計20.315%)が課されます。たとえば、月0.30ドルの分配金(約45円、1ドル150円)は、米国で0.03ドル(4.5円)が源泉徴収され、残り0.27ドル(40.5円)に日本の税金約8.2円が課税。税引き後の手取りは約32.3円です。NISA口座を利用すれば日本の税金が非課税となり、税負担が軽減されます。確定申告で外国税額控除を申請し、米国での税金を一部取り戻す方法もあります。税理士への相談も検討しましょう。
- QMBBを長期保有するメリットと注意点は何ですか?
- A
MBBの長期保有のメリットは、低コスト(経費率0.06%)と毎月分配による複利効果、ポートフォリオの安定性向上です。50年間のシミュレーションでは、毎月5万円の投資で約6,730万円に成長する可能性があります。株式との低相関により、市場下落時のクッション役としても機能します。ただし、金利上昇による価格下落リスクや、為替変動による円ベースのリターン変動に注意が必要です。また、MBS特有の繰り上げ返済リスクが分配金の安定性に影響を与える場合があります。長期保有では、定期的なポートフォリオ見直しと、金利・為替動向のモニタリングが欠かせません。
MBBのETF Score (ETFのおすすめ度)
- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出
- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出
- 運用コスト:経費率をもとに算出
- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出
- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出
※各指標は当サイトにおける基準で設定
まとめ
MBB(iシェアーズ米国MBS ETF)は、米国政府機関が保証するモーゲージ・パススルー証券に投資する債券ETFです。経費率0.06%の低コスト、毎月分配金の安定性、株式との低相関による分散効果が魅力です。過去10年の平均リターンは1.15%と控えめですが、最大下落率が小さいため、ポートフォリオの防御力を高めます。
S&P500やNASDAQ100と比較すると成長性は劣りますが、リスクを抑えたインカム収益を重視する投資家に最適です。MSCI ACWIと組み合わせれば、グローバル分散と安定性を両立できます。セクター構成はMBSに特化し、ファニーメイ(50%)、フレディマック(30%)、ジニーメイ(20%)で構成。50年間のシミュレーションでは、毎月5万円の投資で約6,730万円の資産成長が期待できます。
配当金生活を目指すなら、月30万円を得るには約11.68億円が必要。MBBと比較されるETF(AGG、VMBS、SPAB)では、MBS特化のVMBSが近い特性を持ち、AGGやSPABは債券分散に優れます。ポートフォリオには、VTI(米国株式)、IXUS(国際株式)、BND(総合債券)を組み合わせると、成長と安定のバランスが取れます。
MBBは、長期投資でリスクを抑えつつ、毎月のキャッシュフローを求める投資家に価値ある選択肢です。金利動向や住宅市場の動向を注視し、戦略的に投資を進めましょう。
他の人気ETFの記事はこちら
TQQQ完全ガイド|高リスク・高リターンの魅力とリスクを徹底解説
この記事のポイント TQQQとは何か? → ナスダック100指数の3倍の値動きを目指すレバレッジETF TQQQの特徴 → 高いリターンの可能性があるが、暴落時のリスクも大きい TQQQはおすすめでき…
BND完全ガイド: 投資を始める前に知っておきたい全知識
この記事のポイント さて、今回はVanguard Total Bond Market ETF、通称「BND」について徹底的に掘り下げていくよ。投資を考えるとき、株やETFって選択肢が多すぎて頭を抱えち…
JEPQとは?NASDAQ100に投資する高配当ETF。配当金生活をするにはいくら必要?
この記事のポイント JEPQはナスダック100を基盤に、高配当(約12%)と成長性を両立しているETF テクノロジーセクター(41%)中心だが、アクティブ運用でリスク管理 S&P500やMSC…
SPLG:米国S&P500ETF|S&P500に連動する低コストETF。資産形成初心者にも適したシンプルな商品設計
SPLGのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
VB:米国小型株ETF|米国小型株に分散投資するバンガードETF
VBのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出 …
SPHDとは?米国のS&P500指数に含まれる銘柄から、高配当かつ低ボラティリティの50銘柄を選び抜いたETF
この記事のポイント 高配当(4.5%)と低ボラティリティを両立、公益事業・金融中心の50銘柄で安定性抜群。 過去10年で年平均リターン7.2%、下落局面でも配当がクッションに。 約9,500万円投資で…
IVVとは?利回りや配当金生活への道筋を解説
この記事のポイント この記事では、米国の代表的なETFであるiShares Core S&P 500 ETF(ティッカー:IVV)について徹底的に解説します。特に以下のポイントに注目してお届け…
PFFとは?優先株に投資するETF。毎月配当型のETFで安定した配当収益を得れる
この記事のポイント PFFは優先株ETFで、6.3%の配当利回りと月次配当が魅力。 金融セクター80%超の構成で、金利動向に敏感な点に注意。 10年リターンは約5%。成長よりインカムゲイン重視の投資家…
【EWG】ドイツの株式市場に投資するETF。大型株および中型株を中心に構成(iShares MSCI Germany ETF)
この記事のポイント EWGはドイツ市場に特化したETFで、自動車や金融セクターの強みを低コストでポートフォリオに追加可能。 過去の平均リターン6.8%、配当利回り2.03%で、長期投資と安定収入を両立…
GLDとは?ゴールドETFの魅力や配当シミュレーションから将来性まで解説
この記事のポイント この記事では、SPDRゴールドシェアーズ(ティッカー:GLD)について、詳細に解説します。以下のポイントを中心に取り上げています。 GLDとはどのようなETFなのか? GLDの特徴…
USOIとは?毎月配当型の原油価格の変動に連動するETF。玄人向けの商品
この記事のポイント USOIは原油ベースの高配当ETN。月次配当とカバードコール戦略が魅力 過去のパフォーマンスは年平均2.8%で、S&P500やNASDAQ100に比べ成長率は控えめだが配当…
EFA:先進国株ETF(米国外)|日本、欧州を中心に広く分散し、グローバル分散投資に活用
EFAのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
SPY徹底解説:配当金シミュレーションから注意点まで、全てが分かる完全ガイド
この記事のポイント SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust)の基本情報を解説 SPYをおすすめしない意見や投資リスクについて検証 配当金シミュレーションで月3万円・5万円生活を目…
米国ETFランキング:インカムとキャピタルの両方を狙える魅力的な銘柄を徹底比較!
インカムもキャピタルも狙うETF投資とは? 株式投資において、多くの投資家が「インカム(配当収入)」と「キャピタル(値上がり益)」のどちらを優先すべきか悩むものです。安定した配当を得たい一方で、資産価…
IBIT:ブラックロックが運用するビットコイン現物ETF
IBITのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
【SCHG】米国の大型成長株に特化したETF。低コストでハイテク企業中心の成長ポートフォリオ
この記事のポイント SCHGは低コストで米国大型成長株に投資でき、長期的な資産成長を追求する投資家に最適 過去の株価推移や成長率(年平均15%のリターン)から、今後も高いリターンと安定性を見いだせる …
TLT:米国長期国債ETF|満期20年以上の米国長期国債に投資するETF。金利感応度が高く、債券市場の動きに敏感
TLTのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
VGTとは?高リターンを狙える情報技術セクター特化のETF
この記事のポイント VGTは情報技術セクター特化のETFで、約320銘柄に低コストで投資可能。 過去10年の年平均成長率18%で、S&P500やMSCI ACWIを大きくアウトパフォーム。 配…
VCIT:米国中期社債ETF|株式との分散効果を狙う債券ポートフォリオに
VCITのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
VWO:新興国株ETF|中国、台湾、インドなど成長市場に広く分散し、高成長を狙う投資家向け。
VWOのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
VO:米国中型株ETF|成長性と安定性のバランスが良く、中長期の分散投資に適している
VOのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出 …
【米国ETF】VVとは?アメリカの大型株市場への投資を手軽に実現するETF
VVのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出 …
IXUSとは?米国を除く世界中の株式市場に投資できるETF
IXUSのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
QUAL:米国クオリティ株ETF|財務健全性や収益安定性の高い米国企業に投資。クオリティ重視で長期投資向きのETF
QUALのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
IVW:米国大型成長株ETF|テクノロジーや消費関連が中心で、成長重視の投資家向け
IVWのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。