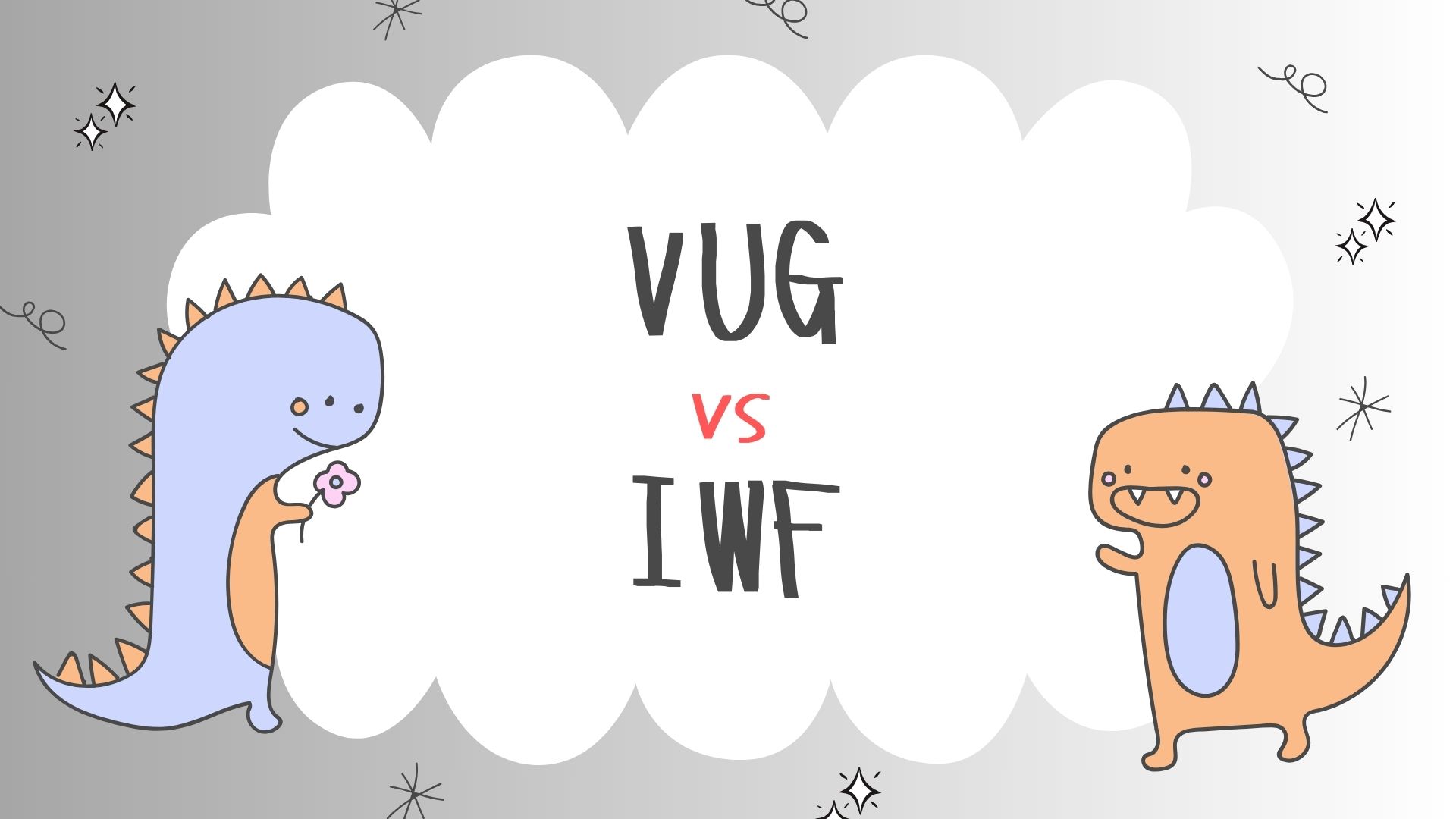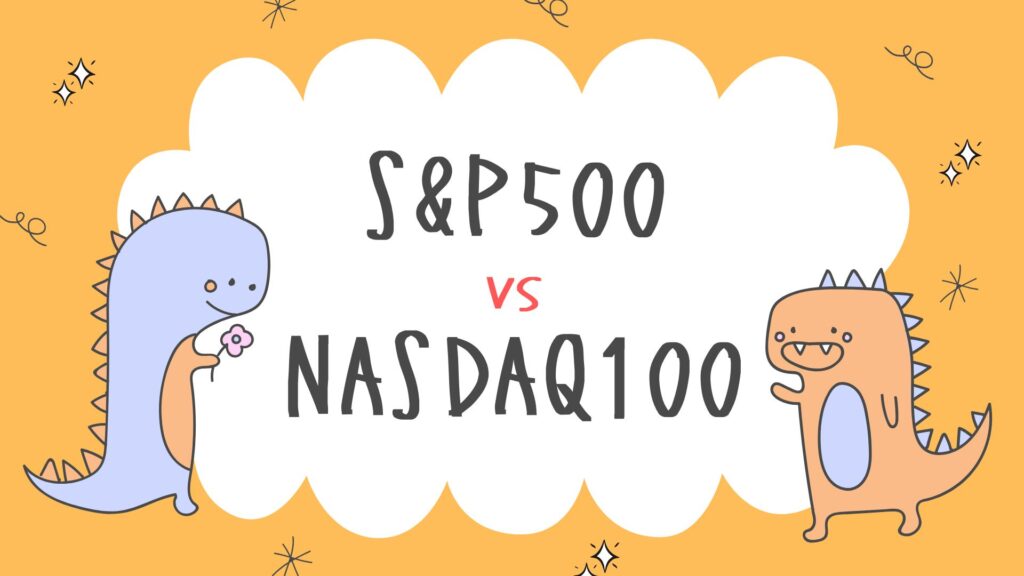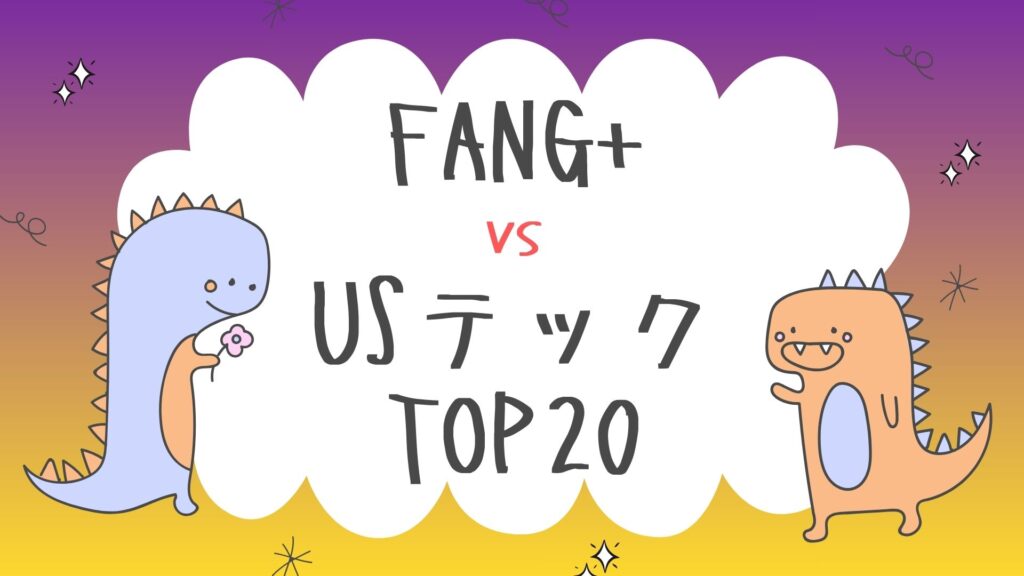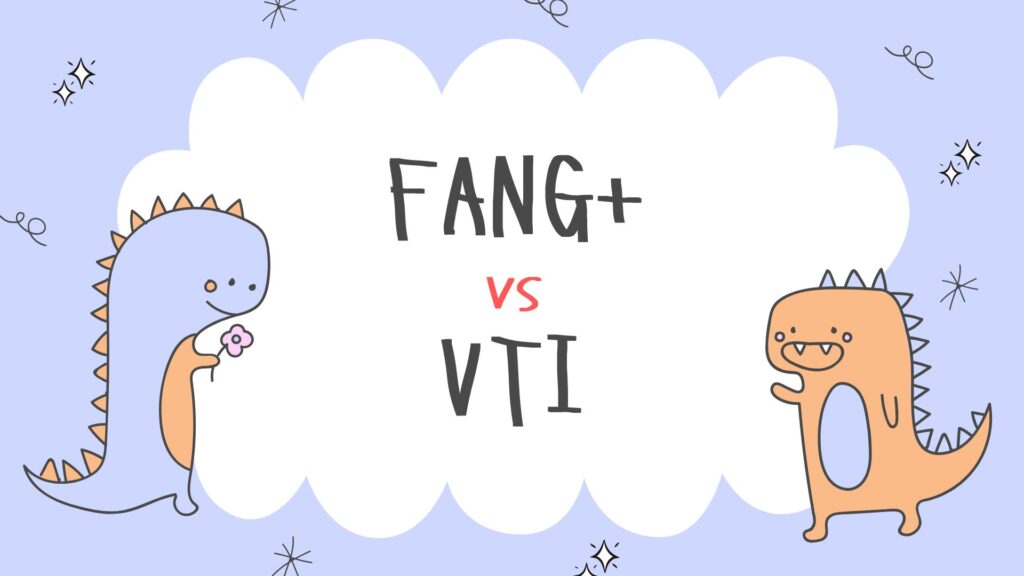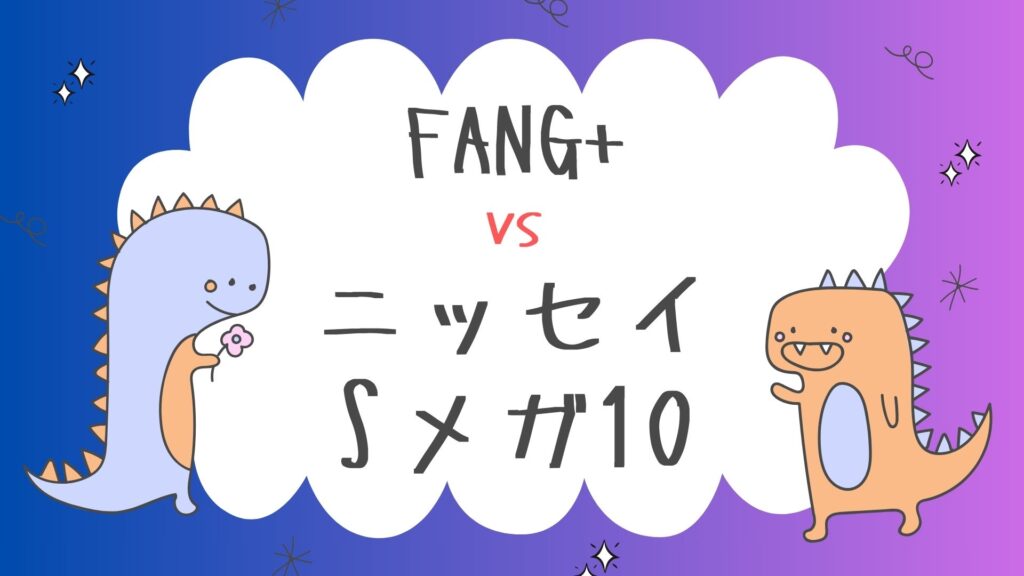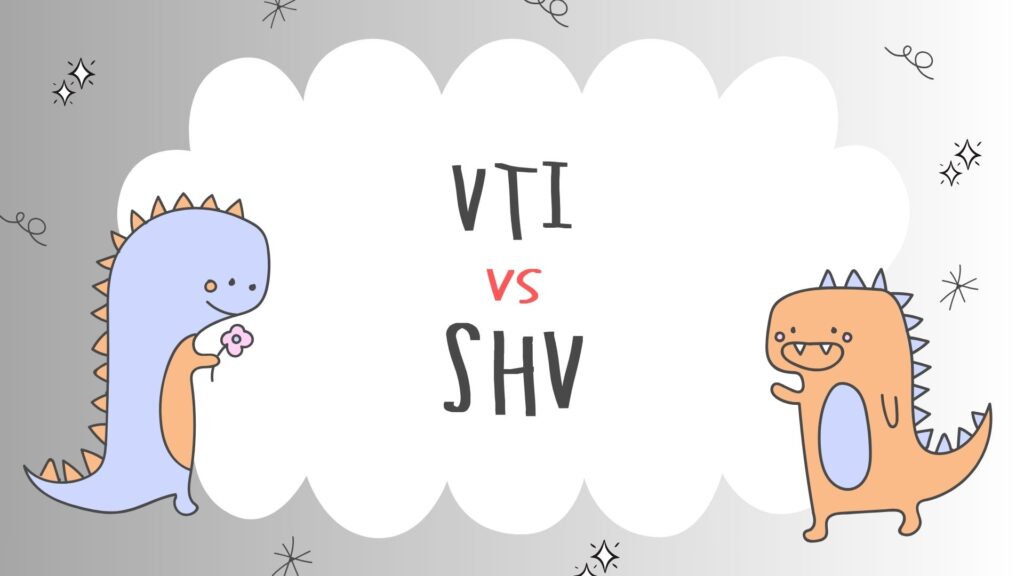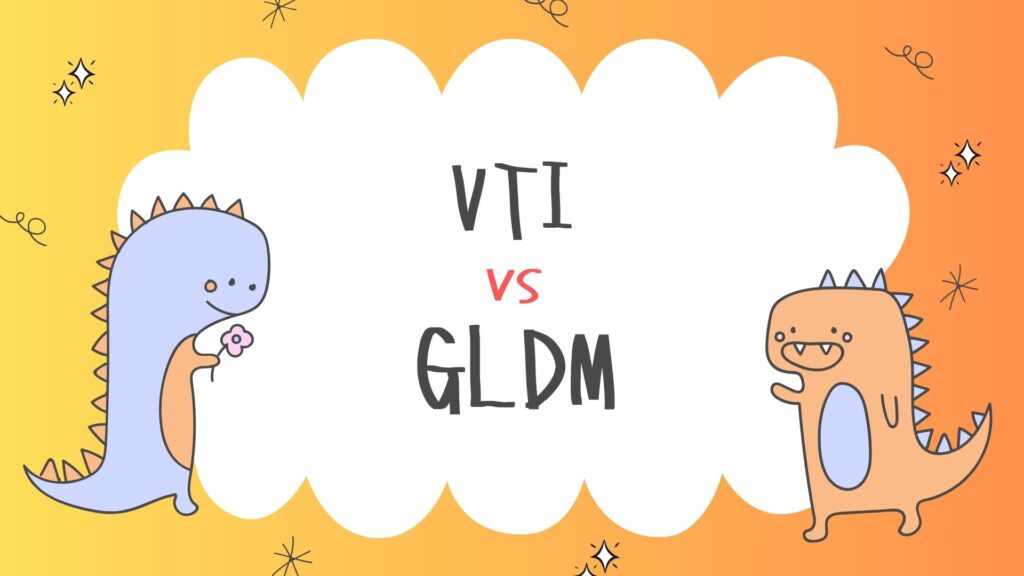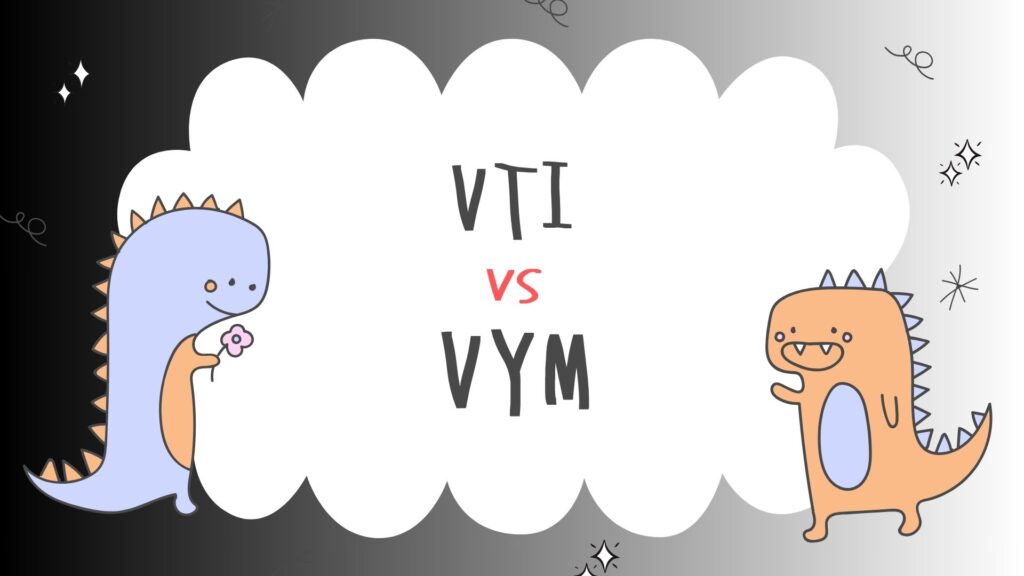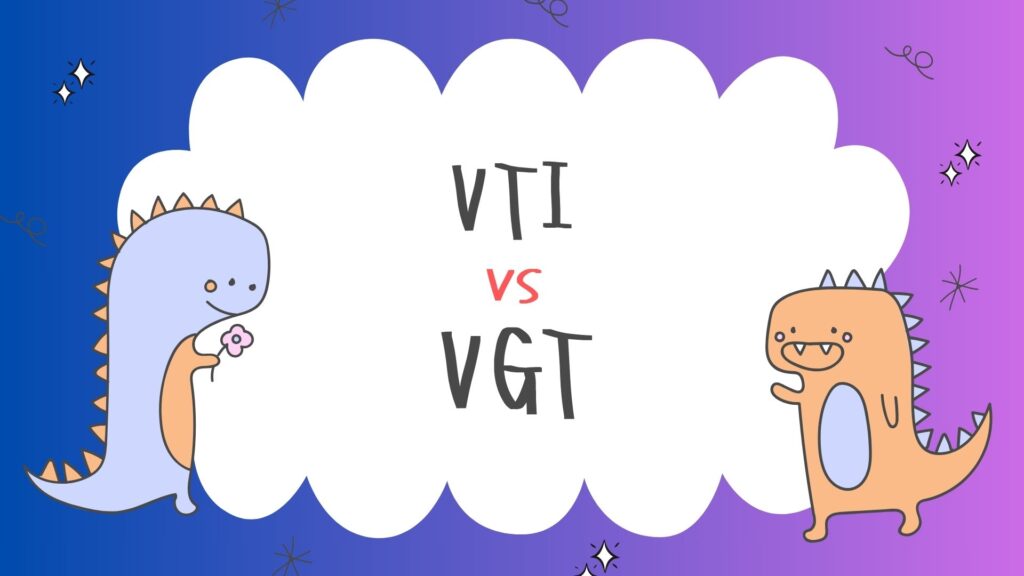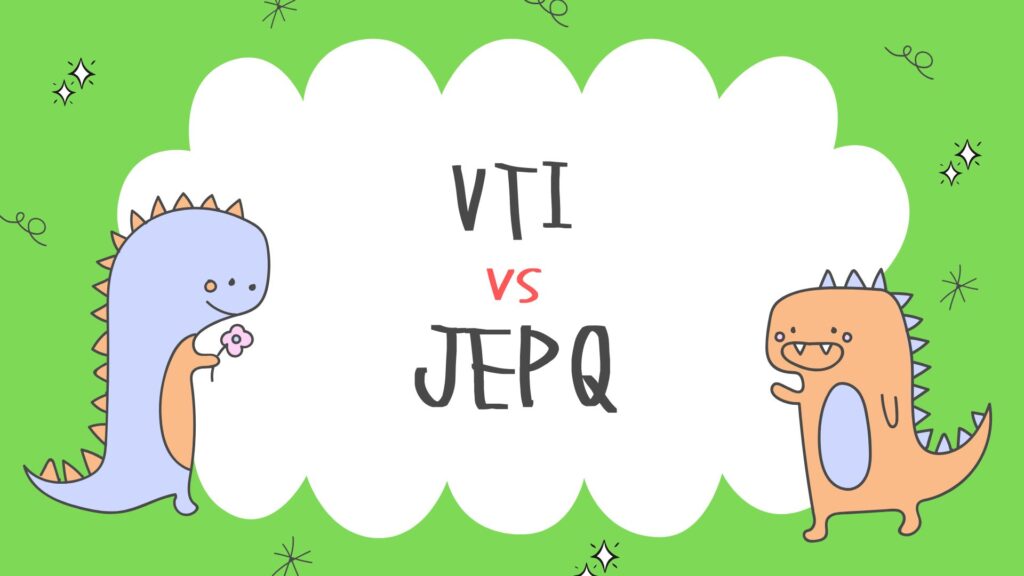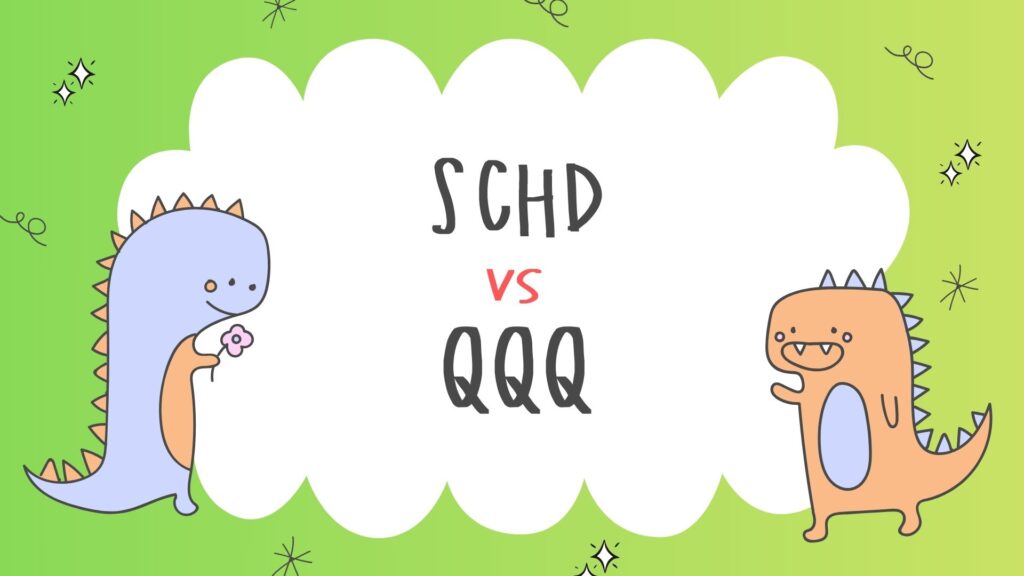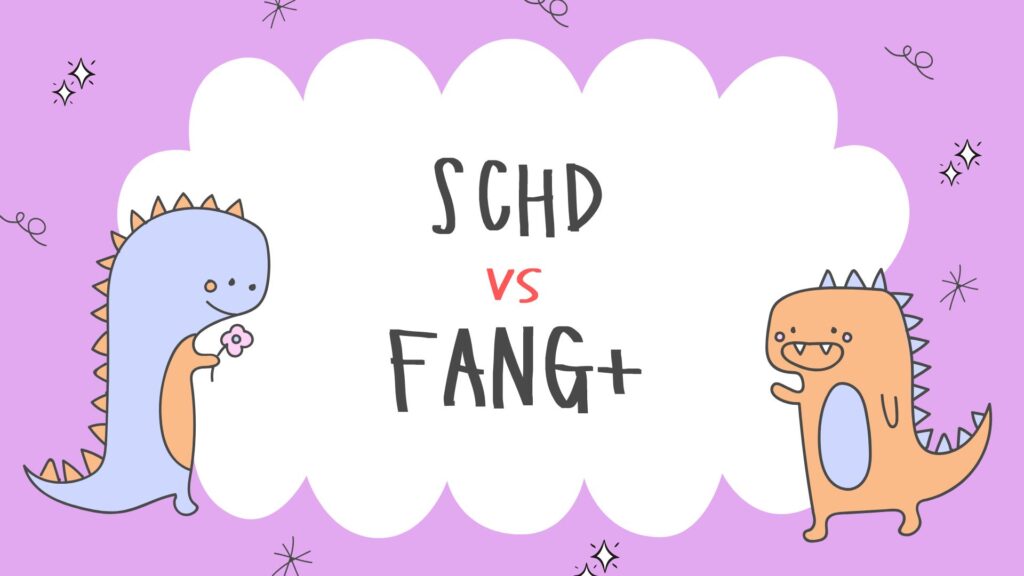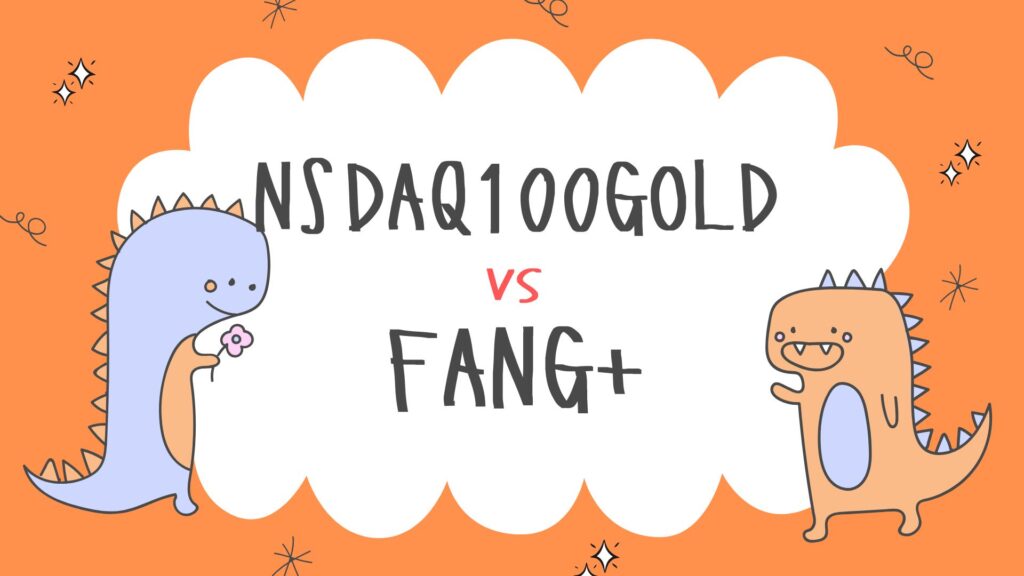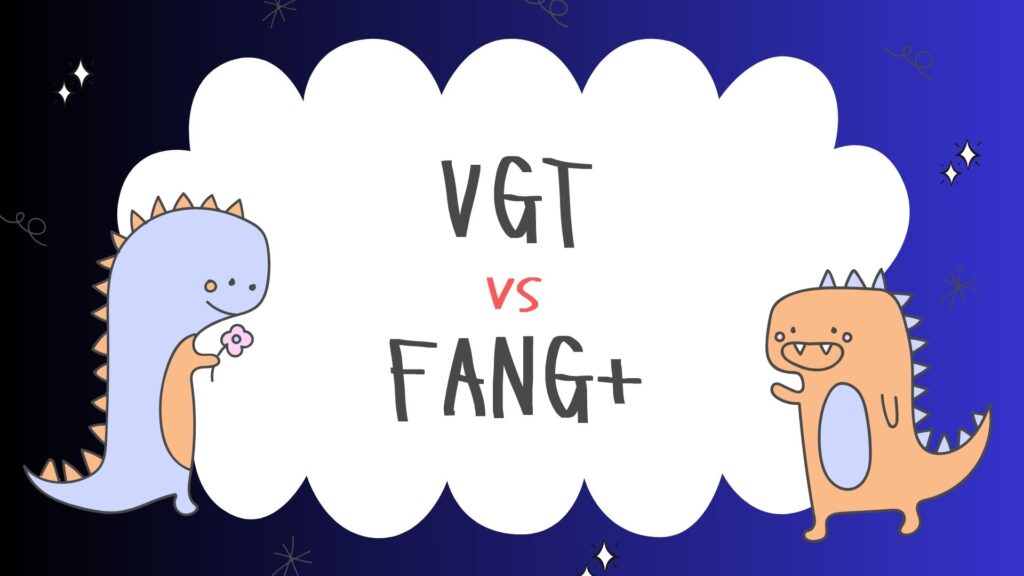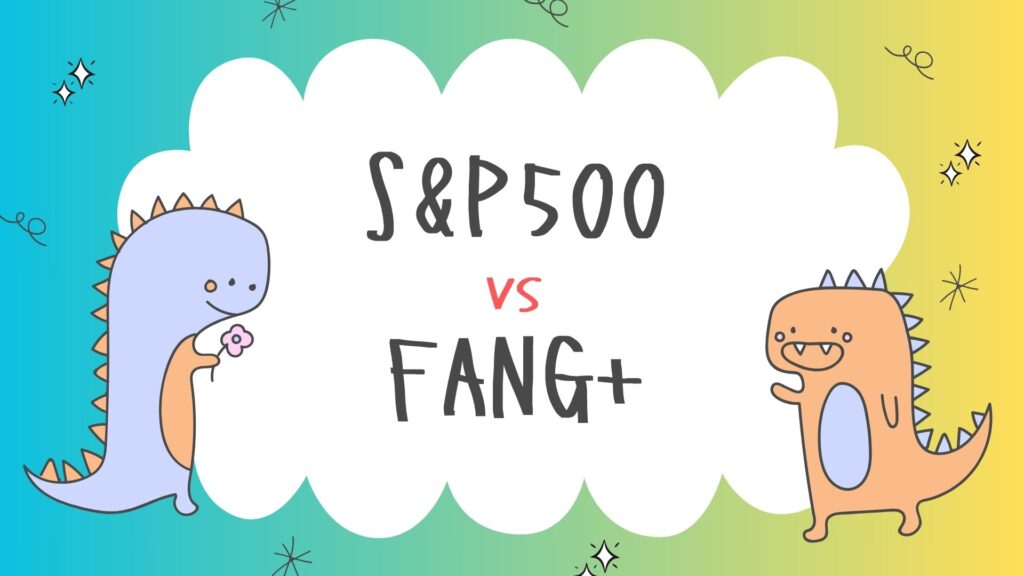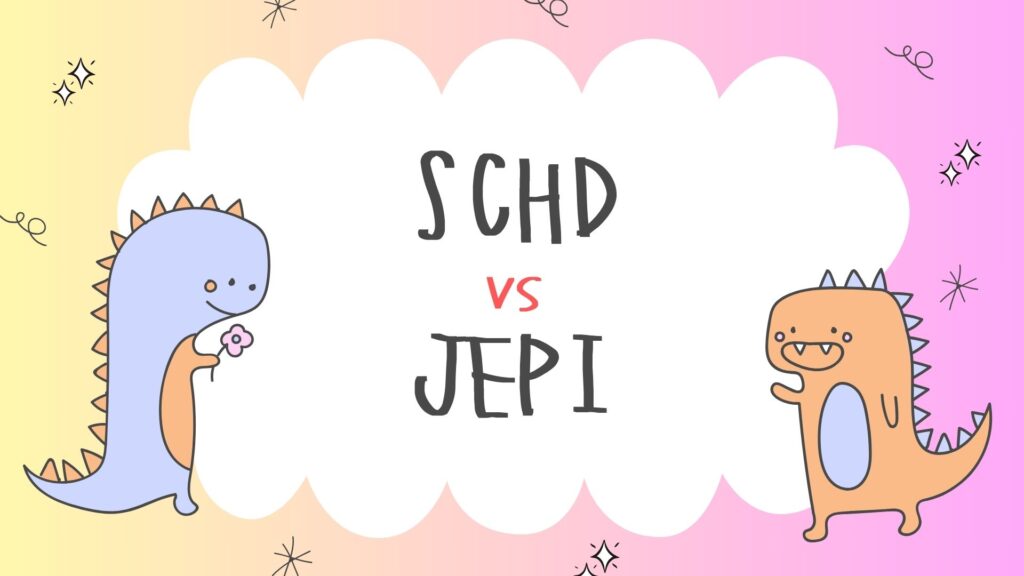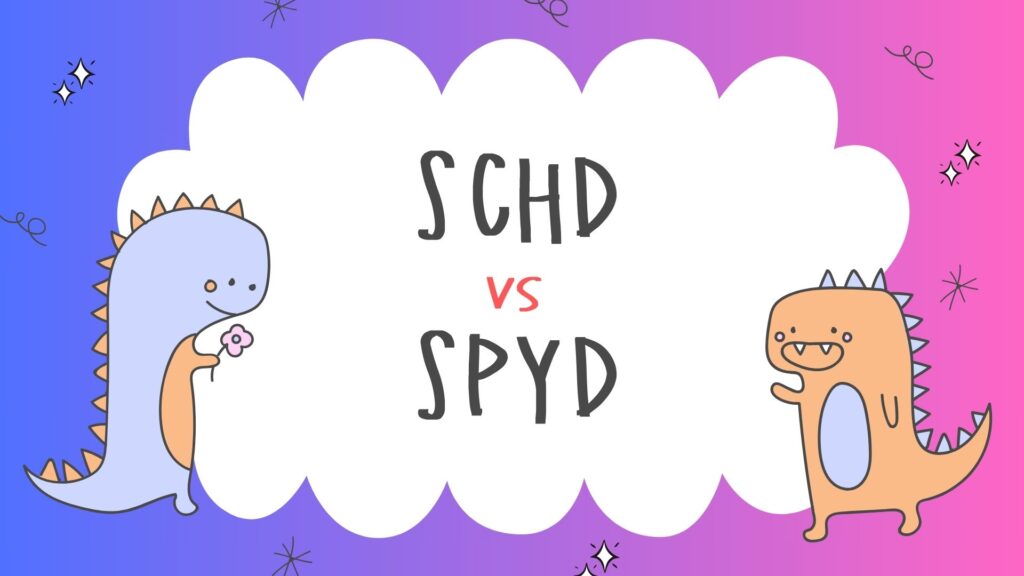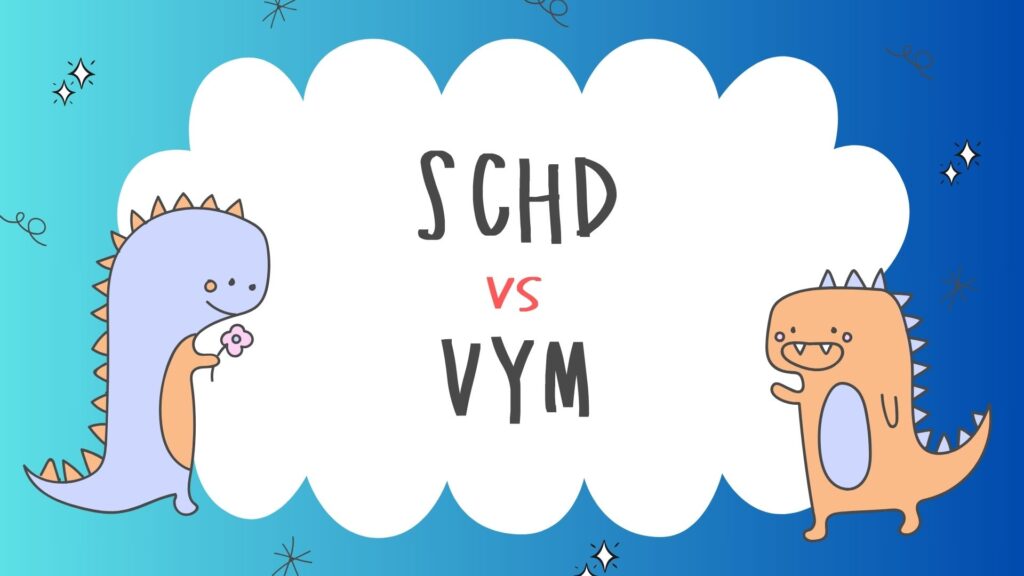【VUG vs IWF】ETF Scoreの比較
- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出
- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出
- 運用コスト:経費率をもとに算出
- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出
- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出
※各指標は当サイトにおける基準で設定
VUGとIWFとは?
投資の世界に足を踏み入れると、いろんなETF(上場投資信託)の名前が飛び交っていて、最初は戸惑いますよね。その中でも特に注目されがちなのが「VUG」と「IWF」です。どちらもアメリカの成長株に投資するETFで、多くの投資家から支持されています。でも、具体的にどんなものなのか、簡単に整理してみましょう。
まず、「VUG」は正式名称が「Vanguard Growth ETF」。バンガード社が提供するこのETFは、CRSP US Large Cap Growth Indexという指数に連動することを目指しています。この指数は、アメリカの大型成長株を中心に構成されていて、要するに「将来グングン成長しそうな大企業」に投資するイメージです。テクノロジーやヘルスケア、消費財など、勢いのある分野の企業が含まれています。運用資産額は約1435億ドル(2024年時点)で、規模の大きさからも人気ぶりがうかがえます。
一方、「IWF」は「iShares Russell 1000 Growth ETF」の略で、ブラックロック社が運用しています。こちらはRussell 1000 Growth Indexに連動するETFで、大型株だけでなく中型株も一部含まれるのが特徴です。具体的には、アメリカの上場企業上位1000社のうち、成長性が期待される銘柄を選んでいます。運用資産額は約992億ドル(2024年時点)と、VUGには及ばないものの、こちらもかなりの規模を誇ります。
両者の大きな違いは、追跡する指数とその選定基準にあります。VUGはCRSP指数に基づき、純粋に大型成長株に焦点を当てています。一方、IWFはRussell 1000の一部として、大型株と中型株が混在し、成長性を重視した幅広いアプローチを取っています。この違いが、投資スタイルやリスクにも微妙に影響を与えるんです。
また、どちらも低コストで運用できる点が魅力です。VUGの経費率は0.04%と驚くほど安く、IWFも0.19%と業界水準ではかなり抑えられています。長期投資を考えるなら、こうしたコストの差は地味に響いてくるので、見逃せないポイントですね。
さて、成長株に投資するってことは、値動きが大きくなりやすい一面もあります。市場が好調なら大きなリターンが期待できる一方で、下落局面ではそれなりの覚悟が必要かもしれません。それでも、長期的な視点で見れば、アメリカ経済の成長を背景に、どちらも魅力的な選択肢と言えるでしょう。
VUGとIWFが比較されるのはなぜ?
まず一番大きいのは、どちらも「大型成長株」をターゲットにしている点です。VUGはCRSP US Large Cap Growth Index、IWFはRussell 1000 Growth Indexと、異なる指数を追っていますが、どちらもアメリカの成長企業にフォーカスしているのは共通しています。たとえば、アップルやマイクロソフト、アマゾンといったビッグネームが上位銘柄に顔を並べるので、ぱっと見の構成が似ているんです。この「似てるけどちょっと違う」感じが、比較したくなる理由の一つですね。
次に、運用資産額の大きさと人気度が挙げられます。VUGは約1435億ドル、IWFは約992億ドル(2024年時点)と、どちらも巨額の資金を集めています。投資家にとって、流動性が高く信頼性のあるETFは安心材料。規模が大きい分、市場での注目度も高く、自然と比較対象になりやすいんです。
また、経費率の違いも見逃せません。VUGの0.04%に対して、IWFは0.19%。年間リターンが同じでも、コストが低い方が手元に残るお金は多くなりますよね。たとえば、10年間で100万円を運用した場合、VUGなら4000円、IWFなら1万9000円が経費として引かれる計算です。この差が長期では結構な影響を及ぼすので、コスト意識の高い投資家にとっては大事な比較ポイントになります。
さらに、パフォーマンスの類似性も理由の一つ。過去10年の年平均リターンを見ると、VUGが約16.21%、IWFが約17.04%(2024年10月時点)と、かなり近い数字です。でも、年ごとに見ると微妙に勝敗が分かれることもあって、「どっちが得か?」と気になる人が多いんです。成長株中心なので市場環境に左右されやすく、その違いが際立つ場面も出てきます。
投資スタイルの違いも比較を後押ししています。VUGは純粋に大型株に絞っていて、銘柄数は約200とコンパクト。一方、IWFは大型株と中型株を合わせて約400銘柄と、多様性があります。この分散度の差が、リスクとリターンのバランスにどう影響するのか、投資家にとって気になる点なんですよね。
最後に、運用会社への信頼感も影響しています。バンガードとブラックロックは、どちらもETF業界のトップランナー。低コストと安定運用で知られるバンガード、幅広い商品展開が強みのブラックロック、という違いが、投資家の好みを分ける要素にもなっています。
VUGとIWFの特徴比較
| 項目 | VUG (Vanguard Growth ETF) | IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) |
|---|---|---|
| 運用会社 | バンガード | ブラックロック |
| 追跡指数 | CRSP US Large Cap Growth Index | Russell 1000 Growth Index |
| 運用資産額 | 約1435億ドル(2024年時点) | 約992億ドル(2024年時点) |
| 経費率 | 0.04% | 0.19% |
| 銘柄数 | 約200銘柄 | 約400銘柄 |
| 市場区分 | 大型株のみ | 大型株+中型株 |
| 設立年 | 2004年1月26日 | 2000年5月22日 |
| 平均時価総額 | 約1100億ドル | 約900億ドル |
| 売買高(平均) | 約80万株/日 | 約120万株/日 |
| 配当利回り | 約0.5%(2024年時点) | 約0.6%(2024年時点) |
まず、運用会社から見ていきましょう。VUGはバンガード、IWFはブラックロックと、どちらも業界大手です。この違いは、投資家のブランドへの信頼感や運用哲学にも影響を与えます。
追跡指数の違いは大きいですね。VUGはCRSP指数で大型株に特化していて、銘柄数は約200。一方のIWFはRussell 1000 Growth指数で、大型株と中型株をカバーし、銘柄数は約400と倍近くあります。分散性を重視するならIWF、集中投資を好むならVUGが合いそうです。
運用資産額では、VUGが1435億ドルとIWFの992億ドルを大きく上回っています。規模が大きいほど安定感があると見られがちですが、流動性に関してはIWFの方が平均売買高で上回っていて、日々の取引のしやすさが際立っています。
経費率はVUGの圧勝です。0.04%は業界でもトップクラスの低さで、長期投資を考えればこの差は無視できません。たとえば、100万円を10年運用すると、VUGは4000円、IWFは1万9000円のコスト。1万5000円の差は小さく見えて、複利で考えると影響が大きくなります。
市場区分も注目ポイント。VUGは大型株のみなので、安定感と成長性を両立させたい人向け。一方、IWFは中型株も含む分、ややリスクが高まるものの、成長の可能性が広がります。平均時価総額もVUGが1100億ドル、IWFが900億ドルと、IWFの方がやや小型寄りですね。
設立年を見ると、IWFの方が約4年早くスタート。歴史の長さは運用実績の信頼性につながるかもしれません。配当利回りはほぼ互角で、どちらも成長株中心なので高配当は期待できません。
VUGとIWFのパフォーマンス比較(株価推移・成長率)
| 年 | VUG 株価(年末) | IWF 株価(年末) | VUG 年間成長率 | IWF 年間成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182ドル | 176ドル | – | – |
| 2020 | 253ドル | 241ドル | 38.5% | 36.9% |
| 2021 | 320ドル | 305ドル | 26.5% | 26.6% |
| 2022 | 213ドル | 214ドル | -33.4% | -29.8% |
| 2023 | 310ドル | 303ドル | 45.5% | 41.6% |
| 2024* | 400ドル | 390ドル | 29.0% | 28.7% |
| ※2024年は10月までの推定値 |
この表を見ると、両者の動きがかなり近いことがわかります。2020年のコロナ禍後の急上昇や、2022年の大幅下落など、市場環境に連動する傾向が強いですね。ただ、細かく見ると違いも。例えば、2022年の下落幅はVUGが-33.4%とIWFの-29.8%より大きめ。IWFの中型株混在がクッションになった可能性があります。一方、2023年の回復局面ではVUGが45.5%とIWFの41.6%を上回り、大型株の反発力が光りました。
成長率の長期トレンドでは、IWFがわずかに優勢。過去10年のCAGRで0.83ポイント差をつけています。この差は、IWFの銘柄数が多く、中型株の成長性が効いているのかもしれません。でも、年ごとのバラつきを見ると、どちらが常に勝つとは限らないんですよね。
株価推移のグラフをイメージすると、2本の線はほぼ並走していて、たまに交差する感じ。コロナショック後の2020年や、2023年の回復期にはVUGがややリード、下落相場の2022年にはIWFが粘りを見せる、といった具合です。
VUGとIWFの年別・過去平均リターン比較
| 年 | VUG リターン | IWF リターン | 差(VUG-IWF) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 13.6% | 13.0% | +0.6% |
| 2015 | 3.3% | 5.7% | -2.4% |
| 2016 | 6.9% | 7.1% | -0.2% |
| 2017 | 27.8% | 30.2% | -2.4% |
| 2018 | -3.3% | -1.5% | -1.8% |
| 2019 | 37.2% | 36.4% | +0.8% |
| 2020 | 40.2% | 38.5% | +1.7% |
| 2021 | 27.4% | 27.6% | -0.2% |
| 2022 | -33.2% | -29.1% | -4.1% |
| 2023 | 46.8% | 42.7% | +4.1% |
次に、過去の平均リターンを計算してみます。
- VUGの10年平均リターン: 16.67%
- IWFの10年平均リターン: 17.06%
この表と平均値を見ると、いくつか面白い傾向が浮かび上がります。まず、10年間でVUGがIWFを上回った年は5回、IWFが勝った年も5回と、完全に互角。年平均リターンではIWFが0.39ポイントリードしていますが、劇的な差ではないですね。
年別の動きを詳しく見ていくと、好調な年にはどちらも大きく伸びます。たとえば、2019年や2020年、2023年は両者とも30~40%超えのハイリターン。特に2023年はVUGが46.8%とIWFの42.7%を4.1ポイント上回り、大型株の回復力が目立ちました。一方で、2017年はIWFが30.2%でVUGの27.8%を上回り、中型株の貢献が光った年です。
下落局面ではどうでしょう。2018年のマイナス幅はVUGが-3.3%、IWFが-1.5%とIWFが優勢。2022年の大幅下落でも、VUGの-33.2%に対しIWFは-29.1%と、IWFの方がダメージが少なめ。この傾向から、IWFの分散性がリスク軽減に役立っている可能性があります。
過去平均リターンでは、IWFがわずかに高いものの、年ごとの勝敗は市場環境次第。好景気ではVUGの大型株集中が効き、不況ではIWFの幅広い銘柄が安定感を出す、という感じですね。長期で見れば、どちらもS&P500(平均約10~12%)を大きく超える実績で、成長株ETFとしての実力は十分です。
VUGとIWFの年別の騰落率比較
| 年 | VUG 騰落率 | IWF 騰落率 | 差(VUG-IWF) |
|---|---|---|---|
| 2020 | +40.2% | +38.5% | +1.7% |
| 2021 | +27.4% | +27.6% | -0.2% |
| 2022 | -33.2% | -29.1% | -4.1% |
| 2023 | +46.8% | +42.7% | +4.1% |
| 2024* | +29.0% | +28.7% | +0.3% |
| ※2024年は10月までの推定値 |
この表を見ると、両者の騰落率はかなり近いですね。上昇局面ではVUGがやや優勢な年が多く、2020年や2023年ではIWFを上回っています。特に2023年の+46.8%は目を引く数字で、大型成長株の爆発力を感じさせます。一方、下落局面ではIWFが粘りを見せる傾向が。2022年の-29.1%はVUGの-33.2%より4.1ポイントマシで、分散効果が効いているのかもしれません。
次に、ボラティリティ(価格変動の大きさ)をチェック。過去5年のデータを基に標準偏差を計算すると、VUGが約3.88%、IWFが約3.97%(月次ベース)。ほぼ同じですが、IWFがわずかに高いです。これは中型株を含む分、値動きが少しだけ大きくなりがちなのかもしれません。
最大下落率(ドローダウン)も見てみましょう。
- VUGの最大下落率: -50.68%(2008年金融危機時)
- IWFの最大下落率: -64.18%(同上)
歴史的な下落を見ると、IWFの方が大きく沈んだ実績があります。ただ、これはIWFの方が設立が早く、厳しい時期を経験している影響も。直近の2022年では、VUGの方が下落率が大きかったので、状況次第で逆転するんですよね。
騰落率の傾向をまとめると、上昇相場ではVUGが少し強く、下落相場ではIWFがややマイルド。リスクを測るボラティリティはほぼ同じで、どちらも成長株らしい激しい動きが特徴です。投資するなら、この上下の波に耐えられるか、自分のリスク許容度と相談する必要がありますね。
VUGとIWFのセクター構成比較
| セクター | VUG 割合 | IWF 割合 | 差(VUG-IWF) |
|---|---|---|---|
| 情報技術 | 45.0% | 45.5% | -0.5% |
| 一般消費財 | 17.5% | 18.0% | -0.5% |
| 通信サービス | 12.0% | 13.0% | -1.0% |
| ヘルスケア | 10.0% | 9.5% | +0.5% |
| 資本財・サービス | 8.0% | 7.5% | +0.5% |
| その他(金融など) | 7.5% | 6.5% | +1.0% |
セクターごとの特徴
まず目を引くのは、情報技術の割合。両者とも45%前後とほぼ半分を占めていて、成長株らしい構成です。アップル、マイクロソフト、NVIDIAといったテックジャイアントが主役で、このセクターの好調さがリターンを牽引しています。差はわずか0.5ポイントで、ほとんど違いはありません。
一般消費財も両者で17~18%と近い数字。アマゾンやテスラが含まれるこの分野は、消費トレンドに左右されやすいですね。IWFが0.5ポイント高いのは、中型株の影響で小売関連銘柄が少し多めなのかもしれません。
通信サービスはIWFが13%でVUGの12%を上回っています。グーグルやメタといった企業が入るここでも、大差はないものの、IWFの方がやや比重が大きいです。
ヘルスケアはVUGが10%、IWFが9.5%とほぼ互角。成長期待の高いバイオ企業などが含まれますが、両者とも主力セクターではないですね。資本財・サービスも8%と7.5%で似たような割合で、製造業や物流関連が中心です。
その他のセクター(金融やエネルギーなど)は、VUGが7.5%、IWFが6.5%。成長株ETFなので、この辺の伝統的な分野は控えめです。
構成の違いと影響
全体を見ると、両者のセクター構成は驚くほど似ています。情報技術が45%前後と圧倒的で、他のセクターも1~2ポイントの差しかないんです。この類似性が、株価推移やリターンが近い理由の一因でしょう。ただ、IWFの中型株混在が、一般消費財や通信サービスでわずかに高い割合を生んでいる可能性があります。
成長株らしいテクノロジー偏重は、リターン期待を高める一方、ITセクターが不調だと一気に影響を受けます。2022年の下落が大きかったのも、この偏りが背景にあるかもしれません。
VUGとIWFの構成銘柄比較
上位10銘柄の比較(2024年時点)
| 順位 | VUG 銘柄 | 割合 | IWF 銘柄 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アップル | 12.5% | アップル | 12.8% |
| 2 | マイクロソフト | 11.8% | マイクロソフト | 12.0% |
| 3 | アマゾン | 6.5% | NVIDIA | 6.8% |
| 4 | NVIDIA | 6.0% | アマゾン | 6.2% |
| 5 | メタ | 4.8% | メタ | 5.0% |
| 6 | アルファベット A | 4.0% | アルファベット A | 4.2% |
| 7 | アルファベット C | 3.5% | アルファベット C | 3.6% |
| 8 | テスラ | 3.0% | テスラ | 3.1% |
| 9 | イーライリリー | 2.5% | イーライリリー | 2.4% |
| 10 | ビザ | 2.0% | ビザ | 2.0% |
上位銘柄の傾向
上位10銘柄を見ると、両者の顔ぶれはほぼ一緒ですね。アップルとマイクロソフトがトップ2で、合わせて24~25%を占めています。この2社だけでETFの4分の1近くを握っているわけで、テクノロジー大手の影響力が大きいのがわかります。
3位と4位では順位が入れ替わっていて、VUGはアマゾン、IWFはNVIDIAが上位。NVIDIAの比重がIWFでやや高いのは、半導体需要の高まりを反映しているのかもしれません。5位以下もメタ、アルファベット(グーグル)、テスラと、おなじみの成長企業が並びます。
上位10銘柄の合計割合は、VUGが約57.5%、IWFが約60.0%。IWFの方が若干集中度が高いですが、大きな差ではないですね。ただ、VUGは200銘柄、IWFは400銘柄と総数が倍違うので、IWFの方が残りの銘柄に分散している分、中型株の影響が薄まっている可能性があります。
違いのポイント
注目すべきは、IWFの中型株混在が上位以外でどう効いてくるか。たとえば、IWFには中型成長株(時価総額100~500億ドル程度)が含まれるので、上位以外で少し違った顔ぶれが見られます。VUGは純粋に大型株のみなので、上位10銘柄以外も似たような大企業が続く傾向です。
この銘柄構成からも、両者の値動きが近い理由が納得できます。ただ、IWFの中型株が市場環境次第でプラスに働くかマイナスになるかは、注目ポイントですね。
VUGとIWFに投資した場合の成長率シミュレーション比較
投資の醍醐味は、将来どれくらい資産が育つかを想像することですよね。ここでは、VUGとIWFに投資した場合の成長率をシミュレーションしてみます。過去の実績を基に、10年後の資産額を計算して、どっちが伸びるか見てみましょう。
シミュレーション条件
- 初期投資額: 100万円
- 期間: 10年
- 成長率: 過去10年の年平均リターン(VUG: 16.21%、IWF: 17.04%)
- 経費率: VUG 0.04%、IWF 0.19%を考慮
- 配当再投資: なし(シンプル化のため)
年次成長シミュレーション
| 年 | VUG 資産額 | VUG 成長率 | IWF 資産額 | IWF 成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100万円 | – | 100万円 | – |
| 1 | 116.17万円 | 16.17% | 116.85万円 | 16.85% |
| 5 | 211.32万円 | 16.17% | 217.56万円 | 16.85% |
| 10 | 446.23万円 | 16.17% | 475.14万円 | 16.85% |
※成長率は経費率差し引き後(VUG: 16.21-0.04=16.17%、IWF: 17.04-0.19=16.85%)
結果の分析
10年後、VUGは約446万円、IWFは約475万円に成長。差額は約29万円で、IWFがリードしています。この差は、IWFの年平均リターンが0.68ポイント高いことが効いているんです。初期の100万円が4.5~4.7倍になるのは、成長株ETFの威力ですね。
でも、経費率の影響も見逃せません。VUGの低コストが長期で有利に働く可能性はありますが、このシミュレーションではIWFの高いリターンがそれを上回りました。たとえば、経費率を無視すると、VUGは約451万円、IWFは約486万円となり、差はさらに広がります。
別の視点:リスク調整後
リスクを考慮するとどうでしょう。ボラティリティがほぼ同じ(VUG 3.88%、IWF 3.97%)なので、リターン÷標準偏差で簡易的なシャープレシオを出すと、VUGが約4.17、IWFが約4.25。IWFがわずかに効率的です。
VUGとIWFに投資した場合の配当金シミュレーション比較
シミュレーション条件
- 初期投資額: 100万円
- 期間: 10年
- 配当利回り: VUG 0.5%、IWF 0.6%(2024年時点)
- 成長率: 考慮せず(配当のみ計算)
- 再投資: なし
年次配当額シミュレーション
| 年 | VUG 配当金 | IWF 配当金 | 差(IWF-VUG) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000円 | 6000円 | +1000円 |
| 5 | 5000円 | 6000円 | +1000円 |
| 10 | 5000円 | 6000円 | +1000円 |
| 合計 | 5万円 | 6万円 | +1万円 |
結果の分析
年間配当は、VUGが5000円、IWFが6000円。10年合計だと、VUGが5万円、IWFが6万円で、IWFが1万円多いです。この差は配当利回りの0.1%の違いからくるもので、額は小さいですがコツコツ積み上がります。
ただし、これは成長率を無視した単純計算。実際は株価が上がれば配当額も増える可能性があります。たとえば、前の成長率シミュレーションを当てはめると、10年目の資産額(VUG 446万円、IWF 475万円)で計算すると:
- VUG: 446万円×0.5%=2.23万円
- IWF: 475万円×0.6%=2.85万円
この場合、10年目の配当差は6200円に拡大。成長株ETFなので配当はオマケ程度ですが、IWFがわずかに有利ですね。
VUGとIWFどちらがおすすめ?(観点別)
1. コスト重視
- VUG: 経費率0.04%と圧倒的に安い。長期投資ならコスト差が効いてきます。
- IWF: 0.19%は低めだけど、VUGには敵わず。
- おすすめ: VUG。10年で1万円以上の差が出る可能性あり。
2. 分散性重視
- VUG: 約200銘柄で大型株のみ。集中度高め。
- IWF: 約400銘柄で中型株も含む。分散性が高い。
- おすすめ: IWF。リスク分散を求めるならこちら。
3. リターン重視
- VUG: 過去10年平均16.21%。年によってはIWFを上回る。
- IWF: 17.04%とわずかに優勢。長期では安定して高い。
- おすすめ: IWF。微差だけどリターンを最大化したいなら。
4. リスク耐性
- VUG: 下落時に落ち幅が大きめ(例: 2022年-33.2%)。
- IWF: 分散のおかげでややマイルド(2022年-29.1%)。
- おすすめ: IWF。値動きの波を抑えたい人に。
5. 流動性
- VUG: 平均売買高80万株/日。十分高い。
- IWF: 120万株/日でさらに取引しやすい。
- おすすめ: IWF。売買の柔軟性を重視するなら。
総合判断
コストを取るか、リターンと分散を取るかのトレードオフですね。長期で低コストを活かしたいならVUG、少しでもリターンと安定性を求めるならIWFが有力です。市場環境にもよるので、成長株が強い局面ではどちらも魅力的ですよ。
まとめ
VUGとIWF、どちらもアメリカの成長株に投資するETFとして、多くの注目を集めています。これまで特徴やパフォーマンス、構成、シミュレーションなどを比較してきましたが、最後にその要点をまとめてみます。
まず、VUGはバンガードが提供する低コスト(経費率0.04%)のETFで、大型成長株に特化。約200銘柄で構成され、テクノロジー中心のポートフォリオが特徴です。一方、IWFはブラックロックの運用で、経費率0.19%とやや高めながら、約400銘柄と大型株+中型株の分散性が強み。どちらもアップルやマイクロソフトといった成長企業が上位を占め、セクター構成も似ています。
パフォーマンスでは、過去10年の平均リターンがVUG16.21%、IWF17.04%とIWFがわずかにリード。年別では市場環境次第で勝敗が分かれ、下落局面ではIWFの分散性が効く一方、上昇期にはVUGの集中力が光ります。成長率シミュレーションでも、10年でIWFがやや優勢(475万円 vs 446万円)、配当金でもIWFが少し上(6万円 vs 5万円)でした。
選び方は投資目的次第。コストを抑えたいならVUG、分散性やリターンを重視するならIWFがおすすめです。どちらも成長株ETFとしての魅力は抜群で、長期投資の軸になり得る選択肢。市場の波に乗りながら、自分のゴールに合った方を選んでみてくださいね!
他の人気ETF比較の記事はこちら
S&P500とNASDAQ100、本当に儲かるのはどっち?リスク・リターン・構成銘柄を徹底比較
この記事の3ポイント要約 長期シミュレーションでは、テクノロジー比率の高いNASDAQ100がS&P500を圧倒するリターンとなった S&P500は500社の広範な分散によりリスクが低…
FANG+とS&P500トップ10はどっちがいい?リターン・コスト・将来性をデータで比較
この記事の3ポイント要約 FANG+はTracers S&P500トップ10より高いリターンが期待できるものの、信託報酬が高く、値動きの激しいハイリスク・ハイリターン Tracers S&am…
【比較】FANG+ vs NASDAQ100、どっちがおすすめか?シミュレーションでわかった本当のリターン差
この記事のポイント 過去のデータに基づくと、極度な集中投資であるFANG+は、分散型のNASDAQ100よりも高いリターンを生み出す傾向にあるが、そのボラティリティも極めて大きい FANG+は均等加重…
【比較】FANG+ vs M7、どっちに投資するべきか?徹底シミュレーション
この記事のポイント M7トラストは7銘柄集中、FANG+は10銘柄集中であり、M7トラストの方が銘柄数が少ない分、リターン期待値もリスクも高くなる傾向がある 50年シミュレーションでは、M7トラスト単…
FANG+ vs Zテック20 | ハイテク投資、米国集中と世界分散の究極の選択。メリット・デメリットを徹底解説
この記事のポイント FANG+は米国10銘柄に超集中、Zテック20は世界の優良テクノロジー企業(約20銘柄)に分散投資する戦略である 50年シミュレーションでは、米国集中型のFANG+が最高リターンを…
【比較】FANG+とUSテック・トップ20 | 勝つのはどっち?徹底シミュレーションとターン最大化の黄金比率を調査
この記事のポイント FANG+は10銘柄に集中投資するため、リターン期待値は高いが、リスクも高水準 USテック・トップ20は20銘柄に分散投資し、信託報酬も低いため、バランスの取れた設計 長期シミュレ…
FANG+ vs JEPQ | どっちが最強?配当と成長を両立する黄金比率を解説
この記事のポイント FANG+は年率20%、JEPQは年率8%と想定したシミュレーションでは、50年後で91億対4,600万円と、成長戦略(FANG+)が圧倒的な差をつける FANG+は少数のハイパー…
FANG+ vs VTI | どっちが儲かる?最適な投資比率は?シミュレーションを用い徹底解説
この記事のポイント FANG+はハイテク集中投資による高い成長ポテンシャルを持つが、VTIは米国市場全体への分散投資による安定性がある FANG+とVTIの「合わせ持ち戦略」は、VTIの安定性とFAN…
【比較】FANG+ vs メガ10!どっちがいい?構成銘柄・平均リターンの違いや欠点を解説
この記事のポイント FANG+はアップルや最新AI銘柄に特化して攻める一方、Sメガ10はテスラや金融・製薬も含み低コストで守りも固める設計 リターン重視ならFANG+一択だが、信託報酬の圧倒的な安さと…
VTIとSHVの「ベスト比率」は?成長と安全を両立するポートフォリオを徹底解説
この記事のポイント VTIは市場全体の成長を享受し長期的な資産最大化を目指す「攻め」のコア資産、SHVは低リスク・安定収入を提供する「守り」の安全資産である。長期リターンではVTIが圧倒的に優位だが、…
VTI vs GLDM(金)徹底比較!資産を最大化しつつ危機をヘッジする「最強の組み合わせ戦略」
この記事のポイント VTIは米国企業の成長力を背景に、長期的なトータルリターン(資産の最大化)でGLDMを大きく上回る傾向にある。GLDM(金)は基本的に配当を生まずインカムゲインはゼロだが、インフレ…
VTIとVYMは結局どっち?リターン・配当・50年シミュレーションで徹底比較
この記事のポイント VTIは長期的なトータルリターン(リターンと成長)でVYMを上回る傾向があり、資産の最大化を目指す若年層・長期投資家向き。VYMはVTIの約2倍の配当利回り(インカムゲイン)を提供…
【比較】VTIとSPYD、過去20年のリターンを徹底分析!配当金生活への最適な組み合わせは?
この記事のポイント VTIは米国市場全体(約4,000銘柄)に投資する「成長重視」のETFであり、長期的には複利の効果で最も高いトータルリターン(想定年平均10.5%)が期待できる。一方、SPYDはS…
VTIとVGT、投資するならどっち?リターン・配当・構成銘柄を詳細比較【最適な組み合わせ戦略も解説】
この記事のポイント VTIは米国全市場に分散投資し、安定性と中程度のリターン、比較的高い配当利回りが特徴の「コア」資産である。VGTは情報技術セクターに集中投資し、高い成長率を期待できるが、ボラティリ…
【成長vs高配当】VTIとJEPQを徹底比較!リターン・配当・成長率で長期投資に最適なのはどっち?
この記事のポイント VTIは米国市場全体に分散投資し、低コストで長期的な資産最大化(キャピタルゲイン)を目指す「成長のコア」である。一方、JEPQはナスダック100を対象としたカバードコール戦略で、毎…
【比較】FANG+ vs BTC|どちらに投資するのがいいのか?
この記事のポイント 100万円を投資した場合、1年ではFANG+が28%増で優位ですが、5年を超えるとBTCが急成長。10年でBTCは45倍、FANG+は12.5倍に達します FANG+は10社のテッ…
【比較】SCHD vs QQQ|違いを理解して投資しよう
この記事のポイント 過去1年で100万円がQQQなら1,237万円、SCHDは995万円。QQQの23.7%急伸が効くが、SCHDは安定感で安心 20年でQQQが1,650万円、SCHDは806万円。…
【比較】SCHD vs VTI。ミックス戦略がおすすめ
この記事のポイント 過去5年でVTIが2倍超に対しSCHD1.57倍だが、20年シミュでSCHD8,860万円 vs VTI7,220万円、配当再投資の長期効果が顕著に現れる VTIはテック31%で成…
【比較】SCHD vs FANG+|どっちも保有するのがおすすめ
この記事のポイント 過去1〜20年リターン比較で、短期(5年以内)はFANG+が3倍以上上回るが、15年超の長期ではSCHDの安定複利が差を縮める SCHDは低コスト0.06%・高配当3.8%・100…
【比較】NASDAQ100ゴールドプラス vs FANG+|組み合わせて保有するのがおすすめ
この記事のポイント 50年シミュレーションでは、両者を半々で保有する戦略が最も滑らかに資産を増やした結果となり、「片方に賭けるよりも、異なる性質を組み合わせる」ことで最大効率の複利成長が得られた 配当…
【比較】VGT vs FANG+|テクノロジーの未来に賭けるならどちらも欠かせないETF
この記事のポイント 過去リターンはFANG+が優勢だが、VGTの安定成長性は不況期にも強い 両ETFを併用することで、“分散×成長”の理想的なポートフォリオが完成する テクノロジーの未来に賭けるなら、…
【比較】S&P500 vs FANG+|リターン重視ならFANG+だがミックスがおすすめ
この記事のポイント 1-5年でFANG+が2-3倍優位だが、20年超ではS&P500の分散が追いつき、複利の安定力が光る。短期爆発 vs 長期着実の選択肢 10年データでFANG+平均28%の…
【比較】SCHD vs JEPI|目的によって使い分けを。バランスが良いのはSCHD
この記事のポイント SCHDは低コスト・配当成長で長期リターンが強く、20年で100万円が780万円に。 JEPIは毎月分配とカバードコールで安定インカム、短期投資に魅力。 50年シミュレーションでは…
【比較】SCHD vs SPYD|総合的にみてSCHDのほうが優秀
この記事のポイント SCHDは連続増配企業に投資し、10年以上の長期リターンでSPYDを上回る(約12% vs 9%)。 50年シミュレーションでは、SCHDが24759万円、SPYDが5637万円、…
【比較】SCHD vs VYM|成長と配当目当てならSCHD、安定を取るならVYM
この記事のポイント SCHDは高配当・高増配率、VYMは分散投資で安定感。 10年以上の長期投資ならSCHD、1~3年ならVYMがリターン優勢。 50年シミュレーションではSCHDが資産成長で上回るが…

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。