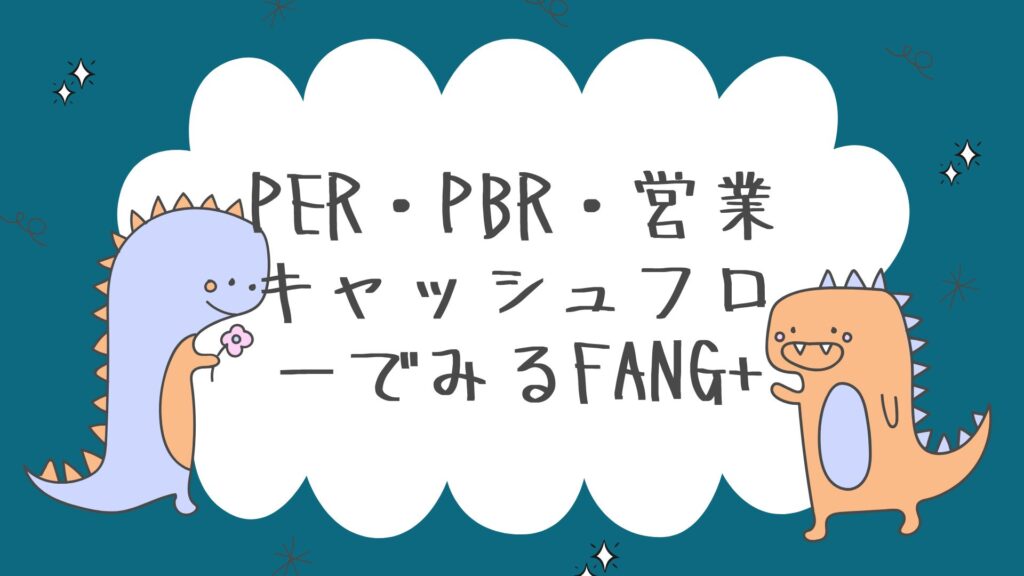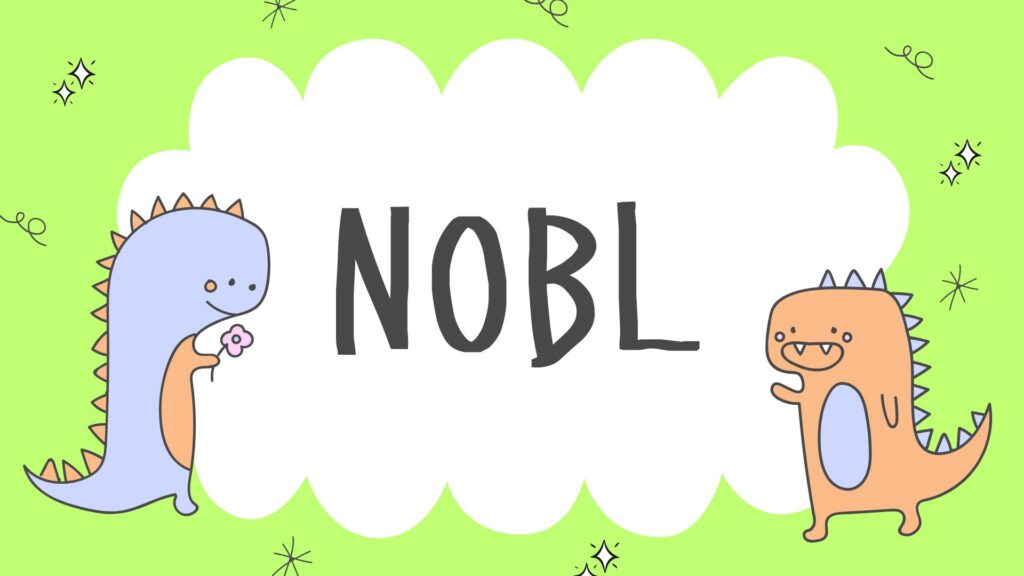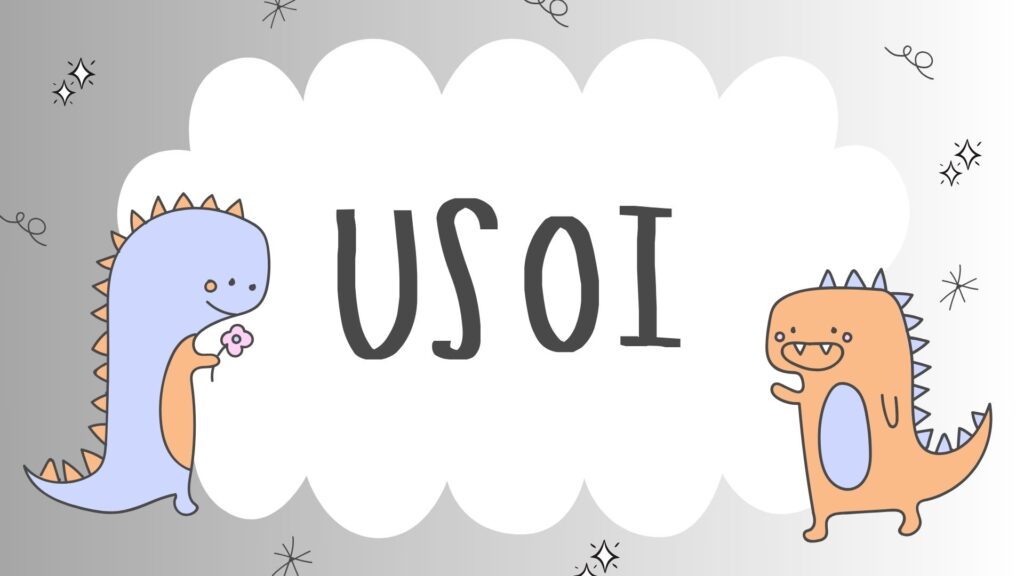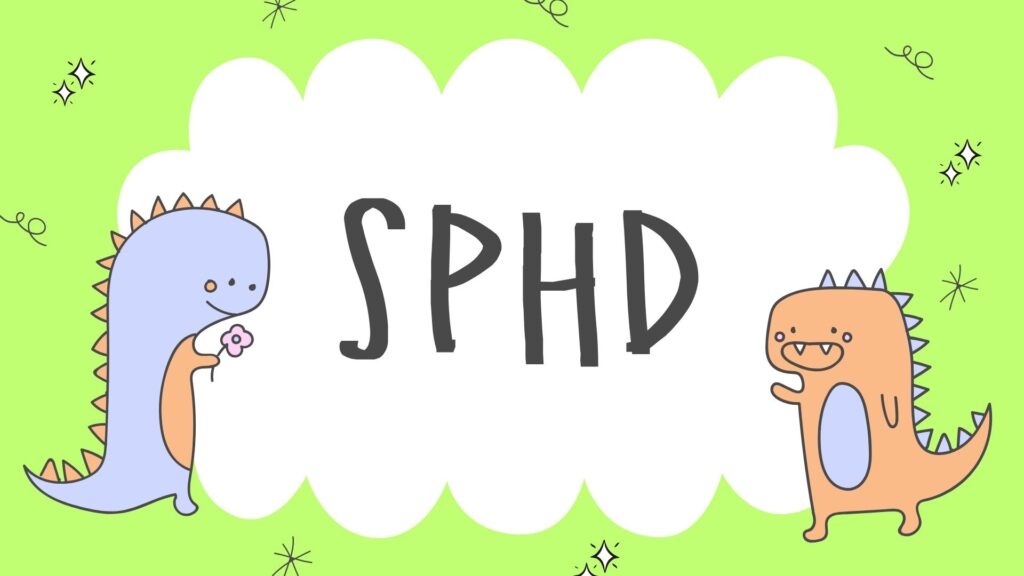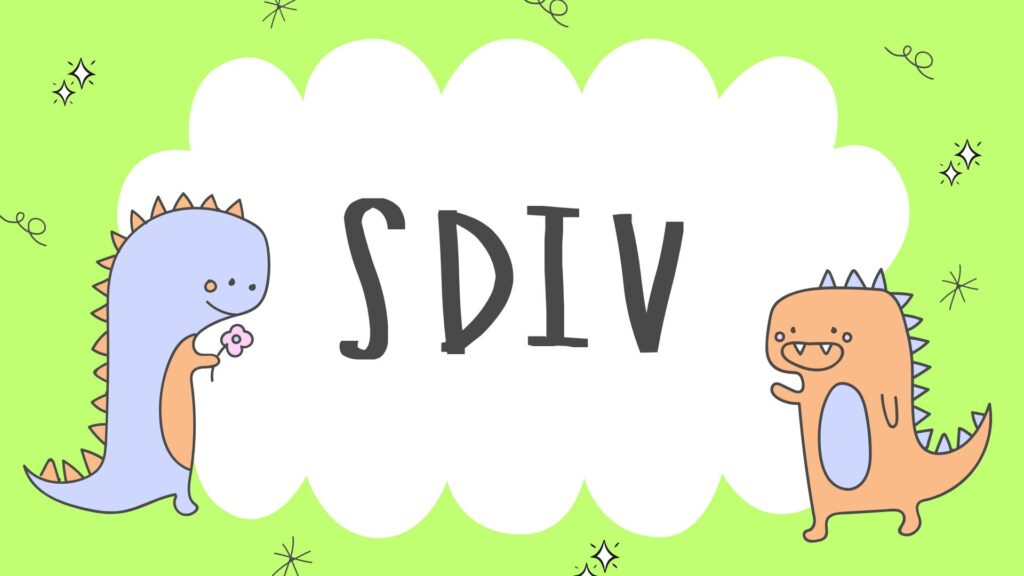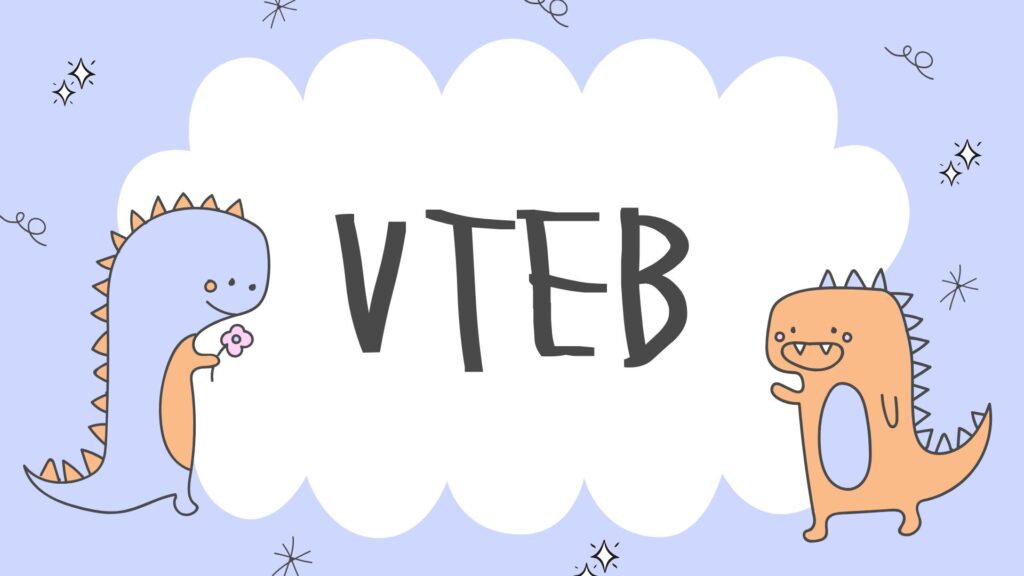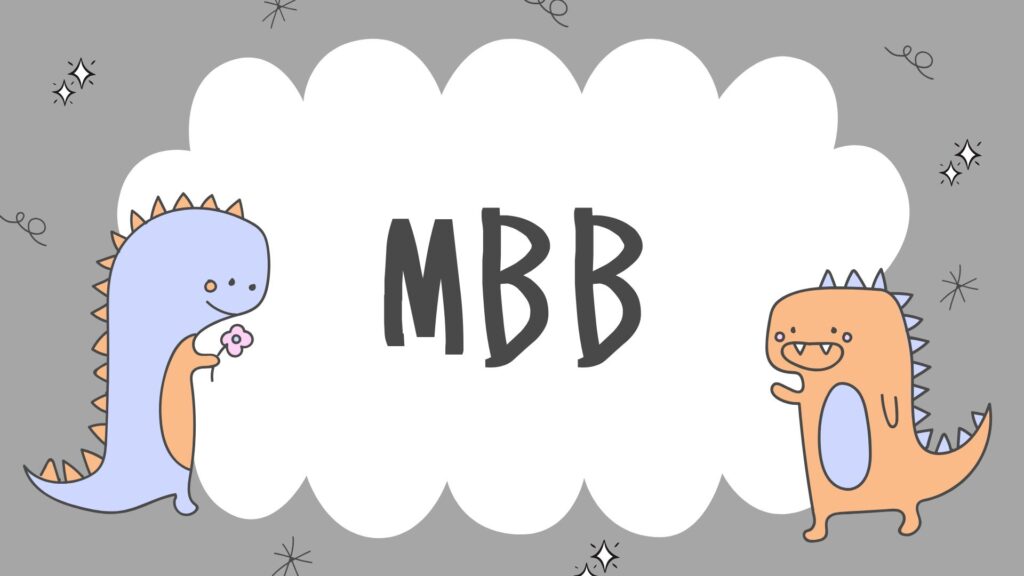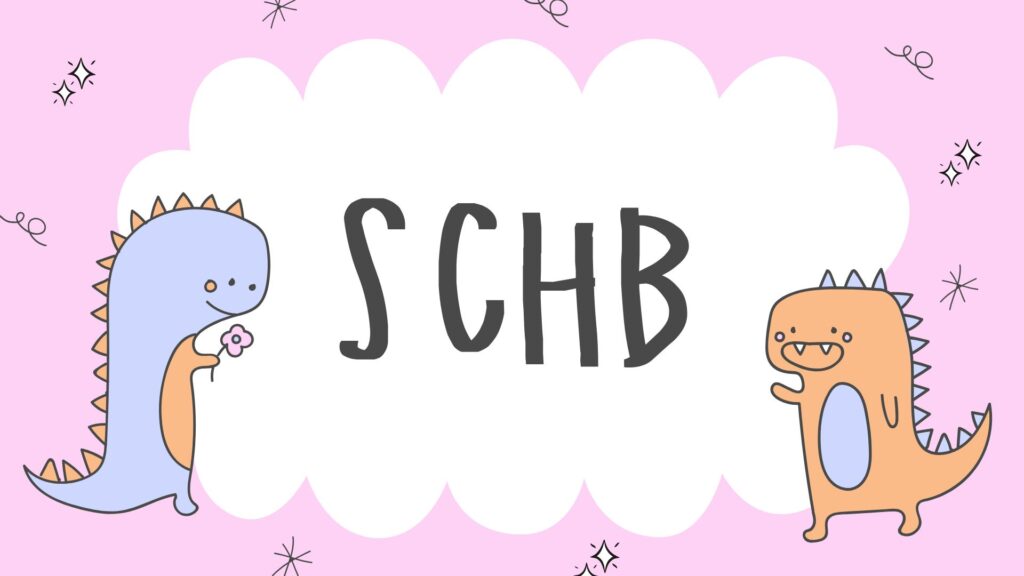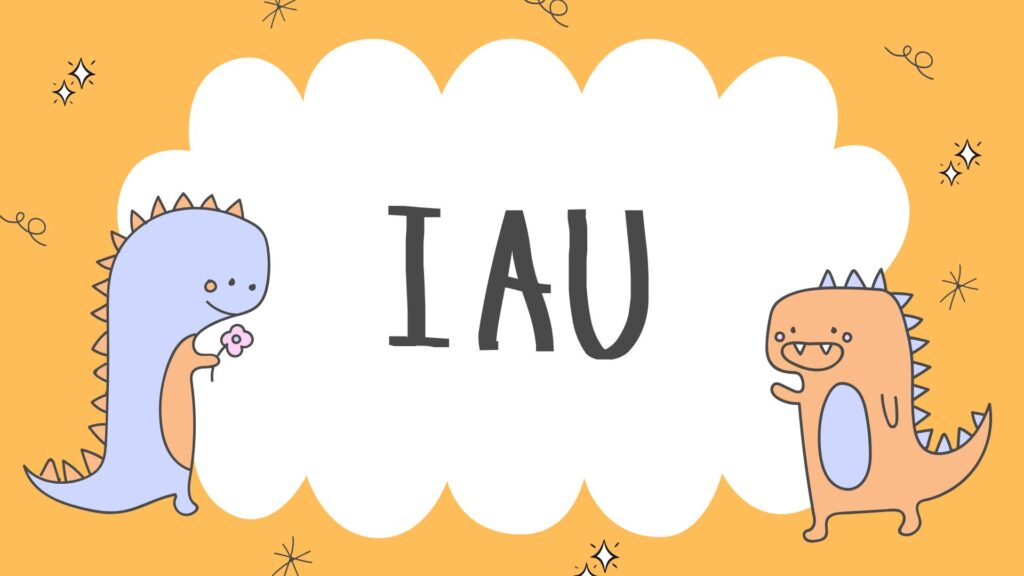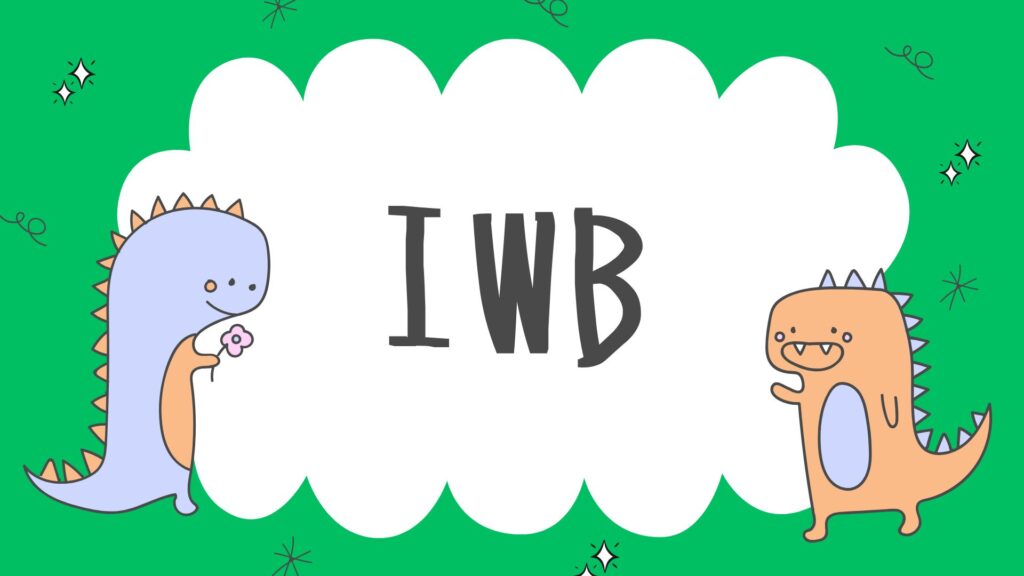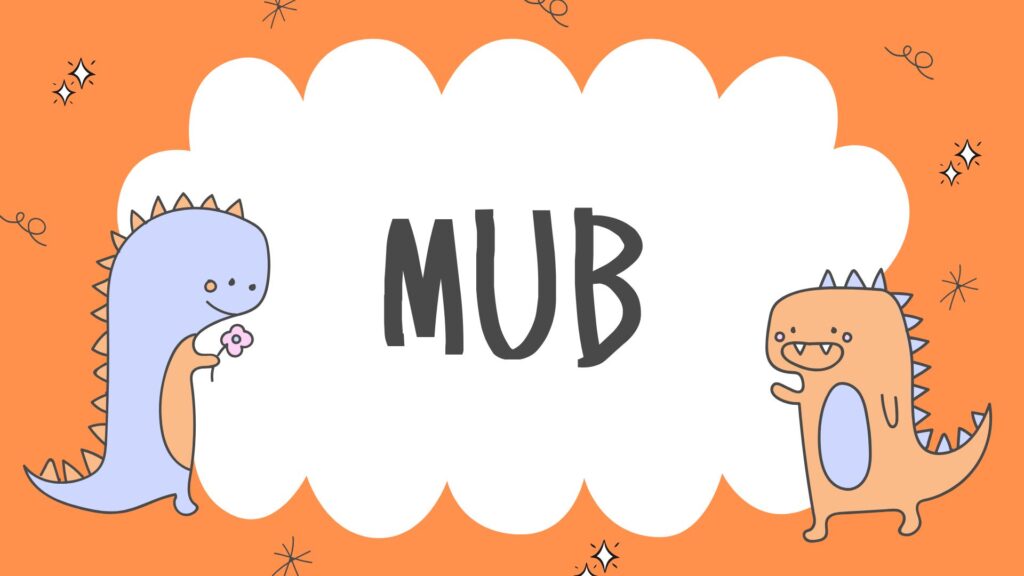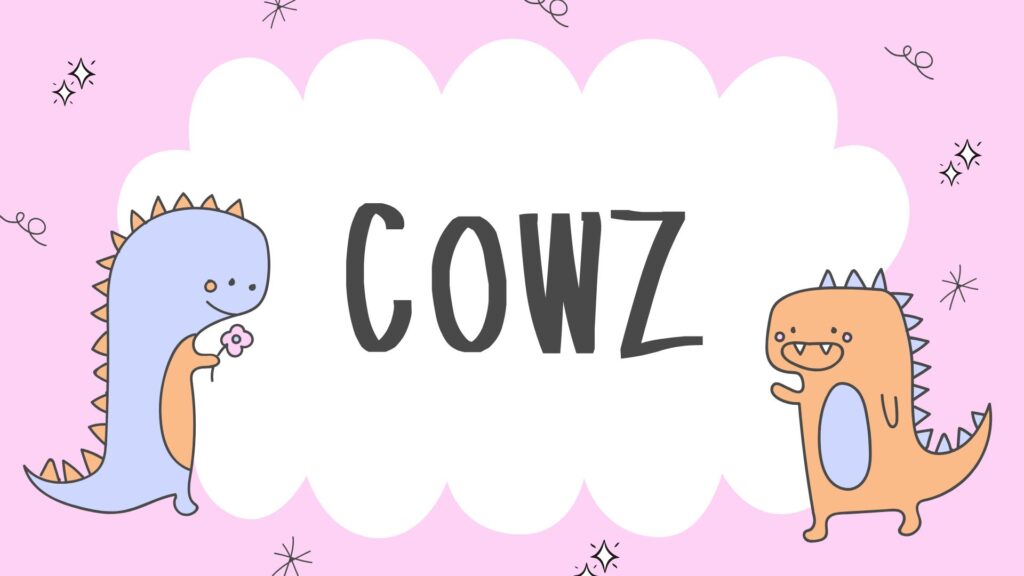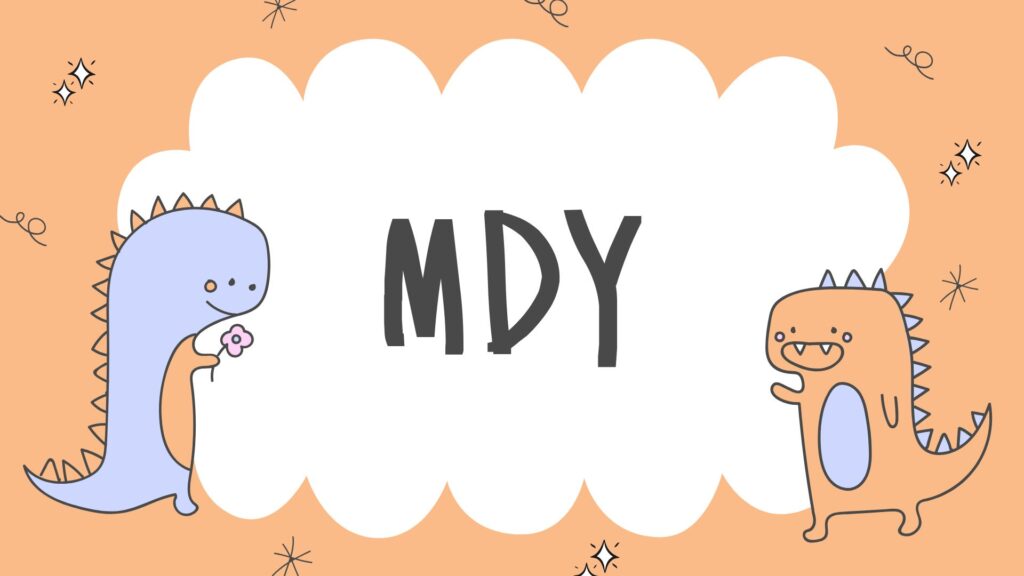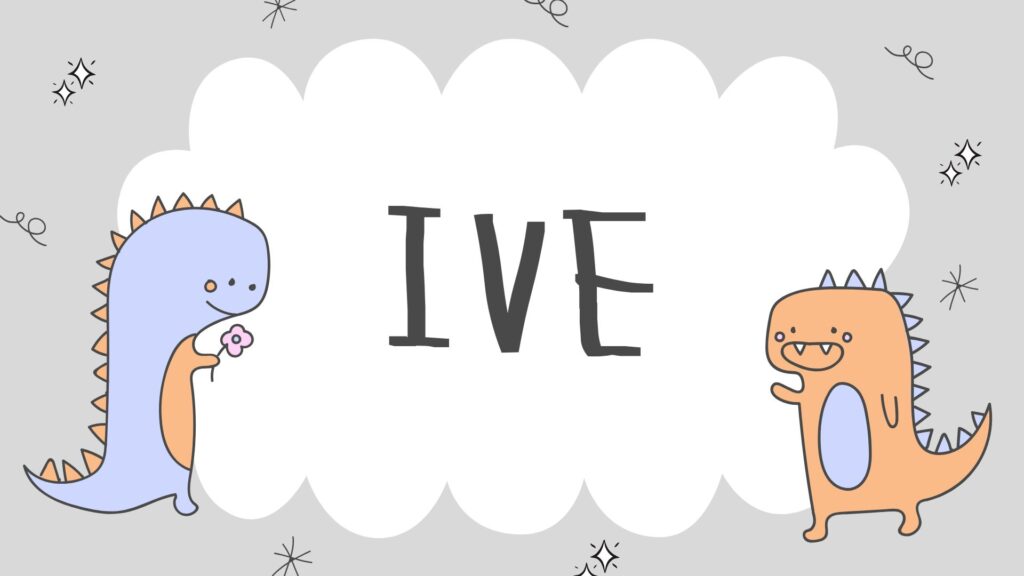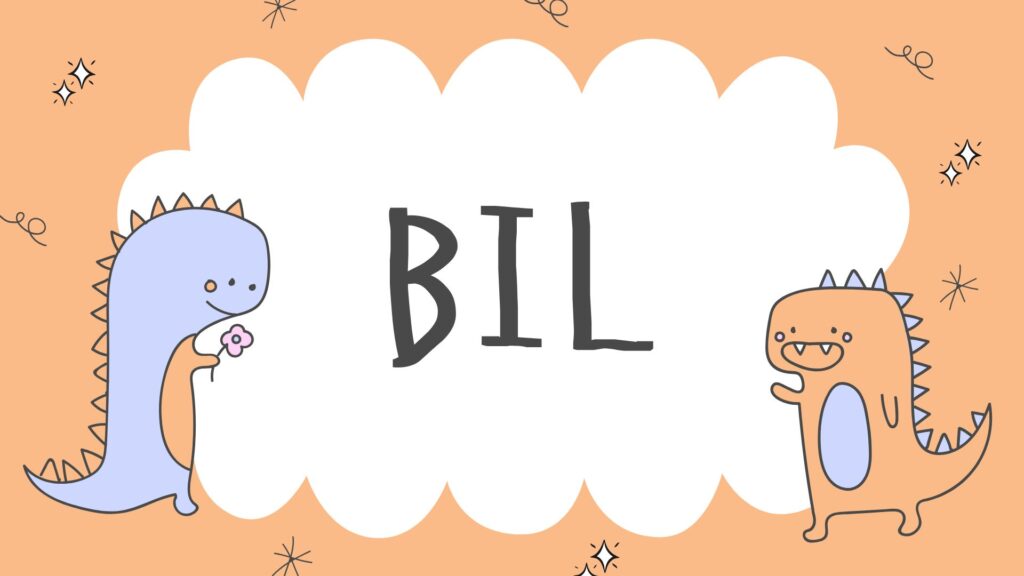VNQのETF Score (ETFのおすすめ度)
- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出
- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出
- 運用コスト:経費率をもとに算出
- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出
- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出
※各指標は当サイトにおける基準で設定
VNQの特徴
米国株式市場で長年愛される「Vanguard Real Estate ETF(VNQ)」は、不動産投資の門戸を広く開く存在です。
VNQの特徴を一言で表すなら、
手軽に分散された不動産投資を、低コストで
このETFは、米国の不動産投資信託(REIT)を中心に、幅広い不動産関連企業をカバーしています。投資家にとって、なぜこれほど魅力的なのか、じっくり見ていきましょう。
まず、VNQの基本構造を整理します。このETFは、MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Indexを追跡し、約160銘柄で構成されています。住宅、商業施設、データセンター、物流施設など、不動産のあらゆる分野に投資できる点が強みです。運用会社バンガードの手数料は驚異の0.12%。これほど低コストで、広範な不動産市場へのアクセスを提供するETFは稀です。
では、どんな投資家に向いているのでしょうか?
配当金を重視する人、インフレ対策を考える人、ポートフォリオの分散を求める人に特に適しています。不動産は株式や債券と異なる値動きをするため、リスク分散に一役買います。さらに、REITは収益の90%以上を配当として分配する義務があり、安定したインカムゲインが期待できるのです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ティッカー | VNQ |
| 運用会社 | Vanguard |
| ベンチマーク | MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index |
| 経費率 | 0.12% |
| 銘柄数 | 約160 |
| 配当利回り(直近) | 約3.8%(2025年3月時点) |
| 設定日 | 2004年9月23日 |
VNQのもう一つの魅力は、流動性の高さ。1日の平均取引量は数百万ドルに及び、売買が容易です。これなら、大きな資金を動かす投資家も安心して取引できます。不動産市場の成長を背景に、長期的な資産形成を目指すなら、VNQは見逃せない選択肢です。ただし、金利上昇局面ではREITの価格が圧迫されることもあるため、経済環境の変化には注意が必要です。
最後に、VNQは単なる「不動産への投資」以上の価値があります。都市化の進展や物流需要の増加、テレワークによるオフィス需要の変化など、社会の大きなトレンドを捉える手段でもあるのです。これらのダイナミズムを、低コストで手に入れられるのは、投資家にとって大きなチャンスと言えるでしょう。
VNQの株価・推移・成長率(パフォーマンス)
※S&P500指数と比較
VNQの株価推移を眺めると、不動産市場の波乱万丈な物語が見えてきます。2004年の設定以来、VNQはリーマンショックやコロナショックを乗り越え、力強い成長を見せてきました。2025年4月時点の株価は約90ドル前後で推移していますが、過去20年のパフォーマンスはどうだったのでしょうか。
リーマンショック(2008-2009年)では、VNQの株価は一時70%以上下落しました。不動産市場の凍結はREITに深刻な打撃を与えたのです。しかし、その後の回復は目覚ましく、2010年代は低金利環境を追い風に、年平均8%近い成長を記録。2020年のコロナショックでも一時30%下落したものの、2021年には40%超のリターンで急回復しました。
| 期間 | 年平均成長率(CAGR) |
|---|---|
| 2004-2014 | 6.5% |
| 2014-2024 | 4.8% |
| 2020-2024(直近) | 7.2% |
この成長率を見ると、VNQは株式市場(S&P 500の約10%)に比べるとやや控えめですが、安定性と配当を加味すれば魅力は十分です。特に、2022-2023年の金利上昇局面では株価が軟調だったものの、2024年以降は利下げ期待から再び上昇基調に。成長の鍵は、物流やデータセンターといった新興分野のREITが牽引している点にあります。
株価の変動要因を考えると、金利動向が最大のポイントです。REITは借入依存度が高いため、金利が上がると資金調達コストが増し、株価に影響します。一方、経済成長や都市化の進展はプラス材料。たとえば、eコマースの拡大で物流施設の需要が急増し、VNQの成長を支えています。
投資家として気になるのは、今後の見通しです。2025年は米国の利下げが進行するとの予想が多く、VNQにとって追い風となる可能性が高いです。ただし、インフレ再燃や地政学リスクが逆風になることも。長期投資を前提に、短期のブレを気にせずコツコツ積み立てるのが賢明でしょう。
VNQの年別・過去平均リターン
| 年 | トータルリターン(%) |
|---|---|
| 2015 | 2.4 |
| 2018 | -6.0 |
| 2020 | -4.7 |
| 2021 | 40.4 |
| 2023 | 11.8 |
| 2024 | 12.9(YTD) |
過去20年の平均トータルリターンは約7.5%。S&P 500の約10%には及ばないものの、配当利回り(平均3-4%)を加味すると、インカム重視の投資家には魅力的です。特に、2021年の40%超のリターンは、コロナ後の経済再開と低金利が後押しした例外的な年でした。一方、2018年や2020年のマイナスリターンは、金利上昇や経済不安の影響を受けた時期です。
リターンのバラつきを見ると、VNQは株式市場ほど劇的な上下動はないものの、経済環境に敏感です。たとえば、2008年のリターンは-37%と壊滅的でしたが、翌2009年は30%のプラスに転じました。この回復力は、REITのビジネスモデル(賃料収入の安定性)に支えられています。
長期で見ると、VNQはインフレ調整後でも実質リターンを確保してきました。1970年代の不動産指数を参考にすると、インフレ率を上回るリターンが期待できるのです。2020年代は、データセンターや物流REITの成長が新たな推進力に。こうしたトレンドは、今後もVNQのリターンを下支えするでしょう。
投資家にとっての教訓は、短期のマイナスリターンを恐れず、長期で保有すること。配当を再投資すれば、複利効果で資産は着実に増えます。VNQのリターンは、忍耐が報われる投資の好例と言えるでしょう。
VNQのセクター構成
| セクター | 割合(%) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 特殊REIT | 28 | データセンター、通信塔など成長分野 |
| 住宅 | 20 | アパート、戸建て賃貸 |
| 商業(オフィス) | 18 | 都市部のオフィスビル |
| リテール | 15 | ショッピングモール、スーパー |
| 工業(物流) | 12 | 倉庫、配送センター |
| ヘルスケア | 5 | 病院、介護施設 |
| その他 | 2 | ホテル、自己ストレージなど |
この構成を見ると、VNQは特定のセクターに偏らず、バランスよく投資しているのがわかります。特に近年は、特殊REITの割合が増加。データセンターを運営するEquinixや、通信塔のAmerican Towerなど、テクノロジー需要を背景にした企業が目立ちます。これに対し、伝統的なオフィスREITはテレワークの影響でやや苦戦気味です。
セクターごとのパフォーマンスも興味深いです。2020年代は、物流とデータセンターが年20%近い成長を見せる一方、オフィスは低迷。こうした違いが、VNQ全体の安定性を支えています。投資家としては、特定のセクターに依存しない点が安心材料と言えるでしょう。
経済環境による影響も見逃せません。たとえば、金利が下がると、借入コストが減り、すべてのセクターが恩恵を受けます。一方、インフレが高まると、賃料収入が伸びる住宅やリテールが強みを発揮。不動産市場のトレンドを広く捉えるVNQは、どんな局面でも一定の耐性を持つのです。
VNQの構成銘柄
| 銘柄 | 割合(%) | セクター | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Prologis | 10.2 | 工業(物流) | 世界最大の物流REIT、eコマース需要で急成長 |
| American Tower | 8.8 | 特殊REIT | 通信塔のグローバルリーダー |
| Equinix | 6.5 | 特殊REIT | データセンターのトップ企業 |
| Public Storage | 4.5 | 自己ストレージ | 個人・企業向けストレージのリーダー |
| Simon Property Group | 4.0 | リテール | 高級ショッピングモールの運営 |
Prologisは、AmazonやFedExのような企業向けに物流施設を提供し、eコマースの拡大で業績を伸ばしています。American Towerは5Gの普及を背景に、通信インフラの需要増に対応。Equinixはクラウドコンピューティングの急成長で、データセンターの需要が爆発的に増えています。
これらの銘柄は、VNQの成長エンジンであると同時に、安定性の源でもあります。たとえば、Public Storageは景気後退時でも安定した賃料収入を確保。Simon Propertyは、コロナ後の消費回復で高級モールの価値を再評価されています。
投資家にとって、VNQの構成銘柄は「個別株投資の手間を省く」利点を提供します。これだけの優良企業を自分で選んで投資するのは至難の業。それを一括で、しかも低コストで保有できるのは、VNQならではの価値です。ただし、トップ銘柄への集中度が高い点は、リスクとして頭に入れておくべきでしょう。
VNQに長期投資した場合のシミュレーション
VNQに100年間投資したら、資産はどうなるのか。壮大な仮定ですが、過去のデータをもとにシミュレーションしてみましょう。不動産市場の長期的な成長力と、VNQの特性を活かした結果は、驚くべきものになります。
仮に2004年の設定時に1万ドルを投資し、配当を再投資した場合を考えてみます。過去20年の平均トータルリターンは7.5%。これを100年に拡張すると、複利効果で資産は約860万ドルに膨らみます。インフレ調整後でも、約150万ドル(実質リターン4%想定)です。
| 期間 | 初期投資 | 想定リターン | 資産額(配当再投資) |
|---|---|---|---|
| 20年 | $10,000 | 7.5% | $42,500 |
| 50年 | $10,000 | 7.5% | $370,000 |
| 100年 | $10,000 | 7.5% | $8,600,000 |
この計算は、過去の平均リターンが続く前提です。しかし、不動産市場は進化します。データセンターや物流施設の成長、都市化の加速は、今後もリターンを押し上げる可能性が高い。一方、気候変動や金利リスクはマイナス要因になり得ます。
もう一つのシナリオとして、毎月100ドルを100年間積み立てる場合を考えてみましょう。7.5%のリターンで計算すると、総投資額12万ドルに対し、最終資産は約1億2000万ドル。インフレ調整後でも数千万ドルに達します。積立投資の力は、時間を味方にすれば驚異的です。
このシミュレーションからわかるのは、VNQのようなETFは、長期投資の強力なツールであること。短期の変動に惑わされず、着実に資産を増やす戦略が、100年後の富を築く鍵なのです。
VNQの配当タイミングと直近の配当
VNQの配当は、インカム投資家にとって大きな魅力です。REITの特性上、収益の90%以上を分配するため、安定したキャッシュフローが期待できます。では、配当のタイミングと最近の動向を見てみましょう。
VNQは四半期ごとに配当を支払います。2025年3月時点の直近データでは、以下のスケジュールです。
| 支払日 | 配当(1株当たり) | 配当利回り |
|---|---|---|
| 2024年3月27日 | $0.931 | 4.0% |
| 2024年6月28日 | $0.920 | 3.9% |
| 2024年9月27日 | $0.925 | 3.9% |
| 2024年12月27日 | $0.935 | 4.0% |
年間配当は約3.71ドルで、利回りは約3.8-4.0%。過去5年の平均利回りは3.5-4.5%で推移し、株式市場の平均(S&P 500の1.5%)を大きく上回ります。ただし、配当額は不動産市場の業績や金利環境に左右されるため、増配が保証されるわけではありません。
配当の安定性はどうでしょうか。VNQの構成銘柄は、賃料収入を基盤とするREITが中心。景気後退時でも、物流や住宅REITは比較的安定した収益を確保します。ただし、2020年のコロナショックでは一部銘柄が配当を削減したため、セクター分散の重要性が再認識されました。
投資家にとって、VNQの配当は「生活費の足し」や「再投資の原資」として魅力的です。特に、退職後の収入源として考えるなら、定期的なキャッシュフローは心強い存在。次のセクションでは、この配当を活かした生活シナリオを考えてみましょう。
VNQで配当金生活は可能か?
VNQの配当を活用して、どれくらいの資産で生活できるのか、具体的にシミュレーションしてみましょう。不労所得で暮らす夢を、現実的な数字で紐解いていきます。
仮に、年間30万円(約2,500ドル)の配当収入を目指す場合を考えてみます。VNQの配当利回りを4%とすると、必要な投資額は以下の通りです。
| 目標配当(年) | 必要投資額 | 必要株数(1株90ドル) |
|---|---|---|
| $2,500 | $62,500 | 約700株 |
| $10,000 | $250,000 | 約2,800株 |
| $50,000 | $1,250,000 | 約14,000株 |
月20万円(約1.6万ドル)の生活費を賄うには、約400万ドル(4.8億円)の投資が必要。日本の平均的な生活費を考えると、1億円程度で十分な配当収入を得られる計算です。
次に、積立投資でこの目標を達成するシナリオを考えてみましょう。30歳から毎月500ドル(約6万円)をVNQに投資し、7%のリターン(配当再投資込み)を仮定。65歳時点で資産は約75万ドル(約9000万円)に成長し、年間3万ドルの配当を生みます。これで、老後の生活費をカバーする基盤が整います。
| 投資期間 | 月額投資 | 最終資産 | 年間配当 |
|---|---|---|---|
| 35年 | $500 | $750,000 | $30,000 |
| 20年 | $500 | $250,000 | $10,000 |
このシミュレーションからわかるのは、早期の積立が大きな差を生むこと。配当金生活は、時間を味方にすれば現実的な目標です。ただし、税金(米国源泉税10%、日本での20.315%)やインフレの影響を考慮し、余裕を持った計画が重要です。
VNQの配当は、夢の第一歩。コツコツ投資を続ければ、働かずとも収入を得る未来が手に入ります。
VNQとよく比較されるETFは?
| ETF | ティッカー | 経費率 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| VNQ | VNQ | 0.12% | 幅広いREIT、バランス型 |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | 0.07% | 低コスト、VNQよりやや集中型 |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | 0.39% | REITに加え不動産関連株も含む |
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR | 0.09% | 大型REIT中心、セクター特化型 |
SCHHは、経費率がVNQより低い点で魅力的。ただし、銘柄数が約100と少なく、分散度はVNQに劣ります。IYRは、不動産管理会社なども含むため、REIT以外の値動きも反映。より広範な不動産投資を求める人に適しています。XLREは、S&P 500の不動産セクターに連動し、約30銘柄に集中投資。成長重視の人向けですが、変動リスクは高めです。
パフォーマンスでは、過去10年でVNQとSCHHがほぼ同等(年4-5%)。IYRは非REIT銘柄の影響でやや不安定、XLREは大型株の強さで上振れする年もあります。配当利回りは、VNQの3.8%に対し、SCHHが3.5%、IYRが3.0%、XLREが3.2%と、VNQがやや優勢です。
どのETFを選ぶかは、投資目標次第。低コストと分散を求めるならVNQ、さらなるコスト削減ならSCHH、成長性を重視するならXLREが候補に挙がります。自分のリスク許容度と相談しながら選ぶのが賢明です。
VNQと合わせてポートフォリオに加えたほうがいいETFは?
| ETF | ティッカー | 資産クラス | 特徴 |
|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 株式 | 米国株式市場全体、低コスト |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 債券 | 債券市場全体、安定性重視 |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 国際株式 | 米国以外の株式、グローバル分散 |
| GLD | SPDR Gold Shares | 金 | インフレヘッジ、代替資産 |
VTIは、VNQの不動産特化を補完する米国株式の総まとめ。経費率0.03%で、テクノロジーやヘルスケアなど成長セクターをカバーします。VNQとの相関は中程度で、株式市場の急落時も不動産がクッションになる可能性があります。
BNDは債券ETFの定番。金利上昇でREITが苦戦する局面でも、債券は安定性を発揮。経費率0.03%と低く、VNQの配当収入を補うインカム源にもなります。
VXUSは、グローバルな視点を取り入れる選択肢。日本、欧州、新興国を含む国際株式に投資し、米国の不動産リスクを分散。VNQと組み合わせることで、地域的な経済ショックへの耐性が上がります。
GLDは、インフレや通貨不安への備え。金は不動産や株式と異なる値動きをし、ポートフォリオの安定性を高めます。ただし、配当がない点は注意が必要です。
理想的な配分例は、VNQ:20%、VTI:40%、BND:30%、GLD:10%など。リスク許容度に応じて調整し、定期的にリバランスするのがポイント。VNQを中心に、資産クラスを広げることで、どんな市場環境でも安心感が増します。
まとめ
VNQは、不動産投資の魅力を手軽に味わえるETFです。低コスト、分散性、配当の安定感を兼ね備え、長期投資の強力なパートナーとなるでしょう。過去20年のパフォーマンスは、経済の荒波を乗り越える実力を証明。データセンターや物流といった成長分野を取り込み、未来への可能性も広がっています。
配当を活用すれば、不労所得の夢も現実味を帯びます。毎月の積立投資で、30年後には生活を支える収入源に育つ可能性も。金利や経済環境の変化には注意が必要ですが、忍耐強く保有すれば、複利の魔法が資産を膨らませてくれるはずです。
他のETFとの組み合わせで、ポートフォリオはさらに強固に。株式、債券、金を加えれば、どんな市場環境にも対応できるバランスが生まれます。VNQは、単なる投資商品ではなく、人生の目標を支える基盤。今日の一歩が、豊かな未来への第一歩になるのです。さあ、VNQとともに、資産形成の旅を始めてみませんか。
他の人気ETFの記事はこちら
FANG+は今後も伸びるのか。PER・PBR・営業キャッシュフローから考えてよう
この記事のポイント FANG+は、AI・クラウド・半導体・広告・サブスクの主要分野を押さえており、売上高や営業キャッシュフロー、OCFマージンも高水準の企業に効率よく投資可能 PER・PBRは高めでも…
DVYとは?米国高配当株に絞ったETF。インカム・キャピタルの両取りができる初心者にもおすすめのETF
この記事のポイント DVYは高配当株ETFで、利回り3.5%、経費率0.38%。公益事業・金融セクター中心で安定志向 過去10年で年平均成長率7.6%。S&P500(13.4%)やNASDAQ…
NOBLとは?S&P500の配当貴族に絞って投資ができる優良ETF
この記事のポイント NOBLは25年以上連続増配の企業に投資するETFで、安定性と配当成長が強み。 過去10年のCAGRは8%、下落局面ではS&P 500やNASDAQ 100より耐性高い。 …
USOIとは?毎月配当型の原油価格の変動に連動するETF。玄人向けの商品
この記事のポイント USOIは原油ベースの高配当ETN。月次配当とカバードコール戦略が魅力 過去のパフォーマンスは年平均2.8%で、S&P500やNASDAQ100に比べ成長率は控えめだが配当…
SPHDとは?米国のS&P500指数に含まれる銘柄から、高配当かつ低ボラティリティの50銘柄を選び抜いたETF
この記事のポイント 高配当(4.5%)と低ボラティリティを両立、公益事業・金融中心の50銘柄で安定性抜群。 過去10年で年平均リターン7.2%、下落局面でも配当がクッションに。 約9,500万円投資で…
PFFとは?優先株に投資するETF。毎月配当型のETFで安定した配当収益を得れる
この記事のポイント PFFは優先株ETFで、6.3%の配当利回りと月次配当が魅力。 金融セクター80%超の構成で、金利動向に敏感な点に注意。 10年リターンは約5%。成長よりインカムゲイン重視の投資家…
SDIVとは?世界中の高配当株に投資する毎月配当型のETF。配当生活は可能か?
この記事のポイント SDIVは約11%の配当利回りで、毎月配当が得られ、キャッシュフローを重視する投資家に最適。 100銘柄に均等加重で投資し、米国や新興国を含む地域リスクの軽減が特徴。 約4700万…
XYLDとは?配当金生活を狙えるS&P500に投資する毎月配当型のETF
この記事のポイント XYLDはS&P 500にカバードコール戦略を組み合わせ、約9~12%の高配当を実現。 株価成長は控えめだが、下落相場での耐性と毎月分配が魅力。 セクター分散が効き、テクノ…
QYLDとは?毎月配当型のETF。インカム重視の投資家におすすめ!配当金生活を目指そう
この記事のポイント QYLDはカバードコール戦略で高分配(年10~12%)と低ボラティリティを実現。インカム重視の投資家に最適。 株価成長率は0.66%と低いが、分配金再投資で50年で資産33倍の可能…
VTEBとは?少し特殊な米国地方債に投資するETF。毎月配当金が得つつ、資金を避難させる先として最適
この記事のポイント VTEBは米国地方債ETF。経費率0.05%、利回り3.1%で税免除メリット。 10年平均成長率0.8%、騰落率±2.5%。株式ETFより低リスク。 毎月配当でキャッシュフロー安定…
【SOXS】半導体セクターに特化した3倍レバレッジのインバースETF。短期トレードに特化
この記事のポイント 半導体セクターの3倍インバースETF。短期トレードに特化し、経費率1.03%、配当利回り2.5%。 過去5年平均リターン-48.1%。2022年+45.8%だが、長期保有はで不向き…
【EWG】ドイツの株式市場に投資するETF。大型株および中型株を中心に構成(iShares MSCI Germany ETF)
この記事のポイント EWGはドイツ市場に特化したETFで、自動車や金融セクターの強みを低コストでポートフォリオに追加可能。 過去の平均リターン6.8%、配当利回り2.03%で、長期投資と安定収入を両立…
【MBB】米国の住宅ローン担保証券(MBS)に投資するETF。債券の中でも利回り重視の投資に向く
この記事のポイント MBBは低コスト(経費率0.06%)で毎月分配金を提供するMBS特化の債券ETF。安定性とインカム収益が魅力 過去10年リターンは1.15%、S&P500(12.8%)やN…
【SCHB】米国株式市場全体に分散投資するETF。低コストで大型・中型・小型株を網羅し、長期投資向け
この記事のポイント SCHBは経費率0.03%、2,500銘柄で米国市場98%をカバーし、初心者にも最適。 過去15年で年平均10.5%のリターン。小型株の成長性と大型株の安定性を両立。 S&…
【IAU】金価格に連動する低コストETF。GLDと同様に金現物を保有し、インフレヘッジや安全資産として活用
この記事のポイント 経費率0.25%で金価格に連動するETF。リスク分散やインフレヘッジに最適で、流動性と信頼性が高い。 過去10年で年平均7.6%。S&P500やNASDAQ100より低いが…
【SCHG】米国の大型成長株に特化したETF。低コストでハイテク企業中心の成長ポートフォリオ
この記事のポイント SCHGは低コストで米国大型成長株に投資でき、長期的な資産成長を追求する投資家に最適 過去の株価推移や成長率(年平均15%のリターン)から、今後も高いリターンと安定性を見いだせる …
【IWB】iShares Russell 1000 ETF|米国の大型株に投資するETF。ラッセル1000指数連動で、S&P500よりやや銘柄範囲が広い
この記事のポイント 米国の大型・中型株約1,000銘柄をカバーし、低コストで分散投資が可能 テクノロジーや金融など多様なセクター構成で、リスク分散 過去の株価推移や配当実績から、長期投資に適した安定感…
【MUB】米国の地方債(ミュニシパルボンド)に投資するETF
この記事のポイント MUBは連邦税免税の地方債ETF。低リスクかつ安定したリターンを提供し、ポートフォリオの基盤に最適 毎月分配型の配当により、定期収入や複利効果による資産成長を目指せる 経費率0.0…
【COWZ】米国農業関連株ETF|高キャッシュフロー銘柄に特化したETF
この記事のポイント フリーキャッシュフロー重視。財務健全な米国企業に投資。市場変動に強く、長期的な資産成長を狙える 月次配当で安定収入を確保しつつ、過去平均13%のリターンでインフレを上回る資産拡大を…
【MDY】S&P400(米国中型株)に投資するETF
この記事のポイント MDYは米国の中型企業に投資するETFで、大型株より高い成長力と小型株より安定性を兼ね備えている 過去20年の平均リターン約8-9%と、分散投資によるリスク低減で、資産形成に適した…
【IWR】米国の中型株に投資するETF。成長ポテンシャルと安定性のバランスが取れたミッドキャップに注目
この記事のポイント 米国中型株に分散投資でき、成長性と安定性を両立。低コストで長期投資に最適 四半期配当で安定収入、過去10年平均リターン10.2%で資産拡大を期待できる VTIやIXUSと組み合わせ…
【SPYV】S&P500構成銘柄のうちバリュー株に特化したETF。配当重視・割安株投資を好む投資家向け
この記事のポイント SPYVは低コストでバリュー株に投資でき、2.2%の配当利回りと市場下落時の安定性が長期資産形成の基盤となる 金融・ヘルスケア中心のセクター分散と7.2%の過去リターンから、100…
【IVE】S&P500構成銘柄のうちバリュー株に特化したETF
この記事のポイント iシェアーズ S&P 500 バリューETF(IVE)は、低コストでバリュー株に投資し、安定性と成長性を両立 金融・ヘルスケア中心のセクター構成と約1.8%の配当利回りで、…
【SPYG】S&P500構成銘柄のうち成長株に特化したETF。ハイテク比率が高く、成長期待を重視する投資家向け
SPYGのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
【BIL】満期1年未満の米国短期国債に投資するETF|SPDRブルームバーグ1-3ヶ月TビルETF
BILのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。