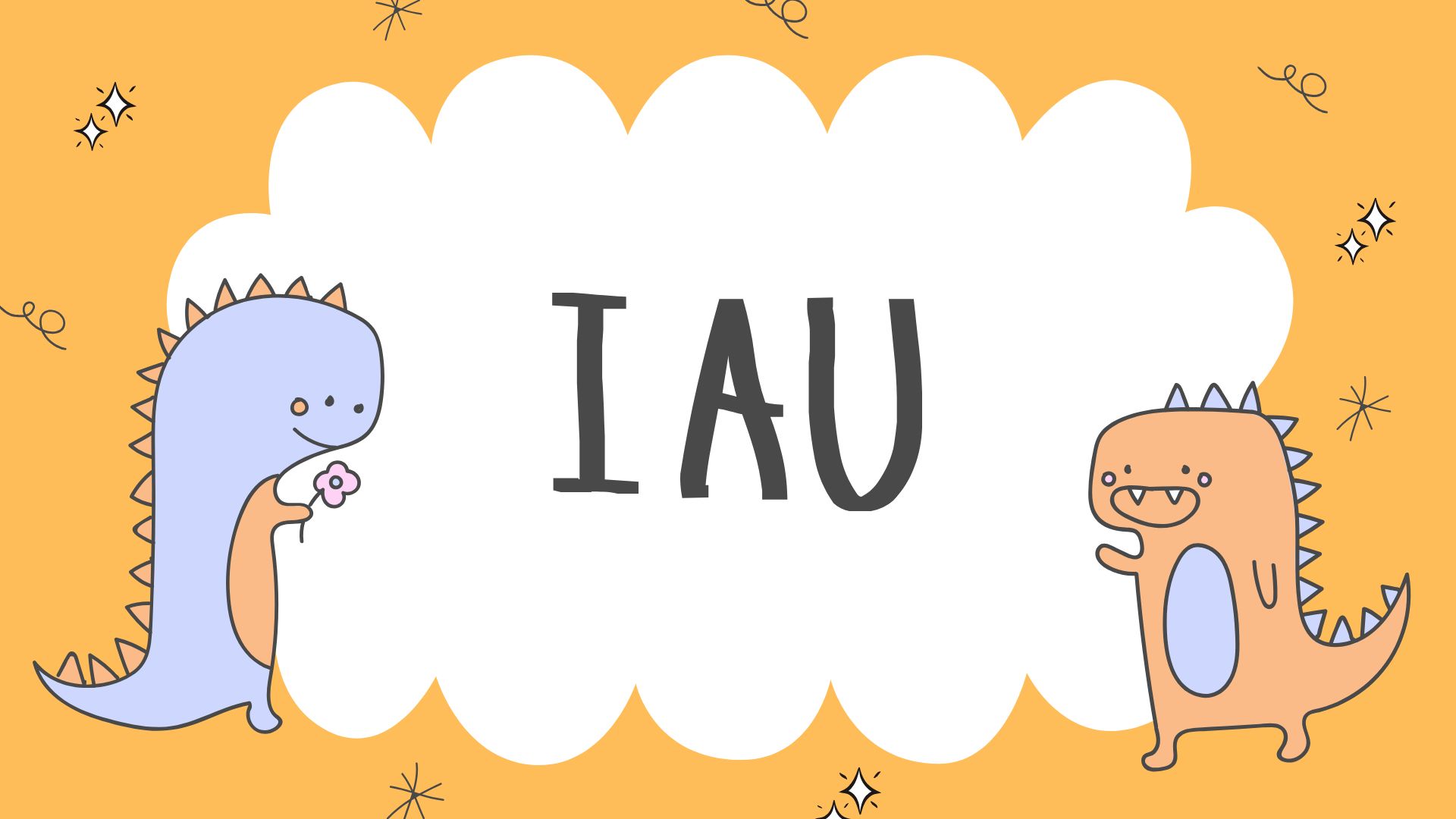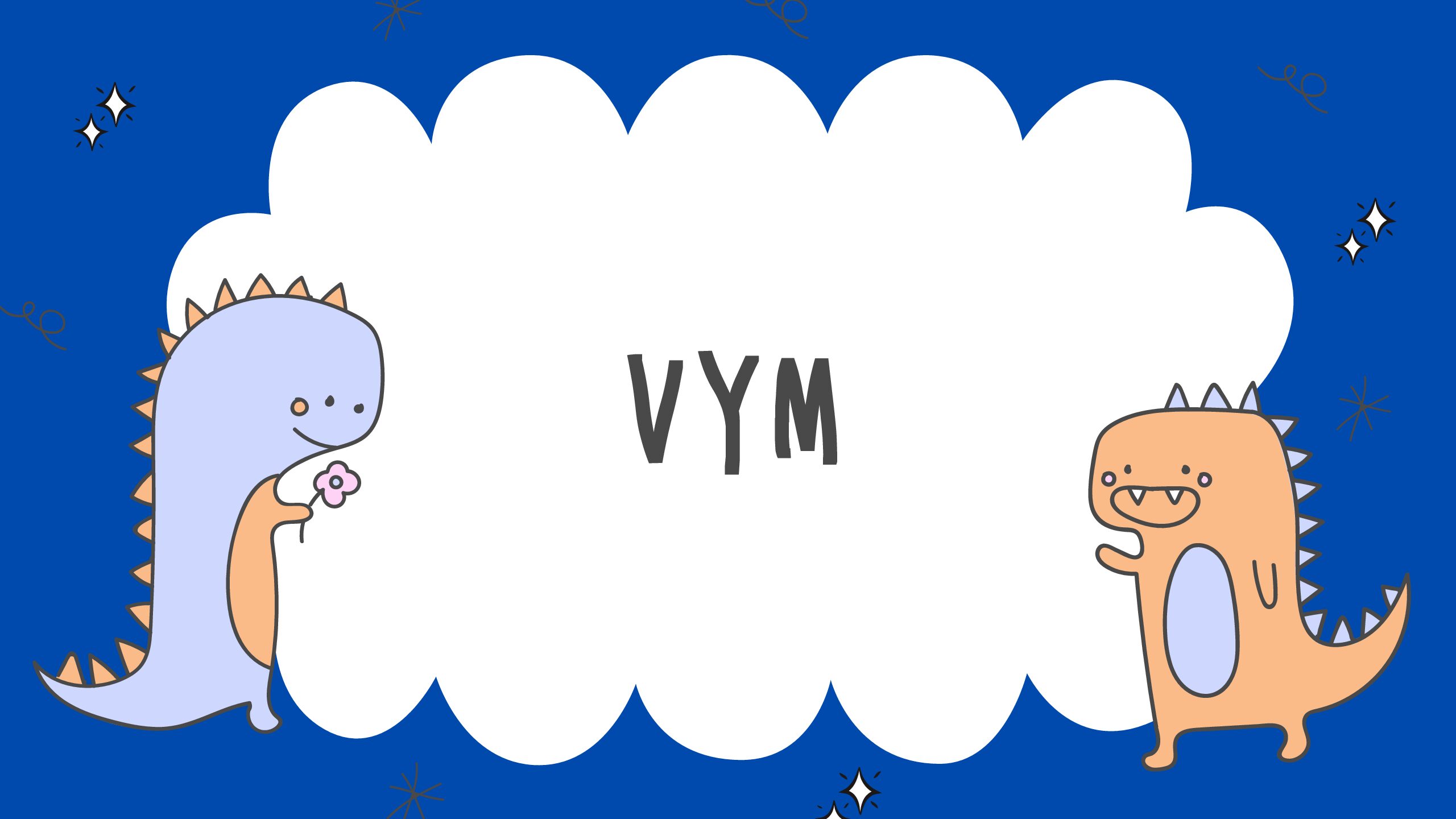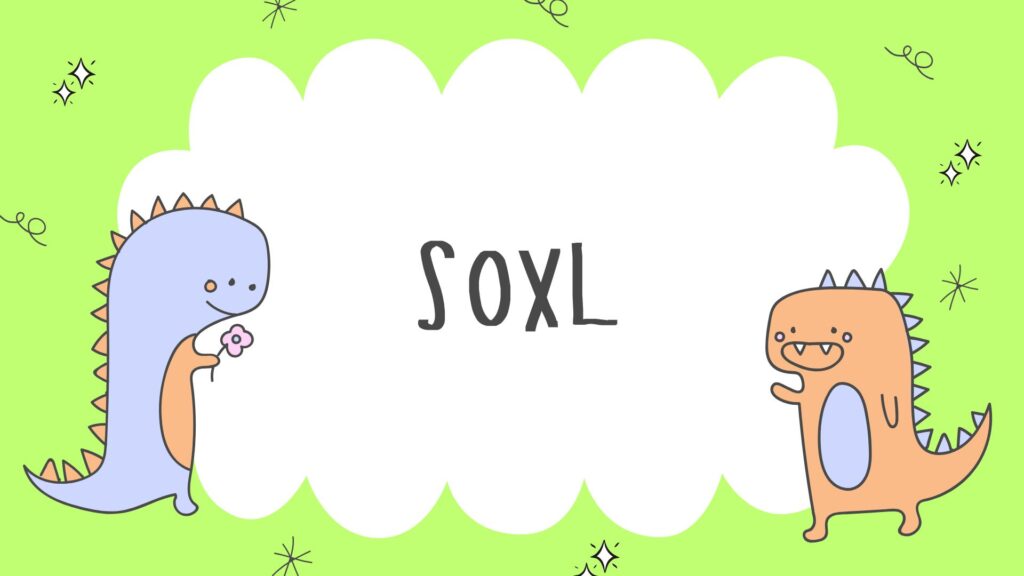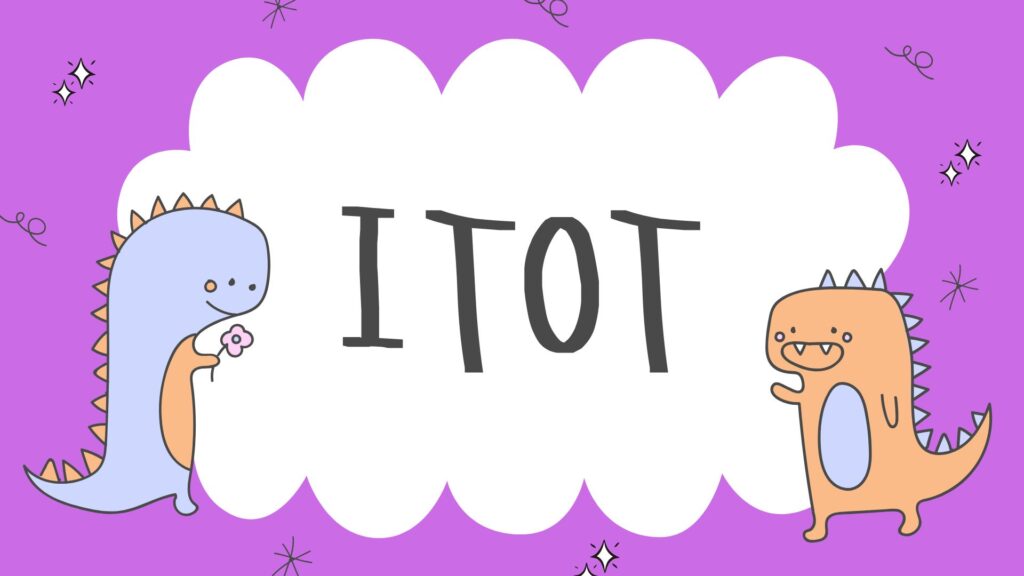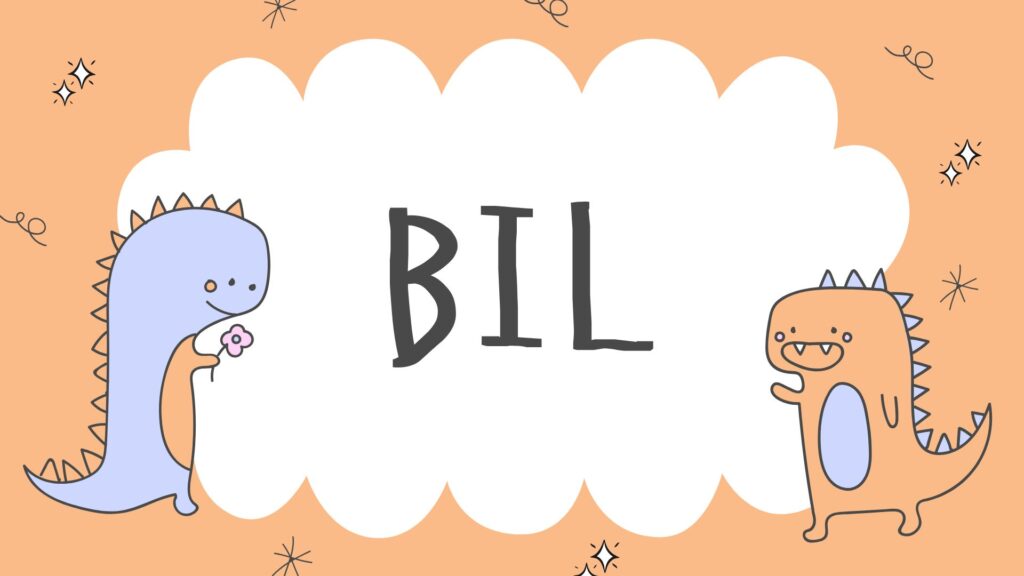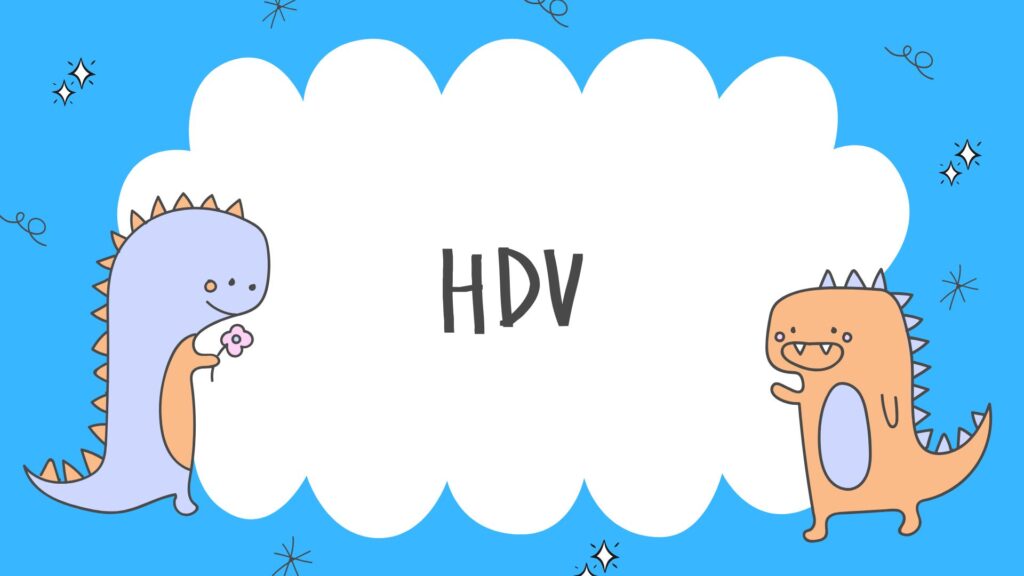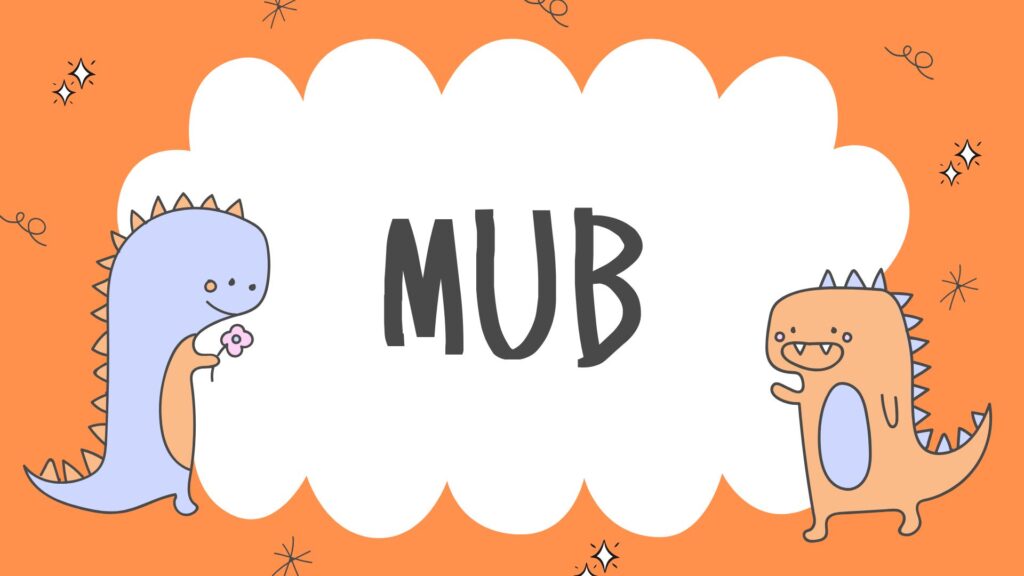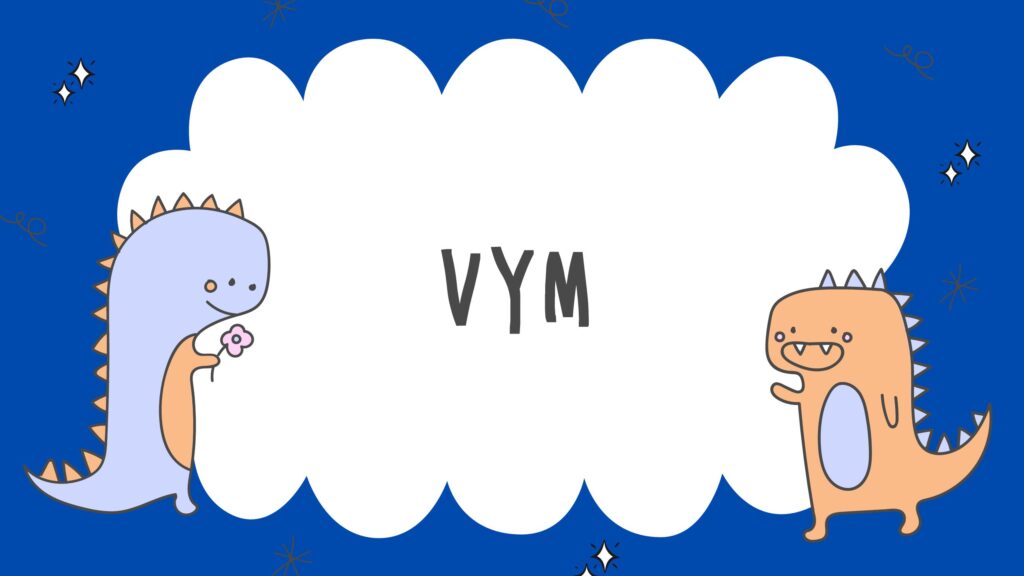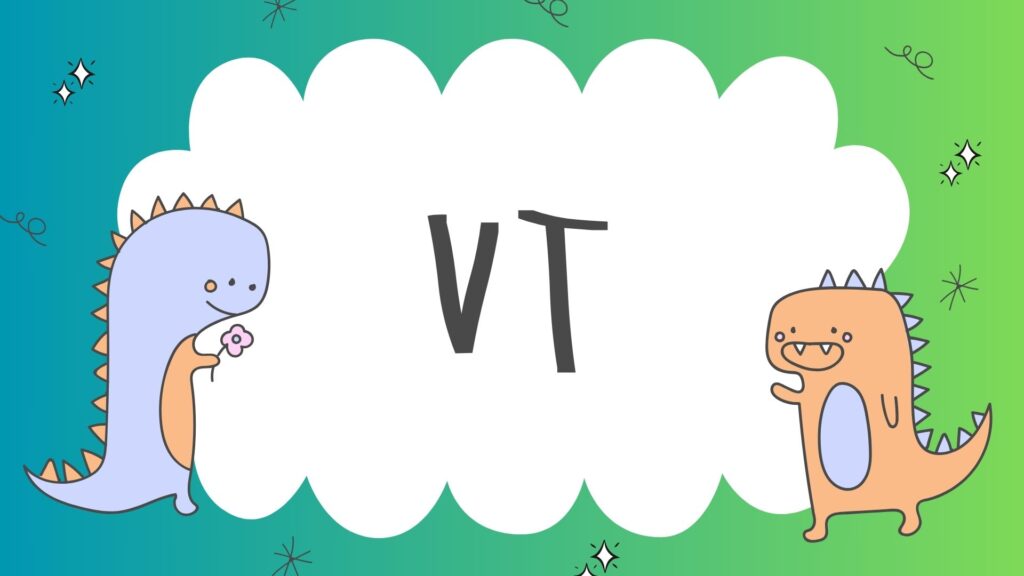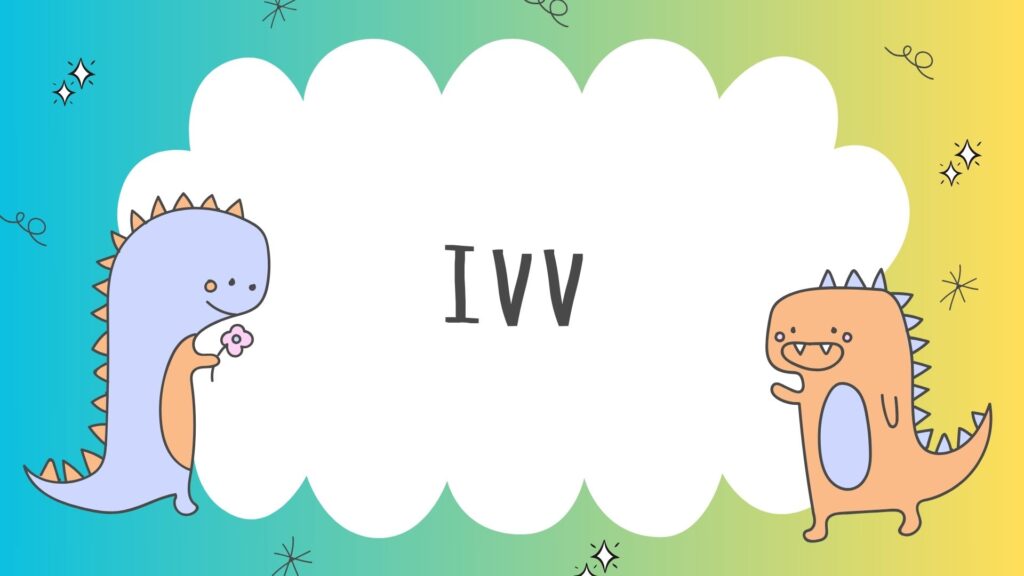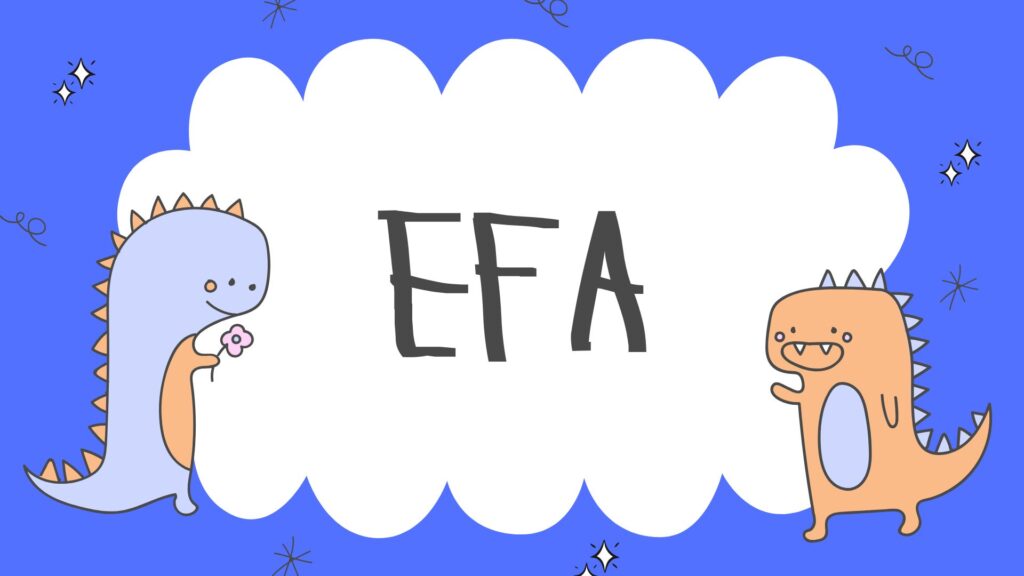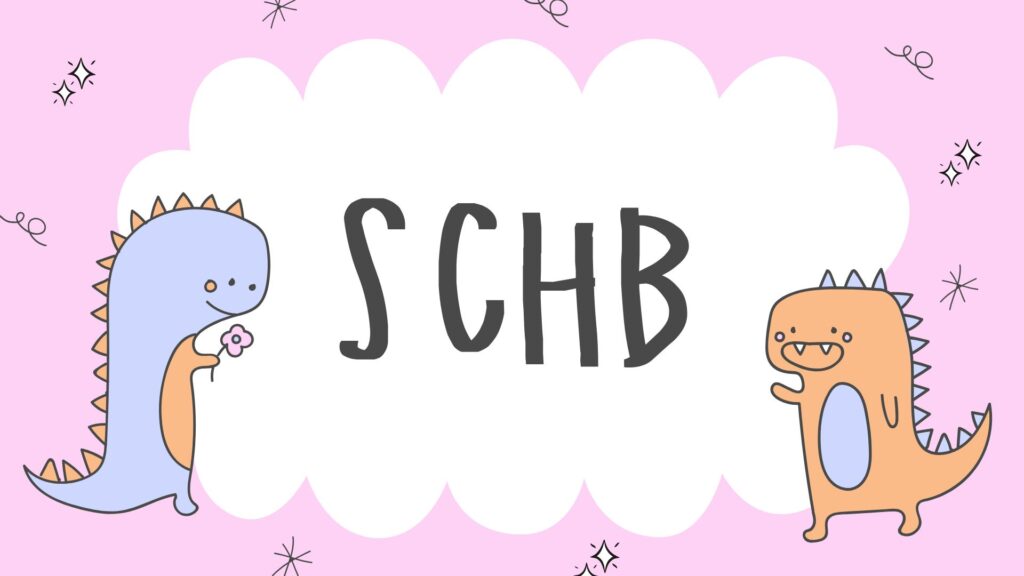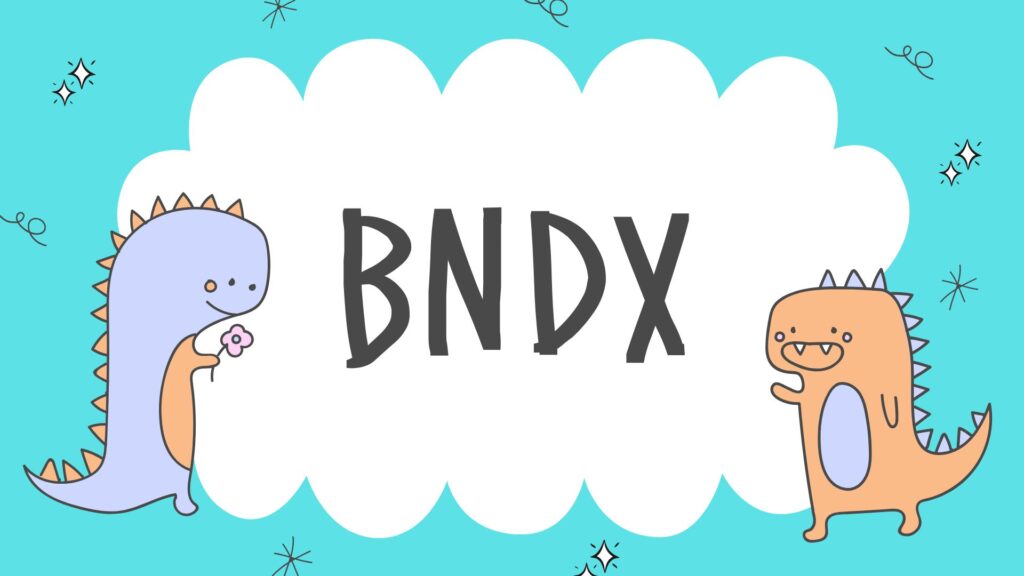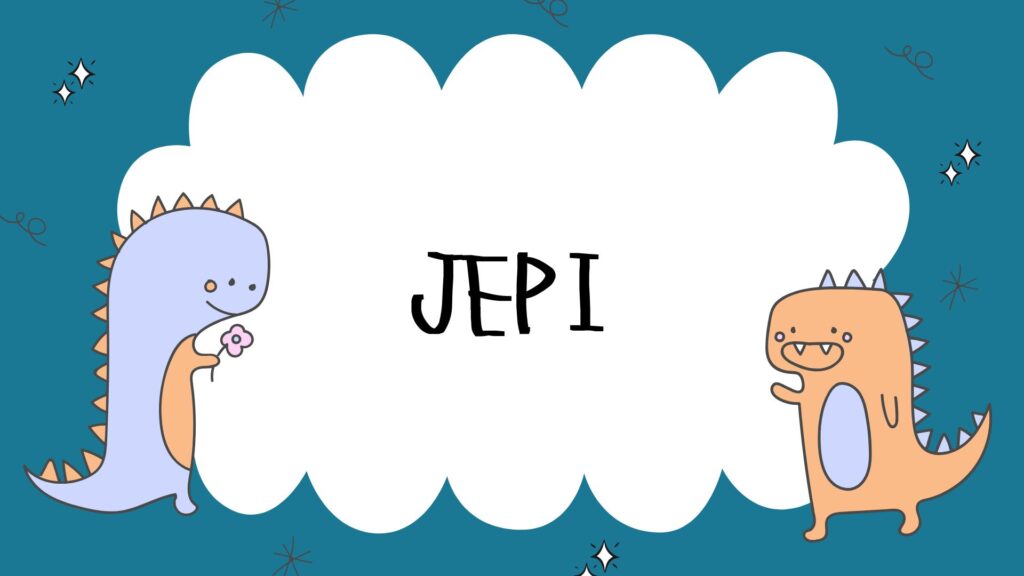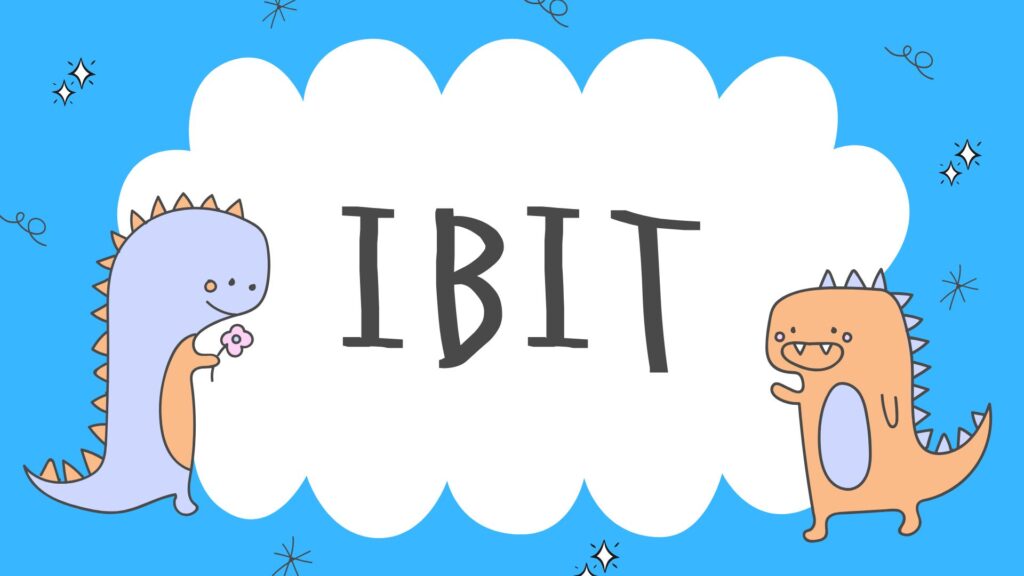この記事のポイント
IAUの特徴

IAUって金そのものに投資するETFだよ!特徴とお得なポイントをバッチリまとめちゃうね!
iShares Gold Trust(IAU)は、金の価格に連動するETFとして、投資家にシンプルかつ低コストで金への投資機会を提供します。金はインフレヘッジや経済不安時の安全資産として知られ、ポートフォリオの多様化に役立ちます。IAUは物理的な金塊を保有し、その価格変動を反映する仕組みです。運用はBlackRockが行い、信頼性が高い点も魅力です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ティッカー | IAU |
| 運用会社 | BlackRock |
| 設定日 | 2005年1月21日 |
| 資産総額 | 約450億ドル(2025年4月時点) |
| 経費率 | 0.25%(低コストで魅力的) |
| 投資対象 | 物理的な金(金塊をロンドンやニューヨークの保管庫で保有) |
| 取引所 | NYSE Arca |
| 配当 | 配当なし(金の価格変動がリターンの主な源泉) |
| ベンチマーク | LBMA金価格(ロンドン金市場協会の金価格) |
IAUの最大の特徴は、金そのものに投資できる点です。金は株や債券とは異なる値動きをするため、ポートフォリオのリスク分散に有効です。また、経費率が0.25%と低く、長期投資に向いています。金の現物を自分で購入する場合、輸送や保管のコストがかかりますが、IAUならその手間が不要です。さらに、流動性が高く、取引所で簡単に売買できるのも強みです。
- 低コスト運用:経費率0.25%は金ETFの中でも競争力があり、長期保有のコストを抑えます。
- インフレ対策:金はインフレ時に価値を保つ傾向があり、購買力の保護に役立ちます。
- 安全資産:経済危機や地政学リスク時に価格が上昇しやすい金の特性を活かせます。
- 高い流動性:NYSE Arcaでの取引量が多く、いつでも売買しやすいです。
- シンプルな仕組み:金価格に連動する分かりやすい設計で、初心者にも親しみやすいです。
IAUの株価・推移・成長率(パフォーマンス)

IAUの株価、どんな風に動いてきたか見てみよう!過去のリターンもガッツリ分析するよ!
※S&P500指数と比較
IAUの株価は、金のスポット価格(LBMA金価格)にほぼ連動します。金価格は経済状況やインフレ、地政学リスク、米ドル価値など複数の要因に影響されます。
| 年 | 年別リターン(%) | 年末株価(ドル) |
|---|---|---|
| 2015 | -10.4% | 10.23 |
| 2016 | 8.1% | 11.06 |
| 2017 | 12.8% | 12.47 |
| 2018 | -1.5% | 12.28 |
| 2019 | 18.2% | 14.51 |
| 2020 | 24.6% | 18.08 |
| 2021 | -4.0% | 17.36 |
| 2022 | 0.3% | 17.41 |
| 2023 | 12.7% | 19.62 |
| 2024 | 15.5% | 22.66 |
過去10年間の平均年リターンは約7.6%です。金の価格は、2019~2020年の上昇期(米中貿易摩擦やコロナ禍による経済不安)や2023~2024年の上昇期(インフレ懸念や地政学リスク)に強いパフォーマンスを見せました。一方、2015年や2021年のように、金価格が下落する年もあり、変動性がある点は留意が必要です。
長期的な視点では、2005年の設定以来、IAUの年平均リターンは約6.5%(2025年4月時点)。これは株式市場の平均リターン(S&P500の約10%)に比べると低めですが、金は値動きが株式と異なるため、ポートフォリオの安定性を高めます。たとえば、2022年の株式市場下落時、IAUはほぼ横ばいで推移し、リスク分散効果を発揮しました。
株価推移を見ると、2020年にピーク(約20ドル)を記録後、2021年に一時下落しましたが、2023年以降は再び上昇トレンドにあります。2025年4月時点の株価は約23ドルで、過去最高値に近い水準です。この背景には、米国の利上げ鈍化やドル安傾向、インフレ懸念の継続があります。
投資家にとって、IAUのリターンは金の需給バランスやマクロ経済環境に左右される点が重要です。金価格は短期的には変動しますが、長期ではインフレ調整後の価値を保つ傾向があります。したがって、IAUは短期の値上がり益を狙うより、資産保全やリスクヘッジを目的とした投資に適しています。
IAUと主要指数の比較

IAUと他の主要指数、どれがどう強い?表でバッチリ比較して、投資のヒント探すよ!
IAU(金ETF)は、S&P500(米国大型株)、NASDAQ100(テクノロジー中心)、MSCI ACWI(グローバル株式)のETFと比較すると、異なる特性を持ちます。
| 項目 | IAU | S&P500 (IVV) | NASDAQ100 (QQQ) | MSCI ACWI (ACWI) |
|---|---|---|---|---|
| 10年CAGR(%) | 7.6% | 12.8% | 17.5% | 9.8% |
| 2018年下落率(%) | -1.5% | -4.4% | -0.1% | -9.4% |
| 2020年コロナショック(%) | 24.6% | 18.4% | 48.6% | 16.3% |
| 2022年下落率(%) | 0.3% | -18.1% | -32.4% | -18.4% |
CAGR比較
S&P500(IVV)やNASDAQ100(QQQ)は、経済成長やテクノロジー企業の躍進により、IAUを上回るリターンを記録しました。特にQQQは17.5%と高い成長率です。一方、MSCI ACWI(ACWI)は新興国を含む分、S&P500よりやや低めですが、IAUより高いリターンです。IAUの7.6%は控えめですが、安定性が強みです。
騰落率の特徴
2018年の市場調整時、IAUは-1.5%と軽微な下落にとどまり、株式ETFより安定していました。2020年のコロナショックでは、IAUが24.6%の上昇を見せ、QQQ(48.6%)に次ぐ好成績でした。しかし、2022年の株式市場下落時、IAUはほぼ横ばい(0.3%)で、S&P500(-18.1%)やNASDAQ100(-32.4%)の大幅下落を回避しました。
投資の視点
IAUは株式市場が下落する局面で輝きます。金は「安全資産」として、経済不安やインフレ時に価値を保つ傾向があります。一方、S&P500やNASDAQ100は経済成長期に強いリターンをもたらします。MSCI ACWIは地域分散が効いており、バランス型投資に適します。したがって、IAUはポートフォリオの守りを固める役割を果たし、株式ETFと組み合わせることでリスクを抑えつつリターンを追求できます。
IAUのセクター構成

IAUのセクター構成、実はめっちゃシンプル!金の魅力、しっかり掘り下げていくよ!
IAUは金ETFであり、株式や債券のようなセクター構成は存在しません。代わりに、投資対象は100%物理的な金(金塊)です。このシンプルさがIAUの特徴であり、セクター分散を考える必要がない点でユニークです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 投資対象 | 物理的な金(100%) |
| セクター | なし(金は単一の資産クラス) |
| 保管場所 | ロンドン、ニューヨークなどのセキュアな保管庫 |
| 純度 | 99.99%以上の金塊 |
| 価格連動 | LBMA金価格(1日2回の価格設定に基づく) |
IAUに長期投資した場合のシミュレーション

IAUに50年投資したらどうなる?円でガッツリシミュレーションしてみるよ!
IAUへの長期投資がどのような成果をもたらすかを、50年間のシミュレーションで検証します。金価格の過去データに基づき、年平均リターン6.5%(過去20年の平均)を仮定し、為替レート(1ドル=150円、2025年4月時点)で円換算します。投資額は100万円(約6,667ドル)からスタートし、複利効果を考慮します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 初期投資額 | 100万円(6,667ドル) |
| 年平均リターン | 6.5%(経費率0.25%を差し引き後) |
| 投資期間 | 50年 |
| 為替レート | 1ドル=150円(固定で計算、変動リスクは後述) |
| 計算方法 | 複利計算(A = P(1+r)^n、P=初期投資、r=年リターン、n=年数) |
シミュレーション結果
100万円をIAUに投資し、年6.5%で50年間運用した場合、複利計算により最終資産は以下の通りです。
- 50年後の資産額:約2,430万円(約162,000ドル)
- 利益:約2,330万円(初期投資の23倍以上)
この成長は、金価格の長期的な上昇傾向に基づいています。過去50年(1975~2025年)の金価格は、年平均で約5~7%上昇しており、インフレ調整後の価値を保つ傾向があります。たとえば、1970年代のインフレ危機や2008年の金融危機、2020年のコロナ禍で金は大きく上昇しました。
現実的な投資戦略
50年は長いため、途中で市場環境が変わる可能性が高いです。たとえば、20年ごとにリバランスを行い、IAUの割合を5~10%に保つ戦略が現実的です。100万円を全額IAUに投資するより、株式や債券と組み合わせることで、リターンを高めつつリスクを抑えられます。仮に、IAU(20%)、S&P500(60%)、債券(20%)のポートフォリオなら、年平均リターン8~9%が期待でき、50年で約4,000万円に成長する可能性があります。
IAUの配当タイミングと直近の配当

IAUの配当ってどうなってる?実はちょっと特殊!詳しくチェックしていくよ!
IAU(iShares Gold Trust)は、金価格に連動するETFであり、株式ETFのような配当金は支払われません。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 配当の有無 | なし(金は配当や利息を生まない資産) |
| リターン源泉 | 金価格の値上がり益 |
| 経費率 | 0.25%(運用コストとして資産から差し引き) |
| 税金 | 売却時に譲渡益税(日本では20.315%)が適用 |
| 分配金代替 | なし(金価格の上昇が投資家の利益) |
配当がない理由
IAUは物理的な金塊を保有し、その価格変動を反映します。金は企業のように利益を分配しないため、配当や分配金は発生しません。投資家にとってのリターンは、IAUの株価上昇(金価格の上昇)によるキャピタルゲインです。たとえば、2023~2024年に金価格が15%上昇したことで、IAUの株価も同様に上昇し、投資家は利益を得ました。
IAUは配当がない分、シンプルで値動きに集中できるETFです。金価格の上昇を長期的に信じる投資家にとって、配当がないことはデメリットではなく、税負担を遅らせられるメリットとも言えます。投資目的に応じて、IAUの特性を活かした戦略を立てましょう。
IAUとよく比較されるETFは?
IAU(iShares Gold Trust)は金ETFとして人気ですが、他の金ETFや類似の資産クラスETFと比較されることが多いです。
| 項目 | IAU | GLD | SGOL | GLDM | SLV |
|---|---|---|---|---|---|
| ティッカー | IAU | GLD | SGOL | GLDM | SLV |
| 運用会社 | BlackRock | State Street | Aberdeen | State Street | BlackRock |
| 経費率 | 0.25% | 0.40% | 0.17% | 0.10% | 0.50% |
| 資産総額 | 約450億ドル | 約650億ドル | 約30億ドル | 約80億ドル | 約150億ドル |
| 投資対象 | 物理的な金 | 物理的な金 | 物理的な金 | 物理的な金 | 物理的な銀 |
| 設定日 | 2005年 | 2004年 | 2009年 | 2018年 | 2006年 |
| 流動性 | 高い | 非常に高い | 中程度 | 高い | 高い |
| 1株あたりの金 | 約0.0095オンス | 約0.094オンス | 約0.1オンス | 約0.01オンス | 銀約1オンス |
比較ポイント
- GLD(SPDR Gold Shares):金ETFの最大手で、資産総額と流動性がトップ。経費率0.40%はIAUより高めですが、機関投資家に人気です。1株あたりの金量が多く、価格がIAUの約10倍です。
- SGOL(Aberdeen Standard Physical Gold Shares):経費率0.17%と低コスト。スイスに金保管庫を持ち、透明性を重視。資産総額は小さめで、流動性がやや劣ります。
- GLDM(SPDR Gold MiniShares):経費率0.10%と最安。少額投資向けで、1株あたりの金量が小さい。設定が新しく、長期実績はIAUに劣ります。
- SLV(iShares Silver Trust):銀に投資するETF。銀は金より価格変動が大きく、工業需要に影響されます。経費率0.50%は高めです。
IAUは、経費率、流動性、運用実績のバランスが優れており、幅広い投資家に適しています。GLDは大口投資家向け、GLDMは少額投資家向け、SGOLは低コスト志向の投資家向けです。SLVは金とは異なる値動きを求める場合に検討価値があります。投資目的や資金規模に応じて、IAUとこれらのETFを比較検討しましょう。
IAUと合わせてポートフォリオに加えたほうがいいETFは?
IAUは金ETFとしてリスク分散に優れますが、単体では成長性や配当収入が限られます。ポートフォリオのバランスを高めるため、株式、債券、配当重視のETFと組み合わせるのが賢明です。
| 項目 | IVV | BND | VYM | ACWI |
|---|---|---|---|---|
| ティッカー | IVV | BND | VYM | ACWI |
| 運用会社 | BlackRock | Vanguard | Vanguard | BlackRock |
| 経費率 | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.32% |
| 資産総額 | 約5000億ドル | 約1000億ドル | 約700億ドル | 約200億ドル |
| 投資対象 | S&P500(米国大型株) | 米国債券(総合) | 米国高配当株 | グローバル株式 |
| 配当利回り | 約1.3% | 約3.5% | 約3.0% | 約1.8% |
| 設定日 | 2000年 | 2007年 | 2006年 | 2008年 |
推奨ポートフォリオ例
- IAU(10%):リスクヘッジと資産保全。
- IVV(50%):米国経済の成長を捉える。
- BND(20%):安定性とインカムゲイン。
- VYM(10%):高配当でキャッシュフロー。
- ACWI(10%):新興国を含むグローバル分散。
各ETFの役割
- IVV(iShares Core S&P 500 ETF):S&P500に連動し、年平均リターン約10%。テクノロジーや金融セクターの成長を捉えます。IAUの低成長を補完。
- BND(Vanguard Total Bond Market ETF):米国債券に幅広く投資。金と同様に安定性が高く、株式市場下落時のクッション役。配当収入も魅力。
- VYM(Vanguard High Dividend Yield ETF):高配当株に投資し、年3%の配当利回り。IAUの配当ゼロを補い、定期的なキャッシュフローを提供。
- ACWI(iShares MSCI ACWI ETF):米国以外の先進国・新興国を含むグローバル株式。地域分散を強化し、IAUの単一資産リスクを軽減。
IAUをポートフォリオの「守りの柱」として活用し、IVV、BND、VYM、ACWIで成長と収入を補完することで、どんな市場環境でも安定した成果を狙えます。
FAQ(よくある質問)
- QIAUはどれくらいの割合でポートフォリオに組み込むべき?
- A
IAUの理想的な割合は、投資家のリスク許容度や目標によりますが、一般的にはポートフォリオの5~10%が推奨されます。金は株式や債券と相関が低く、市場下落時のリスクヘッジに有効です。たとえば、100万円のポートフォリオなら5~10万円をIAUに割り当て、残りを株式(60%)、債券(30%)などに分散するのがバランス型です。リスク回避を重視するなら15%まで増やしても良いですが、20%を超えると金の変動リスクが目立つため注意が必要です。定期的にリバランスを行い、割合を維持しましょう。
- QIAUの金は本当に安全に保管されているの?
- A
はい、IAUの金は非常に安全に保管されています。BlackRockが管理し、ロンドンやニューヨークの厳重な保管庫に99.99%以上の純度の金塊が保管されています。これらの保管庫は、盗難や災害に備えたセキュリティと保険が完備されています。また、IAUの金保有量は定期的に第三者監査を受け、透明性が確保されています。公式ウェブサイトや年次報告書で保有量や監査結果を確認できるため、信頼性は高いです。投資家は物理的な金を直接管理する手間なく、安心して投資できます。
- QIAUは短期投資にも向いている?
- A
IAUは短期投資より長期投資に向いています。金価格は短期的には変動が大きく、たとえば1年で10~20%上下することがあります。2023~2024年の上昇相場では15%のリターンを記録しましたが、2013年のような下落相場では損失が出ます。短期で利益を狙う場合、タイミングを見極めるのが難しく、リスクが高いです。一方、10年以上の長期では、インフレ調整後の価値を保つ傾向があり、資産保全に適しています。短期投資を希望するなら、テクニカル分析や金価格のトレンドを注視し、少額で試すのが賢明です。
IAUのETF Score (ETFのおすすめ度)
- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出
- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出
- 運用コスト:経費率をもとに算出
- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出
- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出
※各指標は当サイトにおける基準で設定
まとめ
IAU(iShares Gold Trust)は、金価格に連動するETFとして、投資家にシンプルかつ低コストで金への投資機会を提供します。経費率0.25%、高い流動性、信頼性の高い運用が特徴で、ポートフォリオのリスク分散や資産保全に最適です。金はインフレヘッジや経済不安時の安全資産として機能し、株式や債券とは異なる値動きで安定性を高めます。
過去10年の年平均リターン7.6%は、S&P500(12.8%)やNASDAQ100(17.5%)に劣るものの、2022年の株式市場下落のような局面では損失を抑える強みを発揮しました。構成は100%物理的な金であり、セクターや銘柄の分散は不要。50年間のシミュレーションでは、100万円が約2,430万円に成長する可能性を示しました。
配当はなく、キャピタルゲインがリターンの源泉です。配当金生活を目指すには、定期売却や高配当ETFとの組み合わせが有効です。IAUと比較されるETF(GLD、SGOL、GLDM、SLV)では、コストと流動性のバランスでIAUが優れています。ポートフォリオには、IVV、BND、VYM、ACWIを加えることで、成長、安定性、収入を強化できます。
IAUは、長期投資家にとって「守りの資産」として価値があります。5~10%の割合で組み込み、市場環境に応じてリバランスすることで、どんな相場でも安定した成果を狙えます。金の特性を理解し、戦略的に活用しましょう。
他の人気ETFの記事はこちら
【SOXL】とは?やめておいたほうがいい?半導体セクターに特化したレバレッジ型ETF
この記事のポイント SOXLは半導体3倍レバレッジETFで、短期トレード向け。過去10年の年平均成長率は33.27%。 最大下落率90.5%と高リスク。S&P500(11.82%)やNASDA…
QQQM:NASDAQ100連動ETF|ナスダック100指数に連動するQQQの低コスト版ETF。長期投資家向けに信託報酬を抑えた設計
QQQMのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
ITOT:米国全市場ETF|米国株式市場全体に投資するETF
ITOTのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
【BIL】満期1年未満の米国短期国債に投資するETF|SPDRブルームバーグ1-3ヶ月TビルETF
BILのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
SPY徹底解説:配当金シミュレーションから注意点まで、全てが分かる完全ガイド
この記事のポイント SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust)の基本情報を解説 SPYをおすすめしない意見や投資リスクについて検証 配当金シミュレーションで月3万円・5万円生活を目…
【SPYG】S&P500構成銘柄のうち成長株に特化したETF。ハイテク比率が高く、成長期待を重視する投資家向け
SPYGのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
VUG徹底解説!成長株ETFの魅力と注意点を徹底分析
この記事のポイント VUG(Vanguard Growth ETF)は、大型成長株に投資するETFである。 配当は少なめだが、長期的な成長が期待できる。 構成銘柄にはAppleやMicrosoftなど…
QYLDとは?毎月配当型のETF。インカム重視の投資家におすすめ!配当金生活を目指そう
この記事のポイント QYLDはカバードコール戦略で高分配(年10~12%)と低ボラティリティを実現。インカム重視の投資家に最適。 株価成長率は0.66%と低いが、分配金再投資で50年で資産33倍の可能…
【VTI】株価推移・配当・シミュレーションを徹底解説!FIREは可能か?「全米を丸ごと買う」ETF投資
この記事のポイント VTIは経費率0.03%で米国市場の約4,000銘柄を網羅し、「全米を丸ごと買う」究極の分散投資を実現可能なETF VTIはS&P500(VOO)と並ぶ優秀なリターンを示し…
HDVとは?配当金生活にはいくら必要?高配当ETFの魅力と注意点を解説
この記事のポイント 米国高配当ETFとして人気のHDV(iShares Core High Dividend ETF)について、初心者にもわかりやすく解説していきます。「配当金で安定収入を得たい!」と…
【MUB】米国の地方債(ミュニシパルボンド)に投資するETF
この記事のポイント MUBは連邦税免税の地方債ETF。低リスクかつ安定したリターンを提供し、ポートフォリオの基盤に最適 毎月分配型の配当により、定期収入や複利効果による資産成長を目指せる 経費率0.0…
XLF:米国金融株ETF|銀行、保険、資産運用会社など金融関連企業が中心
XLFのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
【EWG】ドイツの株式市場に投資するETF。大型株および中型株を中心に構成(iShares MSCI Germany ETF)
この記事のポイント EWGはドイツ市場に特化したETFで、自動車や金融セクターの強みを低コストでポートフォリオに追加可能。 過去の平均リターン6.8%、配当利回り2.03%で、長期投資と安定収入を両立…
VYMとは?配当金やリターンは?配当金生活をするにはいくら必要か?
この記事のポイント この記事では、Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM)の魅力、特性、そして投資家が抱える疑問にお答えします。配当金重視の投資家に人気のあるVYMで…
【XLV】ヘルスケアセクターの企業に焦点を当てたETF(Health Care Select Sector SPDR Fund)
XLVのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
VT:世界全体株式ETF|米国、先進国、新興国すべてを網羅し、超分散投資を実現するETF
VTのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出 …
DGRO完全ガイド:配当成長ETFの魅力と投資のポイントを徹底解説
この記事のポイント 投資って聞くと、なんだか難しそうで手が出しにくいイメージありますよね。でも、もし安定した収入が欲しいとか、将来のためにコツコツ資産を増やしたいって考えるなら、ETF(上場投資信託)…
IVVとは?利回りや配当金生活への道筋を解説
この記事のポイント この記事では、米国の代表的なETFであるiShares Core S&P 500 ETF(ティッカー:IVV)について徹底的に解説します。特に以下のポイントに注目してお届け…
EFA:先進国株ETF(米国外)|日本、欧州を中心に広く分散し、グローバル分散投資に活用
EFAのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
【SCHB】米国株式市場全体に分散投資するETF。低コストで大型・中型・小型株を網羅し、長期投資向け
この記事のポイント SCHBは経費率0.03%、2,500銘柄で米国市場98%をカバーし、初心者にも最適。 過去15年で年平均10.5%のリターン。小型株の成長性と大型株の安定性を両立。 S&…
AGGとは?投資初心者が知っておくべきメリット・デメリットや利回りや配当金生活にはいくら必要かを解説
この記事のポイント この記事では、債券ETFの代表格である「AGG」(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)について、初心者にも分かりやすく解説します。 AGGの基…
BNDX:米国外国債ETF|米国外の投資適格債に投資するETF
BNDXのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
JEPIとは?配当利回りは?配当金生活をするにはいくら必要か
この記事のポイント JEPIは高いインカムゲインと安定したキャピタルゲインを狙うことができるETFで約7.5%の配当リターンと毎月配当金を得れる点が人気となっている ただし安定性は高くなく、リスク許容…
IBIT:ブラックロックが運用するビットコイン現物ETF
IBITのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
IWF:米国大型成長株ETF|テクノロジーや消費関連を中心に構成され、キャピタルゲインを重視するETF
IWFのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。