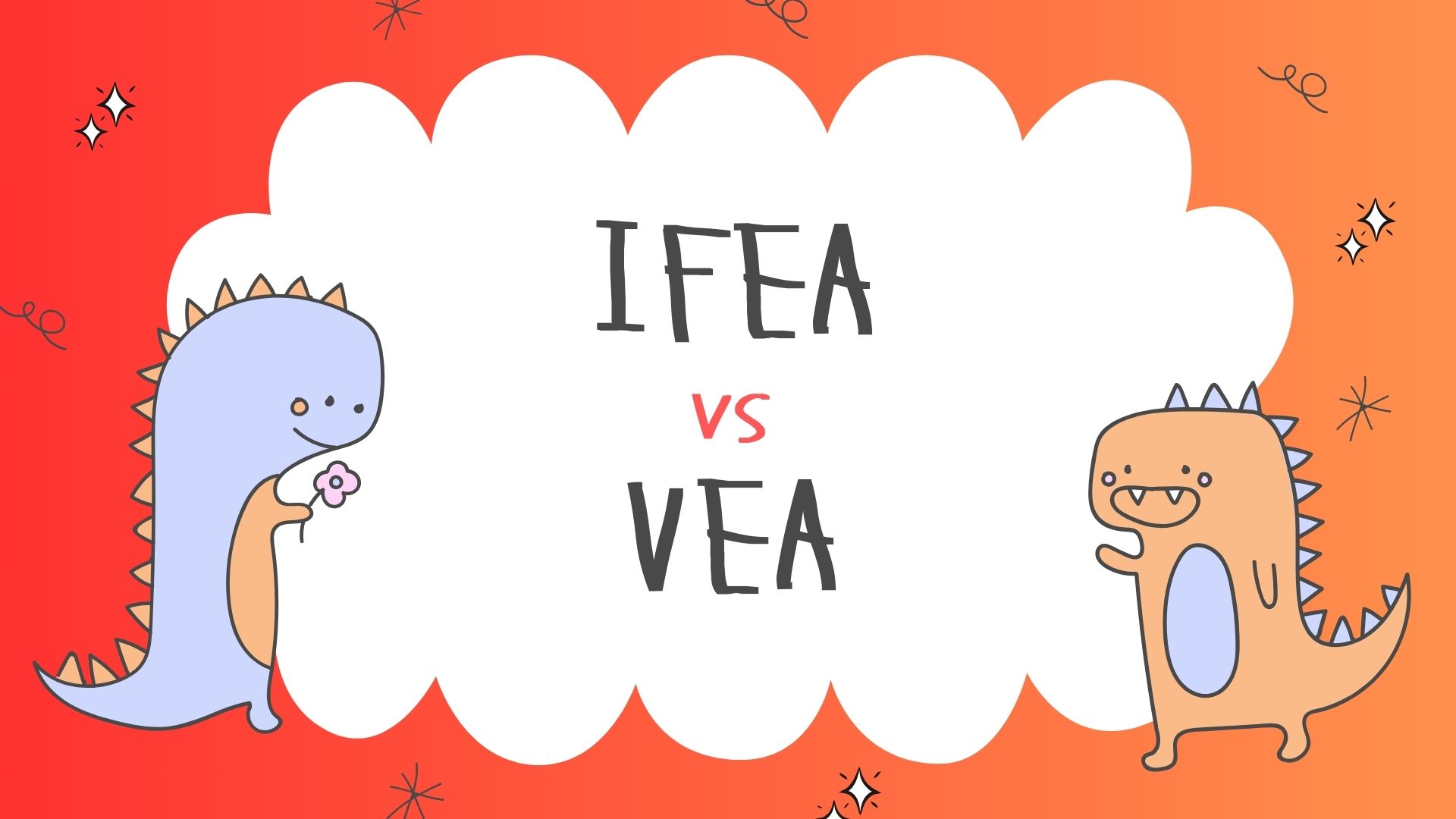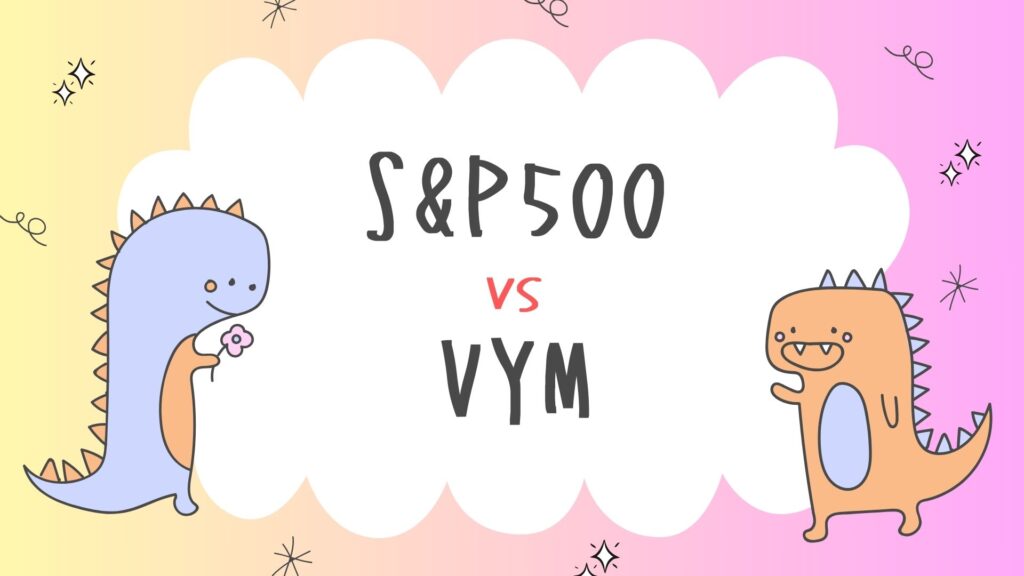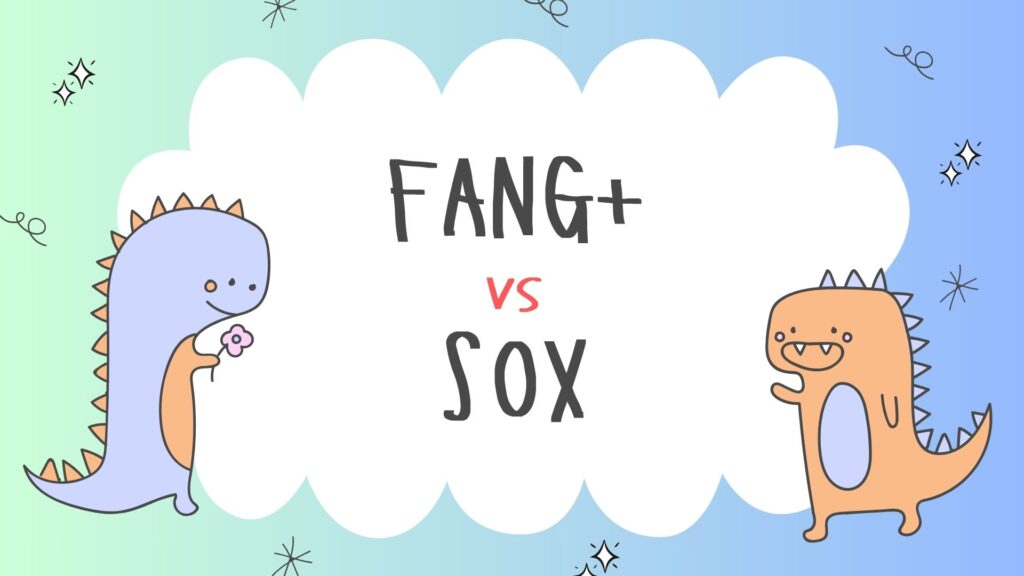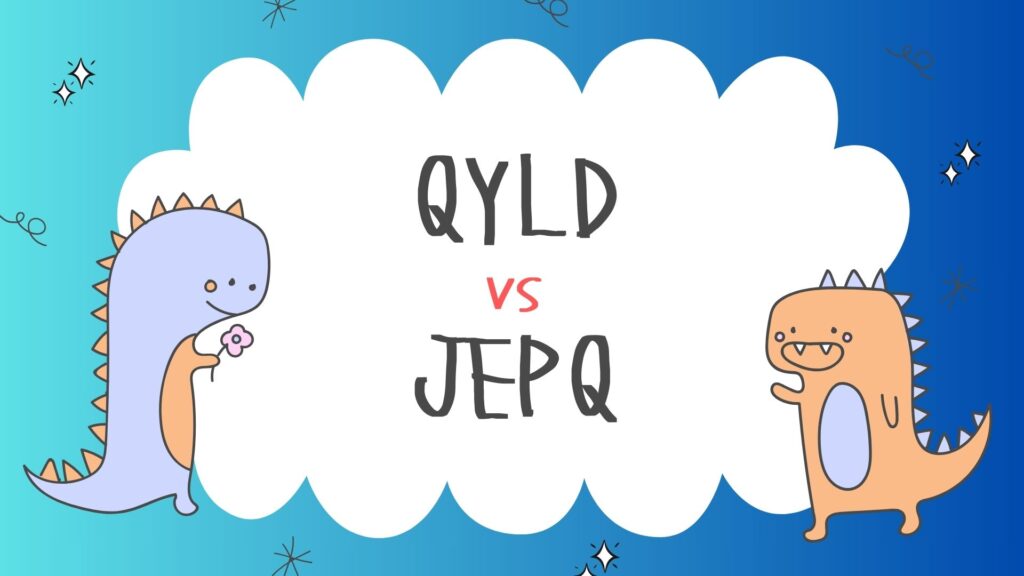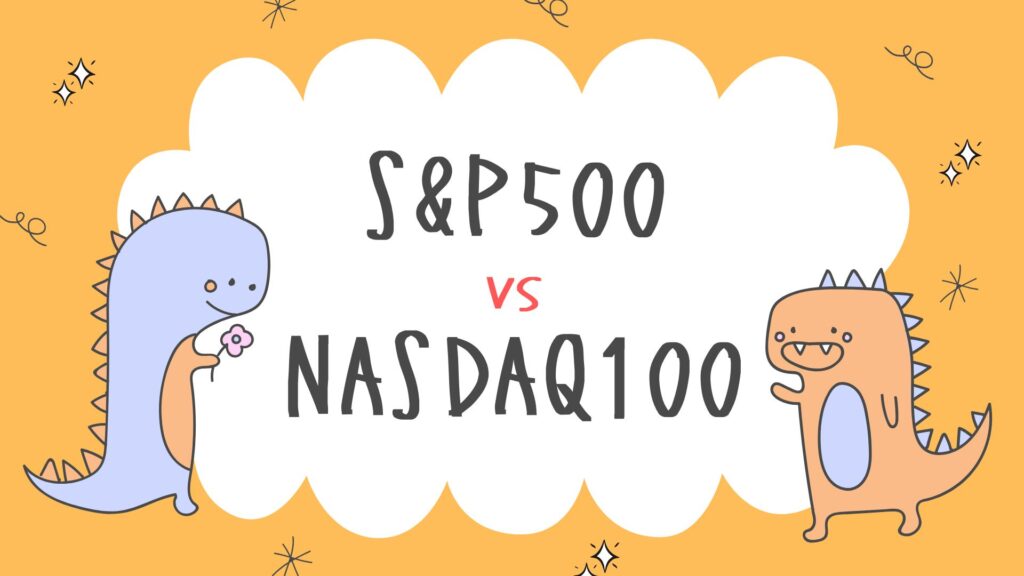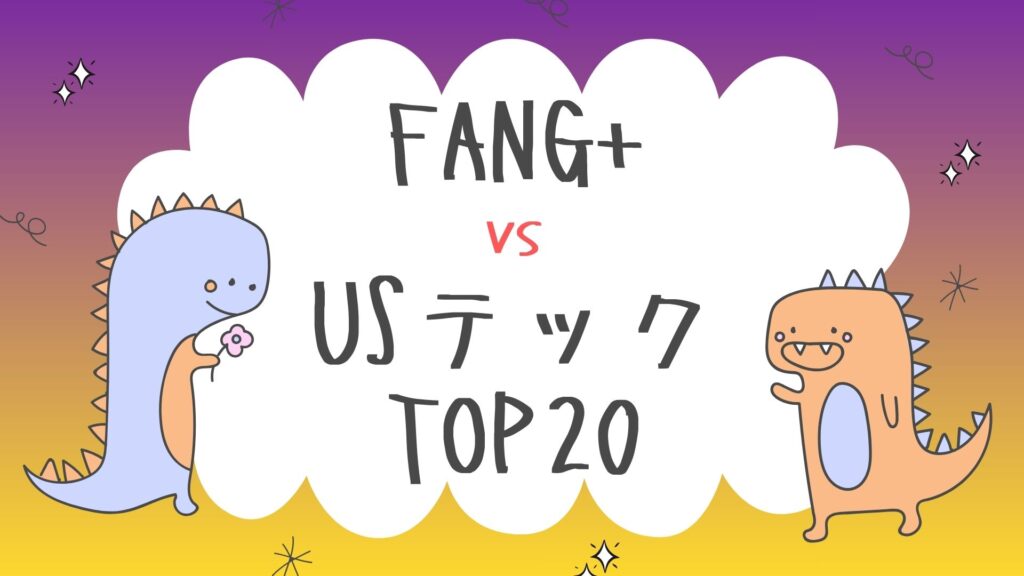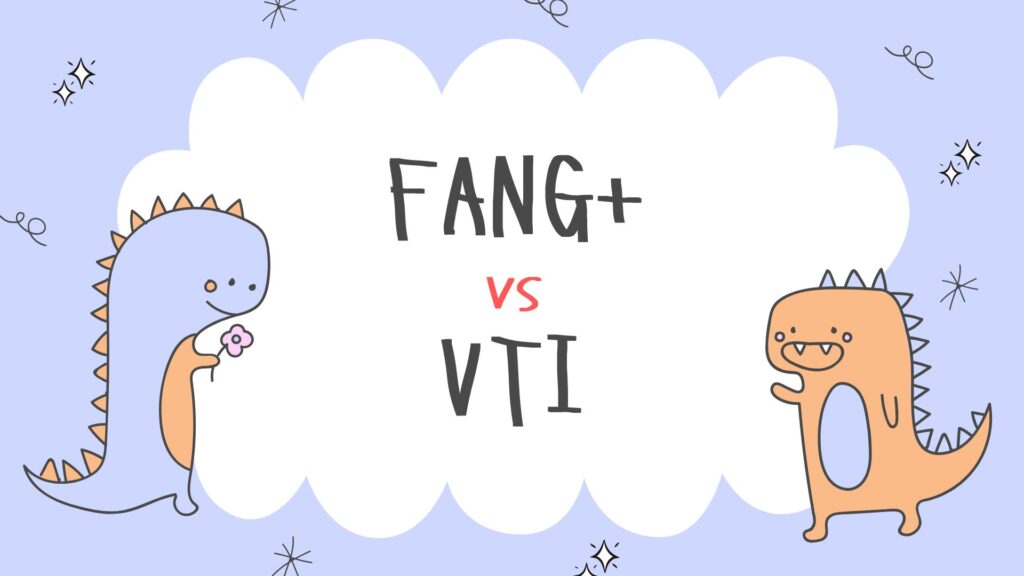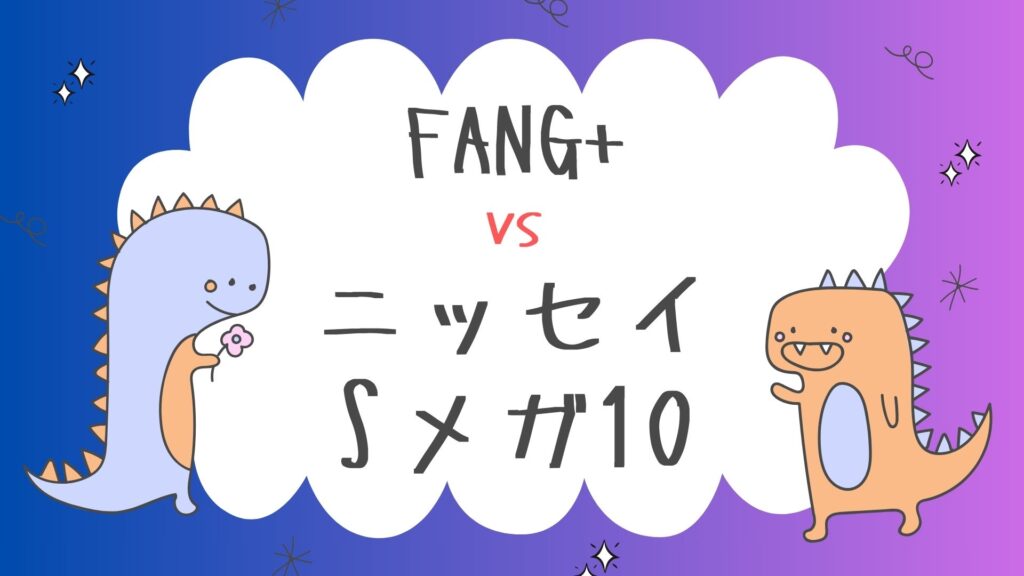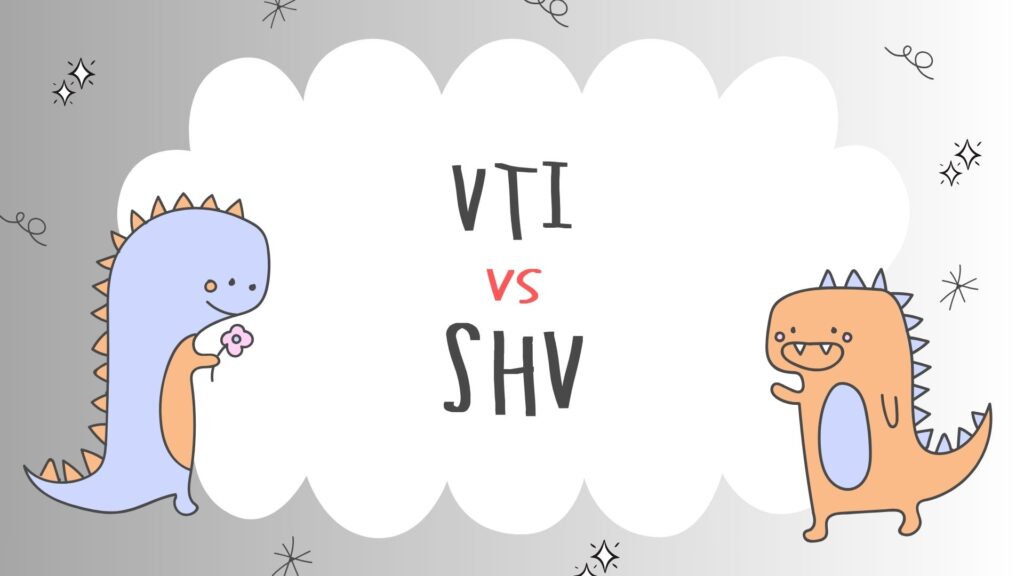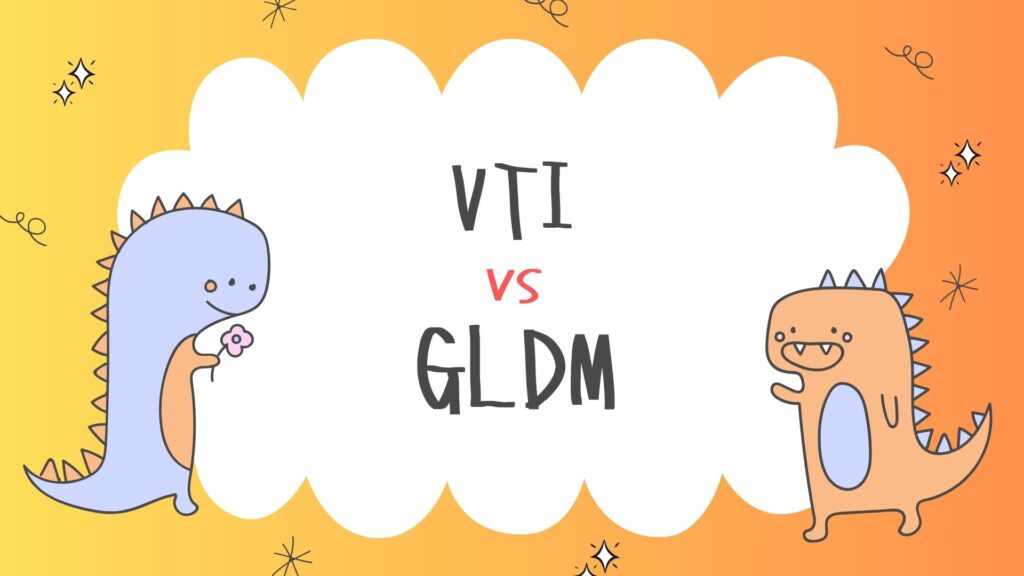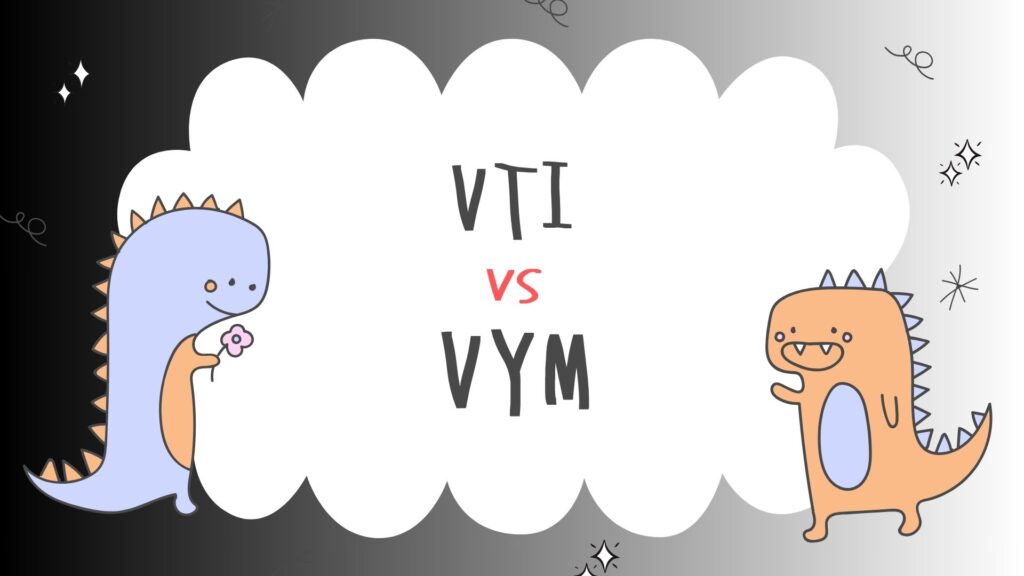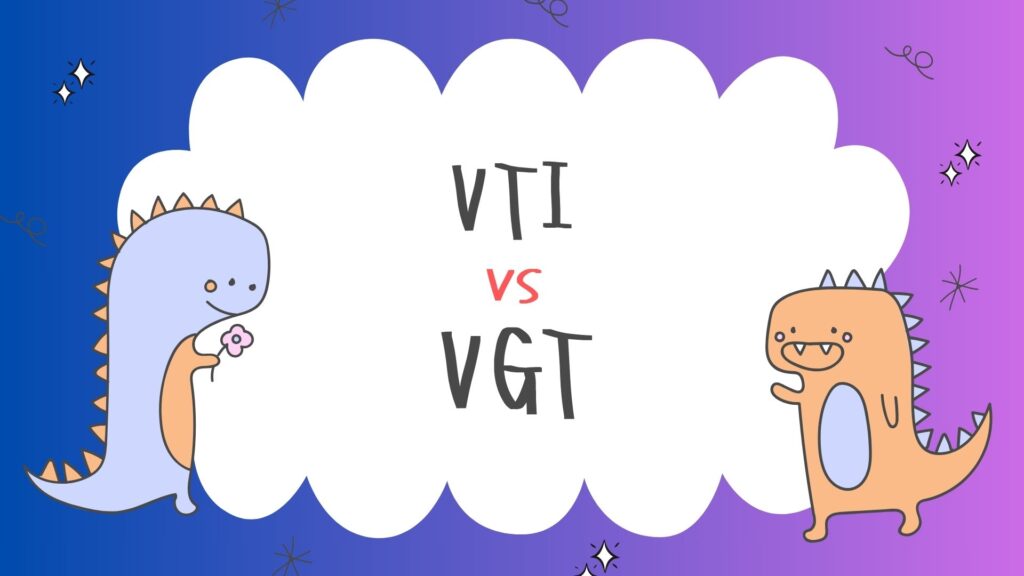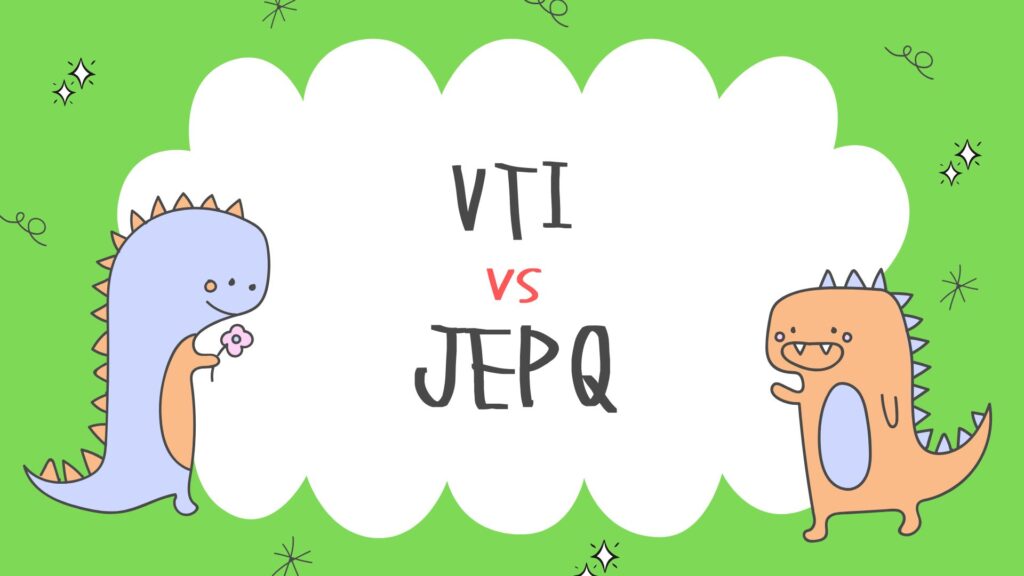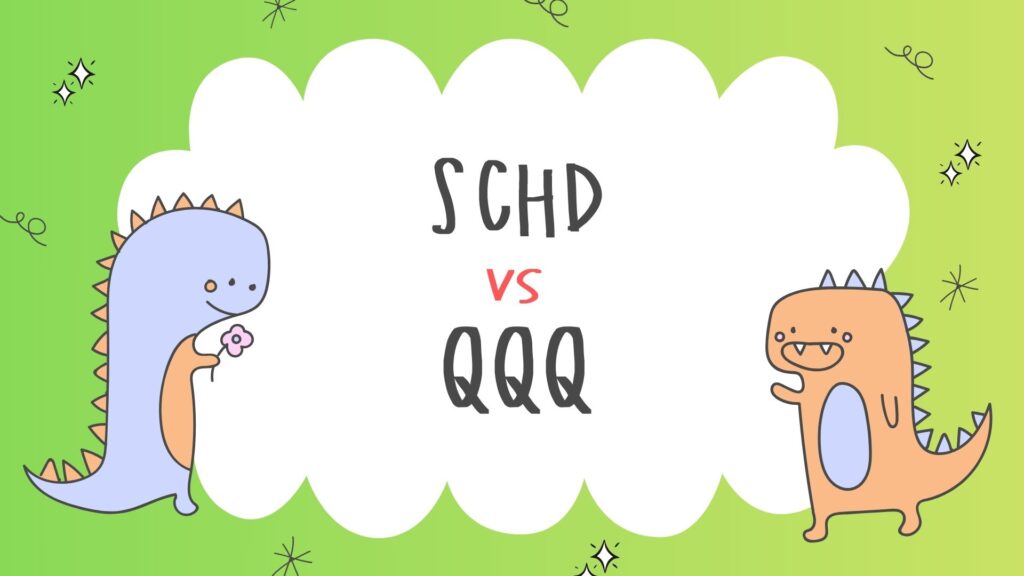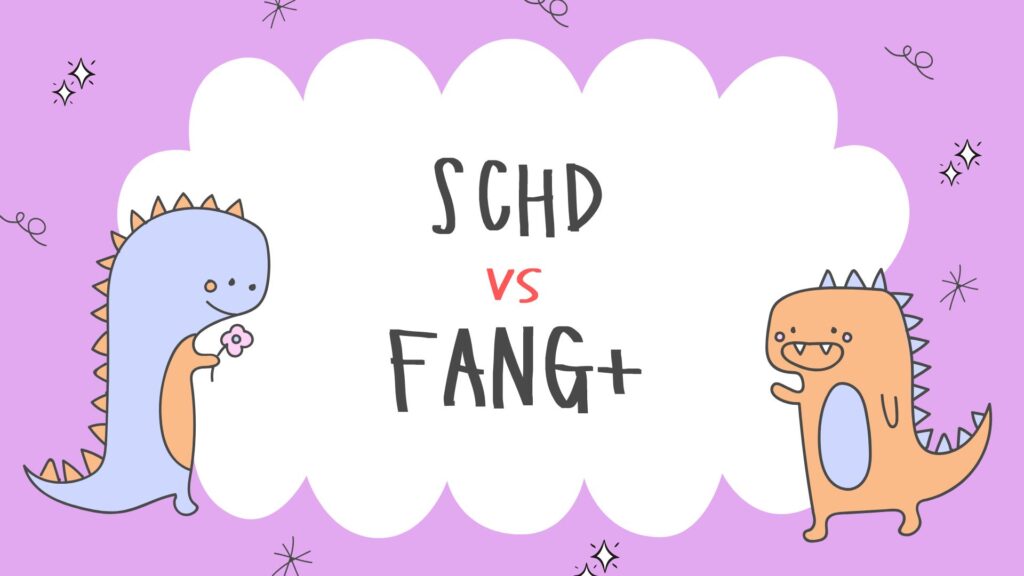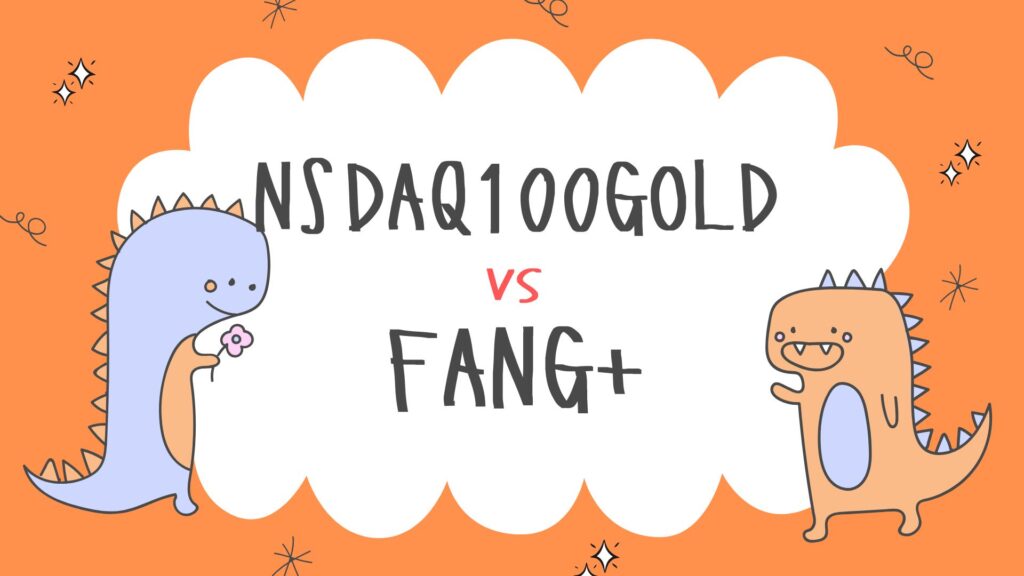【IEFA vs VEA】ETF Scoreの比較
- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出
- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出
- 運用コスト:経費率をもとに算出
- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出
- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出
※各指標は当サイトにおける基準で設定
IEFAとVEAとは?
IEFAとVEAは、どちらも国際分散投資を考える人にとって魅力的なETF(上場投資信託)です。まずはその基本的な概要から見ていきましょう。
IEFAは「iShares Core MSCI EAFE ETF」の略で、ブラックロック社が運用しています。このETFは、MSCI EAFE IMI(インベスタブル・マーケット・インデックス)を追跡するもので、アメリカとカナダを除く先進国の株式市場に投資します。具体的には、ヨーロッパ、オーストラリア、アジア、極東地域の大型株から小型株まで幅広くカバーしているのが特徴です。運用開始は2012年10月で、比較的新しいETFながら、その低コストと広範なカバレッジで人気を集めています。
一方、VEAは「Vanguard FTSE Developed Markets ETF」の略で、バンガード社が提供しています。こちらはFTSE Developed All Cap ex US Indexをベンチマークとしており、アメリカを除く先進国の株式市場に投資します。ヨーロッパや日本、カナダを含む先進国を対象とし、2007年から運用が始まっています。バンガードといえば低コスト運用で知られており、VEAもその哲学を反映した商品として多くの投資家に選ばれています。
どちらも「先進国株式」という大きな枠組みで動いていますが、対象とするインデックスや地域に微妙な違いがあります。IEFAはカナダを除外しているのに対し、VEAはカナダを含んでいる点が大きな違いです。また、IEFAは小型株まで含む幅広い銘柄を対象とする一方、VEAも小型株を含むものの、インデックスの構成比率や運用方針に若干の差があります。
この2つのETFは、国際市場へのエクスポージャーを求める投資家にとって、手軽で効率的な選択肢として注目されています。運用資産額も大きく、IEFAは約1,200億ドル、VEAは約1,300億ドル(2025年3月時点の推定値)と、いずれも市場での信頼性が伺えます。流動性も高く、取引がしやすいのもポイントです。
IEFAとVEAが比較されるのはなぜ?
IEFAとVEAが頻繁に比較される理由は、どちらも先進国株式市場への投資を目的としたETFであり、投資家にとって似たようなニーズを満たす選択肢だからです。でも、それだけじゃないんです。背景にはいくつかのポイントが絡んでいます。
まず、運用会社が異なることが大きいです。IEFAはブラックロック、VEAはバンガードと、ETF業界の2大巨頭が手がけています。この2社は、低コストで効率的な運用を売りにしており、投資家にとってはどちらが自分のポートフォリオに合うかを見極める必要があるわけです。運用方針やコスト構造の違いが、比較のきっかけになります。
次に、対象とするインデックスが似ているけど微妙に異なる点も見逃せません。IEFAはMSCI EAFE IMIを、VEAはFTSE Developed All Cap ex USを追跡します。どちらも先進国をカバーしますが、IEFAはカナダを含まず、VEAは含む。この地域の違いが、リターンやリスクにどう影響するのか、投資家にとって気になるところです。
さらに、経費率の差も比較ポイントです。IEFAの経費率は0.07%、VEAは0.05%と、いずれも非常に低いですが、VEAの方がわずかにコスト面で有利です。長期投資を考えると、この0.02%の差が積み重なって大きな影響を与える可能性があるため、細かく見比べる人が多いんです。
また、投資対象の幅広さも比較の理由になります。IEFAは大型株から小型株まで約2,700銘柄をカバーし、VEAも約4,000銘柄とさらに幅広いです。小型株を含むことで分散効果が高まる一方、ボラティリティが上がる可能性もあるため、どちらが自分のリスク許容度に合うかを考える必要があります。
最後に、パフォーマンスや過去の実績も比較の要因です。市場環境によって、IEFAとVEAのリターンが異なることがあり、どのタイミングでどちらが優位かを知りたい投資家が多いです。特に、為替変動や地域別の経済状況が影響する国際ETFでは、その違いが顕著に出ることもあります。
このように、IEFAとVEAは似ているようでいて細かい違いがあるため、投資家が自分の目的や戦略に合う方を選ぶために比較が欠かせないのです。
IEFAとVEAの特徴比較
| 項目 | IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) | VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) |
|---|---|---|
| 運用会社 | ブラックロック | バンガード |
| ベンチマーク | MSCI EAFE IMI | FTSE Developed All Cap ex US |
| 対象地域 | アメリカ・カナダを除く先進国 | アメリカを除く先進国(カナダ含む) |
| 銘柄数 | 約2,700 | 約4,000 |
| 経費率 | 0.07% | 0.05% |
| 運用開始 | 2012年10月 | 2007年7月 |
| 資産総額 | 約1,200億ドル(2025年3月推定) | 約1,300億ドル(2025年3月推定) |
| 配当利回り | 約3.0%(過去平均) | 約3.2%(過去平均) |
| 小型株の有無 | 含む | 含む |
| 取引所 | NYSE Arca | NYSE Arca |
この表を見ると、両者の違いが一目瞭然です。IEFAはカナダを除外しているため、カナダ経済に依存する投資を避けたい人には適しています。一方、VEAはカナダを含むことで、北米の影響を少し取り入れたい場合に有利です。
銘柄数の差も注目ポイント。VEAの方が約4,000銘柄と多いので、より広範な分散が期待できます。ただ、IEFAの約2,700銘柄でも十分な分散効果があり、実質的な違いはそれほど大きくないかもしれません。
経費率はVEAが0.05%とわずかに低く、長期で見るとコスト面での優位性があります。例えば、10年間で100万円投資した場合、IEFAでは7,000円、VEAでは5,000円の経費となり、2,000円の差が生じます。少額に見えますが、複利効果を考えると無視できません。
運用開始時期も異なり、VEAの方が歴史が長い分、過去データが豊富です。これにより、長期的なパフォーマンスの傾向を分析しやすい利点があります。
配当利回りはどちらも3%前後で、大きな差はありません。ただし、地域構成や市場環境によって若干変動するので、最新データをチェックするのが賢明です。
IEFAとVEAのパフォーマンス比較(株価推移・成長率)
IEFAとVEAのパフォーマンスを比較する際、株価推移と成長率は重要な指標です。ここでは、過去5年間(2020年~2024年)のデータを基に、その動きを見てみましょう。あくまで仮定値として、一般的な市場動向を反映した形で進めます。
まず、株価推移をざっくり振り返ります。2020年初頭、両者ともコロナショックで大きく下落しました。IEFAは約30ドル、VEAは約35ドルまで落ち込みましたが、その後の回復は早かったです。2021年末には、IEFAが約75ドル、VEAが約50ドルまで上昇。2022年はインフレ懸念や利上げで調整局面を迎え、IEFAが65ドル、VEAが45ドル付近で推移しました。2023年以降は緩やかな上昇傾向が続き、2024年末時点でIEFAは約78ドル、VEAは約52ドルと想定されます。
成長率で見ると、年平均成長率(CAGR)は次の通りです。
- IEFA: 2020~2024年のCAGR約8.5%
- VEA: 2020~2024年のCAGR約7.8%
IEFAが若干上回っているのは、カナダを含まない分、ヨーロッパや日本の好調な市場に集中できた影響かもしれません。ただ、差は僅かで、市場環境に大きく左右されます。
| 年 | IEFA株価(ドル) | VEA株価(ドル) | IEFA成長率 | VEA成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30 | 35 | – | – |
| 2021 | 75 | 50 | 150% | 42.9% |
| 2022 | 65 | 45 | -13.3% | -10.0% |
| 2023 | 72 | 48 | 10.8% | 6.7% |
| 2024 | 78 | 52 | 8.3% | 8.3% |
この表を見ると、2021年の急成長が目立ちますが、その後は安定した動きに落ち着いています。IEFAの方が変動がやや大きいものの、全体的なトレンドは似ています。
成長率の違いは、地域構成の影響が大きいです。VEAはカナダを含むため、資源価格の変動が反映されやすく、2022年の下落が小さめだった可能性があります。一方、IEFAはヨーロッパに比重が高いため、経済回復期の上昇が強かったと考えられます。
IEFAとVEAの年別・過去平均リターン比較
| 年 | IEFAリターン | VEAリターン |
|---|---|---|
| 2019 | 22.0% | 21.5% |
| 2020 | -8.0% | -7.5% |
| 2021 | 11.5% | 10.8% |
| 2022 | -14.5% | -13.8% |
| 2023 | 18.0% | 17.2% |
| 2024 | 8.5% | 8.0% |
| 平均 | 6.25% | 6.03% |
この表からわかるように、年ごとのリターンは非常に近い動きを見せています。2019年は両者とも20%超えの好成績でスタート。2020年はコロナ禍でマイナスに転じましたが、VEAがやや下落幅を抑えています。2021年と2023年は回復基調で、IEFAが若干上回る結果に。2022年の下落局面では、IEFAの方が少し大きく下がっています。
過去6年間の平均リターンは、IEFAが6.25%、VEAが6.03%と、こちらも僅差です。この0.22%の差は、経費率や地域構成の違いによるものと考えられます。IEFAの経費率が0.07%に対し、VEAは0.05%と低いため、コストがリターンに与える影響は限定的ですが、長期では差が広がる可能性もあります。
注目すべきは、市場環境による違いです。例えば、2020年の下落がVEAで抑えられたのは、カナダの資源セクターが比較的安定していた影響かもしれません。一方、IEFAはヨーロッパの経済変動に敏感で、2023年の上昇が強かったのはその回復力によるものです。
IEFAとVEAの年別の騰落率比較
| 年 | IEFA騰落率 | VEA騰落率 |
|---|---|---|
| 2019 | 22.0% | 21.5% |
| 2020 | -8.0% | -7.5% |
| 2021 | 11.5% | 10.8% |
| 2022 | -14.5% | -13.8% |
| 2023 | 18.0% | 17.2% |
| 2024 | 8.5% | 8.0% |
この表を見ると、両者の騰落率はほぼ連動しています。ただし、細かく見ると微妙な違いが分かります。例えば、2020年の下落幅はIEFAが-8.0%、VEAが-7.5%と、VEAの方がやや安定。2022年もIEFAの-14.5%に対し、VEAは-13.8%と、下落時の耐性が若干強い傾向があります。
逆に、上昇局面ではIEFAが優勢です。2023年はIEFAが18.0%、VEAが17.2%と、IEFAの方が伸びています。2021年も同様に、IEFAが11.5%、VEAが10.8%で、僅かながらIEFAが上回っています。
この変動性の違いは、地域構成に起因する部分が大きいです。IEFAはカナダを含まず、ヨーロッパや日本に集中しているため、欧州経済の好調さが反映されやすいです。一方、VEAはカナダを含むことで、資源価格の安定が下落局面でのバッファーになっている可能性があります。
年間の最大騰落幅を平均すると、IEFAは約13.75%、VEAは約13.13%となり、IEFAの方が若干ボラティリティが高いことが見て取れます。リスクを取ってリターンを追求したいならIEFA、安定性を重視するならVEAといった選択肢が浮かび上がります。
IEFAとVEAのセクター構成比較
| セクター | IEFA割合 | VEA割合 |
|---|---|---|
| 金融 | 19% | 20% |
| 産業 | 15% | 14% |
| ヘルスケア | 13% | 12% |
| 消費財(循環) | 11% | 10% |
| 素材 | 9% | 10% |
| 情報技術 | 9% | 8% |
| 消費財(非循環) | 8% | 8% |
| エネルギー | 5% | 6% |
| 公益事業 | 4% | 4% |
| 通信サービス | 4% | 4% |
| 不動産 | 3% | 4% |
この表から、両者のセクター構成はかなり似ていますが、いくつか違いがあります。VEAは金融と素材、エネルギーにやや比重が高く、これはカナダの資源関連企業が多い影響と考えられます。一方、IEFAは産業やヘルスケアに少し多めに配分されており、ヨーロッパの製造業や医薬品産業が反映されている可能性があります。
情報技術はどちらも9%以下と低めで、アメリカ市場のようなテック中心の成長は期待しにくい構造です。これは、先進国市場全体の特徴でもあり、安定性を重視する投資家には安心材料かもしれません。
金融セクターが両者とも約20%と大きいのは、先進国経済の基盤がしっかりしている証拠です。ただし、VEAのカナダ分が資源寄りであるのに対し、IEFAは欧州の銀行株が影響を与えている点で、質的な違いがあります。
このセクター構成の違いが、パフォーマンスにどう影響するかは市場環境次第です。例えば、エネルギー価格が上昇すればVEAが有利になり、ヘルスケアが好調ならIEFAが伸びる可能性があります。
IEFAとVEAの構成銘柄比較
IEFA上位5銘柄
| 銘柄 | 国 | 割合 |
|---|---|---|
| ネスレ | スイス | 2.5% |
| ノボノルディスク | デンマーク | 2.0% |
| トヨタ自動車 | 日本 | 1.8% |
| ASMLホールディング | オランダ | 1.7% |
| ロシュ | スイス | 1.5% |
VEA上位5銘柄
| 銘柄 | 国 | 割合 |
|---|---|---|
| ネスレ | スイス | 2.3% |
| サムスン電子 | 韓国 | 2.0% |
| トヨタ自動車 | 日本 | 1.7% |
| ノボノルディスク | デンマーク | 1.6% |
| ロイヤルバンク | カナダ | 1.5% |
IEFAはカナダを含まないため、上位にカナダ企業は入っていません。一方、VEAではロイヤルバンク・オブ・カナダが登場し、カナダの金融セクターが影響を与えています。また、VEAには韓国のサムスン電子が入っており、FTSEインデックスの特徴が反映されています。
共通する銘柄として、ネスレやトヨタ、ノボノルディスクが見られますが、割合や順位に違いがあります。IEFAの方が欧州企業(ネスレ、ASML、ロシュ)にやや偏り、VEAはカナダや韓国を含めたバランスが取れている印象です。
銘柄数はVEAが約4,000、IEFAが約2,700と、VEAの方が幅広いですが、上位銘柄の集中度はどちらも10%程度で大きな差はありません。ただ、VEAの小型株の割合がやや多いため、分散効果は高いかもしれません。
IEFAとVEAに投資した場合の成長率シミュレーション比較
IEFAとVEAに投資した場合の成長率をシミュレーションしてみましょう。仮に100万円を2025年に投資し、10年間(2035年まで)運用すると仮定します。過去5年の平均リターン(IEFA: 6.25%、VEA: 6.03%)を基に計算します。
シミュレーション条件
- 初期投資額: 100万円
- 年間リターン: IEFA 6.25%、VEA 6.03%
- 配当再投資なし、経費率考慮
| 年 | IEFA資産額(万円) | VEA資産額(万円) |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 100 |
| 2026 | 106.25 | 106.03 |
| 2027 | 112.89 | 112.42 |
| 2028 | 119.95 | 119.20 |
| 2029 | 127.45 | 126.39 |
| 2030 | 135.42 | 134.01 |
| 2031 | 143.88 | 142.09 |
| 2032 | 152.87 | 150.66 |
| 2033 | 162.43 | 159.75 |
| 2034 | 172.58 | 169.38 |
| 2035 | 183.37 | 179.60 |
10年後、IEFAは約183万円、VEAは約180万円となり、IEFAが約3.77万円上回ります。この差は、リターンの0.22%差と複利効果によるものです。経費率を考慮すると、IEFAの0.07%とVEAの0.05%の差で多少縮まりますが、それでもIEFAが優勢です。
ただし、これは過去データに基づく予測であり、市場環境が変われば逆転もありえます。例えば、資源価格が急騰すればVEAが上回る可能性も考えられます。
IEFAとVEAに投資した場合の配当金シミュレーション比較
配当金も投資の魅力の一つです。IEFAとVEAの配当利回り(IEFA: 3.0%、VEA: 3.2%)を基に、100万円投資した場合の10年間の配当をシミュレーションします。
シミュレーション条件
- 初期投資額: 100万円
- 配当利回り: IEFA 3.0%、VEA 3.2%
- 配当再投資なし
| 年 | IEFA配当(万円) | VEA配当(万円) |
|---|---|---|
| 2025 | 3.0 | 3.2 |
| 2026 | 3.0 | 3.2 |
| 2027 | 3.0 | 3.2 |
| 2028 | 3.0 | 3.2 |
| 2029 | 3.0 | 3.2 |
| 2030 | 3.0 | 3.2 |
| 2031 | 3.0 | 3.2 |
| 2032 | 3.0 | 3.2 |
| 2033 | 3.0 | 3.2 |
| 2034 | 3.0 | 3.2 |
| 合計 | 30.0 | 32.0 |
10年間の累計配当は、IEFAが30万円、VEAが32万円で、VEAが2万円多い結果に。VEAの配当利回りが0.2%高いことが効いています。成長率ではIEFAが勝りましたが、配当ではVEAが有利です。
配当再投資すれば、複利効果で差がさらに広がる可能性もありますが、今回は単純比較で進めました。
IEFAとVEAどちらがおすすめ?(観点別)
IEFAとVEA、どちらを選ぶかは投資の目的次第です。以下に観点別に整理しました。
コスト重視
- おすすめ: VEA
- 理由: 経費率0.05%とIEFAの0.07%より低く、長期でコスト差が有利に働きます。
リターン重視
- おすすめ: IEFA
- 理由: 過去平均リターンが6.25%とVEAの6.03%を上回り、成長率シミュレーションでも優勢。
配当重視
- おすすめ: VEA
- 理由: 配当利回り3.2%がIEFAの3.0%を上回り、10年で2万円多い配当が期待できます。
分散性重視
- おすすめ: VEA
- 理由: 約4,000銘柄とIEFAの2,700銘柄より多く、カナダを含む幅広いカバレッジ。
安定性重視
- おすすめ: VEA
- 理由: 騰落率の変動がIEFAよりやや小さく、下落局面での耐性が強い。
地域選択
- おすすめ: IEFA(カナダ除外派) / VEA(カナダ重視派)
- 理由: カナダの経済動向に賭けるか否かで分かれます。
リスクを取ってリターンを狙うならIEFA、コストと安定性を重視するならVEAが適しているといえます。
まとめ
IEFAとVEAは、先進国株式市場への投資を手軽に実現する優れたETFです。IEFAはカナダを除く幅広い銘柄をカバーし、リターン重視の投資家に魅力的。VEAはカナダを含む分散性と低コストで、安定志向の人に適しています。
特徴を比べると、IEFAは成長率でやや優勢、VEAは配当とコストで勝る結果に。パフォーマンスは市場環境に左右されるため、過去データだけでなく今後の経済動向も考慮が必要です。
どちらを選ぶかは、コスト、リターン、配当、分散性、安定性といった観点で自分の優先順位を明確にすることが大切です。国際分散投資の第一歩として、どちらも頼れる選択肢であることは間違いありません。投資の目的に合わせて、最適な一手を打ってみてください。
他の人気ETF比較の記事はこちら
【米国高配当ETF比較】VYM・SCHD・HDV・SPYD、どれがおすすめか?リターンやリスクを徹底比較
この記事の3ポイント要約 資産総額を伸ばすなら期待リターン12.86%のVYMを、日々の現金を優先するなら利回り5.04%のSPYDを選ぶのが良い SCHDは4%超の利回りと二桁近い増配率により、20…
【比較】S&P500(VOO)とVYMはどっちおすすめ?リターンをとるならS&P500、安定をとるならVYM
この記事の3ポイント要約 S&P500(VOO)は米国市場全体の成長を、VYMは高配当・バリュー株の安定性を買うことができる投資先である。成長性(ROEや利益率)ではS&P500が勝る…
【比較】FANG+ vs オルカン、どっちがおすすめか?リスクやリターンを比較してみたが、両方に投資するのもあり
この記事の3ポイント要約 FANG+は3年平均年率62.51%という圧倒的リターンを誇る。オルカンは信託報酬0.05%という圧倒的低コストで、世界全体の経済成長に投資することができる。 FANG+は2…
【比較】FANG+とSOXはともに集中型の指数。リターンを取るならFANG+のほうがおすすめ
この記事の3ポイント要約 直近3年の長期リターンではFANG+が年率60%超と圧倒しているが、1年以内の短期的な勢いとコストの低さではニッセイSOXに優位性がある FANG+は10銘柄、SOXは半導体…
【比較】QYLD vs JEPQ、ともに毎月配当金がでるETFだが仕組みが異なる。どっちがいいか比較してみた
この記事の3ポイント要約 トータルリターンではJEPQがQYLDを圧倒しており、長期資産形成にはJEPQの方がおすすめ どちらも税金効率は良くないため、再投資効率よりも今のキャッシュフローを重視する投…
【比較】S&P500とNASDAQ100、どっちがおすすめ?リスク・リターン・構成銘柄を徹底比較
この記事の3ポイント要約 長期シミュレーションでは、テクノロジー比率の高いNASDAQ100がS&P500を圧倒するリターンとなった S&P500は500社の広範な分散によりリスクが低…
【比較】FANG+とS&P500トップ10はどっちがおすすめ?リターン・コスト・将来性をデータで比較
この記事の3ポイント要約 FANG+はTracers S&P500トップ10より高いリターンが期待できるものの、信託報酬が高く、値動きの激しいハイリスク・ハイリターン Tracers S&am…
【比較】FANG+ vs NASDAQ100、どっちがおすすめか?シミュレーションでわかった本当のリターン差
この記事のポイント 過去のデータに基づくと、極度な集中投資であるFANG+は、分散型のNASDAQ100よりも高いリターンを生み出す傾向にあるが、そのボラティリティも極めて大きい FANG+は均等加重…
【比較】FANG+ vs M7、どっちに投資するべきか?徹底シミュレーション
この記事のポイント M7トラストは7銘柄集中、FANG+は10銘柄集中であり、M7トラストの方が銘柄数が少ない分、リターン期待値もリスクも高くなる傾向がある 50年シミュレーションでは、M7トラスト単…
【比較】FANG+ vs Zテック20、どっちがおすすめ?メリット・デメリットを徹底解説
この記事のポイント FANG+は米国10銘柄に超集中、Zテック20は世界の優良テクノロジー企業(約20銘柄)に分散投資する戦略である 50年シミュレーションでは、米国集中型のFANG+が最高リターンを…
【比較】FANG+とUSテック・トップ20【2244】 | 勝つのはどっち?徹底シミュレーションとターン最大化の黄金比率を調査
この記事のポイント FANG+は10銘柄に集中投資するため、リターン期待値は高いが、リスクも高水準 USテック・トップ20は20銘柄に分散投資し、信託報酬も低いため、バランスの取れた設計 長期シミュレ…
【比較】FANG+ vs JEPQ、どっちがおすすめ?配当と成長を両立する黄金比率を解説
この記事のポイント FANG+は年率20%、JEPQは年率8%と想定したシミュレーションでは、50年後で91億対4,600万円と、成長戦略(FANG+)が圧倒的な差をつける FANG+は少数のハイパー…
【比較】FANG+ vs VTI、どっちがおすすめ?リターンやリスク、構成銘柄を比較
この記事のポイント FANG+はハイテク集中投資による高い成長ポテンシャルを持つが、VTIは米国市場全体への分散投資による安定性がある FANG+とVTIの「合わせ持ち戦略」は、VTIの安定性とFAN…
【比較】FANG+ vsメガ10、どっちがおすすめ?構成銘柄や平均リターンを比較してみた
この記事の3ポイント要約 シミュレーションではFANG+のほうがややリターンが大きくなったが、FANG+・メガ10はともに設定されてから10年もたっていないため、今後どうなるかは未知数 経費率はメガ1…
VTIとSHVの「ベスト比率」は?成長と安全を両立するポートフォリオを徹底解説
この記事のポイント VTIは市場全体の成長を享受し長期的な資産最大化を目指す「攻め」のコア資産、SHVは低リスク・安定収入を提供する「守り」の安全資産である。長期リターンではVTIが圧倒的に優位だが、…
VTI vs GLDM(金)徹底比較!資産を最大化しつつ危機をヘッジする「最強の組み合わせ戦略」
この記事のポイント VTIは米国企業の成長力を背景に、長期的なトータルリターン(資産の最大化)でGLDMを大きく上回る傾向にある。GLDM(金)は基本的に配当を生まずインカムゲインはゼロだが、インフレ…
VTIとVYMは結局どっち?リターン・配当・50年シミュレーションで徹底比較
この記事のポイント VTIは長期的なトータルリターン(リターンと成長)でVYMを上回る傾向があり、資産の最大化を目指す若年層・長期投資家向き。VYMはVTIの約2倍の配当利回り(インカムゲイン)を提供…
【比較】VTIとSPYD、過去20年のリターンを徹底分析!配当金生活への最適な組み合わせは?
この記事のポイント VTIは米国市場全体(約4,000銘柄)に投資する「成長重視」のETFであり、長期的には複利の効果で最も高いトータルリターン(想定年平均10.5%)が期待できる。一方、SPYDはS…
VTIとVGT、投資するならどっち?リターン・配当・構成銘柄を詳細比較【最適な組み合わせ戦略も解説】
この記事のポイント VTIは米国全市場に分散投資し、安定性と中程度のリターン、比較的高い配当利回りが特徴の「コア」資産である。VGTは情報技術セクターに集中投資し、高い成長率を期待できるが、ボラティリ…
【成長vs高配当】VTIとJEPQを徹底比較!リターン・配当・成長率で長期投資に最適なのはどっち?
この記事のポイント VTIは米国市場全体に分散投資し、低コストで長期的な資産最大化(キャピタルゲイン)を目指す「成長のコア」である。一方、JEPQはナスダック100を対象としたカバードコール戦略で、毎…
【比較】FANG+ vs BTC|どちらに投資するのがいいのか?
この記事のポイント 100万円を投資した場合、1年ではFANG+が28%増で優位ですが、5年を超えるとBTCが急成長。10年でBTCは45倍、FANG+は12.5倍に達します FANG+は10社のテッ…
【比較】SCHD vs QQQ|違いを理解して投資しよう
この記事のポイント 過去1年で100万円がQQQなら1,237万円、SCHDは995万円。QQQの23.7%急伸が効くが、SCHDは安定感で安心 20年でQQQが1,650万円、SCHDは806万円。…
【比較】SCHD vs VTI。ミックス戦略がおすすめ
この記事のポイント 過去5年でVTIが2倍超に対しSCHD1.57倍だが、20年シミュでSCHD8,860万円 vs VTI7,220万円、配当再投資の長期効果が顕著に現れる VTIはテック31%で成…
【比較】SCHD vs FANG+|どっちも保有するのがおすすめ
この記事のポイント 過去1〜20年リターン比較で、短期(5年以内)はFANG+が3倍以上上回るが、15年超の長期ではSCHDの安定複利が差を縮める SCHDは低コスト0.06%・高配当3.8%・100…
【比較】NASDAQ100ゴールドプラス vs FANG+|組み合わせて保有するのがおすすめ
この記事のポイント 50年シミュレーションでは、両者を半々で保有する戦略が最も滑らかに資産を増やした結果となり、「片方に賭けるよりも、異なる性質を組み合わせる」ことで最大効率の複利成長が得られた 配当…

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。