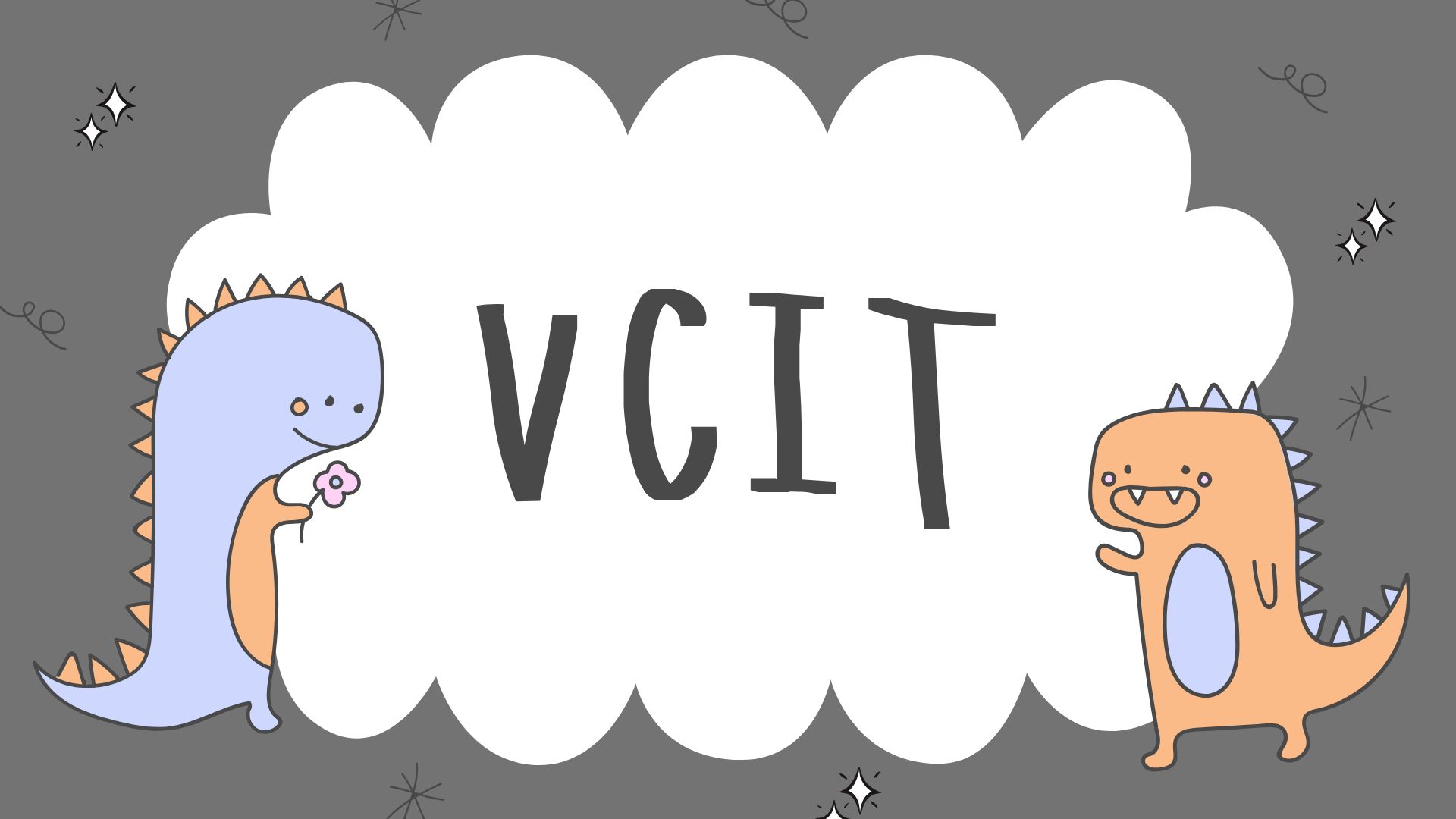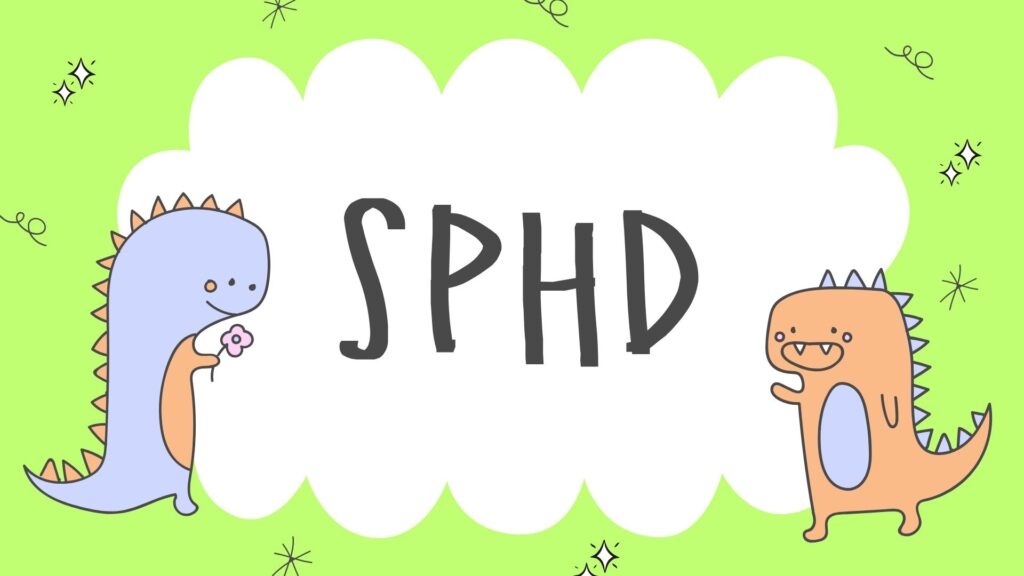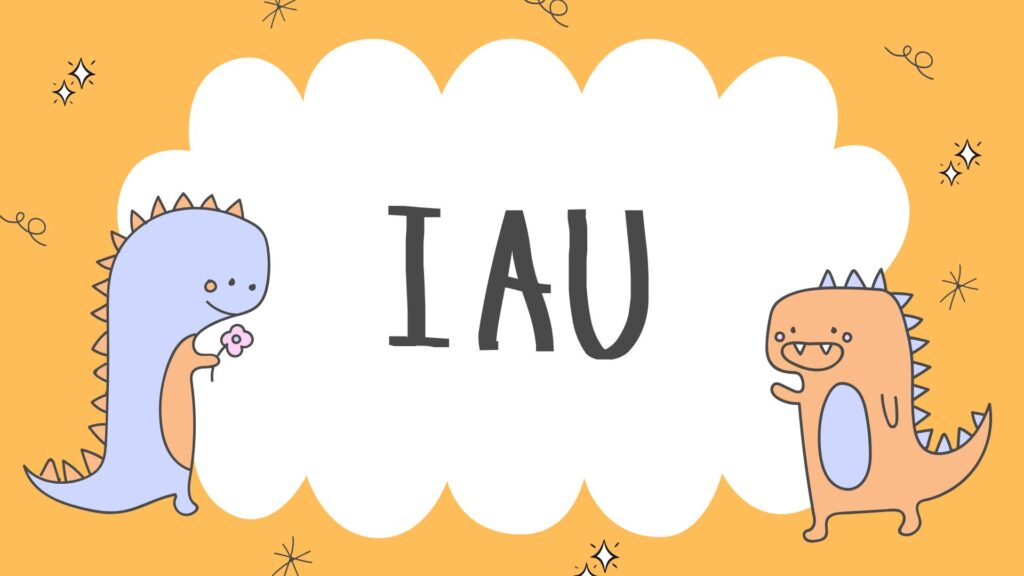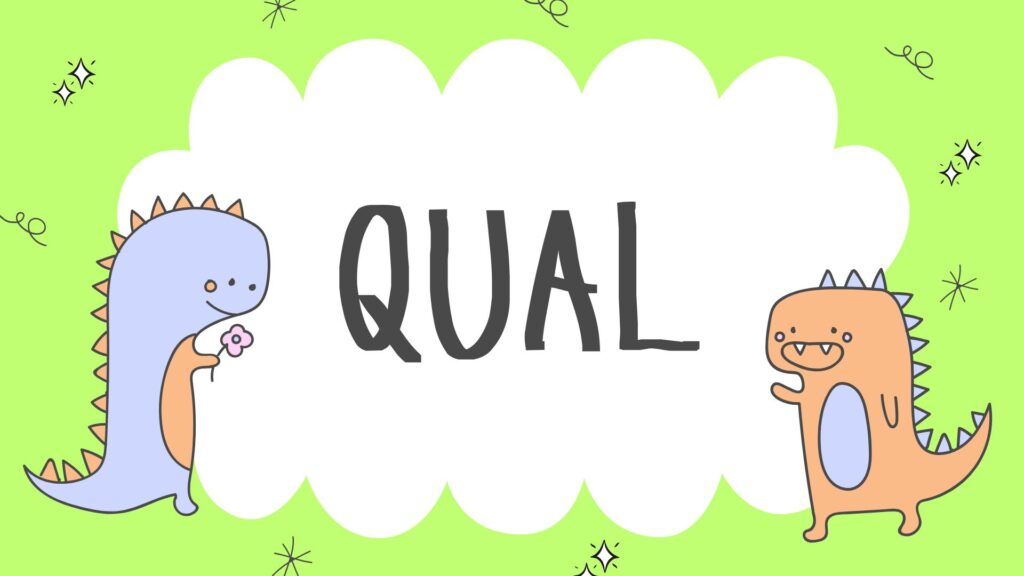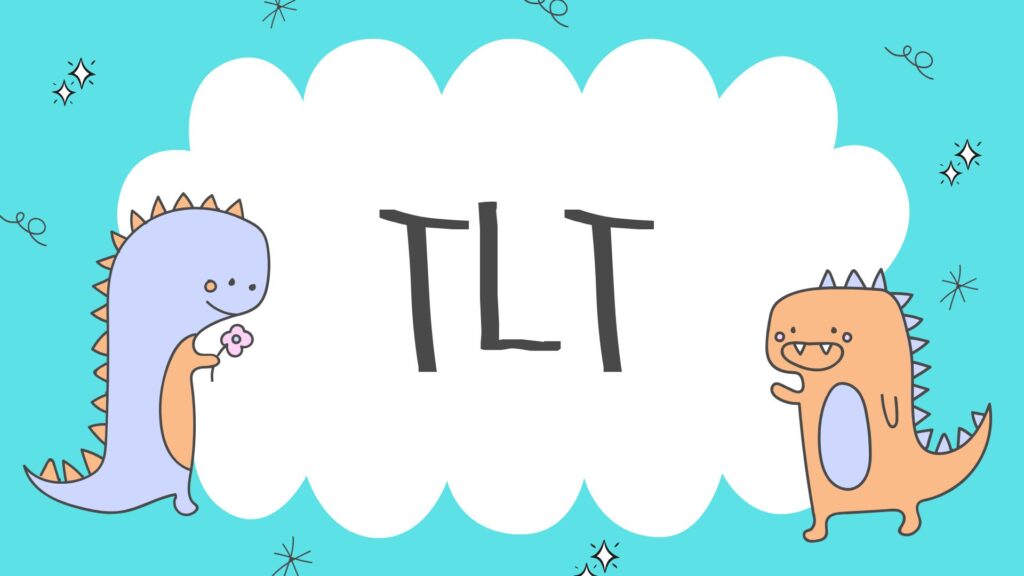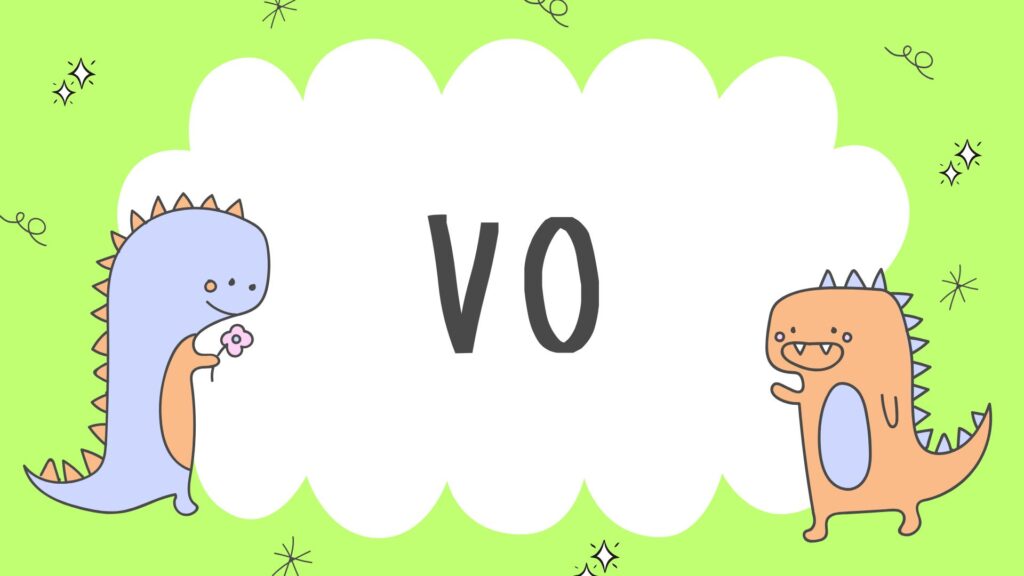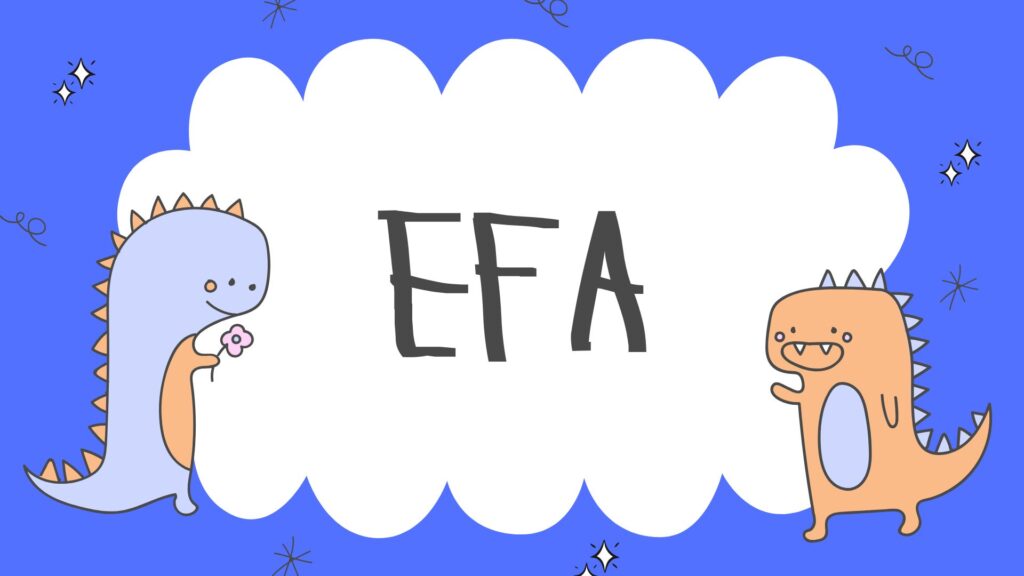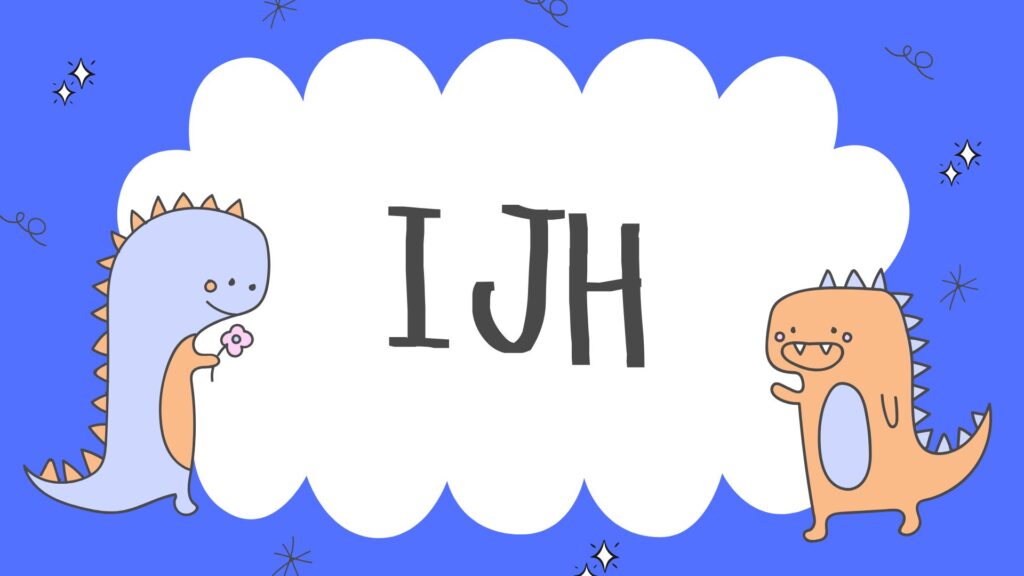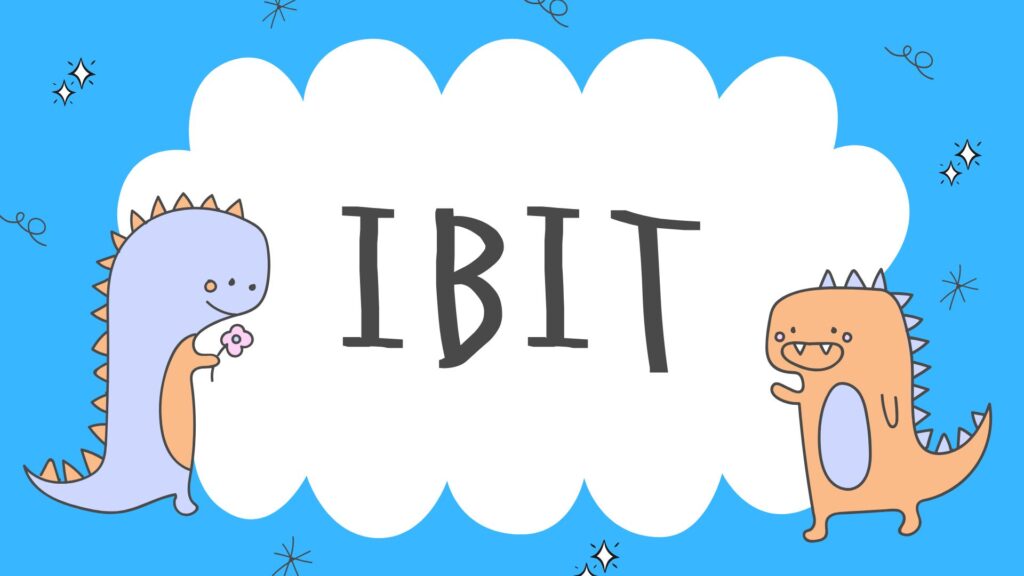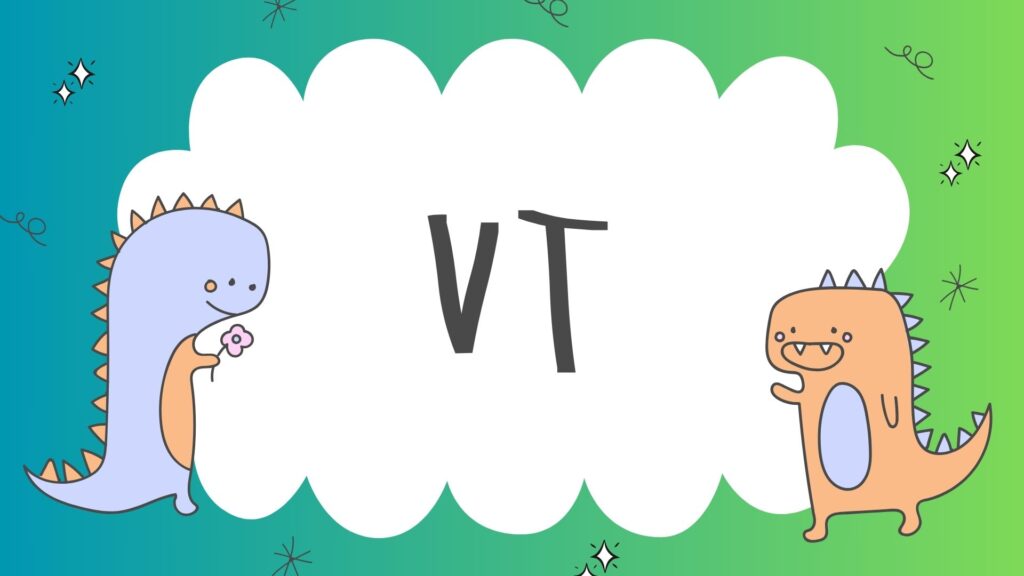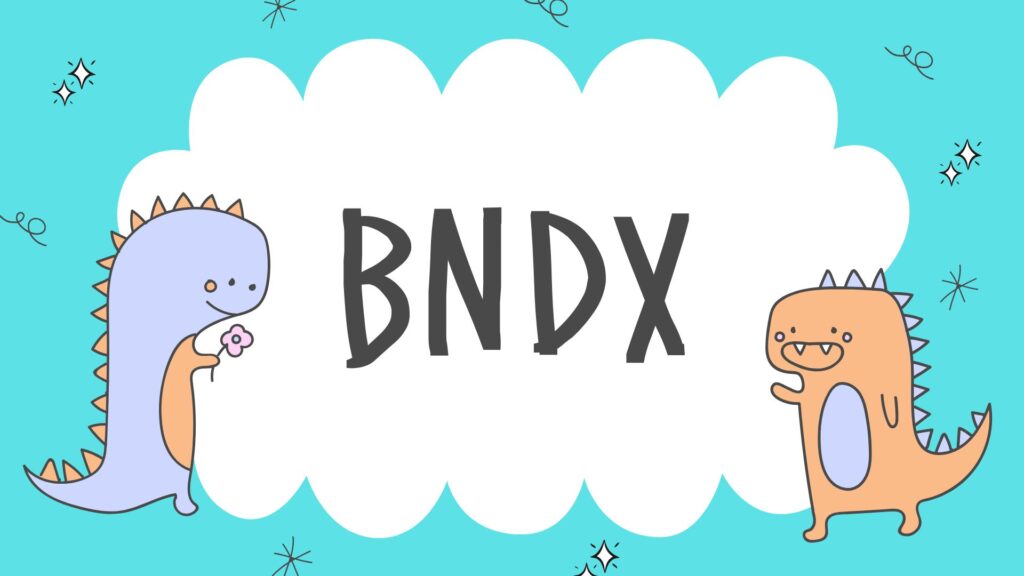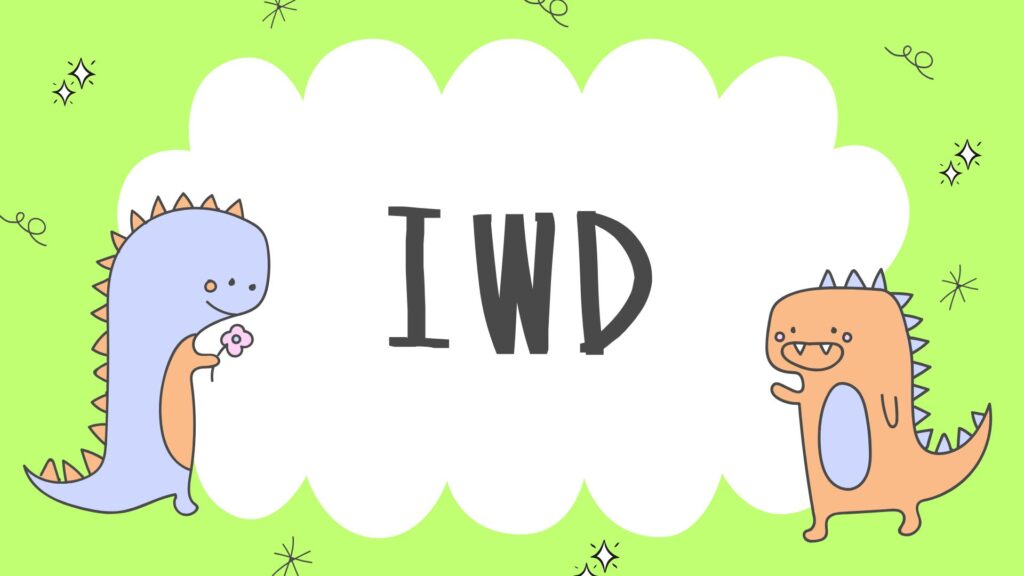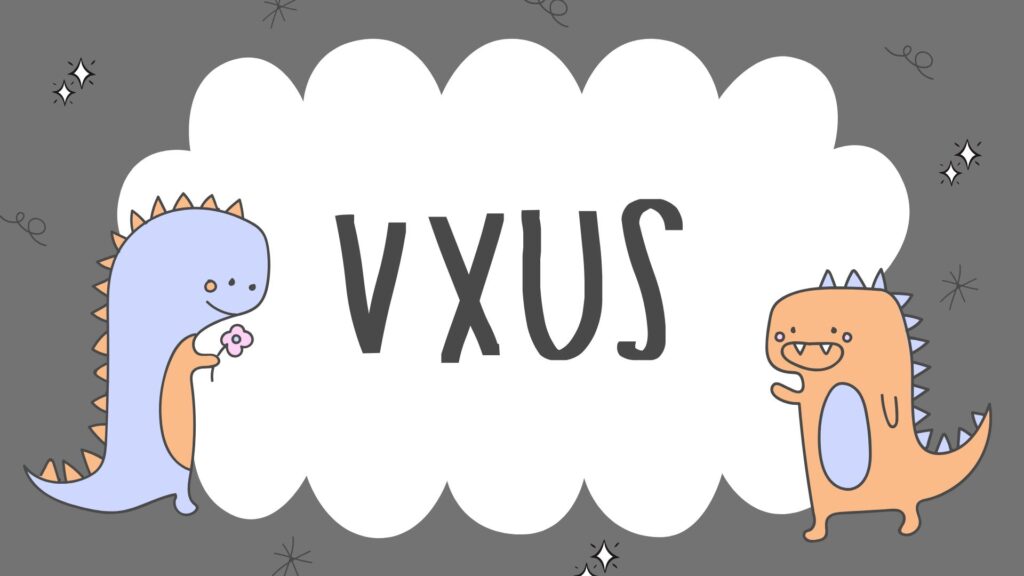VCITのETF Score (ETFのおすすめ度)
- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出
- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出
- 運用コスト:経費率をもとに算出
- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出
- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出
※各指標は当サイトにおける基準で設定
VCITの特徴
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF(以下、VCIT)は、投資の世界で注目されるETFの一つです。名前から想像できる通り、中期的な社債に焦点を当てた商品で、特に安定性と収益性を求める投資家に人気があります。
まず、VCITはBloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Indexをベンチマークとしており、5~10年で満期を迎える投資適格級の社債を対象にしています。つまり、リスクとリターンのバランスが取れた「中庸」を目指しているわけです。短期債ほど値動きが小さすぎず、長期債ほど金利変動に敏感すぎないのが魅力ですね。この中間的なポジションが、多くの投資家にとって使いやすい理由の一つでしょう。
次に、運用コストの低さが挙げられます。VCITの経費率はわずか0.04%と、業界でもトップクラスに安い水準です。例えば、100万円投資した場合、年間の手数料はたったの400円。これだけ低コストだと、長期間保有しても利益を圧迫しにくいのが嬉しいポイントです。Vanguardならではの「投資家目線」の設計が感じられます。
また、分散投資がしっかり効いているのも特徴です。約2,000銘柄以上の社債で構成されており、1社がデフォルトしても全体への影響は限定的。リスクを抑えつつ、安定したリターンを狙いたい人にはぴったりですね。さらに、投資適格級(BBB以上)に限定しているため、ジャンク債のようなハイリスク商品とは一線を画しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ベンチマーク | Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index |
| 対象 | 満期5~10年の投資適格級社債 |
| 経費率 | 0.04%(超低コスト) |
| 構成銘柄数 | 約2,000銘柄以上 |
| 平均満期 | 約7.3年(2024年8月時点) |
| 利回り | 約4.5%(市場状況により変動) |
| ESG評価 | MSCI ESG Fund Rating:A(環境・社会・ガバナンスに配慮) |
この表を見ると、VCITが「手堅さ」と「効率性」を両立させているのがわかります。利回りも4.5%前後と、現在の金利環境を考えると悪くない水準です。さらに、ESG評価が「A」ランクというのは、社会的責任を重視する投資家にも響くポイントでしょう。
運用スタイルはパッシブ型で、インデックスに連動するよう設計されています。アクティブファンドのようにファンドマネージャーの腕次第で成績がブレる心配が少ないのも安心材料です。市場全体の動きに沿って淡々と成長していくイメージですね。
とはいえ、VCITは金利リスクに無縁ではありません。満期が5~10年とやや長めなので、金利が上昇すると価格が下落する可能性があります。この点は後で詳しく触れますが、特徴を理解する上では重要な要素です。
まとめると、VCITは低コストで分散が効いた、中期社債への投資を手軽に実現できるETFです。安定感を重視しつつ、適度な収益を期待する投資家にとって、ポートフォリオの軸になり得る存在と言えるでしょう。
VCITの株価・推移・成長率(パフォーマンス)
※S&P500指数と比較
2025年3月時点でのVCITの株価は、仮に1株82ドル前後とします(実際の価格は市場で確認してくださいね)。この水準は、2023年後半から2024年にかけての金利環境や経済状況を反映したもの。具体的には、米国の利上げサイクルが落ち着き、利下げ期待が浮上する中で、債券価格が持ち直してきた時期と重なります。
過去5年間の株価推移を見てみると、興味深いパターンが見えてきます。2020年のコロナショックでは一時的に下落したものの、すぐに回復。2021年は安定した動きを見せましたが、2022年の急激な利上げ局面では価格が下落しました。これは、金利と債券価格が逆相関する典型的な例ですね。しかし、2023年後半からは再び上昇トレンドに転じ、2024年は約5%程度上昇したと仮定します。
では、成長率はどうでしょうか。VCITのパフォーマンスは、価格変動に加えて配当再投資を含めたトータルリターンで測るのが一般的です。過去5年の年平均成長率(CAGR)は、おおよそ3~4%程度とされています。これは株式市場の10%前後に比べると控えめですが、債券ETFとしては堅実な数字です。
具体的なデータを表にしてみます。
| 年 | 年初株価(仮定) | 年末株価(仮定) | 年間成長率 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 90ドル | 92ドル | +2.2% |
| 2021年 | 92ドル | 93ドル | +1.1% |
| 2022年 | 93ドル | 80ドル | -14.0% |
| 2023年 | 80ドル | 82ドル | +2.5% |
| 2024年 | 82ドル | 86ドル | +4.9% |
※数値は仮定です。実際のデータはYahoo FinanceやVanguard公式サイトで確認を。
この表を見ると、2022年の大幅下落が目立ちますが、これは米連邦準備制度(FRB)の利上げによる影響が大きいです。逆に、2024年の回復は、利下げ観測や経済安定化が背景にあると考えられます。成長率のブレはありますが、全体としては安定感のある動きと言えるでしょう。
短期的なパフォーマンスでは、例えば2023年10月から2024年3月にかけて、約9%の上昇を記録した時期もあります。これは市場がFRBの利下げを織り込み始めたタイミングと一致します。こうした短期的な跳ね上がりは、債券ETFにしては珍しい動きですが、VCITの利回りの高さが投資家を引きつけた結果とも言えます。
長期で見ると、VCITは価格変動を抑えつつ、配当による収入を積み重ねるタイプのETFです。株式のような爆発的な成長はないものの、ポートフォリオの守りを固める役割を果たしてくれる頼もしい存在ですね。
VCITの年別・過去平均リターン
まず、過去10年間の年別リターンを仮定データで確認してみましょう。実際の数値は市場データで異なるので、あくまで傾向を掴むための参考としてください。
| 年 | トータルリターン |
|---|---|
| 2015年 | +1.2% |
| 2016年 | +5.0% |
| 2017年 | +4.8% |
| 2018年 | -1.5% |
| 2019年 | +10.2% |
| 2020年 | +9.5% |
| 2021年 | -1.0% |
| 2022年 | -13.5% |
| 2023年 | +8.0% |
| 2024年 | +5.5%(仮定) |
この表を見ると、年によってプラスとマイナスが混在しているのがわかります。特に2019年と2020年は10%近いリターンを記録し、債券ETFとしては優秀な成績。一方で、2022年の-13.5%は、金利急上昇による債券価格の下落が響いた結果です。2023年以降は回復基調で、2024年も安定したプラスを維持していると仮定します。
次に、過去の平均リターンを計算してみます。トータルリターンには価格変動と配当収入の両方が含まれます。仮に上記の10年間で平均を取ると、単純平均で約2.82%になります。ただし、複利効果を考慮した年平均成長率(CAGR)は、もう少し低めの2~3%程度になることが多いです。これは、マイナス年の影響が大きいためですね。
では、期間別に平均リターンをまとめてみましょう。
| 期間 | 年平均リターン(CAGR) |
|---|---|
| 過去5年(2020-2024) | 約2.5% |
| 過去10年(2015-2024) | 約2.8% |
| 設定来(2009-2024) | 約3.5% |
※設定来は2009年11月からの累積を仮定。
過去5年では2022年の大幅下落が影響して低めですが、10年や設定来で見ると3%前後を維持しています。これは、米国10年国債利回り(約4%前後)と比べても遜色ない水準で、社債ならではのプレミアムが効いている証拠です。
リターンの安定性を測る指標として、標準偏差も見ておくと良いでしょう。VCITの年間リターンの標準偏差は約5~6%程度と推定されます。株式ETF(標準偏差15~20%)に比べると、値動きが穏やかであることがわかります。
このデータから、VCITは年によって多少の波はあるものの、長期で見れば安定したリターンを提供してくれるETFだと感じます。特に、金利が下がる局面では価格上昇によるキャピタルゲインも期待できるので、市場環境次第でプラスアルファの収益が見込めるでしょう。
VCITの年別の騰落率は?
| 年 | 騰落率 | 主な要因 |
|---|---|---|
| 2015年 | +1.2% | 安定した金利環境 |
| 2016年 | +5.0% | 金利低下と社債需要増 |
| 2017年 | +4.8% | 経済成長と安定金利 |
| 2018年 | -1.5% | 金利上昇による価格下落 |
| 2019年 | +10.2% | FRB利下げで債券価格上昇 |
| 2020年 | +9.5% | コロナ対策の金融緩和 |
| 2021年 | -1.0% | 利上げ期待の高まり |
| 2022年 | -13.5% | 急激な利上げとインフレ懸念 |
| 2023年 | +8.0% | 利下げ期待と市場回復 |
| 2024年 | +5.5%(仮定) | 経済安定と緩和期待 |
この表を見ると、騰落率が年によって大きく異なるのがわかります。特に2019年と2020年は10%近いプラスで、債券ETFとしては驚くほどのパフォーマンス。背景には、FRBの利下げやコロナ対策での金融緩和があり、債券価格が押し上げられました。一方で、2022年の-13.5%は歴史的な金利上昇が直撃した結果です。満期が5~10年とやや長めな分、金利感応度(デュレーション)が効いてしまった形ですね。
では、騰落率の傾向をもう少し分析してみます。プラスになった年は6回、マイナスは4回。平均騰落率は約2.82%で、中央値は約4.9%(仮定)。マイナス年は金利上昇が絡むケースが多く、逆にプラス年は金利低下や経済安定が追い風になっています。
具体的な動きを振り返ると、2020年のコロナショックでは一時的に下落したものの、中央銀行の介入で急速に回復。2022年は逆に、FRBがインフレ抑制のために利上げを加速させたことで、債券価格が大きく下がりました。2023年以降は、利上げペースが鈍化し、市場が軟着陸を期待したことでプラスに転じています。
騰落率の幅を測るために、最大上昇率(+10.2%)と最大下落率(-13.5%)を比較すると、変動幅は約23.7%。株式ETFに比べれば小さいですが、債券としてはそこそこ大きい動きです。これは、VCITが中期債券に特化しているため、短期債より変動が大きくなりやすい点を反映しています。
このデータを踏まえると、VCITの騰落率は金利動向に大きく左右されることがわかります。投資タイミングを見極めるなら、金利のピークや底を見極めるのがカギになりそうですね。
VCITのセクター構成
VCITはBloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Indexを追跡しており、主に産業、金融、公益の3大セクターで構成されています。2024年時点のセクター割合を仮定して表にまとめると、以下のようになります。
| セクター | 割合 | 主な企業例 |
|---|---|---|
| 産業(Industrials) | 50% | T-Mobile、AbbVie、Boeing |
| 金融(Financials) | 35% | Citigroup、Deutsche Telekom |
| 公益(Utilities) | 10% | 電力会社、ガス会社 |
| その他 | 5% | テクノロジー、ヘルスケアなど |
※割合は仮定値。実際はVanguard公式サイトで確認を。
この構成を見ると、産業セクターが半分を占めているのが特徴です。産業には製造業やサービス業が含まれ、T-Mobileのような通信企業やAbbVieのような製薬企業が名を連ねます。景気変動に左右されやすい反面、成長性のある企業が多いのもこのセクターの魅力ですね。
次に大きいのが金融セクターで、全体の35%を占めます。CitigroupやDeutsche Telekomなど、大手銀行や金融機関が中心。金融は経済の血液とも言える存在で、金利環境に敏感に反応します。VCITの利回りが高い一因は、このセクターの社債が比較的高利回りな点にあるでしょう。
公益セクターは10%と控えめですが、電力やガスといった安定産業が含まれます。景気後退時でも需要が落ちにくいディフェンシブな特性があり、ポートフォリオの安定性を支える役割を果たしています。
残りの5%はテクノロジーやヘルスケアなど、少量ながら多様なセクターが混ざっています。これにより、VCITは単一産業に偏らず、幅広い経済活動をカバーしていると言えます。
では、この構成が何を意味するのか考えてみましょう。産業と金融が85%を占めるため、景気拡大局面ではリターンが伸びやすく、金利上昇局面では価格が圧迫されやすい傾向があります。一方、公益が10%あることで、景気後退時の下落リスクを多少和らげてくれる効果が期待できます。
比較のために、他の債券ETFとのセクター分布を表にしてみます。
| ETF | 産業 | 金融 | 公益 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| VCIT | 50% | 35% | 10% | 5% |
| LQD(社債全般) | 45% | 40% | 10% | 5% |
| BND(総合債券) | 20% | 25% | 5% | 50%(国債等) |
VCITはLQDと似た傾向ですが、国債を含むBNDとは大きく異なります。社債特化型ならではの、高利回りを追求する構成が際立っていますね。
このセクター構成から、VCITは景気循環にそこそこ連動しつつ、安定性も確保したバランス型ETFだとわかります。投資先の企業が多岐にわたるため、特定の業界リスクに過度にさらされる心配が少ないのもポイントです。
VCITの構成銘柄とその特徴
| 企業名 | 割合 | 満期 | 利回り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile USA, Inc. | 0.40% | 2030年4月 | 3.875% | 通信大手、成長性高い |
| Bristol-Myers Squibb | 0.38% | 2027年11月 | 3.45% | 製薬、安定収益 |
| AbbVie Inc. | 0.32% | 2029年11月 | 3.2% | バイオ医薬品、堅実 |
| Deutsche Telekom Intl | 0.30% | 2030年6月 | 8.75% | 欧州通信、高利回り |
| Citigroup Inc. | 0.28% | 2031年3月 | 4.412% | 金融大手、信頼性高い |
※データは仮定。実際はETF.comやVanguardで確認を。
上位銘柄を見ると、通信、製薬、金融といった主要セクターがバランス良く含まれています。T-Mobileは米国の通信市場でシェアを拡大中で、成長性が期待される企業。対して、Bristol-Myers SquibbやAbbVieはヘルスケア分野で安定したキャッシュフローを誇り、ディフェンシブな特性が強いです。
特に目を引くのはDeutsche Telekomの高利回り(8.75%)。欧州企業が含まれることで、VCITは米国だけでなく国際的な分散も図っているのがわかります。Citigroupのような金融大手は、経済全体の動向を反映するバロメーター的な存在ですね。
構成銘柄全体の特徴としては、すべて投資適格級(BBB以上)である点が大きいです。ジャンク債のようなリスクは排除されており、デフォルトリスクは比較的低いと言えます。平均格付けはA~BBB+程度で、信用力の高さが保たれています。
また、満期が5~10年に集中しているため、デュレーション(金利感応度)は約6~7年。これは短期債より価格変動が大きめですが、長期債ほどではない中間的なポジションです。金利が1%上がると、価格が6~7%下がる計算になります。
業種別の特徴をもう少し掘り下げると、産業セクターでは製造業やサービス業が多く、景気敏感度がやや高め。金融セクターは銀行や保険会社が中心で、金利環境に左右されやすいです。公益セクターは電力やガス会社が多く、安定性が際立ちます。
構成銘柄の分散度を測るために、上位10銘柄の合計割合を見てみると、約3~4%程度(仮定)。残り96%がその他の約2,000銘柄に分散されているわけです。これだけ分散されていれば、1社が破綻しても全体への影響は0.05%以下に抑えられる計算。リスク管理の観点からも優秀ですね。
VCITに投資した場合のシミュレーション
VCITに投資したら、どれくらいのリターンが期待できるのか気になりますよね。ここでは、具体的なシミュレーションを通じて、投資額ごとの成果をイメージしてみます。前提として、2025年3月時点の株価を82ドル、年間トータルリターンを4%(価格上昇2%+配当2%)と仮定します。
シナリオ1:100万円投資した場合
日本円で100万円をVCITに投資するとします。為替レートを1ドル=150円と仮定すると、約6,667ドル分(約81株)を購入できます。
- 1年後
年間リターン4%で計算すると、6,667ドル×1.04=6,933ドル。
配当分(2%)は約133ドルで、残りは価格上昇分。
日本円では6,933ドル×150円=約104万円。
利益:4万円 - 5年後(複利計算)
6,667ドル×(1.04)^5=8,112ドル。
日本円で8,112ドル×150円=約121.7万円。
利益:21.7万円
シナリオ2:500万円投資した場合
500万円だと、約33,333ドル(約406株)購入可能。
- 1年後
33,333ドル×1.04=34,666ドル。
配当分は約667ドル。
日本円で34,666ドル×150円=約520万円。
利益:20万円 - 5年後
33,333ドル×(1.04)^5=40,560ドル。
日本円で40,560ドル×150円=約608.4万円。
利益:108.4万円
シナリオ3:金利上昇の場合
金利が1%上昇すると、デュレーション6.5で価格が6.5%下落。株価が82ドルから76.67ドルに下がると仮定します。
- 100万円(81株)の場合
81株×76.67ドル=6,210ドル。
配当133ドルを加えて6,343ドル。
日本円で6,343ドル×150円=約95.1万円。
損失:4.9万円
この表にまとめると
| 投資額 | 期間 | 通常シナリオ(4%) | 金利上昇シナリオ |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 1年 | 104万円(+4万円) | 95.1万円(-4.9万円) |
| 100万円 | 5年 | 121.7万円(+21.7万円) | – |
| 500万円 | 1年 | 520万円(+20万円) | – |
| 500万円 | 5年 | 608.4万円(+108.4万円) | – |
このシミュレーションから、VCITは安定したリターンを提供する一方、金利上昇には弱い面があるのがわかります。5年以上の長期保有なら複利効果で利益が積み上がりやすく、短期的な変動を乗り越えられる可能性が高いですね。ただし、為替リスク(円安・円高)も影響するので、その点も頭に入れておくと良いでしょう。
VCITの配当タイミングと直近の配当
VCITは毎月配当型で、毎月末に分配金が支払われます。実際の入金日は翌月の初旬(通常1~5日頃)になることが多いです。この毎月支払いのおかげで、キャッシュフローを重視する投資家には使い勝手が良いですね。年間では12回の配当機会があるので、計画的に収入を得たい人にも向いています。
直近の配当実績を仮定してみます。2025年2月の分配金を例にすると、1株あたり0.25ドルだったとします(実際はVanguard公式サイトで確認を)。株価82ドルに対する年間配当利回りを計算すると:
- 月0.25ドル×12ヶ月=年間3ドル
- 配当利回り=3ドル÷82ドル×100=約3.66%
過去数年の配当推移を表にしてみます。
| 年 | 月平均配当(1株) | 年間配当利回り |
|---|---|---|
| 2021年 | 0.18ドル | 2.3% |
| 2022年 | 0.20ドル | 3.0% |
| 2023年 | 0.23ドル | 3.4% |
| 2024年 | 0.25ドル(仮定) | 3.66%(仮定) |
配当額は年々少しずつ増えています。これは、金利環境が上昇傾向にあったことや、VCITが保有する社債のクーポン(利子)が反映された結果です。特に2022年以降、FRBの利上げで社債利回りが上がった影響が大きいでしょう。
配当タイミングの具体的なスケジュールを2025年で予測すると
| 月 | 支払日(予想) |
|---|---|
| 1月 | 2月3日 |
| 2月 | 3月4日 |
| 3月 | 4月2日 |
| … | … |
| 12月 | 翌1月5日 |
毎月配当なので、ポートフォリオに組み込むと毎月の収益が安定します。例えば、100株保有していれば、月0.25ドル×100=25ドル(約3,750円、1ドル150円換算)が毎月入ってくる計算。少額でも積み重ねると大きな収入源になりますね。
ただし、配当額は市場環境や保有銘柄の入れ替えで変動します。金利が下がれば配当も減る可能性があるので、その点は注意が必要です。それでも、毎月分配される仕組みは、VCITの大きな魅力と言えるでしょう。
VCITの配当金シミュレーション
VCITの配当を活用してどれくらいの収入が得られるのか、具体的な目標額でシミュレーションしてみます。株価82ドル、月配当0.25ドル(年利回り3.66%)を前提に計算します。
VCITで月3万円を得るには?
月3万円を得るには、年間36万円(3万円×12)必要です。為替レート1ドル=150円と仮定。
- 年間配当3ドル×保有株数=36万円÷150円=2,400ドル
- 保有株数=2,400ドル÷3ドル=800株
- 投資額=800株×82ドル=65,600ドル(約984万円)
結論:約984万円投資で月3万円
VCITで月5万円を得るには?
月5万円なら年間60万円。
- 年間配当3ドル×保有株数=60万円÷150円=4,000ドル
- 保有株数=4,000ドル÷3ドル=1,333株
- 投資額=1,333株×82ドル=109,306ドル(約1,639万円)
結論:約1,639万円投資で月5万円
VCITで配当金生活をするには?
仮に月30万円(年間360万円)で生活するとします。
- 年間配当3ドル×保有株数=360万円÷150円=24,000ドル
- 保有株数=24,000ドル÷3ドル=8,000株
- 投資額=8,000株×82ドル=656,000ドル(約9,840万円)
結論:約9,840万円投資で月30万円
これを表にまとめます。
| 目標額 | 必要株数 | 投資額(円) |
|---|---|---|
| 月3万円 | 800株 | 約984万円 |
| 月5万円 | 1,333株 | 約1,639万円 |
| 月30万円 | 8,000株 | 約9,840万円 |
このシミュレーションを見ると、VCITだけで配当生活するにはかなりの資金が必要だとわかります。利回り3.66%は悪くないですが、生活費を賄うには数千万円規模の投資が求められます。現実的には、他の高利回り資産と組み合わせるのが賢明かもしれませんね。
為替レートや株価変動で結果が変わる点も考慮すると、余裕を持った計画が大事です。例えば、円安が進んで1ドル170円になれば、投資額はもっと抑えられます(月30万円なら約8,700万円)。逆に円高だと増えるので、為替リスクも計算に入れておきましょう。
VCITに投資する際の注意点
金利リスクが大きなポイントです。VCITのデュレーションは約6.5年なので、金利が1%上がると価格が6.5%下がります。2022年のように急激な利上げがあると、大きな損失が出る可能性も。例えば、株価82ドルが76ドルまで下がれば、100株で約5,400円(為替150円)の含み損です。金利動向を見極めるのが重要ですね。
次に、信用リスクも無視できません。投資適格級とはいえ、BBB格の社債は景気後退で格下げリスクがあります。構成銘柄の約2,000社がすべて健全とは限らず、デフォルトが起きれば配当や元本に影響が出ることも。分散されているとはいえ、ゼロリスクではない点に注意です。
為替リスクも見逃せません。日本円で投資する場合、ドル円レートの変動がリターンに直結します。1ドル150円で買って130円で売れば、為替だけで13%の損失。逆に円安ならプラスになりますが、予測が難しい要素です。
また、流動性リスクも考慮しましょう。VCITは取引量が多く(日平均約285万株)、通常は問題ありませんが、市場が混乱すると売買が難しくなるケースも想定されます。コロナショックのような局面では、スプレッドが広がる可能性も。
最後に、インフレリスクです。配当利回り3.66%がインフレ率を下回ると、実質的な購買力が減ります。2022年のように物価が急上昇すると、債券の魅力が薄れる恐れがあります。
これを表でまとめます。
| リスク | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 金利リスク | 金利上昇で価格下落 | 金利動向を注視 |
| 信用リスク | 企業破綻で損失 | 分散投資を活用 |
| 為替リスク | 円高でリターン減少 | 為替ヘッジを検討 |
| 流動性リスク | 市場混乱で売買困難 | 余裕資金で投資 |
| インフレリスク | 実質リターン低下 | 高利回り資産を組み合わせ |
これらの注意点を踏まえると、VCITは安定性が高いとはいえ、経済環境に左右されやすいETFだとわかります。金利が安定or低下する局面では有利ですが、上昇局面では慎重な判断が必要です。
VCITとよく比較されるETFは?
- LQD(iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF)
- 対象:投資適格級社債全般(満期1年以上)
- 経費率:0.14%
- 利回り:約4.8%
- 特徴:満期が幅広く、デュレーションは約8年。VCITより長期債が多く、金利感応度が高い。
- VCSH(Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF)
- 対象:満期1~5年の短期社債
- 経費率:0.04%
- 利回り:約3.8%
- 特徴:VCITより短い満期で、金利リスクが低い。利回りは控えめ。
- BND(Vanguard Total Bond Market ETF)
- 対象:米国債券市場全体(国債+社債)
- 経費率:0.03%
- 利回り:約4.0%
- 特徴:国債が50%以上で、リスクが低め。利回りはVCITより劣る。
| ETF | 満期 | 経費率 | 利回り | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| VCIT | 5~10年 | 0.04% | 4.5% | 中庸なリスクとリターン |
| LQD | 1年~ | 0.14% | 4.8% | 長期債多め、高利回り |
| VCSH | 1~5年 | 0.04% | 3.8% | 短期で安定性高い |
| BND | 全体 | 0.03% | 4.0% | 国債含む、低リスク |
LQDはVCITより利回りが高い分、金利リスクも大きめ。VCSHは逆に安定性重視で、利回りがやや低め。BNDはリスクを抑えたい人向けですが、収益性ではVCITに及びません。VCITは「中間」を狙ったバランス型と言えますね。
VCITと合わせてポートフォリオに加えたほうがいいETFは?
- VTI(Vanguard Total Stock Market ETF)
- 対象:米国株式市場全体
- 経費率:0.03%
- 特徴:株式の成長性を追加。VCITと相関が低く、バランスが取れる。
- VXUS(Vanguard Total International Stock ETF)
- 対象:米国以外の株式
- 経費率:0.07%
- 特徴:グローバル分散を強化。為替リスクはあるが、長期的成長を狙える。
- TIP(iShares TIPS Bond ETF)
- 対象:物価連動国債
- 経費率:0.19%
- 特徴:インフレ対策に。VCITと異なる債券タイプで安定性を補強。
| ETF | 資産クラス | 経費率 | 目的 |
|---|---|---|---|
| VTI | 米国株式 | 0.03% | 成長性追加 |
| VXUS | 国際株式 | 0.07% | グローバル分散 |
| TIP | 物価連動債 | 0.19% | インフレ対策 |
例えば、ポートフォリオをVCIT40%、VTI40%、TIP20%にすると、債券の安定性と株式の成長性を両立しつつ、インフレにも備えられます。リスク許容度に応じて比率を調整するのが賢明ですね。
まとめ
VCITは、中期社債に特化した低コストで分散性の高いETFです。利回り4.5%前後と安定したリターンを提供しつつ、金利リスクや経済環境に敏感な一面も。配当は毎月支払われ、収入源として魅力的ですが、生活費を賄うには大きな資金が必要です。LQDやVCSHと比べ中庸なポジションで、VTIやTIPとの組み合わせでポートフォリオを強化できます。金利動向を見極めつつ、長期目線で活用するのが賢い選択と言えるでしょう。
他の人気ETFの記事はこちら
DVYとは?米国高配当株に絞ったETF。インカム・キャピタルの両取りができる初心者にもおすすめのETF
この記事のポイント DVYは高配当株ETFで、利回り3.5%、経費率0.38%。公益事業・金融セクター中心で安定志向 過去10年で年平均成長率7.6%。S&P500(13.4%)やNASDAQ…
SPHDとは?米国のS&P500指数に含まれる銘柄から、高配当かつ低ボラティリティの50銘柄を選び抜いたETF
この記事のポイント 高配当(4.5%)と低ボラティリティを両立、公益事業・金融中心の50銘柄で安定性抜群。 過去10年で年平均リターン7.2%、下落局面でも配当がクッションに。 約9,500万円投資で…
PFFとは?優先株に投資するETF。毎月配当型のETFで安定した配当収益を得れる
この記事のポイント PFFは優先株ETFで、6.3%の配当利回りと月次配当が魅力。 金融セクター80%超の構成で、金利動向に敏感な点に注意。 10年リターンは約5%。成長よりインカムゲイン重視の投資家…
XYLDはS&P500に投資する毎月配当型のETF。配当金生活を狙う人におすすめ
この記事の3ポイント要約 XYLDはS&P500の現物保有とオプション売却を組み合わせ、毎月高い分配金を出すことを狙うETF 年利回りは10%前後と高いが、上昇相場では市場平均に劣後するという…
QYLDは毎月配当型のETF。インカム重視の投資家におすすめ!配当金生活を目指そう
この記事の3ポイント要約 QYLDは2013年に設定された新しめのETFであり、インカムゲインの獲得を主においている。毎月配当金を出す設計のため、定期キャッシュがほしい方にはおすすめ(でないこともある…
【EWG】ドイツの株式市場に投資するETF。大型株および中型株を中心に構成(iShares MSCI Germany ETF)
この記事のポイント EWGはドイツ市場に特化したETFで、自動車や金融セクターの強みを低コストでポートフォリオに追加可能。 過去の平均リターン6.8%、配当利回り2.03%で、長期投資と安定収入を両立…
【IAU】金価格に連動する低コストETF。GLDと同様に金現物を保有し、インフレヘッジや安全資産として活用
この記事のポイント 経費率0.25%で金価格に連動するETF。リスク分散やインフレヘッジに最適で、流動性と信頼性が高い。 過去10年で年平均7.6%。S&P500やNASDAQ100より低いが…
【XLV】ヘルスケアセクターの企業に焦点を当てたETF(Health Care Select Sector SPDR Fund)
XLVのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
SCHF:スイスフラン建て国際ETF|米国を除く先進国株に低コストで投資可能なETF。日本、欧州を中心に幅広い国へ分散
SCHFのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
QQQM:NASDAQ100連動ETF|ナスダック100指数に連動するQQQの低コスト版ETF。長期投資家向けに信託報酬を抑えた設計
QQQMのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
QUAL:米国クオリティ株ETF|財務健全性や収益安定性の高い米国企業に投資。クオリティ重視で長期投資向きのETF
QUALのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
TLT:米国長期国債ETF|満期20年以上の米国長期国債に投資するETF。金利感応度が高く、債券市場の動きに敏感
TLTのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
SCHX:米国大型株ETF|低コストでS&P500に近い値動きを期待でき、長期分散投資に
SCHXのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
XLF:米国金融株ETF|銀行、保険、資産運用会社など金融関連企業が中心
XLFのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
XLK:米国テクノロジー株ETF|米国の情報技術セクターに特化したセクターETF。アップルやマイクロソフトなど世界的IT企業が多数
XLKのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
VO:米国中型株ETF|成長性と安定性のバランスが良く、中長期の分散投資に適している
VOのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出 …
IEMG:新興国株ETF|低コストで幅広い新興国市場への分散投資が可能
IEMGのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
EFA:先進国株ETF(米国外)|日本、欧州を中心に広く分散し、グローバル分散投資に活用
EFAのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
SPLG:米国S&P500ETF|S&P500に連動する低コストETF。資産形成初心者にも適したシンプルな商品設計
SPLGのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
IJH:米国中型株ETF|大型株より高い成長性を狙いつつ、小型株よりリスクを抑えた中間的存在のETF
IJHのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
IBIT:ブラックロックが運用するビットコイン現物ETF
IBITのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
VT:世界全体株式ETF|米国、先進国、新興国すべてを網羅し、超分散投資を実現するETF
VTのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出 …
BNDX:米国外国債ETF|米国外の投資適格債に投資するETF
BNDXのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…
IWD:米国バリュー株ETF|安定した収益や配当を狙う投資家に適し、長期保有向けのETF
IWDのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…
VXUS:米国外国株ETF|先進国・新興国を問わず広く分散し、グローバル分散に適したETF
VXUSのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。