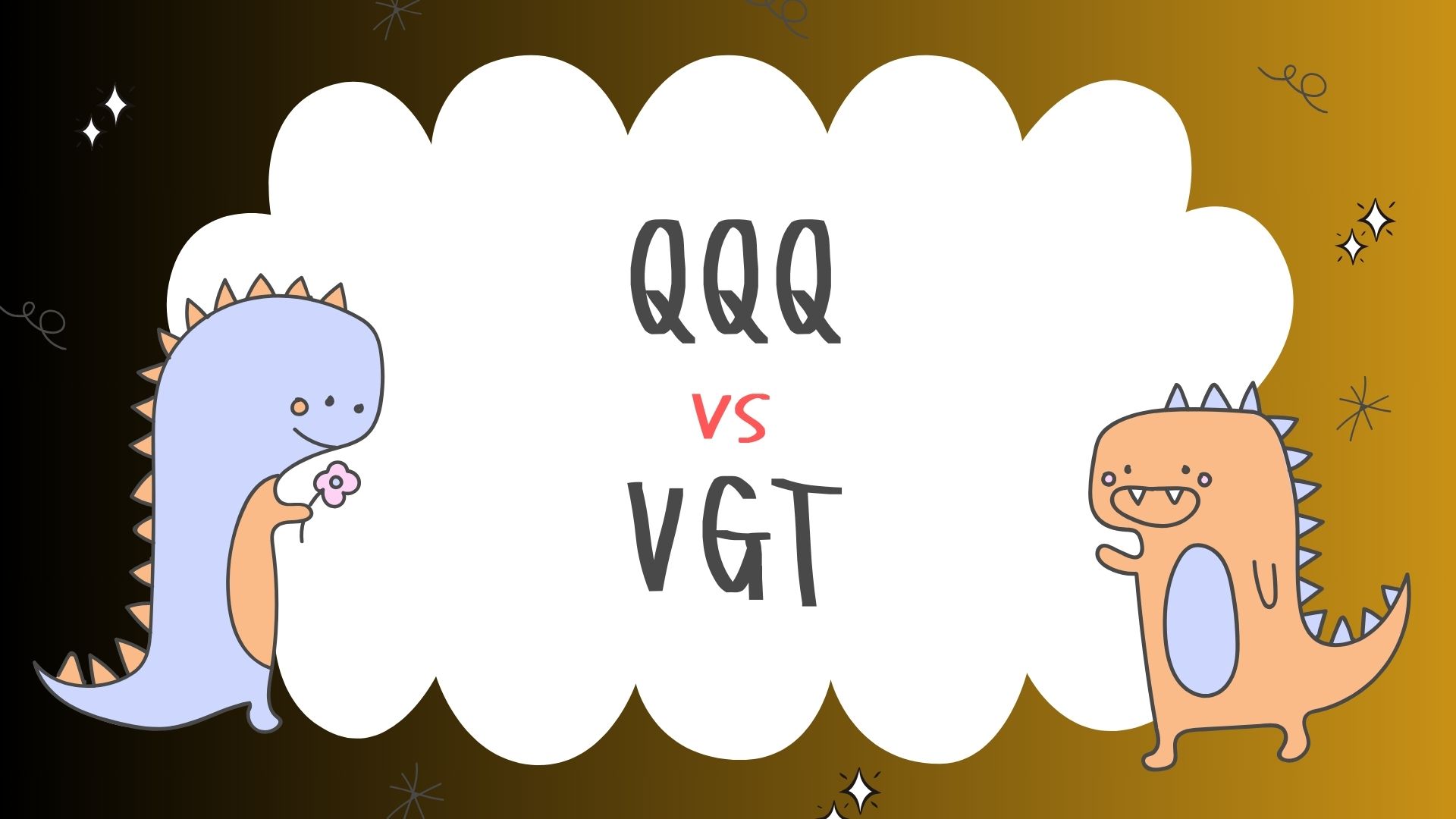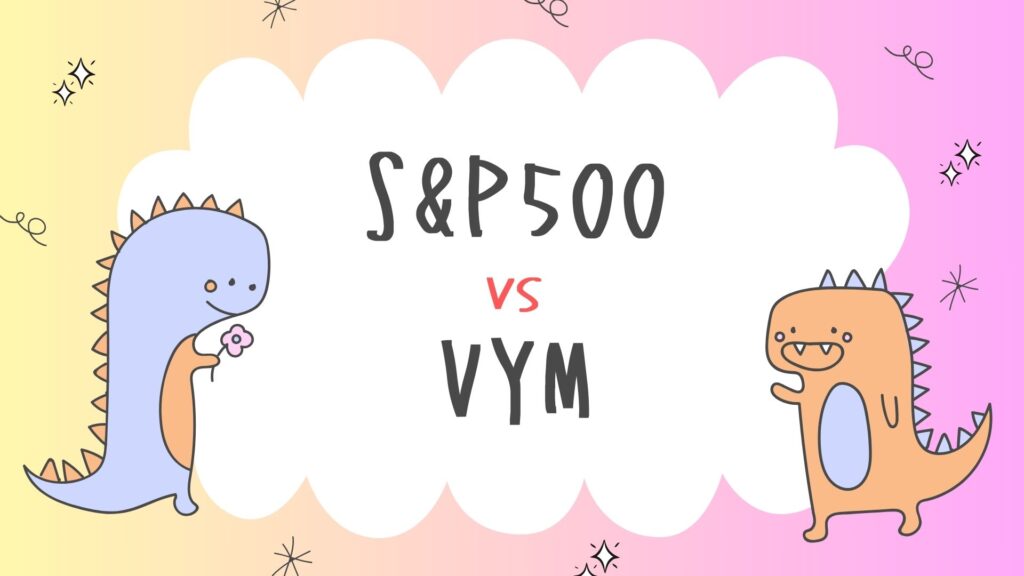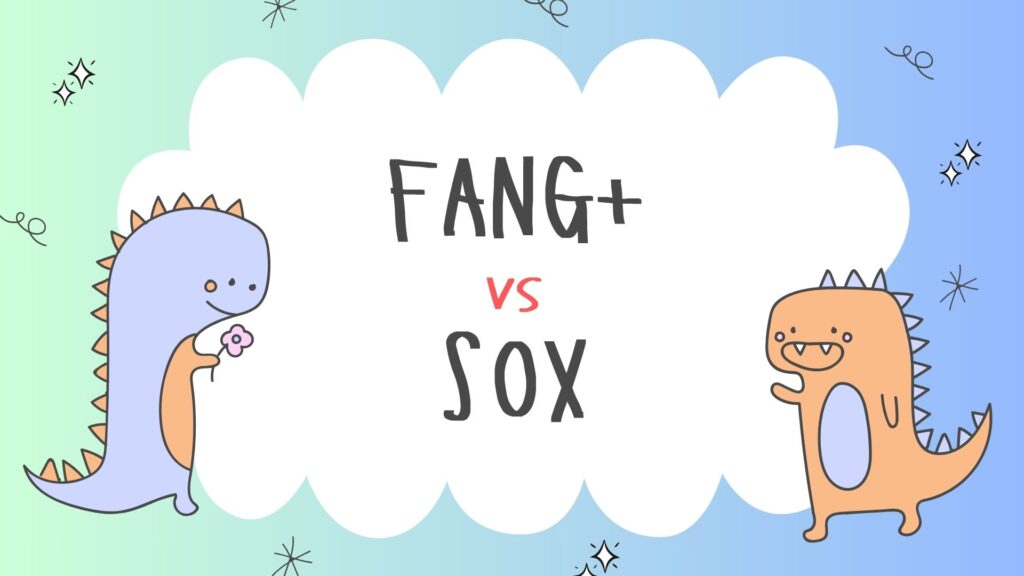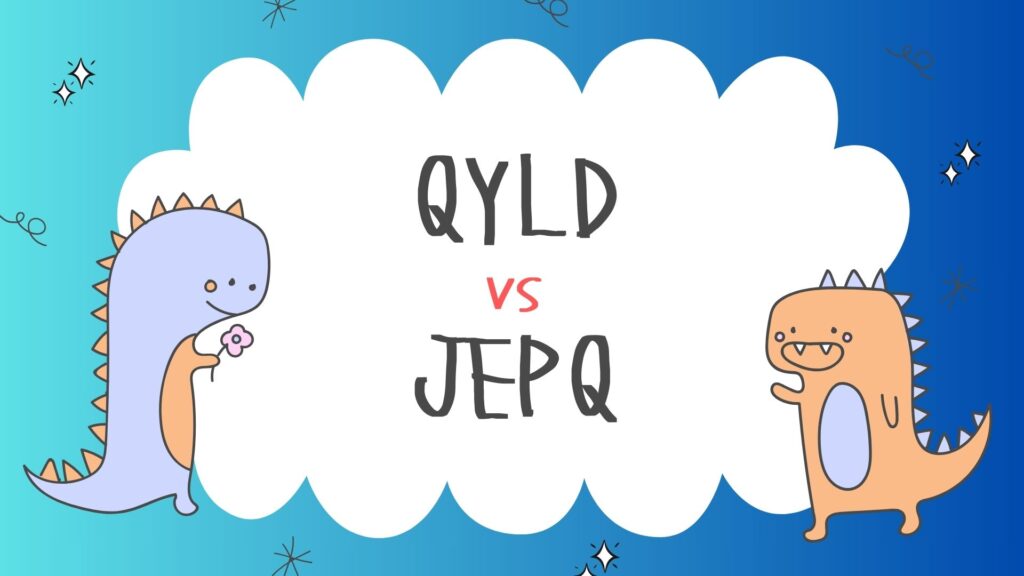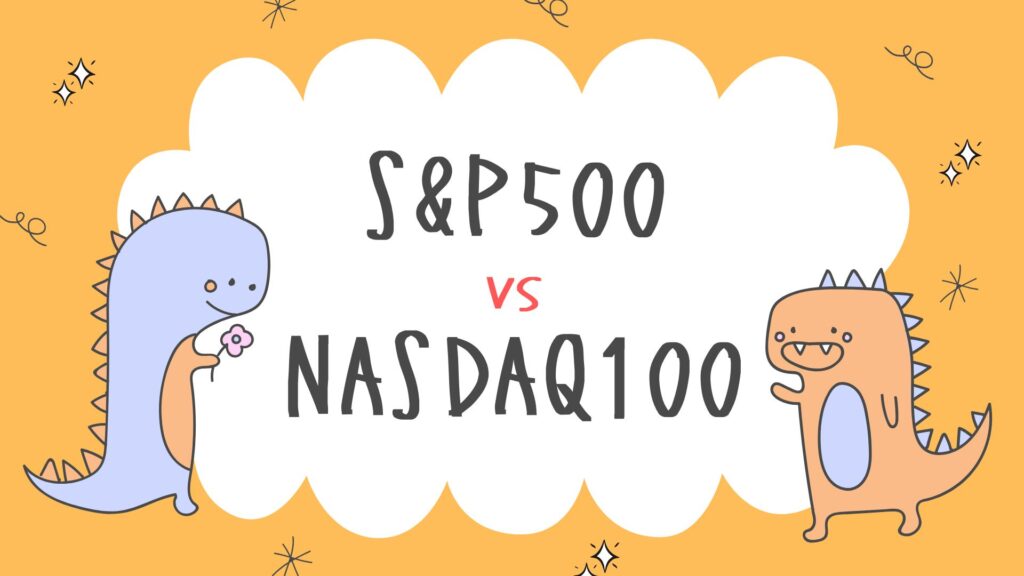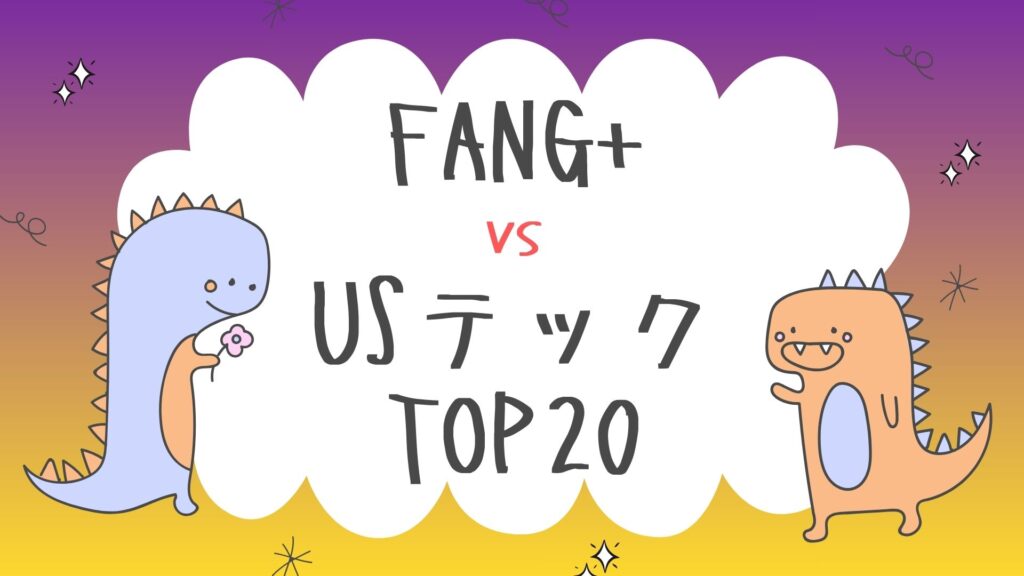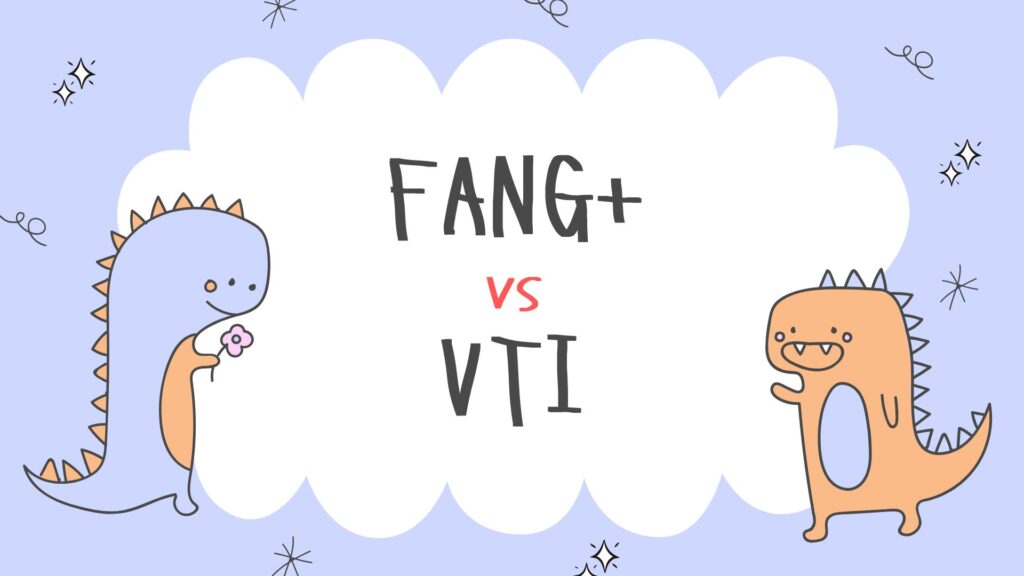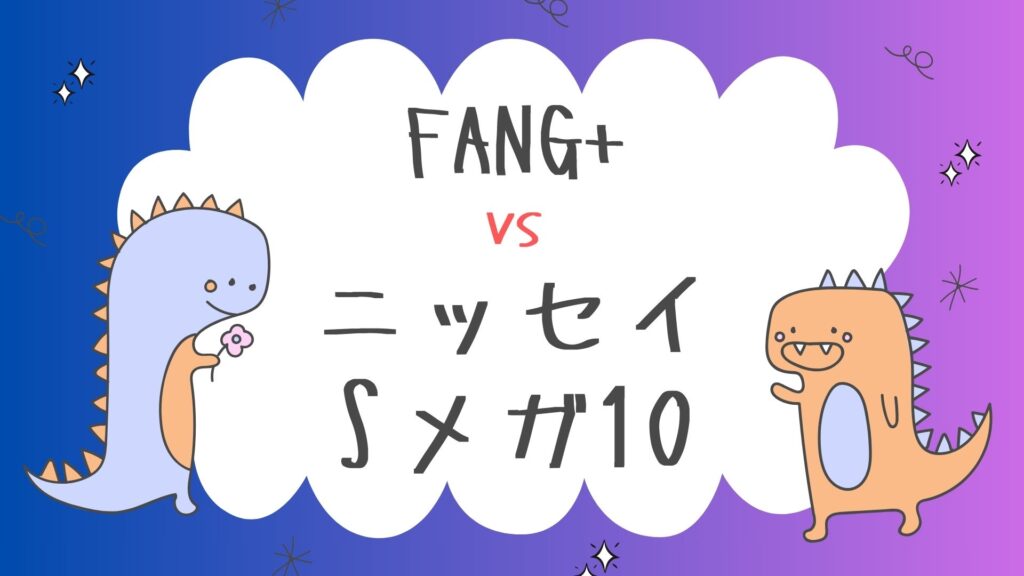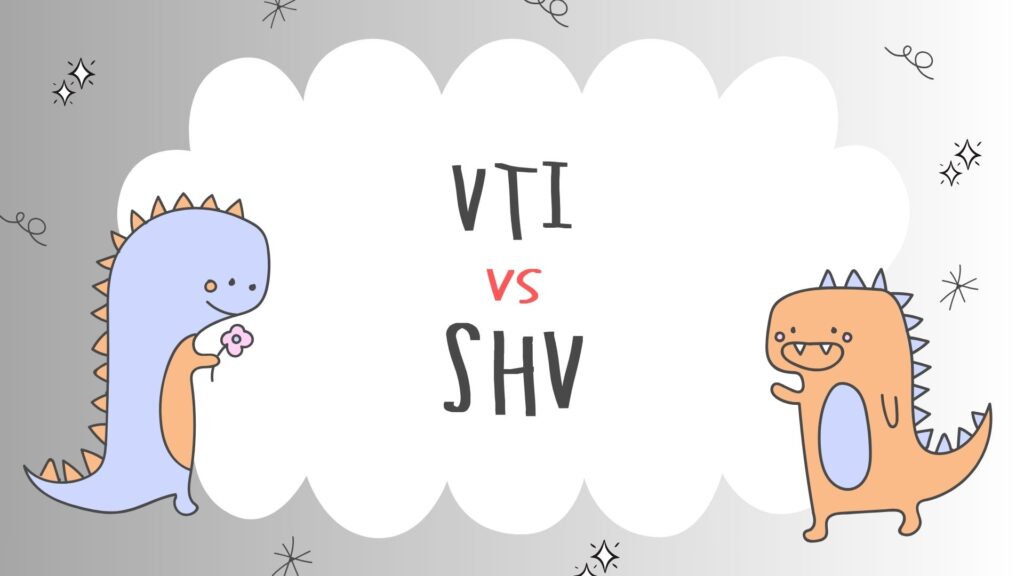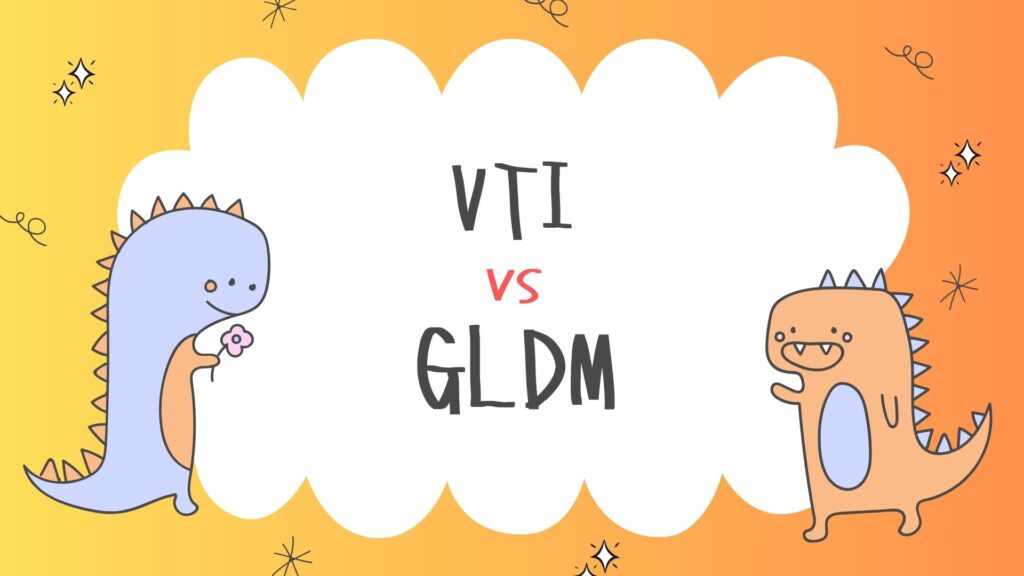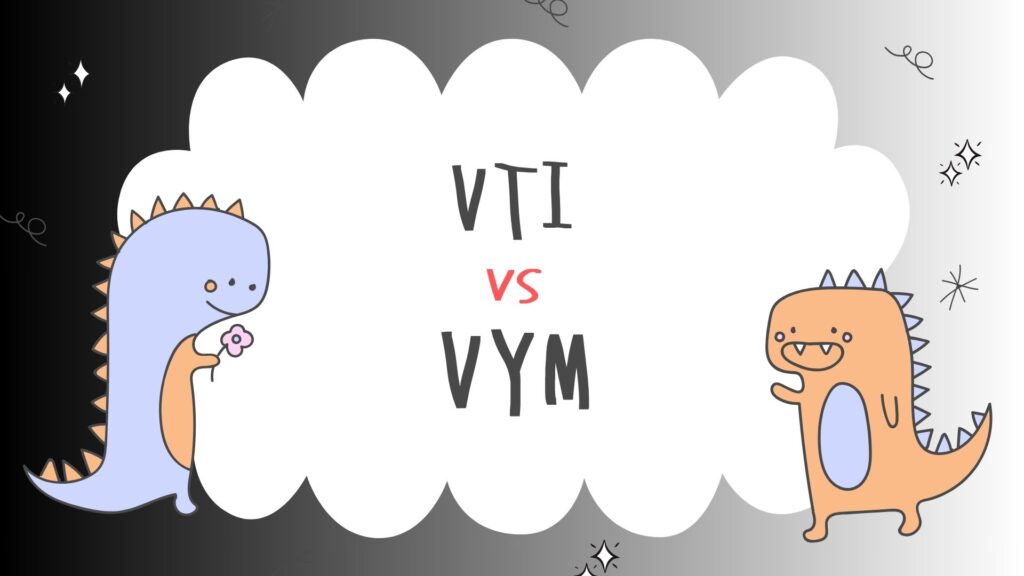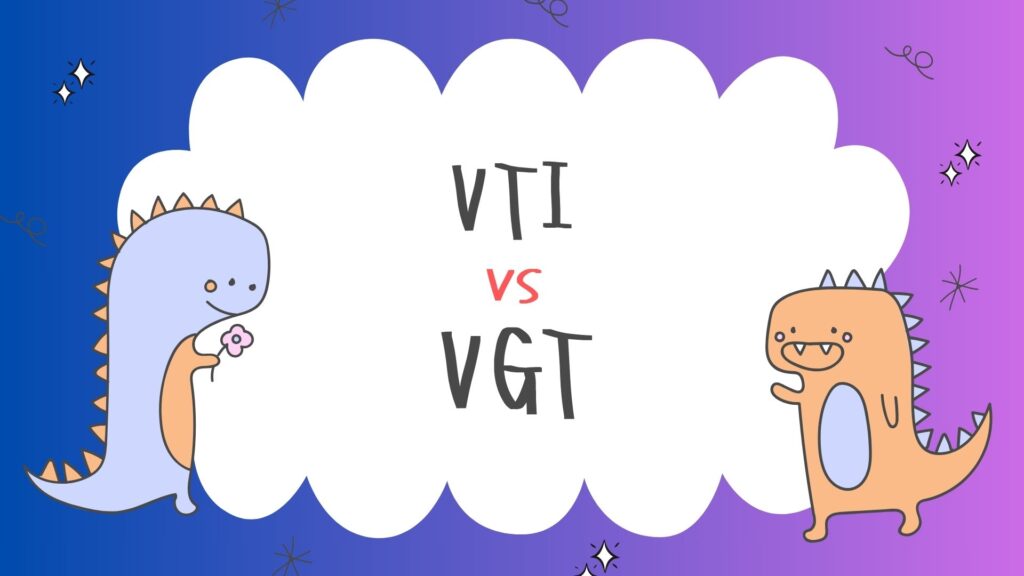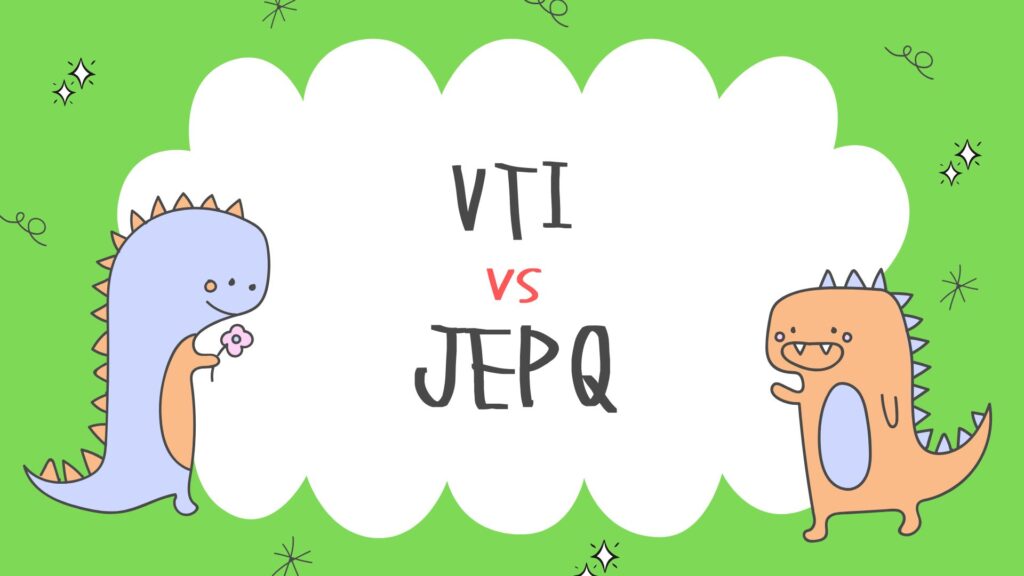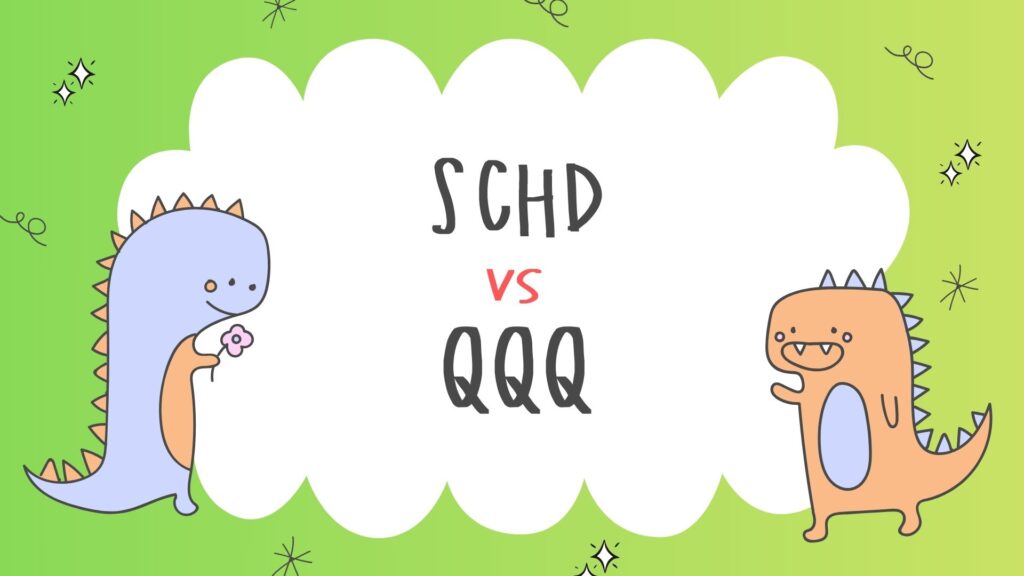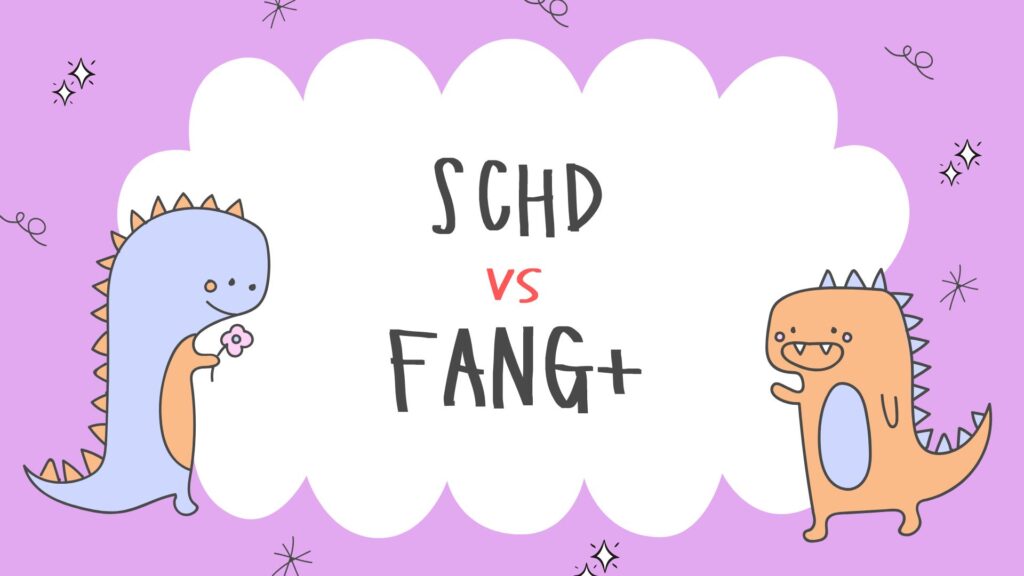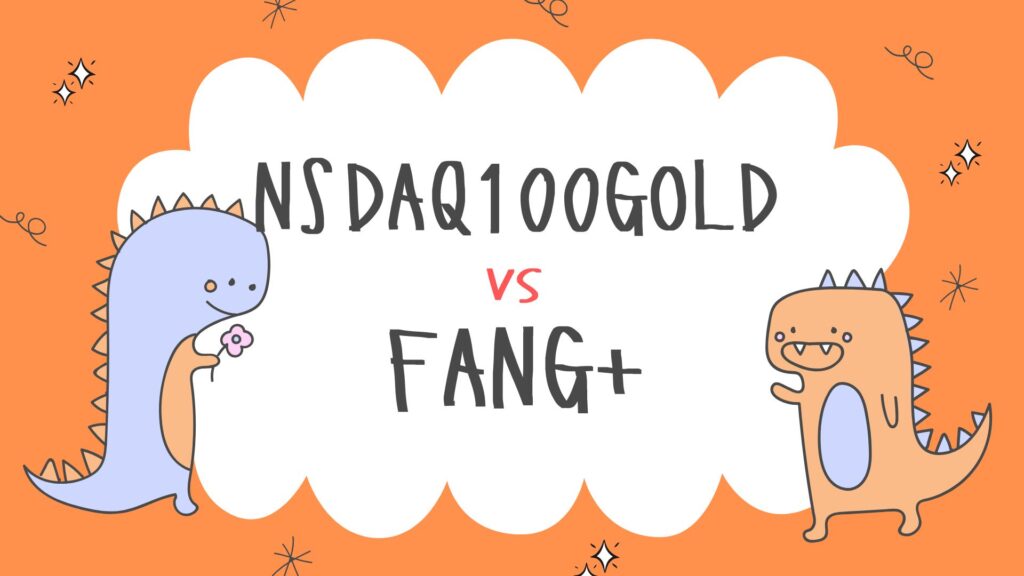【QQQ vs VGT】ETF Scoreの比較
- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出
- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出
- 運用コスト:経費率をもとに算出
- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出
- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出
※各指標は当サイトにおける基準で設定
QQQとVGTとは?
さあ、投資の世界に飛び込むなら、まず押さえておきたいのがETF(上場投資信託)です。その中でも特に注目を集めるのが「QQQ」と「VGT」。名前を耳にしたことはあるけど、いまいち何なのか分からないという人も多いのではないでしょうか。ここでは、この2つのETFが何者なのか、どんな特徴を持っているのかを分かりやすく紐解いていきます。
まず「QQQ」から。正式名称は「Invesco QQQ Trust Series 1」で、アメリカのインベスコ社が運用しています。このETFは、ナスダック100指数(NASDAQ 100)に連動するように設計されています。ナスダック100とは、ナスダック市場に上場する企業の中から、金融セクターを除いた時価総額上位100社を選んだもの。具体的には、アップル、マイクロソフト、アマゾンといったテック界の巨人が名を連ねています。1999年に設定されて以来、テクノロジー中心の成長株に投資したい人に人気の選択肢です。
一方の「VGT」は、「Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares」。こちらはバンガード社が提供するETFで、MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Indexに連動します。簡単に言うと、アメリカの情報技術(IT)セクターに特化したETFです。構成銘柄数は約320社とQQQより多く、IT関連企業のパフォーマンスを幅広く捉えたい人向け。2004年に誕生し、低コストでITに集中投資できる点が魅力とされています。
この2つ、どちらも科技術分野にフォーカスしている点で共通していますが、実はアプローチが少し違うんです。QQQはナスダック100に連動するので、IT以外に消費財やヘルスケアも少し含まれる一方、VGTは純粋にITセクターだけを対象にしています。この違いが、後で比較する際に大きなポイントになってきます。
イメージしやすいように言うと、QQQは「テクノロジー中心だけどちょっとバラエティ豊かなお弁当」で、VGTは「ITだけを詰め込んだ特化型弁当」。どちらを選ぶかは、何を重視するか次第ですね。ちなみに、ETFって株みたいに取引所で売買できるから、気軽に投資を始められるのもいいところ。純資産総額で見ると、QQQは約2,700億ドル、VGTは約700億ドル(2025年3月時点)と、規模感も違います。
ここで簡単に表にまとめてみましょう。
| 項目 | QQQ | VGT |
|---|---|---|
| 正式名称 | Invesco QQQ Trust Series 1 | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares |
| 運用会社 | インベスコ | バンガード |
| 連動指数 | NASDAQ 100 | MSCI US IMI IT 25/50 |
| 設定年 | 1999年 | 2004年 |
| 主要セクター | テクノロジー中心+他 | 情報技術のみ |
QQQとVGTが比較されるのはなぜ?
投資の話をしていると、QQQとVGTがセットで話題に上がること、結構多いですよね。ネットやSNSでも「どっちがいい?」なんて議論が飛び交っています。では、なぜこの2つのETFがこんなに比較されるのでしょうか。その背景には、投資家が求めるものと両者の特性が深く関係しています。
まず一番の理由は、どちらも「テクノロジー分野」に強いということ。現代の経済って、正直テクノロジーが牽引している部分が大きいじゃないですか。スマホ、パソコン、クラウドサービス、AI…日常生活でもITの進化を感じますよね。QQQはナスダック100に連動するから、テクノロジー企業が約60%を占めています。一方、VGTは100%がITセクター。テクノロジーの成長に賭けたい投資家にとって、どちらも魅力的な選択肢なんです。
次に、パフォーマンスの優秀さも見逃せません。過去10年とか見てみると、どちらもS&P 500(アメリカの主要500社指数)を大きく上回るリターンを叩き出しています。たとえば、IT革命が加速したここ数年、両者は年率20%近い成長を見せた時期も。こんな成績を見せられたら、投資家が「お、こっちの方が儲かるかも?」と比べてみたくなるのも当然です。
そして、コストの違いも比較ポイント。ETFを選ぶとき、経費率って大事ですよね。QQQの経費率は0.20%、VGTは0.10%。長期で運用するなら、この0.10%の差がじわじわ効いてきます。たとえば、100万円を20年運用したとき、経費率の差だけで数万円の差が出ることも。コスト重視派は、ここでVGTに目が行くわけです。
さらに、投資スタイルの違いも比較を後押ししています。QQQはナスダック100だから、IT以外に消費財(アマゾンとか)や通信(グーグルとか)も入っていて、少し分散が効いている。一方、VGTはIT特化で、集中投資型。リスクを取ってITに全振りしたいか、少し安定感を求めるかで意見が分かれるんですよね。
市場での人気も大きい要素です。QQQは純資産総額がVGTの約4倍。流動性が高く、取引量も多いから、売り買いしやすい。対するVGTは規模こそ小さいけど、バンガードの低コスト哲学が支持されてファンが多い。この「メジャー感」と「コスパ感」の対決も、比較される理由の一つですね。
| 比較理由 | 詳細 |
|---|---|
| テクノロジー重視 | 両者ともIT中心で成長性が高い |
| パフォーマンス | S&P 500を上回るリターンで注目 |
| 経費率 | QQQ: 0.20%、VGT: 0.10%でコスト意識が働く |
| 分散性 | QQQは多セクター、VGTはIT特化 |
| 人気と流動性 | QQQはメジャー、VGTはコスパで人気 |
こんな感じで、QQQとVGTは似ているようでいて、微妙に違う。だからこそ、投資家が自分の目的に合うのはどっちかを見極めようと、比べたくなるんです。
QQQとVGTの特徴比較
QQQとVGT、どちらもテクノロジー系のETFだけど、具体的に何がどう違うのか。ここでは、両者の特徴をガッツリ比較して、表を使って視覚的に分かりやすく整理していきます。投資判断のヒントになれば嬉しいです。
まず、基本情報から。QQQはナスダック100に連動するETFで、運用はインベスコ。VGTはITセクターに特化したETFで、バンガードが手掛けています。設定年はQQQが1999年、VGTが2004年と、QQQの方が歴史が長いですね。純資産総額はQQQが約2,700億ドル、VGTが約700億ドルと、規模感もQQQがリード。
構成銘柄数は、QQQが100社、VGTが約320社。QQQは厳選されたトップ企業、VGTはIT業界を広くカバーするイメージです。経費率はQQQが0.20%、VGTが0.10%で、VGTの方が低コスト。配当利回りはどちらも低めで、QQQが約0.6%、VGTが約0.7%(2025年3月時点)。
セクター構成も大きな違い。QQQはテクノロジーが約60%、通信サービスや消費財が20-30%入る。一方、VGTは100%が情報技術。分散性を求めるならQQQ、ITに集中したいならVGTですね。
さて、ここで詳細な比較表をどうぞ。
| 項目 | QQQ | VGT |
|---|---|---|
| 正式名称 | Invesco QQQ Trust Series 1 | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares |
| 運用会社 | インベスコ | バンガード |
| 連動指数 | NASDAQ 100 | MSCI US IMI IT 25/50 |
| 設定年 | 1999年 | 2004年 |
| 純資産総額 | 約2,700億ドル | 約700億ドル |
| 構成銘柄数 | 100社 | 約320社 |
| 経費率 | 0.20% | 0.10% |
| 配当利回り | 約0.6% | 約0.7% |
| 主要セクター | テクノロジー(約60%)、通信、消費財 | 情報技術(100%) |
| 取引量(流動性) | 非常に高い | 高い |
この表を見ると、QQQは規模と流動性で勝り、VGTはコストとIT特化で優位性があるのが分かります。たとえば、経費率0.10%の差は、100万円投資で年間1,000円の違い。10年だと1万円以上になるから、長く持つなら地味に響きますね。
リスク面でも違いが。QQQはセクターが分散している分、ITが不調でも他のセクターで多少カバーできる可能性がある。VGTはIT一本勝負だから、ITがコケると直撃。でも、ITが絶好調ならVGTの方が伸びる可能性も高いです。
投資スタイルで見ると、QQQは「テクノロジー中心だけど安定感も欲しい」人向け。VGTは「ITの成長に全力で乗りたい」人向け。どちらも魅力的なんですが、自分のリスク許容度や目標に合う方を選ぶのが大事ですね。
QQQとVGTのパフォーマンス比較(株価推移・成長率)
投資先を選ぶとき、やっぱり気になるのは「どれだけ儲かるか」ですよね。QQQとVGT、どちらもテクノロジー系で優秀な成績を残していますが、実際のところどうなのか。株価推移と成長率を比較して、どちらが優勢か見てみましょう。
まず、過去10年の株価推移から。QQQは2015年の約100ドルから、2025年3月には約480ドルに。単純計算で約4.8倍。VGTは同じく2015年の約100ドルから約600ドルへ、約6倍です。初期の株価が近いので、VGTの方が成長率で上回っているのが分かります。
年平均成長率(CAGR)で見ると、2015-2025年の10年間で、QQQは約17%、VGTは約20%。この差は、VGTがITに特化している分、テクノロジーブームをフルに享受した結果と言えそうです。たとえば、AIや半導体の急成長がVGTの追い風に。QQQも負けてないけど、IT以外のセクターが少し足を引っ張った形ですね。
ここで、5年ごとの推移を表にしてみます。
| 期間 | QQQ株価 | VGT株価 | QQQ成長率 | VGT成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 約100ドル | 約100ドル | – | – |
| 2020年 | 約310ドル | 約350ドル | 210% | 250% |
| 2025年(3月) | 約480ドル | 約600ドル | 55%(20年比) | 71%(20年比) |
この表を見ると、VGTが一貫してQQQを上回っているのが分かります。特に2020年以降、ITの勢いが加速した時期に差が広がった感じ。コロナ禍でのデジタル化需要とか、半導体不足での注目度アップが影響したんでしょうね。
ただ、株価推移だけじゃなくボラティリティも大事。2022年のような金利上昇局面では、QQQが約33%下落、VGTが約35%下落。IT特化のVGTの方が少し下げ幅が大きかった。これは、分散性の違いが効いてくる場面です。逆に、2023年の回復局面ではVGTが約50%上昇、QQQが約45%と、VGTが反発力を見せました。
成長率の背景には、構成銘柄の影響も。QQQはGAFAM(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフト)が大きく、安定感がある。一方、VGTはエヌビディアやブロードコムといった半導体企業のパフォーマンスが効いてます。
QQQとVGTの年別・過去平均リターン比較
パフォーマンスを測るなら、年別のリターンを見るのが分かりやすいですよね。QQQとVGTがどれくらい儲けてきたのか、過去10年のデータを引っ張ってきて比較してみます。平均リターンも合わせてチェックして、長期的な実力を探ります。
さっそく、2015年から2024年までの年別リターンを表にまとめました(2025年は3月時点で未確定なので除外)。
| 年 | QQQリターン | VGTリターン |
|---|---|---|
| 2015 | 9.5% | 5.0% |
| 2016 | 7.0% | 14.8% |
| 2017 | 32.7% | 37.1% |
| 2018 | -0.1% | 2.5% |
| 2019 | 39.0% | 48.7% |
| 2020 | 48.6% | 46.0% |
| 2021 | 27.2% | 30.5% |
| 2022 | -32.6% | -35.9% |
| 2023 | 54.9% | 52.7% |
| 2024 | 18.5% | 20.2% |
この表から、VGTが6勝、QQQが4勝と、年別ではVGTがやや優勢。特に2019年の48.7%とか、2017年の37.1%とか、VGTの爆発力が目立ちますね。QQQも2020年の48.6%とか2023年の54.9%で負けてないけど、全体的にVGTの方が上振れが大きい印象。
過去10年の平均リターンを出すと、QQQが約20.5%、VGTが約22.2%。この差は、VGTのIT特化がテクノロジーブームにバッチリハマった結果でしょう。ただ、マイナス幅を見ると、2022年はVGTが-35.9%とQQQの-32.6%より厳しい。リスクも少し高いってことです。
面白いのは、好調時の差が大きいこと。2019年なんて、VGTがQQQを10%以上上回ってる。半導体やソフトウェア企業の躍進が効いたんでしょうね。逆に、不調時はQQQの分散性が少し助けになってる感じ。たとえば2018年、QQQはほぼトントンだけど、VGTはプラスを維持。
長期で見ると、どちらもS&P 500(平均10-12%程度)を大きく超える成績。テクノロジーの成長力って本当にすごいんだなって思います。
QQQとVGTの年別の騰落率比較
年別リターンを見たところで、今度は騰落率にフォーカスして、QQQとVGTの値動きの違いを掘り下げます。どれくらい上がって、どれくらい下がるのか、リスクとリターンのバランスが分かると投資判断もしやすくなりますよね。
さっきの年別リターンを基に、騰落率の特徴を整理してみます。プラスとマイナスの動きを強調した表をどうぞ。
| 年 | QQQ騰落率 | VGT騰落率 | 差(VGT-QQQ) |
|---|---|---|---|
| 2015 | +9.5% | +5.0% | -4.5% |
| 2016 | +7.0% | +14.8% | +7.8% |
| 2017 | +32.7% | +37.1% | +4.4% |
| 2018 | -0.1% | +2.5% | +2.6% |
| 2019 | +39.0% | +48.7% | +9.7% |
| 2020 | +48.6% | +46.0% | -2.6% |
| 2021 | +27.2% | +30.5% | +3.3% |
| 2022 | -32.6% | -35.9% | -3.3% |
| 2023 | +54.9% | +52.7% | -2.2% |
| 2024 | +18.5% | +20.2% | +1.7% |
この表で分かるのは、VGTの方が値動きが大きい傾向。プラスが大きい年(2019年とか)はQQQを大きく引き離すけど、マイナスが大きい年(2022年とか)も下落幅が目立つ。標準偏差で見ると、QQQが約18.5%、VGTが約19.5%と、VGTの方がボラティリティが高いです。
たとえば、2019年の+48.7%(VGT)と+39.0%(QQQ)の差は約10%。IT特化のVGTが半導体ブームに乗った結果ですね。一方、2022年の下げ幅はVGTが-35.9%、QQQが-32.6%。3%程度の差だけど、IT集中がリスクになった瞬間です。
回復力も注目ポイント。2022年の下落後、2023年にVGTが52.7%、QQQが54.9%と、QQQが若干上回ってる。IT以外のセクターが反発を支えた可能性があります。リスクを取れるならVGTの上振れ狙いもアリだし、安定感ならQQQがいいかも。
10年間の最大上昇率はQQQが54.9%(2023年)、VGTが48.7%(2019年)。最大下落率はQQQが-32.6%(2022年)、VGTが-35.9%(2022年)。リスクとリターンのトレードオフがはっきり見えますね。
QQQとVGTのセクター構成比較
QQQとVGTの違いを語るなら、セクター構成は外せません。どんな業界にお金を預けるのかで、リターンもリスクも変わってきます。ここでは、両者のセクター構成を詳しく比べてみます。
まず、QQQ。ナスダック100に連動するから、テクノロジーがメインだけど他も混ざってます。2025年3月時点の内訳はこんな感じ。
- 情報技術:約60%
- 通信サービス:約15%
- 一般消費財:約10%
- ヘルスケア:約7%
- その他:約8%
テクノロジーが6割を占めるけど、アマゾン(消費財)やグーグル(通信)が入ることで分散が効いてます。一方、VGTはシンプル。
- 情報技術:100%
ITオンリーで、他のセクターは一切なし。ソフトウェア、半導体、ITサービスなど、IT業界を網羅しています。
これを表で比べると分かりやすいです。
| セクター | QQQ割合 | VGT割合 |
|---|---|---|
| 情報技術 | 60% | 100% |
| 通信サービス | 15% | 0% |
| 一般消費財 | 10% | 0% |
| ヘルスケア | 7% | 0% |
| その他 | 8% | 0% |
QQQは多様性がある分、ITが不調でも他のセクターでカバーできる可能性が。たとえば、2022年のIT不振時、消費財やヘルスケアが多少支えました。対してVGTはITの好不調に全てがかかってる。ITが絶好調なら爆発的なリターンだけど、不調だと逃げ場がない。
具体例を挙げると、QQQにはアマゾン(消費財)やテスラ(消費財)が含まれるけど、VGTにはなし。VGTにはビザやマスターカード(IT扱い)が入るけど、QQQには入らない。この違いが、パフォーマンスにも影響してきます。
リスク分散を考えるならQQQ、ITの成長に一点集中ならVGT。
QQQとVGTの構成銘柄比較
セクター構成が分かったところで、今度は具体的な銘柄を見ていきます。QQQとVGTがどんな企業で成り立っているのか、上位銘柄を比較してみましょう。
まず、QQQの上位10銘柄(2025年3月時点)。
| 順位 | 企業名 | セクター | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | アップル | 情報技術 | 9.5% |
| 2 | マイクロソフト | 情報技術 | 8.8% |
| 3 | アマゾン | 一般消費財 | 6.2% |
| 4 | エヌビディア | 情報技術 | 5.8% |
| 5 | メタ | 通信サービス | 4.9% |
| 6 | アルファベット(A) | 通信サービス | 4.5% |
| 7 | テスラ | 一般消費財 | 3.8% |
| 8 | ブロードコム | 情報技術 | 3.5% |
| 9 | アルファベット(C) | 通信サービス | 3.2% |
| 10 | コストコ | 一般消費財 | 2.8% |
合計で約53%を占めます。GAFAMがしっかり入っていて、テスラやコストコで消費財もカバー。
次に、VGTの上位10銘柄。
| 順位 | 企業名 | セクター | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | アップル | 情報技術 | 18.0% |
| 2 | マイクロソフト | 情報技術 | 16.5% |
| 3 | エヌビディア | 情報技術 | 10.2% |
| 4 | ブロードコム | 情報技術 | 4.8% |
| 5 | アドビ | 情報技術 | 2.5% |
| 6 | セールスフォース | 情報技術 | 2.3% |
| 7 | シスコ | 情報技術 | 2.0% |
| 8 | オラクル | 情報技術 | 1.8% |
| 9 | アクセンチュア | 情報技術 | 1.7% |
| 10 | クアルコム | 情報技術 | 1.6% |
合計で約61%。ITオンリーで、アップルとマイクロソフトの比率がQQQより高いですね。
大きな違いは、QQQにアマゾンやメタ、テスラが入るけど、VGTにはない点。逆にVGTにはアドビやオラクルが上位にくる。集中度で見ると、VGTの方が上位10社で61%と、やや偏りが強いです。
QQQとVGTに投資した場合の成長率シミュレーション比較
実際にお金を入れたらどうなるのか、気になる人も多いはず。ここでは、QQQとVGTに投資した場合の成長率をシミュレーションしてみます。過去10年のデータを使って、具体的な数字で比べてみましょう。
仮に2015年に100万円を投資したとします。年平均成長率はQQQが17%、VGTが20%(2015-2025年)。単利で計算すると、毎年どれくらい増えるか見てみます。
| 年 | QQQ資産額 | VGT資産額 |
|---|---|---|
| 2015 | 100万円 | 100万円 |
| 2016 | 117万円 | 120万円 |
| 2017 | 134万円 | 140万円 |
| 2018 | 151万円 | 160万円 |
| 2019 | 168万円 | 180万円 |
| 2020 | 185万円 | 200万円 |
| 2021 | 202万円 | 220万円 |
| 2022 | 219万円 | 240万円 |
| 2023 | 236万円 | 260万円 |
| 2024 | 253万円 | 280万円 |
| 2025 | 270万円 | 300万円 |
10年でQQQは270万円、VGTは300万円。差は30万円で、VGTの方が成長率が高い分、資産が増えます。でも、複利で計算するとさらに差が開く。複利だと、QQQが約470万円、VGTが約620万円。150万円の差は大きいですね。
もちろん、過去の実績が未来を保証するわけじゃない。金利上昇とかIT不況が来たら、両方下がるリスクもある。ただ、これまでの傾向だと、VGTのIT集中がリターンを押し上げてます。
QQQとVGTに投資した場合の配当金シミュレーション比較
成長率も大事だけど、配当金も気になるポイント。QQQとVGTはどちらも配当利回りが低いけど、長期でどうなるかシミュレーションしてみます。
2025年3月時点で、QQQの配当利回りは0.6%、VGTは0.7%。100万円投資した場合、年間配当はQQQが6,000円、VGTが7,000円。10年分の累積を見てみます(再投資なし)。
| 年 | QQQ配当 | VGT配当 |
|---|---|---|
| 2015 | 6,000円 | 7,000円 |
| 2016 | 6,000円 | 7,000円 |
| 2017 | 6,000円 | 7,000円 |
| 2018 | 6,000円 | 7,000円 |
| 2019 | 6,000円 | 7,000円 |
| 2020 | 6,000円 | 7,000円 |
| 2021 | 6,000円 | 7,000円 |
| 2022 | 6,000円 | 7,000円 |
| 2023 | 6,000円 | 7,000円 |
| 2024 | 6,000円 | 7,000円 |
| 合計 | 60,000円 | 70,000円 |
10年でQQQが6万円、VGTが7万円。1万円の差ですね。でも、資産が増えると配当も増える。さっきの成長率シミュレーション(単利)を基に、毎年資産に応じた配当を計算すると。
| 年 | QQQ資産 | QQQ配当 | VGT資産 | VGT配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 100万円 | 6,000円 | 100万円 | 7,000円 |
| 2020 | 185万円 | 11,100円 | 200万円 | 14,000円 |
| 2025 | 270万円 | 16,200円 | 300万円 | 21,000円 |
10年合計だと、QQQが約11.5万円、VGTが約14万円。成長率が高いVGTの方が配当も上回ります。
QQQとVGTどちらがおすすめ?(観点別)
結局、QQQとVGTどっちに投資すべきか。観点別にメリットを整理して、自分に合う方を見極めましょう。
1. 成長率重視
- おすすめ:VGT
- 理由:過去10年で年平均20%と、QQQの17%を上回る。IT特化で上振れが大きい。
2. リスク分散重視
- おすすめ:QQQ
- 理由:IT以外に通信や消費財が入り、下落時のダメージがVGTより小さい。
3. コスト重視
- おすすめ:VGT
- 理由:経費率0.10%でQQQの0.20%より安い。長期ならコスト差が効く。
4. 流動性重視
- おすすめ:QQQ
- 理由:純資産総額がVGTの4倍、取引量も多く、売買しやすい。
5. 配当重視
- おすすめ:VGT
- 理由:利回り0.7%でQQQの0.6%を上回る。ただ、どちらも配当は少なめ。
表でまとめます。
| 観点 | QQQ | VGT |
|---|---|---|
| 成長率 | ◯ | ◎ |
| リスク分散 | ◎ | △ |
| コスト | △ | ◎ |
| 流動性 | ◎ | ◯ |
| 配当 | △ | ◯ |
リスクを取れるならVGT、安定感ならQQQ。投資期間や資金量でも変わりますね。
まとめ
QQQとVGT、どちらもテクノロジー系のスターETF。それぞれの特徴、パフォーマンス、構成を比べてきました。QQQは分散性と流動性で安定感、VGTは成長率と低コストで攻めの姿勢が光ります。過去10年ではVGTがリードだけど、リスクも少し高め。自分の目標やリスク許容度に合わせて選ぶのが一番ですね。どちらも未来の成長に期待できる選択肢、迷ったら両方少しずつ持つのもありかも!
他の人気ETF比較の記事はこちら
【米国高配当ETF比較】VYM・SCHD・HDV・SPYD、どれがおすすめか?リターンやリスクを徹底比較
この記事の3ポイント要約 資産総額を伸ばすなら期待リターン12.86%のVYMを、日々の現金を優先するなら利回り5.04%のSPYDを選ぶのが良い SCHDは4%超の利回りと二桁近い増配率により、20…
【比較】S&P500(VOO)とVYMはどっちおすすめ?リターンをとるならS&P500、安定をとるならVYM
この記事の3ポイント要約 S&P500(VOO)は米国市場全体の成長を、VYMは高配当・バリュー株の安定性を買うことができる投資先である。成長性(ROEや利益率)ではS&P500が勝る…
【比較】FANG+ vs オルカン、どっちがおすすめか?リスクやリターンを比較してみたが、両方に投資するのもあり
この記事の3ポイント要約 FANG+は3年平均年率62.51%という圧倒的リターンを誇る。オルカンは信託報酬0.05%という圧倒的低コストで、世界全体の経済成長に投資することができる。 FANG+は2…
【比較】FANG+とSOXはともに集中型の指数。リターンを取るならFANG+のほうがおすすめ
この記事の3ポイント要約 直近3年の長期リターンではFANG+が年率60%超と圧倒しているが、1年以内の短期的な勢いとコストの低さではニッセイSOXに優位性がある FANG+は10銘柄、SOXは半導体…
【比較】QYLD vs JEPQ、ともに毎月配当金がでるETFだが仕組みが異なる。どっちがいいか比較してみた
この記事の3ポイント要約 トータルリターンではJEPQがQYLDを圧倒しており、長期資産形成にはJEPQの方がおすすめ どちらも税金効率は良くないため、再投資効率よりも今のキャッシュフローを重視する投…
【比較】S&P500とNASDAQ100、どっちがおすすめ?リスク・リターン・構成銘柄を徹底比較
この記事の3ポイント要約 長期シミュレーションでは、テクノロジー比率の高いNASDAQ100がS&P500を圧倒するリターンとなった S&P500は500社の広範な分散によりリスクが低…
【比較】FANG+とS&P500トップ10はどっちがおすすめ?リターン・コスト・将来性をデータで比較
この記事の3ポイント要約 FANG+はTracers S&P500トップ10より高いリターンが期待できるものの、信託報酬が高く、値動きの激しいハイリスク・ハイリターン Tracers S&am…
【比較】FANG+ vs NASDAQ100、どっちがおすすめか?シミュレーションでわかった本当のリターン差
この記事のポイント 過去のデータに基づくと、極度な集中投資であるFANG+は、分散型のNASDAQ100よりも高いリターンを生み出す傾向にあるが、そのボラティリティも極めて大きい FANG+は均等加重…
【比較】FANG+ vs M7、どっちに投資するべきか?徹底シミュレーション
この記事のポイント M7トラストは7銘柄集中、FANG+は10銘柄集中であり、M7トラストの方が銘柄数が少ない分、リターン期待値もリスクも高くなる傾向がある 50年シミュレーションでは、M7トラスト単…
【比較】FANG+ vs Zテック20、どっちがおすすめ?メリット・デメリットを徹底解説
この記事のポイント FANG+は米国10銘柄に超集中、Zテック20は世界の優良テクノロジー企業(約20銘柄)に分散投資する戦略である 50年シミュレーションでは、米国集中型のFANG+が最高リターンを…
【比較】FANG+とUSテック・トップ20【2244】 | 勝つのはどっち?徹底シミュレーションとターン最大化の黄金比率を調査
この記事のポイント FANG+は10銘柄に集中投資するため、リターン期待値は高いが、リスクも高水準 USテック・トップ20は20銘柄に分散投資し、信託報酬も低いため、バランスの取れた設計 長期シミュレ…
【比較】FANG+ vs JEPQ、どっちがおすすめ?配当と成長を両立する黄金比率を解説
この記事のポイント FANG+は年率20%、JEPQは年率8%と想定したシミュレーションでは、50年後で91億対4,600万円と、成長戦略(FANG+)が圧倒的な差をつける FANG+は少数のハイパー…
【比較】FANG+ vs VTI、どっちがおすすめ?リターンやリスク、構成銘柄を比較
この記事のポイント FANG+はハイテク集中投資による高い成長ポテンシャルを持つが、VTIは米国市場全体への分散投資による安定性がある FANG+とVTIの「合わせ持ち戦略」は、VTIの安定性とFAN…
【比較】FANG+ vsメガ10、どっちがおすすめ?構成銘柄や平均リターンを比較してみた
この記事の3ポイント要約 シミュレーションではFANG+のほうがややリターンが大きくなったが、FANG+・メガ10はともに設定されてから10年もたっていないため、今後どうなるかは未知数 経費率はメガ1…
VTIとSHVの「ベスト比率」は?成長と安全を両立するポートフォリオを徹底解説
この記事のポイント VTIは市場全体の成長を享受し長期的な資産最大化を目指す「攻め」のコア資産、SHVは低リスク・安定収入を提供する「守り」の安全資産である。長期リターンではVTIが圧倒的に優位だが、…
VTI vs GLDM(金)徹底比較!資産を最大化しつつ危機をヘッジする「最強の組み合わせ戦略」
この記事のポイント VTIは米国企業の成長力を背景に、長期的なトータルリターン(資産の最大化)でGLDMを大きく上回る傾向にある。GLDM(金)は基本的に配当を生まずインカムゲインはゼロだが、インフレ…
VTIとVYMは結局どっち?リターン・配当・50年シミュレーションで徹底比較
この記事のポイント VTIは長期的なトータルリターン(リターンと成長)でVYMを上回る傾向があり、資産の最大化を目指す若年層・長期投資家向き。VYMはVTIの約2倍の配当利回り(インカムゲイン)を提供…
【比較】VTIとSPYD、過去20年のリターンを徹底分析!配当金生活への最適な組み合わせは?
この記事のポイント VTIは米国市場全体(約4,000銘柄)に投資する「成長重視」のETFであり、長期的には複利の効果で最も高いトータルリターン(想定年平均10.5%)が期待できる。一方、SPYDはS…
VTIとVGT、投資するならどっち?リターン・配当・構成銘柄を詳細比較【最適な組み合わせ戦略も解説】
この記事のポイント VTIは米国全市場に分散投資し、安定性と中程度のリターン、比較的高い配当利回りが特徴の「コア」資産である。VGTは情報技術セクターに集中投資し、高い成長率を期待できるが、ボラティリ…
【成長vs高配当】VTIとJEPQを徹底比較!リターン・配当・成長率で長期投資に最適なのはどっち?
この記事のポイント VTIは米国市場全体に分散投資し、低コストで長期的な資産最大化(キャピタルゲイン)を目指す「成長のコア」である。一方、JEPQはナスダック100を対象としたカバードコール戦略で、毎…
【比較】FANG+ vs BTC|どちらに投資するのがいいのか?
この記事のポイント 100万円を投資した場合、1年ではFANG+が28%増で優位ですが、5年を超えるとBTCが急成長。10年でBTCは45倍、FANG+は12.5倍に達します FANG+は10社のテッ…
【比較】SCHD vs QQQ|違いを理解して投資しよう
この記事のポイント 過去1年で100万円がQQQなら1,237万円、SCHDは995万円。QQQの23.7%急伸が効くが、SCHDは安定感で安心 20年でQQQが1,650万円、SCHDは806万円。…
【比較】SCHD vs VTI。ミックス戦略がおすすめ
この記事のポイント 過去5年でVTIが2倍超に対しSCHD1.57倍だが、20年シミュでSCHD8,860万円 vs VTI7,220万円、配当再投資の長期効果が顕著に現れる VTIはテック31%で成…
【比較】SCHD vs FANG+|どっちも保有するのがおすすめ
この記事のポイント 過去1〜20年リターン比較で、短期(5年以内)はFANG+が3倍以上上回るが、15年超の長期ではSCHDの安定複利が差を縮める SCHDは低コスト0.06%・高配当3.8%・100…
【比較】NASDAQ100ゴールドプラス vs FANG+|組み合わせて保有するのがおすすめ
この記事のポイント 50年シミュレーションでは、両者を半々で保有する戦略が最も滑らかに資産を増やした結果となり、「片方に賭けるよりも、異なる性質を組み合わせる」ことで最大効率の複利成長が得られた 配当…

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。