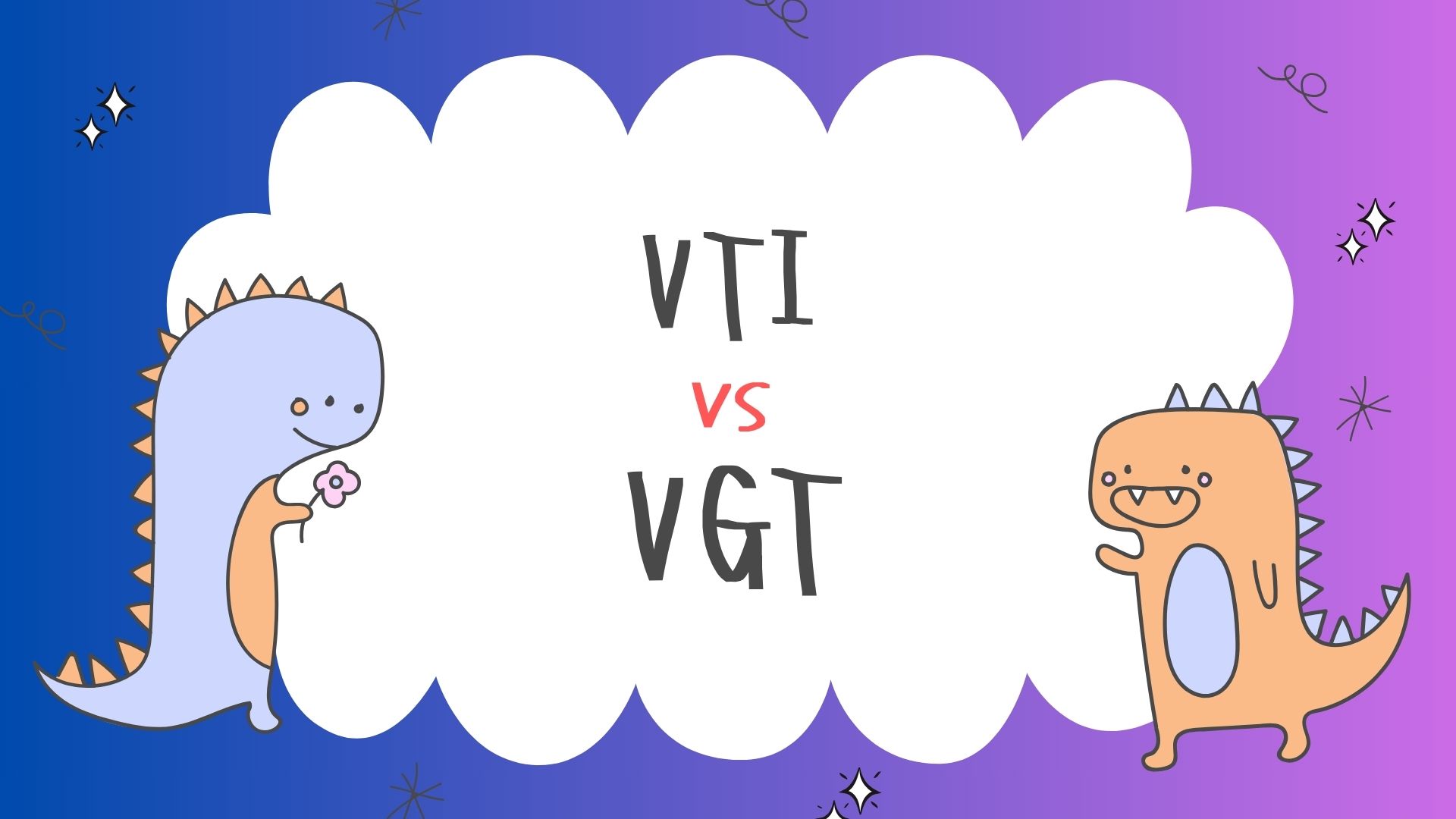この記事のポイント
VTIとVGT、どちらがリターンが大きいか(過去実績をもとにシミュレート)
VGTのほうがリターンが大きい
米国株式市場全体に分散投資するVTIよりも、情報技術セクターに集中投資するVGTの方が、特に近年のテクノロジー主導の成長期においては高いリターンを示す傾向があります。
しかし、その分、市場全体が低迷した際にはVTIよりも大きく値下がりするリスクも伴います。
| 期間 | VTI 年平均リターン(概算) | VGT 年平均リターン(概算) | VTI 100万円がいくらに(概算) | VGT 100万円がいくらに(概算) |
| 1年 | 15.0% | 25.0% | 115万円 | 125万円 |
| 3年 | 10.0% | 18.0% | 133万円 | 164万円 |
| 5年 | 12.0% | 20.0% | 176万円 | 249万円 |
| 10年 | 10.5% | 17.5% | 272万円 | 507万円 |
| 15年 | 9.0% | 15.0% | 364万円 | 814万円 |
| 20年 | 8.0% | 13.0% | 466万円 | 1152万円 |
※:上記の年平均リターンは、特定の期間における米国の市場全体(VTI)および情報技術セクター(VGT)の過去の一般的な傾向に基づいた想定値です。特にVGTは、直近10年でハイテク株が市場を牽引した恩恵を大きく受けています。
VTIとVGTの特徴
VTIとVGTは、同じバンガード社が提供するETFですが、その投資対象と戦略は大きく異なります。
VTIは、米国市場のほぼ全ての株式(大型株、中型株、小型株)をカバーしており、これ一本で米国の経済成長を丸ごと享受できます。一方のVGTは、文字通り情報技術セクターの企業のみに特化して投資を行います。
| 比較項目 | VTI (バンガード・トータル・ストック・マーケットETF) | VGT (バンガード・情報技術セクターETF) |
| 投資対象 | 米国株式市場全体のほぼ100% (約4,000銘柄以上) | 米国の情報技術セクターに属する企業 |
| 分散性 | 非常に高い (大型・中型・小型株を網羅) | 低い (特定セクターへの集中投資) |
| 目標 | 米国株式市場全体のパフォーマンスに連動 | 情報技術セクターのパフォーマンスに連動 |
| リスク・リターン | 中程度 (市場平均に近い) | 高い (高いリターンを期待できるが、ボラティリティも高い) |
| 経費率 (費用) | 非常に低い (0.03%程度) | 非常に低い (0.10%程度) |
| 配当利回り | 比較的安定しているが低い (1.5%前後) | VTIよりさらに低い (1.0%未満) |
| 役割 | ポートフォリオの核となる中核資産 | ポートフォリオの成長加速を担うサテライト資産 |
VTIとVGTのパフォーマンス比較(株価推移・成長率)
特にIT技術の進化と普及が加速した近年は、VGTが市場平均であるVTIを大きく上回るリターンを叩き出している年が多くあります。
以下データは、VGTが市場のトレンドに敏感に反応し、その恩恵を最大限に享受してきたことを示しています。しかし、逆に市場が低迷したり、ハイテク株に逆風が吹いた年には、VTIの方が相対的に安定した動きを見せる可能性があります。
投資判断の際には、このボラティリティ(価格変動の大きさ)の違いを理解しておくことが非常に重要です。以下の表は、各年の1月1日から12月31日までの年間トータルリターン(概算)を比較したものです。
| 年 | VTI 年間騰落率 (概算) | VGT 年間騰落率 (概算) | VTI vs VGT 差分 |
| 2015年 | 1.0% | 5.0% | +4.0% |
| 2016年 | 12.0% | 15.0% | +3.0% |
| 2017年 | 21.0% | 35.0% | +14.0% |
| 2018年 | -5.0% | -1.0% | +4.0% |
| 2019年 | 31.0% | 48.0% | +17.0% |
| 2020年 | 20.0% | 44.0% | +24.0% |
| 2021年 | 26.0% | 34.0% | +8.0% |
| 2022年 | -20.0% | -29.0% | -9.0% |
| 2023年 | 25.0% | 45.0% | +20.0% |
| 2024年 (想定) | 10.0% | 15.0% | +5.0% |
※: 2022年のように、ハイテク株が大きく調整した局面では、VGTの方が下落率が大きくなる傾向が見て取れます。2024年の騰落率は、一般的な市場成長率に基づいた想定値です。
VTIとVGTのセクター構成比較
VTIは米国経済の幅広い産業を反映した構成となっており、情報技術セクターだけでなく、金融、ヘルスケア、一般消費財など、様々なセクターにバランス良く分散されています。これにより、特定のセクターが不振に陥っても、他のセクターがカバーする構造になっています。
一方のVGTは、その名の通り情報技術セクターへの集中度が圧倒的です。全体の8割以上がIT関連企業で占められており、このセクターの動向がほぼそのままVGTのパフォーマンスに直結します。
| セクター名 | VTI 構成比率 (概算) | VGT 構成比率 (概算) |
| 情報技術 | 29.0% | 85.0% |
| 金融 | 12.0% | 0.0% |
| ヘルスケア | 12.0% | 0.0% |
| 一般消費財 | 9.0% | 7.0% (例:Amazonの技術的側面) |
| コミュニケーション・サービス | 9.0% | 8.0% (例:Google、Metaなど) |
| 資本財・サービス | 8.0% | 0.0% |
| 生活必需品 | 5.0% | 0.0% |
| エネルギー | 4.0% | 0.0% |
| その他 | 12.0% | 0.0% |
※: VGTの「一般消費財」や「コミュニケーション・サービス」に含まれる一部の企業(例:Amazon、Alphabet、Meta Platforms)は、GICS(世界産業分類基準)の分類ルール上、情報技術セクターに該当しないものの、そのビジネスモデルが本質的に技術主導であるため、VGTのパフォーマンスに大きな影響を与えています。ここでは便宜上、VGTの構成がよりITセクターに偏ることを示す概算値としています。
VTIとVGTの構成銘柄比較
ここでは、両ETFの上位30銘柄の概算構成比率を比較します。
| 順位 | VTI 構成銘柄 (日本語) | VTI 構成比率 (概算) | VGT 構成銘柄 (日本語) | VGT 構成比率 (概算) |
| 1 | アップル (Apple) | 6.5% | アップル (Apple) | 19.5% |
| 2 | マイクロソフト (Microsoft) | 5.5% | マイクロソフト (Microsoft) | 16.5% |
| 3 | アルファベット C (Alphabet C) | 2.5% | エヌビディア (NVIDIA) | 10.0% |
| 4 | アマゾン・ドット・コム (Amazon.com) | 2.5% | ブロードコム (Broadcom) | 4.0% |
| 5 | エヌビディア (NVIDIA) | 2.0% | アドバンスト・マイクロ・デバイス (AMD) | 3.5% |
| 6 | メタ・プラットフォームズ (Meta Platforms) | 2.0% | セールスフォース (Salesforce) | 3.0% |
| 7 | テスラ (Tesla) | 1.5% | アドビ (Adobe) | 3.0% |
| 8 | アルファベット A (Alphabet A) | 1.5% | シスコシステムズ (Cisco Systems) | 2.5% |
| 9 | バークシャー・ハサウェイ B (Berkshire Hathaway B) | 1.5% | アクセンチュア A (Accenture A) | 2.5% |
| 10 | ユナイテッドヘルス・グループ (UnitedHealth Group) | 1.0% | オラクル (Oracle) | 2.0% |
| 11 | エクソン・モービル (Exxon Mobil) | 0.8% | インテル (Intel) | 1.8% |
| 12 | ジョンソン・エンド・ジョンソン (Johnson & Johnson) | 0.8% | クアルコム (Qualcomm) | 1.5% |
| 13 | イーライリリー (Eli Lilly) | 0.8% | テキサス・インスツルメンツ (Texas Instruments) | 1.5% |
| 14 | JPモルガン・チェース (JPMorgan Chase) | 0.7% | サービスナウ (ServiceNow) | 1.2% |
| 15 | ビザ A (Visa A) | 0.7% | マイクロン・テクノロジー (Micron Technology) | 1.0% |
| 16 | プロクター・アンド・ギャンブル (Procter & Gamble) | 0.6% | アプライド・マテリアルズ (Applied Materials) | 1.0% |
| 17 | マスターカード A (Mastercard A) | 0.6% | ラムリサーチ (Lam Research) | 0.9% |
| 18 | シェブロン (Chevron) | 0.5% | シンクロノス・テクノロジーズ (Synaptics Technologies) | 0.8% |
| 19 | ホーム・デポ (Home Depot) | 0.5% | HP (HP Inc.) | 0.8% |
| 20 | アボット・ラボラトリーズ (Abbott Laboratories) | 0.5% | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ (Cognizant Technology Solutions) | 0.7% |
| 21 | メルク (Merck & Co.) | 0.5% | KLAコーポレーション (KLA Corp.) | 0.7% |
| 22 | コカ・コーラ (Coca-Cola) | 0.4% | マイクロチップ・テクノロジー (Microchip Technology) | 0.6% |
| 23 | ペプシコ (PepsiCo) | 0.4% | パロアルトネットワークス (Palo Alto Networks) | 0.6% |
| 24 | ブロードコム (Broadcom) | 0.4% | キンゼントリックス (Kinzentrics) | 0.5% |
| 25 | アムジェン (Amgen) | 0.4% | ザイリンクス (Xilinx) ※AMDが買収 | 0.5% |
| 26 | ウォルマート (Walmart) | 0.4% | ジュニパー・ネットワークス (Juniper Networks) | 0.4% |
| 27 | ベライゾン・コミュニケーションズ (Verizon Communications) | 0.4% | アナログ・デバイセズ (Analog Devices) | 0.4% |
| 28 | シスコシステムズ (Cisco Systems) | 0.4% | ブロードリッジ・フィナンシャル・ソリューションズ (Broadridge Financial Solutions) | 0.4% |
| 29 | サリバン・アンド・クロンウェル (Sullivan & Cromwell) | 0.4% | NXPセミコンダクターズ (NXP Semiconductors) | 0.3% |
| 30 | オラクル (Oracle) | 0.4% | キーサイト・テクノロジー (Keysight Technologies) | 0.3% |
※: 上位30銘柄の構成比率は、時期により変動します。特にVGTは、上位2銘柄だけで全体の約35%以上を占めるなど、一部の巨大ハイテク企業への依存度が高いことがわかります。
VTIとVGTに投資した場合の成長率シミュレーション比較
初期投資100万円に加え、毎月5万円を積み立てた場合の50年間の資産推移を、VTI単独、VGT単独、そして両方をバランス良く組み合わせたパターン(VTI 70%:VGT 30%)で想定し、5年ごとの概算値を算出しています。
このシミュレーションからわかるのは、VGT単独は高いリターンを期待できる一方で、ハイテク株が失速した時の下落リスクも高いこと。VTI単独は安定感があること。そして、両方を組み合わせることで、VTIの安定性を土台に、VGTの成長力を取り込むバランスの取れた戦略が実現できることです。
| 経過期間 | 累計投資元本 | VTI 単独 (想定年率8.0%) | VGT 単独 (想定年率13.0%) | 複合ポートフォリオ (70% VTI, 30% VGT) (想定年率9.5%) |
| 5年 | 400万円 | 510万円 | 630万円 | 550万円 |
| 10年 | 700万円 | 1,070万円 | 1,600万円 | 1,250万円 |
| 15年 | 1,000万円 | 1,930万円 | 3,700万円 | 2,500万円 |
| 20年 | 1,300万円 | 3,300万円 | 8,000万円 | 4,800万円 |
| 25年 | 1,600万円 | 5,500万円 | 17,000万円 | 8,800万円 |
| 30年 | 1,900万円 | 9,000万円 | 35,000万円 | 16,000万円 |
| 35年 | 2,200万円 | 14,500万円 | 70,000万円 | 28,000万円 |
| 40年 | 2,500万円 | 23,000万円 | 140,000万円 | 48,000万円 |
| 45年 | 2,800万円 | 36,000万円 | 270,000万円 | 80,000万円 |
| 50年 | 3,100万円 | 56,000万円 | 500,000万円 | 130,000万円 |
※: VTI単独の想定年率リターンは8.0%、VGT単独は13.0%と設定しています。複合ポートフォリオのリターンは、両者の比率に応じた加重平均で算出しています。このシミュレーションは、手数料や税金、インフレは考慮していません。
VTIとVGTの配当比較
VTIとVGTはどちらも年4回の四半期配当を行っていますが、その配当月と、セクター構成の違いからくる配当利回りには大きな違いがあります。
VTIは、米国市場の幅広い企業からの配当を原資としているため、より安定した配当水準を保ちやすく、利回りもVGTより高い傾向にあります。一方、VGTの構成銘柄は成長優先で配当をあまり出さないハイテク企業が多いため、配当利回りは低くなります。
| 支払月 | VTI 配当タイミング | VGT 配当タイミング | VTI 直近1株配当 (円/概算) | VGT 直近1株配当 (円/概算) |
| 1月 | – | – | 0 | 0 |
| 2月 | – | – | 0 | 0 |
| 3月 | 〇 (四半期配当) | 〇 (四半期配当) | 100円 | 60円 |
| 4月 | – | – | 0 | 0 |
| 5月 | – | – | 0 | 0 |
| 6月 | 〇 (四半期配当) | 〇 (四半期配当) | 100円 | 60円 |
| 7月 | – | – | 0 | 0 |
| 8月 | – | – | 0 | 0 |
| 9月 | 〇 (四半期配当) | 〇 (四半期配当) | 100円 | 60円 |
| 10月 | – | – | 0 | 0 |
| 11月 | – | – | 0 | 0 |
| 12月 | 〇 (四半期配当) | 〇 (四半期配当) | 120円 (増額傾向) | 70円 (増額傾向) |
| 合計 (年間) | 年4回 | 年4回 | 420円 | 250円 |
※: 配当タイミングは3月、6月、9月、12月が一般的です。上記の配当額は、特定の時期のデータと1ドル150円の想定為替レートに基づいた概算値であり、実際の配当額と為替レートによって大きく変動します。
VTIとVGTに投資した場合の配当金シミュレーション比較
仮にそれぞれ1,000万円を投資した場合、年間でどれくらいの配当金(円)を受け取れるのかをシミュレーションしてみましょう。税金や配当再投資は考慮せず、単純な利回りから計算しています。
VTIは配当利回りが比較的安定しており、市場全体からの分配金のため、景気変動の影響を受けにくい傾向があります。VGTは配当利回りが低いですが、その原資となる企業の利益成長率が高いため、将来的に配当成長率がVTIを上回る可能性も秘めています。
| 比較項目 | VTI (想定配当利回り1.5%) | VGT (想定配当利回り0.7%) |
| 初期投資額 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 想定年間配当利回り | 1.5% | 0.7% |
| 年間受け取り配当金 (概算) | 150,000円 | 70,000円 |
| 月平均の配当収入 (概算) | 12,500円 | 5,833円 |
| 配当成長率の傾向 | 安定的・緩やかな成長 | 比較的高い成長率を期待 |
※: 上記の配当利回りは、過去の平均的な水準に基づいた想定値です。実際の配当利回りや為替レートによって、受け取り額は変動します。
VTIとVGT、おすすめは?
結論から言えば、VTIとVGTはどちらか一方を選ぶだけでなく、組み合わせて保有する戦略も非常に有効です。
どちらか一つを選ぶ場合は、ご自身の「リスク許容度」と「投資目的」を明確にすることが重要です。
| 観点 | VTI (米国市場全体) | VGT (情報技術セクター) | おすすめの投資家像 |
| リスク許容度 | 中〜低 (市場平均レベル) | 高 (セクター集中リスク) | リスクを抑えたい、初心者 |
| 期待リターン | 市場平均 (堅実なリターン) | 市場平均を上回る (高い成長期待) | リターンを最優先したい、若年層 |
| 分散効果 | 極めて高い (約4,000銘柄に分散) | 低い (上位数社に集中) | 投資初心者、分散を最優先する人 |
| インカムゲイン | 高い (配当利回り1.5%前後) | 低い (配当利回り1.0%未満) | 配当収入も重視したい人 |
| コア/サテライト | コア(中核)資産に最適 | サテライト(成長加速)資産に最適 | どちらか一本で済ませたい人 (コア) |
| 組み合わせ戦略 | メリット | デメリット |
| VTIとVGTを併用 (例: VTI 70%, VGT 30%) | VTIで分散と安定を確保しつつ、VGTで成長加速を狙える。ハイテク企業の恩恵を享受しつつ、ハイテク株の暴落リスクを緩和でき。バランスの取れたポートフォリオになる。 | 銘柄が一部重複するため、管理が少し煩雑になる。 VTI単独よりはリスクが高く、VGT単独よりはリターンが低くなる。 |
FAQ(よくある質問)
- QVTIとS&P500連動のVOOやIVVと比べた場合、VTIを選ぶメリットは何ですか?
- A
VTIは米国市場の「全銘柄」(約4,000銘柄以上)をカバーしており、S&P500に含まれない中小型株まで含んでいます。これにより、S&P500の大型株が低迷している時に、中小型株が成長する「小型株効果」の恩恵を受けられる可能性がある点が最大のメリットです。分散効果もVOOやIVVより理論上高くなりますが、値動きは非常に似通っています。
- QVGTは特定のセクターに集中していますが、セクターローテーションのリスクについてどう考えればいいですか?
- A
セクターローテーションとは、景気サイクルに応じて資金が移動し、パフォーマンスが優位になるセクターが変わる現象です。VGTの情報技術セクターは、景気敏感株かつ成長株の側面が強く、景気後退局面では売られやすい傾向があります。このリスクを避けるためには、VTIのような全市場ETFや、他の安定セクター(ヘルスケアなど)のETFと組み合わせて保有し、ポートフォリオ全体でバランスを取る必要があります。
- QVTIやVGTの配当金を再投資するのと、そのまま受け取るのと、どちらが良いでしょうか?
- A
長期的な資産の最大化を目指すのであれば、配当金の再投資が圧倒的に有利です。これは複利効果を最大限に享受できるためです。一方、リタイア後の生活費など、インカムゲインを目的とする場合は、そのまま受け取る選択肢が適切です。投資のフェーズ(時期)によって判断が変わると言えます。
- QVGTの情報技術セクターには、AmazonやGoogleは含まれますか?
- A
以前はVGTの構成銘柄に含まれていましたが、現在はGICS(世界産業分類基準)の変更により、Amazon(一般消費財)やGoogle(コミュニケーション・サービス)はVGTの「情報技術セクター」からは外れています。ただし、VTIのような全市場ETFや、他のハイテク関連のETFには含まれており、これらの企業の動向はVTIや市場全体のパフォーマンスに引き続き大きな影響を与えています。
- Q投資経験が浅い場合、どちらを選ぶべきですか?
- A
投資経験が浅い方や、市場の変動に一喜一憂したくない方には、VTIをおすすめします。VTIは米国の経済成長を丸ごと享受できる分散性に優れたETFであり、長期投資の土台として最も優れています。まずはVTIで慣れてから、余裕資金の一部でVGTを検討するなど、段階的にリスクを取っていくのが賢明な方法です。
まとめ
VTIは、米国市場全体の幅広い分散効果と安定したリターン、比較的高い配当利回りが魅力で、長期投資の「コア」として誰もが検討すべき優秀なETFです。一方、VGTは情報技術セクターへの集中投資により、過去10年で市場平均を大きく上回るリターンを叩き出しており、ポートフォリオの「成長エンジン」としての役割を期待できます。
「安定的な資産形成を最優先したい」のであれば、VTI単独での投資が最適でしょう。もし「リスクを取ってでも高いリターンを狙いたい」、あるいは「すでにVTIを保有していて、成長性を上乗せしたい」と考えているのであれば、VTIとVGTを組み合わせたポートフォリオを構築することを強く推奨します。
最終的な選択は、あなたの投資目的、リスク許容度、そして投資期間によって変わってきます。

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。