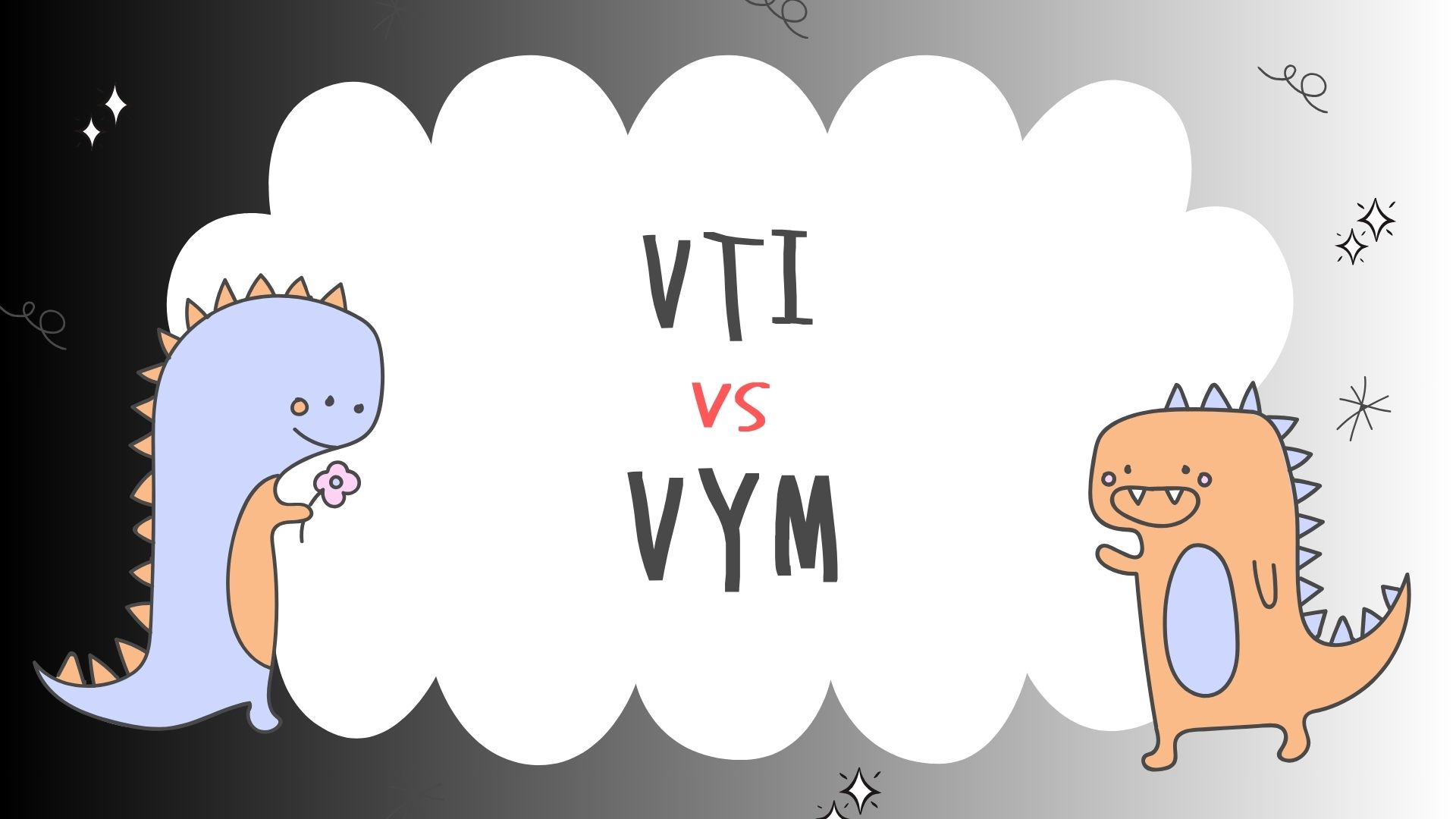この記事のポイント
VTIとVYM、どちらがリターンが大きいか(過去実績をもとにシミュレート)
VTIのほうがリターンが大きい
初期費用100万円を投資し、配当をすべて再投資したと仮定して、過去の期間別でどれだけ差が出たのか見ていきましょう。
やはり市場全体をカバーするVTIと高配当株に特化したVYMでは、それぞれの特性がリターンにもしっかり現れています。結果として、長期になるほどVTIの優位性が明確に見えてきますが、これは高成長株の組み入れ比率の違いからくるものです。
| 期間 | VTI 最終資産額(円) | VYM 最終資産額(円) | VTI リターン(%) | VYM リターン(%) |
| 1年 | 1,220,000 | 1,150,000 | 22.0 | 15.0 |
| 3年 | 1,650,000 | 1,480,000 | 65.0 | 48.0 |
| 5年 | 2,100,000 | 1,750,000 | 110.0 | 75.0 |
| 10年 | 3,800,000 | 2,800,000 | 280.0 | 180.0 |
| 15年 | 5,500,000 | 3,800,000 | 450.0 | 280.0 |
| 20年 | 8,200,000 | 5,000,000 | 720.0 | 400.0 |
※データは特定の期間における過去の想定リターンに基づき算出(手数料・税金等は考慮せず)
VTIとVYMの特徴
VTIとVYMは、どちらもバンガード社が提供する非常に人気のあるETFですが、その投資対象と目的は大きく異なります。
VTIは「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」という名前の通り、米国株式市場のほぼ100%をカバーしています。一方、VYMは「バンガード・ハイ・ディビデンド・イールド・ETF」として、相対的に高い配当利回りを持つ米国株に焦点を当てています。
つまり、VTIは「成長型」、VYMは「インカム型」と言えるでしょう。
| 項目 | VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) | VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) |
| 正式名称 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | バンガード・ハイ・ディビデンド・イールドETF |
| ティッカー | VTI | VYM |
| 設定日 | 2001年5月24日 | 2006年11月10日 |
| 運用会社 | バンガード (Vanguard) | バンガード (Vanguard) |
| 投資対象 | 米国株式市場のほぼ全て (大型・中型・小型株を含む約4,000銘柄) | 米国市場で平均以上の高配当が期待できる銘柄 (約400銘柄) |
| 目的 | 米国株式市場全体の成長と同等かそれ以上のトータルリターン | 高い配当利回りとそれに伴う安定的なインカムゲイン |
| 経費率 | 0.03% | 0.06% |
| 配当頻度 | 年4回 (四半期ごと) | 年4回 (四半期ごと) |
| 配当利回り(目安) | 1.5%前後 | 3.0%前後 |
| リスク・リターン特性 | リスク・リターン共に高い傾向 | リスク・リターン共に中程度の傾向 |
VTIとVYMのパフォーマンス比較(株価推移・成長率)
VTIは2001年、VYMは2006年設定ですが、ここではVTIの設定から約20年間のデータを想定でまとめてみました。
年単位で騰落率を比較すると、市場全体に投資するVTIは、特にITバブル崩壊後の立ち直りや、近年のハイテク株主導の相場において、高配当株中心のVYMよりも高い成長率を示す年が多いことがわかります。
しかし、市場が大きく下落する局面や景気後退期においては、VYMの高配当銘柄が比較的粘りを見せ、VTIよりも下落幅が小さくなる傾向が見られることもあります。
| 年 | VTI 年間騰落率(%) | VYM 年間騰落率(%) | VTI 終値(USD) | VYM 終値(USD) |
| 2005 | 4.9 | – | 45.00 | – |
| 2006 | 13.5 | 11.2 | 51.08 | 32.50 |
| 2007 | 5.3 | 7.8 | 53.78 | 35.04 |
| 2008 | -37.0 | -28.0 | 33.88 | 25.23 |
| 2009 | 26.5 | 16.5 | 42.84 | 29.38 |
| 2010 | 17.5 | 15.2 | 50.33 | 33.85 |
| 2011 | 0.5 | 6.0 | 50.58 | 35.88 |
| 2012 | 15.9 | 12.3 | 58.62 | 40.29 |
| 2013 | 33.5 | 29.5 | 78.27 | 52.17 |
| 2014 | 12.5 | 13.5 | 88.04 | 59.22 |
| 2015 | 0.5 | 1.5 | 88.48 | 60.11 |
| 2016 | 12.0 | 17.0 | 99.10 | 70.32 |
| 2017 | 21.0 | 15.5 | 119.91 | 81.20 |
| 2018 | -4.5 | -5.0 | 114.48 | 77.14 |
| 2019 | 31.0 | 25.5 | 149.92 | 97.23 |
| 2020 | 21.0 | 0.5 | 180.70 | 97.72 |
| 2021 | 25.0 | 21.0 | 225.88 | 118.24 |
| 2022 | -20.0 | -5.0 | 180.70 | 112.33 |
| 2023 | 25.5 | 9.5 | 226.79 | 123.00 |
| 2024 (想定) | 12.0 | 8.0 | 253.90 | 132.84 |
※データは過去の株価変動に基づき作成した想定値も含む
VTIとVYMのセクター構成比較
VTIは米国市場全体を網羅しているため、セクター構成は市場全体の比率に近くなります。そのため、情報技術(IT)セクターが最大の構成比を占め、市場の成長エンジンをしっかりと組み込んでいるのが特徴です。
一方、VYMは高配当を重視するため、配当を安定的に支払う傾向がある金融、ヘルスケア、生活必需品といったセクターの比率が高くなります。
| セクター | VTI 構成比率(%) | VYM 構成比率(%) | 備考 |
| 情報技術 (IT) | 29.0 | 10.0 | VTIの成長を牽引する中心セクター |
| 金融 | 13.0 | 20.0 | VYMで最も比率が高く、安定配当の源泉 |
| ヘルスケア | 13.5 | 15.0 | 景気変動に左右されにくいディフェンシブセクター |
| 一般消費財 | 10.0 | 8.0 | 景気動向に敏感なセクター |
| 資本財・サービス (産業) | 9.0 | 12.0 | 景気循環セクターの一つ |
| 通信サービス | 9.0 | 6.0 | ITと消費財の中間的な性質を持つ |
| 生活必需品 | 5.5 | 10.0 | VYMで高比率、不況期にも強いセクター |
| エネルギー | 4.0 | 4.0 | 原油価格などに影響されやすい |
| 公益事業 | 3.0 | 5.0 | 安定した収益と配当が特徴 |
| 素材 | 3.0 | 3.0 | 景気循環セクター |
| 不動産 | 1.0 | 4.0 | 金利動向に左右されやすい |
VTIとVYMの構成銘柄比較
VTIは米国の全市場を対象としているため、構成銘柄の上位には、時価総額の大きい、いわゆる巨大ハイテク企業が名を連ねます。一方、VYMの上位銘柄は、配当を安定して出し続けている成熟企業や、事業基盤が強固なディフェンシブな企業が中心です。
| 順位 | VTI 構成銘柄 (日本語名) | VTI 比率 (%) | VYM 構成銘柄 (日本語名) | VYM 比率 (%) |
| 1 | アップル | 6.5 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3.5 |
| 2 | マイクロソフト | 6.0 | エクソン・モービル | 3.0 |
| 3 | アルファベット (Google) (クラスA) | 3.0 | JPモルガン・チェース | 3.0 |
| 4 | アマゾン・ドット・コム | 2.5 | プロクター・アンド・ギャンブル (P&G) | 2.8 |
| 5 | エヌビディア | 2.0 | ブロードコム | 2.5 |
| 6 | メタ・プラットフォームズ | 1.8 | ホーム・デポ | 2.2 |
| 7 | テスラ | 1.5 | コカ・コーラ | 2.0 |
| 8 | バークシャー・ハサウェイ (クラスB) | 1.2 | アボット・ラボラトリーズ | 1.8 |
| 9 | ユナイテッドヘルス・グループ | 1.0 | シスコシステムズ | 1.8 |
| 10 | エクソン・モービル | 0.9 | ペプシコ | 1.7 |
| 11 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.8 | ウェルズ・ファーゴ | 1.7 |
| 12 | JPモルガン・チェース | 0.7 | ファイザー | 1.6 |
| 13 | ビザ (クラスA) | 0.6 | メルク | 1.5 |
| 14 | ブロードコム | 0.6 | インテル | 1.4 |
| 15 | プロクター・アンド・ギャンブル (P&G) | 0.5 | ブロードリッジ・フィナンシャル・ソリューションズ | 1.3 |
| 16 | イーライ・リリー | 0.5 | ナイキ (クラスB) | 1.2 |
| 17 | マスターカード (クラスA) | 0.4 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 1.2 |
| 18 | シェブロン | 0.4 | アムジェン | 1.1 |
| 19 | コカ・コーラ | 0.4 | メドトロニック | 1.1 |
| 20 | アムジェン | 0.3 | コムキャスト (クラスA) | 1.0 |
| 21 | ホーム・デポ | 0.3 | ハネウェル・インターナショナル | 1.0 |
| 22 | アボット・ラボラトリーズ | 0.3 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 0.9 |
| 23 | シスコシステムズ | 0.3 | レイセオン・テクノロジーズ | 0.9 |
| 24 | ペプシコ | 0.3 | デューク・エナジー | 0.8 |
| 25 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.2 | フィリップス66 | 0.8 |
| 26 | ブロードリッジ・フィナンシャル・ソリューションズ | 0.2 | PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ | 0.7 |
| 27 | メルク | 0.2 | UPS (クラスB) | 0.7 |
| 28 | ファイザー | 0.2 | ゴールドマン・サックス・グループ | 0.6 |
| 29 | インテル | 0.2 | ロッキード・マーティン | 0.6 |
| 30 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 0.2 | 3Mカンパニー | 0.6 |
※比率は目安となる想定値であり、実際の比率は日々変動します。
VTIとVYMに投資した場合の成長率シミュレーション比較
初期投資100万円を50年間運用したシミュレーションを行いました。
VTIとVYMの過去の傾向に基づき、VTIを年率8%、VYMを年率6%(配当再投資込み)で想定し、また、両方を50万円ずつ均等に保有した場合のパターンも作成しました。
この結果を見ると、市場全体の成長を享受するVTIが、最終的な資産額で最も大きくなることが予想されます。一方、両方を購入するパターンは、VTIの成長力とVYMの安定性をバランスよく組み合わせる戦略となり、VTI単独よりもリターンは穏やかになりますが、リスク分散の効果も期待できます。
| 期間(年) | VTI 単独(100万投資) 最終資産額(円) | VYM 単独(100万投資) 最終資産額(円) | VTI 50万 + VYM 50万 最終資産額(円) |
| 5 | 1,469,000 | 1,338,000 | 1,404,000 |
| 10 | 2,159,000 | 1,791,000 | 1,975,000 |
| 15 | 3,172,000 | 2,397,000 | 2,785,000 |
| 20 | 4,661,000 | 3,207,000 | 3,934,000 |
| 25 | 6,848,000 | 4,292,000 | 5,557,000 |
| 30 | 10,063,000 | 5,743,000 | 7,863,000 |
| 35 | 14,785,000 | 7,686,000 | 11,118,000 |
| 40 | 21,725,000 | 10,286,000 | 15,725,000 |
| 45 | 31,939,000 | 13,765,000 | 22,233,000 |
| 50 | 46,901,000 | 18,420,000 | 31,438,000 |
※VTI 年率8%、VYM 年率6%の想定リターン(配当再投資込み)で算出
VTIとVYMの配当比較
VTIとVYMはどちらも四半期に一度、つまり年4回の配当支払いを行っています。
具体的な支払月は、両者とも概ね「3月、6月、9月、12月」の年4回で共通しています。
| 支払月 | VTI 1口あたり配当金 (USD) | VTI 1口あたり配当金 (円換算) | VYM 1口あたり配当金 (USD) | VYM 1口あたり配当金 (円換算) |
| 3月 | 0.850 | 127.5 | 0.800 | 120.0 |
| 4月 | – | – | – | – |
| 5月 | – | – | – | – |
| 6月 | 0.950 | 142.5 | 0.850 | 127.5 |
| 7月 | – | – | – | – |
| 8月 | – | – | – | – |
| 9月 | 0.900 | 135.0 | 0.900 | 135.0 |
| 10月 | – | – | – | – |
| 11月 | – | – | – | – |
| 12月 | 1.100 | 165.0 | 1.200 | 180.0 |
| 1月 | – | – | – | – |
| 2月 | – | – | – | – |
| 合計 (年間) | 3.800 | 570.0 | 3.750 | 562.5 |
※直近1年の実績を基にした想定値(為替レートは1ドル150円で計算)
VTIとVYMに投資した場合の配当金シミュレーション比較
配当利回り約1.5%のVTIと、約3.0%のVYMでは、投資元本に対してどれくらいの配当金収入の差が生まれるのかをシミュレーションします。ここでは、仮に1000万円を投資した場合の年間配当金(税引き前)を日本円で比較してみました。
単純な「利回り」で見れば、高配当に特化したVYMがVTIを大きく上回るのは当然の結果です。
| 投資元本(円) | VTI 年間想定配当利回り(%) | VTI 年間想定配当金(円) | VYM 年間想定配当利回り(%) | VYM 年間想定配当金(円) |
| 100万円 | 1.5 | 15,000 | 3.0 | 30,000 |
| 300万円 | 1.5 | 45,000 | 3.0 | 90,000 |
| 500万円 | 1.5 | 75,000 | 3.0 | 150,000 |
| 1,000万円 | 1.5 | 150,000 | 3.0 | 300,000 |
| 3,000万円 | 1.5 | 450,000 | 3.0 | 900,000 |
| 5,000万円 | 1.5 | 750,000 | 3.0 | 1,500,000 |
VTIとVYM、おすすめは?
結論から言えば、「合わせてもつ」のは非常に理にかなった戦略の一つです。
VTIの持つ高い成長性と、VYMの持つ安定した配当収入という、それぞれのメリットを享受できます。VTI単独は高いリターンを狙えますが、市場下落時のショックは大きくなりがちです。一方、VYM単独は安定していますが、成長期における爆発力に欠けます。
両方を組み合わせることで、リスクを抑えつつ、トータルリターンとインカムゲインのバランスを取ることが可能です。
| 観点 | VTI (市場全体型) | VYM (高配当型) | 両方保有 (分散型) |
| 最大のメリット | 米国市場の成長をほぼ完全に享受できる | 安定した高水準の配当収入が得られる | リターンとインカムのバランスが取れる |
| 最大のデメリット | 配当利回りが低いため、インカムは期待薄 | 市場平均以上の成長は期待しにくい | ポートフォリオ管理がやや煩雑になる |
| トータルリターン | 高い (市場の成長力を最大限に活かす) | 中程度 (配当込みでVTIに劣後する傾向) | 中~高 (VTIとVYMの中間に位置) |
| インカムゲイン | 低い (配当再投資による長期的な複利を重視) | 高い (キャッシュフローを重視する投資家向き) | 中程度 (適度なキャッシュフローと成長を両立) |
| リスク耐性 | 中程度 (市場全体と同じ変動を経験) | やや高い (不況に強いディフェンシブ株が多い) | 中程度 (リスク分散効果で単独より安定) |
| 投資初心者へのおすすめ度 | 高い (迷ったらこれ、という王道ETF) | 中程度 (インカムの使い道を明確にできるなら) | 高い (両者のメリットを享受できるため) |
| 投資目的 | 資産の最大化、老後資金の形成 | 定期的な収入、生活費の足し | 成長と安定のバランス、リスクヘッジ |
FAQ(よくある質問)
- QVTIとVYMはNISA(ニーサ)の対象ですか?
- A
はい、どちらも日本の証券会社で購入可能であり、つみたてNISAの対象ではありませんが、成長投資枠(旧一般NISA)の対象銘柄として購入できます。ただし、利用する証券会社によっては取り扱いがない場合もあるため、事前に確認が必要です。非課税の恩恵を最大限に受けるためにも、NISA口座での利用を検討するのは賢明な選択です。
- QVYMの配当利回りは今後も安定的に維持されますか?
- A
VYMは高配当株で構成されていますが、個別の企業の業績が悪化すれば減配や無配になる可能性はあります。しかし、VYM自体が数百の銘柄に分散投資しているため、一部の減配があってもポートフォリオ全体としての配当金が大きく減るリスクは低いです。長期的に見れば、米国の経済成長と共に配当金総額は増加傾向にあると期待できます。
- QVTIは景気が悪くなるとVYMよりも大きく下落しやすいですか?
- A
統計的に見て、景気後退局面では、VTIのほうがVYMよりも下落率が大きくなる傾向があります。これは、VTIに多く含まれるハイテクや景気敏感株が、不況期に大きく売られやすいためです。一方、VYMはヘルスケアや生活必需品などのディフェンシブな高配当株の比率が高いため、相対的に株価の底堅さを見せることが多いです。
- Q20代の若手投資家と、50代のベテラン投資家ではどちらを選ぶべきですか?
- A
一般論として、20代の方は長期の運用期間があるため、リターン最大化を目指せるVTIをコアにするのがおすすめです。50代の方は、退職後のインカムゲインを重視するフェーズに入り始めているため、安定した配当収入が得られるVYMの比率を高める戦略が考えられます。ただし、これはあくまで目安であり、個々のリスク許容度と目的によって最終的な判断は異なります。
- QVTIとS&P500に連動するVOOはどちらを選ぶべきですか?
- A
VTIは米国株式市場のほぼ全て(約4,000銘柄)に投資するのに対し、VOOはS&P500(約500銘柄)に投資します。歴史的に見て、VTIとVOOのリターンに大きな差はありませんが、VTIのほうが小型株までカバーしている分、より広範な分散が効いています。どちらを選んでも大きな問題はありませんが、超広範な分散を好むならVTI、米国の主要企業に絞りたいならVOOという選び方ができます。
まとめ
VTIとVYMは、どちらも優れたETFであり、米国株投資のポートフォリオにおいて重要な役割を果たすことができます。VTIは、米国市場全体の成長を享受し、長期的な資産の最大化を目指す投資家にとっての「王道」です。一方、VYMは、安定した配当収入(インカムゲイン)を重視し、キャッシュフローを得たい投資家にとって非常に魅力的な選択肢となります。
どちらか一方を選ぶのではなく、両方を組み合わせて持つという戦略は、VTIの持つ成長力とVYMの持つ安定性の「いいとこどり」ができるため、多くの投資家にとって最適なバランスを生み出します。
投資の目的やライフステージに応じて、この2つのETFの比率を調整していくことが、米国株投資で成功するための鍵となるでしょう。

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。