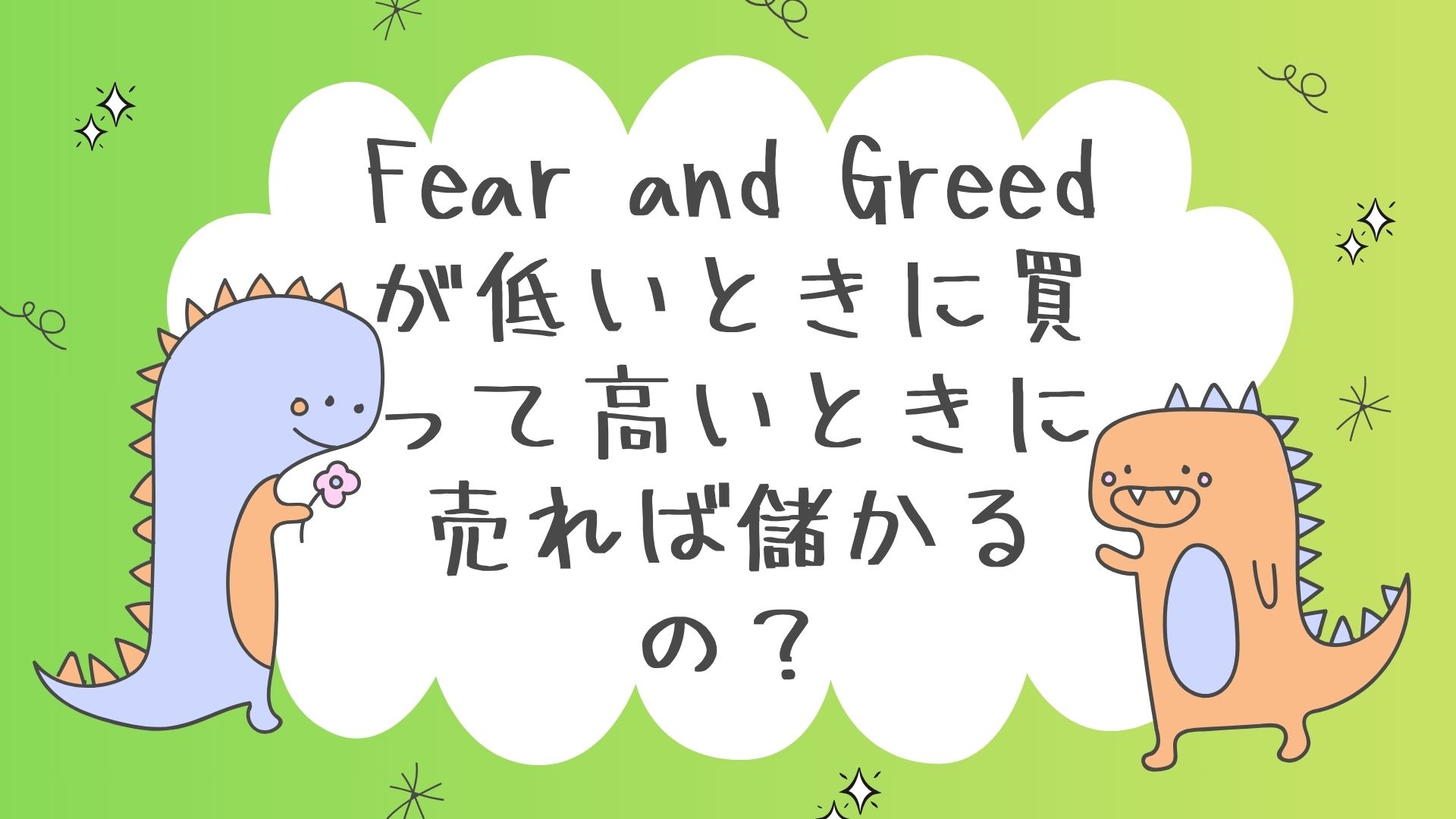投資家の感情を数値化した「Fear & Greed Index」
投資を続けていると、「もう怖くて買えない」と感じる時期と、「これは絶対に上がる!」と強気になる時期が交互に訪れます。CNNが公開している「Fear & Greed Index(恐怖と強欲指数)」は、まさにその投資家心理を定量的に測ろうとする試みです。
指数は0〜100で表され、
- 0に近いほど市場が恐怖に支配され、
- 100に近いほど強欲が蔓延している状態を示します。
構成要素は7つ。株価モメンタム、プット・コール比率、ボラティリティ、ジャンク債スプレッドなど、
短期のリスク選好度を示す指標を組み合わせて算出されています。
人間の心理は価格に先行する。そう考える投資家は少なくありません。
このため、「Fearのときに買い、Greedのときに売る」という逆張りルールは、
昔から多くの投資家が心のどこかで信じている“黄金律”のような存在でもあります。


実際シミュレートをしてみた。Fearが25以下で買い、Greedが75以上で売る
では実際に、この単純なルールがどの程度通用するのか。
過去10年分(2014〜2024年)のデータでシミュレーションを行ってみました。
使ったデータは以下の通りです。
| データ | 内容 |
|---|---|
| Fear & Greed Index | 有志が収集した日次履歴(CNN公式指標をもとに) |
| S&P500(SPY) | Yahoo Finance経由で取得した日次終値 |
| 期間 | 2014年1月〜2024年10月 |
| 売買ルール | FG≤25で翌営業日寄りに買い、FG≥75で翌営業日寄りに売却 |
| 初期資金 | 10万ドル、全額投資・全額現金化の単純モデル |
つまり、市場が「恐怖」に震えているときに買い、「強欲」が頂点に達したときに売るという、
まさに“感情の逆張り”を数値的に再現した戦略です。
検証結果
結果をざっくり整理すると、次のようになりました。
| 指標 | Fear & Greed戦略 | Buy & Hold(SPY) |
|---|---|---|
| 総リターン | 約 +86% | 約 +140% |
| 年率リターン | 約 +6.3% | 約 +9.2% |
| 最大ドローダウン | 約 -23% | 約 -33% |
| 年間ボラティリティ | 約 13% | 約 17% |
| シャープレシオ | 約 0.48 | 約 0.54 |
| 売買回数 | 28回(約年3回ペース) | なし(保有しっぱなし) |
一見してわかるのは、「Fear & Greed戦略」はリスクを抑えながらも、リターンは劣るという結果でした。
暴落局面で買うためドローダウンは浅くなりやすいのですが、
その代償として上昇トレンドを“逃す期間”が長くなる傾向があります。
感情の逆張りは理屈では正しくても、現実は甘くない
この結果を見て「やっぱりそんなに簡単じゃないのか」と思う人も多いでしょう。
実際、理屈のうえでは“安く買って高く売る”という完璧な戦略のはずです。
それでも長期で見ると、ただ持ち続けるシンプルなBuy & Holdのほうが結果的に優れてしまうことが多いのです。
その理由はいくつかあります。
- Fear & Greedの反応は速すぎる
指数は短期的な感情の動きを反映するため、
実際の価格転換点よりも一歩早くシグナルを出すことがあります。
つまり「まだ下がる途中で買う」「まだ上がる途中で売る」動きになりやすい。 - 過去データでうまく見えても、未来は違う
過去10年の市場は量的緩和とAIブームの影響で、
“強欲”が長く続く局面が多かった。
こうした相場環境では、早売りはむしろ機会損失になります。 - 心理的にも実行が難しい
Fearが20を切るような場面は、ニュースも真っ暗。
投資家の心は冷えきっており、実際には“買い向かう勇気”が必要になります。
指数上では「買いシグナル」でも、体感的にはまったくそう思えないのが現実です。
“逆張り”より“鈍感力”
もう少し視点を変えてみましょう。
Fear & Greedのような心理指数を使った逆張りが機能しにくくなっている背景には、市場参加者の構造変化があります。
近年はアルゴリズム取引やETF自動リバランスなど、
感情に左右されにくいマネーが増えています。
つまり、市場全体が“感情的に動く”割合が下がってきているのです。
その結果、短期的な恐怖の揺れがリバウンドに直結する場面は減り、
むしろ「下がっているのに買われ続ける」あるいは「上がっているのに売られない」局面が増えています。
Fear & Greedが70を超えても、そこからさらに半年上昇することも珍しくありません。
それでも活用価値は高い
とはいえ、Fear & Greed指数を無視してよいわけではありません。
むしろ行動を“止める”ための道具としては非常に有効です。
たとえば、次のような活用が現実的です。
| 状況 | 活用法 |
|---|---|
| FGが20台以下 | 新規の売りや空売りを控える。過度な悲観に流されないよう警戒。 |
| FGが80超 | 追加買いを控える。利益確定やポジション調整の検討。 |
| FGが中立(40〜60) | 相場の方向性が曖昧な時期。焦らず静観する。 |
こうした“温度感の確認”としてFear & Greedを見ると、感情的な売買を減らす助けになります。
「今の市場は熱狂しているのか、冷えきっているのか」を冷静に捉えるための“体温計”として使うのが一番の使い道です。
まとめ
バックテストの数字が教えてくれるのは、
「恐怖で買い、強欲で売る」というシンプルな理屈の正しさではなく、“それを実行し続ける難しさ”です。
Fear & Greedは、確かに市場心理を映す鏡です。
しかし、その鏡を見ながら「ここで買う」「ここで売る」を決めるのは、やはり最終的に人間の心です。

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。