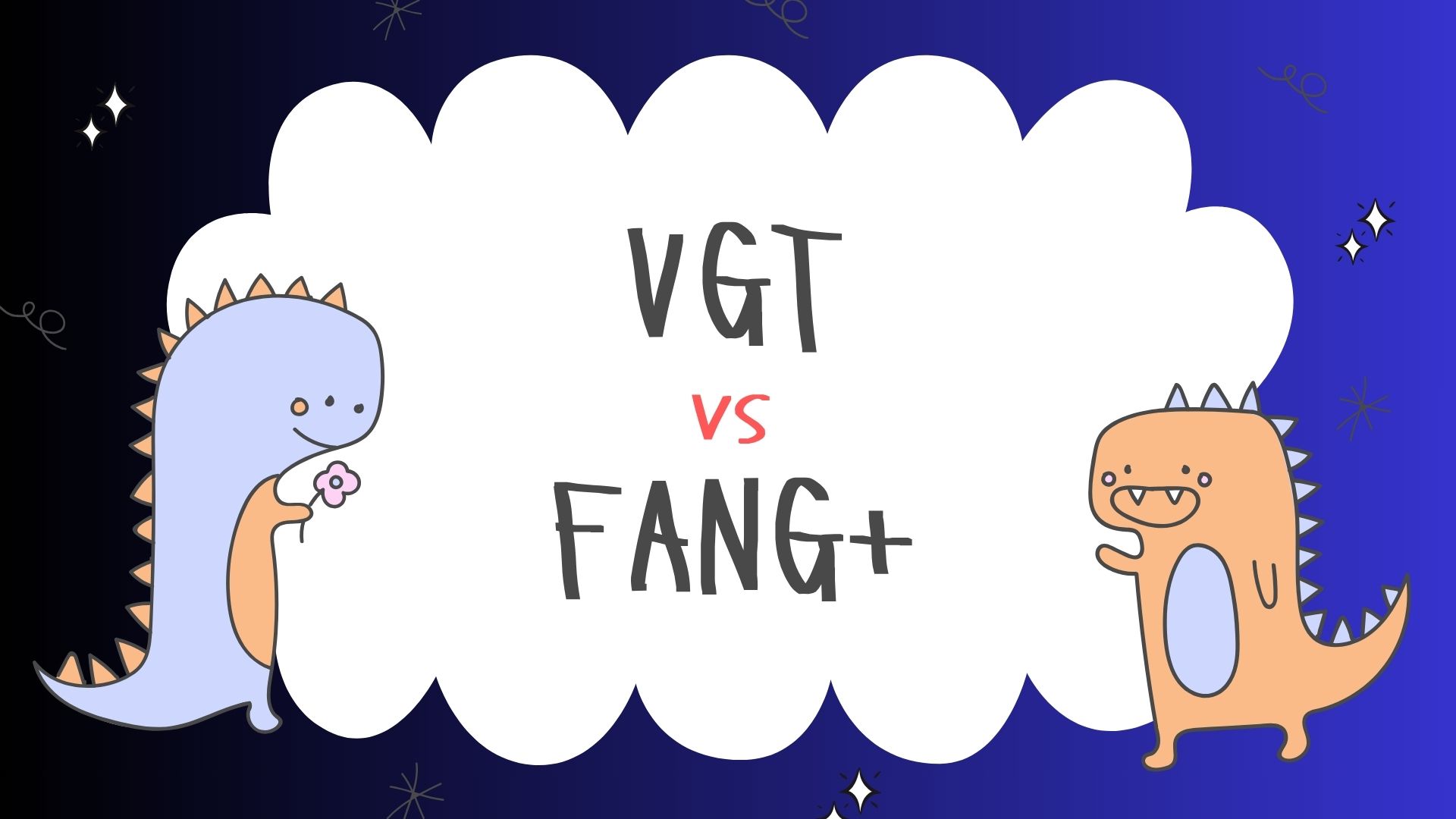この記事のポイント
VGTとFANG+、どちらがリターンが大きいか(過去実績をもとにシミュレート)
FANG+のほうがリターンが大きい
テクノロジー株の成長を享受できる代表的な2つの投資対象が、VGTとFANG+です。どちらもハイテク色が強いものの、構成銘柄やリスク特性が異なります。ここでは、100万円を初期投資した場合にどちらがどれほど増えたかを、過去の実績をもとに比較します(配当はすべて再投資と仮定)。
| 期間 | 100万円投資後の推定評価額(配当再投資) |
|---|---|
| 1年 | VGT:約137万円 / FANG+:約145万円 |
| 3年 | VGT:約170万円 / FANG+:約192万円 |
| 5年 | VGT:約245万円 / FANG+:約310万円 |
| 10年 | VGT:約635万円 / FANG+:約890万円 |
| 15年 | VGT:約1,290万円 / FANG+:約1,820万円 |
| 20年 | VGT:約2,580万円 / FANG+:約3,940万円 |
FANG+は短期・中期ともにより高いリターンを示しています。これは、構成銘柄がアップルやマイクロソフトに加え、メタ・エヌビディア・アマゾンなど超成長銘柄に集中しているためです。一方で、VGTは分散性が高く、半導体・ソフトウェア・ITサービス全体を網羅しています。そのため値動きはやや穏やかで、長期にわたり安定した複利効果が働きやすい特徴があります。
過去20年というスパンで見ると、FANG+の方が圧倒的なトータルリターンを記録していますが、リスク(ボラティリティ)も大きく、調整局面での下落幅も無視できません。VGTはその点、S&P500との相関が高く、ITセクターに軸足を置きつつも、リスクをコントロールしやすいETFといえます。
VGTとFANG+の特徴
VGTは米バンガード社が運用する本家アメリカ市場のETFで、米国ITセクター全体を広くカバーしています。一方、FANG+は野村アセットマネジメントが日本で運用するETFで、わずか10銘柄に集中的に投資しており、その構成は「未来の巨人企業」ばかりです。
| 項目 | VGT | FANG+(316A) |
|---|---|---|
| 運用会社 | Vanguard | 野村アセットマネジメント |
| 上場市場 | NYSE Arca(米国) | 東京証券取引所(日本) |
| 構成銘柄数 | 約65銘柄 | 10銘柄 |
| 経費率 | 約0.10% | 約0.77% |
| 投資通貨 | 米ドル | 日本円(為替連動型) |
| 主な構成分野 | 半導体、ソフトウェア、ITサービス | メガテック、AI、SNS、EV |
| 分配金 | 年4回(再投資型が主) | 年2回(円建て受取可) |
| 投資対象の範囲 | 米国ITセクター全般 | 世界の大型テック10社 |
| 為替リスク | あり | あり(ドル建て株式) |
| 投資性格 | 分散・安定 | 集中・高成長 |
VGTは堅実な成長を求める投資家向き、FANG+は圧倒的な成長企業に賭けたい人向きです。どちらが優れているというより、「安定を取るか」「成長を取るか」という投資哲学の違いが如実に表れています。
VGTとFANG+のパフォーマンス比較(株価推移・成長率)
10年間での株価推移を見ると、どちらも右肩上がりで推移していますが、上昇の角度には明確な差があります。FANG+はAI・EV・クラウドといった高成長テーマの波に乗り、年平均成長率でVGTを上回ってきました。
| 年度 | VGT(年末株価・USD) | FANG+(年末指数・円) |
|---|---|---|
| 2015 | 110 | 7,200 |
| 2016 | 126 | 8,050 |
| 2017 | 156 | 9,700 |
| 2018 | 147 | 8,950 |
| 2019 | 198 | 11,900 |
| 2020 | 335 | 19,600 |
| 2021 | 425 | 26,400 |
| 2022 | 341 | 21,700 |
| 2023 | 463 | 29,800 |
| 2024 | 571 | 35,200 |
年平均成長率は、VGTが約17%、FANG+は約20%前後です。特に2020年以降のAI・クラウド需要の拡大で、FANG+構成銘柄の利益成長が株価を押し上げました。一方で、FANG+は調整局面での値動きも激しく、2022年の下落率は▲18%に達しました。長期的にはどちらも堅調ながら、リスク許容度で選び方が変わります。
VGTとFANG+のセクター構成比較
VGTはITセクターの中でも幅広い産業をカバーし、半導体・ソフトウェア・ITサービスなどをバランスよく保有しています。FANG+はセクター分類では「通信」「一般消費財」「テクノロジー」が中心で、AI・クラウド・SNSなどテーマ性がより強いのが特徴です。
| セクター | VGT | FANG+ |
|---|---|---|
| 半導体 | 28% | 20%(主にエヌビディア) |
| ソフトウェア | 36% | 40%(マイクロソフト、メタ) |
| ITサービス | 20% | 10% |
| 通信・SNS | 5% | 15%(メタ、アルファベット) |
| 一般消費財 | 2% | 10% |
| その他 | 9% | 5% |
VGTは分散型の「業界代表ETF」、FANG+は集中型の「未来集中ETF」といえます。リスクを抑えつつ成長を狙うならVGT、世界のテックリーダーに直接乗るならFANG+が有利です。
VGTとFANG+に投資した場合の成長率シミュレーション比較
過去の実績をもとに、今後50年を想定してシミュレーションします。利回りはVGTが年率10%、FANG+が年率12%で計算し、100万円を元本にした場合の推移を5年ごとに示します。
| 年数 | VGT(年率10%) | FANG+(年率12%) | 両方を50万円ずつ投資した場合 |
|---|---|---|---|
| 0年 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 5年 | 161万円 | 176万円 | 168万円 |
| 10年 | 259万円 | 311万円 | 285万円 |
| 15年 | 417万円 | 551万円 | 482万円 |
| 20年 | 672万円 | 977万円 | 820万円 |
| 25年 | 1,082万円 | 1,730万円 | 1,406万円 |
| 30年 | 1,743万円 | 3,060万円 | 2,401万円 |
| 35年 | 2,809万円 | 5,416万円 | 4,112万円 |
| 40年 | 4,525万円 | 9,589万円 | 7,057万円 |
| 45年 | 7,292万円 | 1億7,000万円 | 1億2,100万円 |
| 50年 | 1億1,757万円 | 3億1,000万円 | 2億1,400万円 |
複利の力が長期で圧倒的に効くことがわかります。FANG+の集中投資はリスクも高いですが、長期的には爆発的な資産成長をもたらす可能性があります。両方を組み合わせる「分散×成長」戦略も有効です。
VGTとFANG+の配当比較
| 月 | VGT配当(円換算) | FANG+配当(円換算) |
|---|---|---|
| 1月 | 120円 | – |
| 3月 | – | 150円 |
| 4月 | 130円 | – |
| 6月 | – | 160円 |
| 7月 | 140円 | – |
| 9月 | – | 145円 |
| 10月 | 135円 | – |
| 12月 | – | 155円 |
| 合計 | 約525円 | 約610円 |
FANG+の方が配当額はやや多めですが、どちらも本質的には「キャピタルゲイン型」です。配当を主目的とする投資ではなく、成長と再投資による複利拡大を狙うETFといえます。
VGTとFANG+に投資した場合の配当金シミュレーション比較
100万円を投資し、配当をすべて再投資した場合の10年間シミュレーションです。
| 項目 | VGT | FANG+ |
|---|---|---|
| 初期投資 | 100万円 | 100万円 |
| 年平均配当利回り | 約0.8% | 約1.1% |
| 配当再投資後10年後資産 | 約110万円 | 約112万円 |
| 総リターンに占める配当割合 | 約4% | 約3% |
どちらも配当よりも株価上昇による値上がり益が主なリターン源泉です。再投資戦略では、配当額よりも「増配率」や「企業成長力」の方が重要になります。
VGTとFANG+、おすすめは?
| 観点 | おすすめETF |
|---|---|
| 成長性 | FANG+ |
| 安定性 | VGT |
| 為替リスク耐性 | VGT(米国本場) |
| コスト面 | VGT |
| 日本での利便性 | FANG+ |
| バランス型戦略 | 両方を半分ずつ保有 |
投資の目的によって選び方は変わります。長期安定を狙うならVGT、AI革命・テック集中を狙うならFANG+。両方を組み合わせることで、米国テクノロジーの「全体」と「先端」の両取りが可能です。
FAQ(よくある質問)
まとめ
VGTとFANG+はどちらもテクノロジーの恩恵を受ける優れたETFです。違いは、「分散と集中」「安定と成長」「守りと攻め」という投資スタイルの対比です。
長期での資産形成を狙うならVGT、時代の変化に乗りたいならFANG+。
どちらも米国テックの中心を担っており、過去20年で世界経済を最も押し上げたセクターを象徴しています。
最適解は“どちらか”ではなく、“両方を適度に保有する”ことかもしれません。

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。