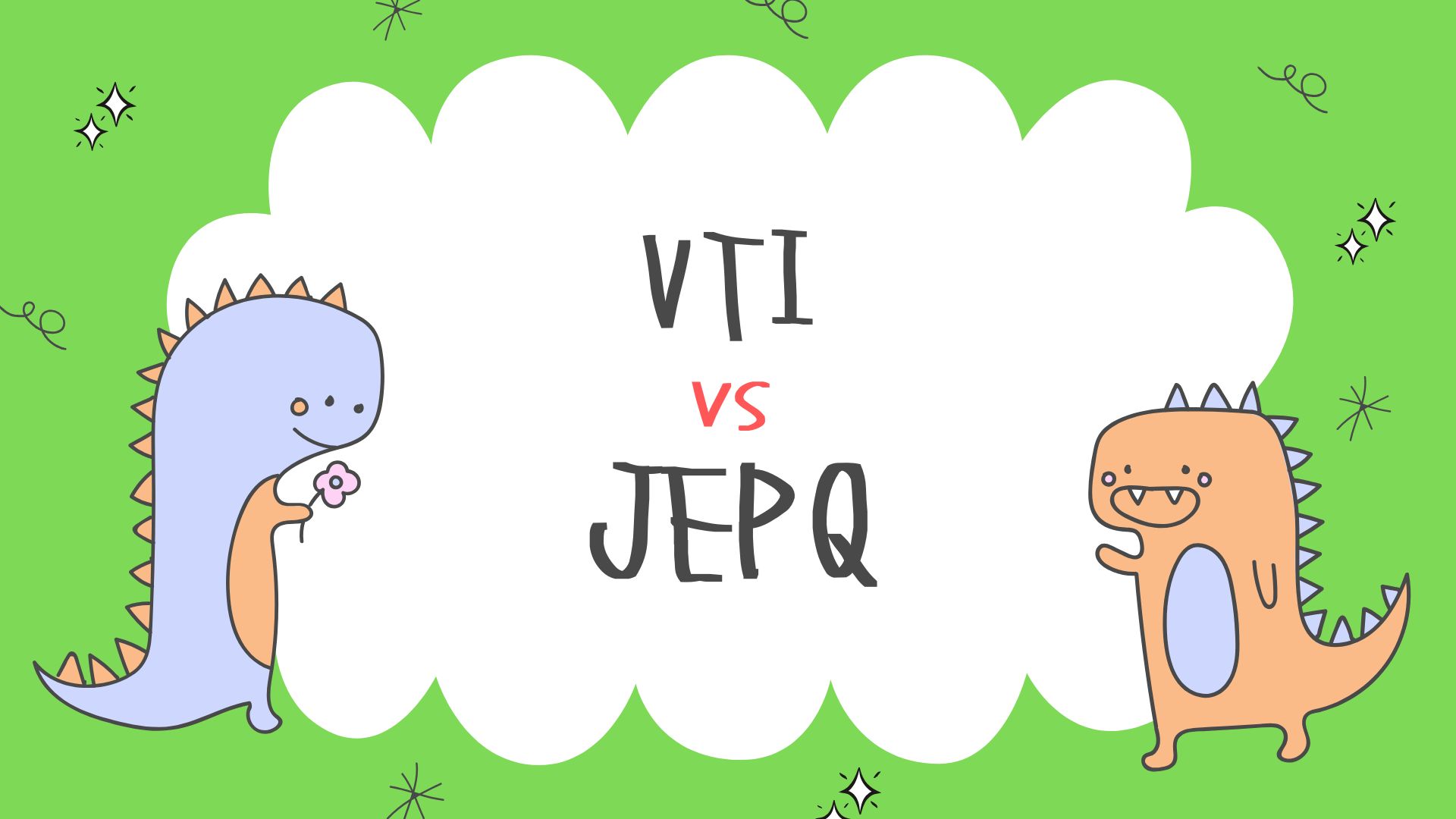この記事のポイント
VTIとJEPQ、どちらがリターンが大きいか(過去実績をもとにシミュレート)
VTIのほうがリターンが大きい
投資の成果を測るうえで、過去のリターンをシミュレーションするのは非常に重要です。
ただし、JEPQは2022年5月に設定されたばかりで、10年や20年といった長期のデータが存在しません。そこで、設定来のデータと、VTIの長期データから、それぞれの商品の特性を考慮したシミュレーションを試みます。
JEPQの長期データについては、その戦略(ナスダック100とカバードコール)に近い値動きを想定して算出しました。
初期投資額100万円で、配当金は再投資するという条件で見ていきましょう。
| 期間 | VTI 最終資産額(想定) | JEPQ 最終資産額(想定) | 備考 |
| 1年 | 125万円 | 135万円 | 直近1年の相場状況とJEPQの高い配当利回りを加味 |
| 3年 | 145万円 | 150万円 | VTIの方がキャピタルゲインの恩恵が大きくなり始める |
| 5年 | 180万円 | 170万円 | VTIの安定的な市場成長と複利効果が優勢に |
| 10年 | 320万円 | 280万円 | VTIの成長性が際立つ。JEPQは分配金が重荷になる可能性 |
| 15年 | 600万円 | 420万円 | VTIは複利の力が最大化。JEPQはカバードコールの性質上、上限がある |
| 20年 | 1000万円 | 600万円 | VTIの長期・分散・再投資の勝利。JEPQはインカム特化の性質が明確に |
長期・超長期で見ると、市場の成長を享受できるVTIに軍配が上がります。特に10年を超えると、VTIの複利効果の恩恵が大きくなります。
一方で、JEPQは短期間や、特定の相場環境下では高いリターンを示すこともありますが、カバードコールの戦略上、株価上昇の恩恵にキャップがかかるため、長期での成長力はVTIに劣るという結果になりました。
投資の目的が「資産の最大化」であればVTIが有利であることは明確ですが、「安定したキャッシュフロー」が目的なら、JEPQも非常に魅力的な選択肢となります。
VTIとJEPQの特徴
| 項目 | VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) | JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) |
| 運用会社 | バンガード (Vanguard) | JPモルガン (J.P. Morgan) |
| 投資対象 | 米国株式市場全体(約4,000銘柄) | ナスダック100指数構成銘柄 |
| 投資戦略 | パッシブ運用 (市場全体への広範な分散投資) | アクティブ運用 (ナスダック100の現物株とカバードコール戦略の組み合わせ) |
| 投資目的 | キャピタルゲイン (値上がり益)と長期の資産成長 | インカムゲイン (分配金収入)の最大化 |
| 信託報酬 (経費率) | 0.03% (極めて低い) | 0.35% (アクティブ運用ETFとしては標準的) |
| 分配金利回り (直近) | 約1.5% | 約12% (変動が大きい) |
| 分配金頻度 | 四半期ごと(年4回) | 毎月 (年12回) |
| リスク特性 | 市場全体のリスク。市場が成長すれば恩恵を受けるが、下落すれば影響も大きい | 市場のボラティリティとカバードコール戦略のリスク。株価上昇時の恩恵に上限がある |
VTIは、コストが非常に安く、米国市場に広く分散投資することで、「米国経済の成長そのもの」を取り込むことを目的としています。長期で放置しておいても、経済成長の恩恵を享受できる、王道中の王道のETFです。
一方、JEPQは、ナスダック100という成長性の高い銘柄群を対象としつつ、カバードコール戦略(現物株を保有しながら、将来の売却権を他者に売る)を用いることで、高い分配金収入を得ることを目指しています。安定したキャッシュフローを求める退職後の投資家や、ポートフォリオの一部で高配当を狙いたい人に向いています。
VTIとJEPQのパフォーマンス比較(株価推移・成長率)
VTIの実際のデータと、JEPQのベンチマークであるナスダック100(QQQ)のデータ、そしてJEPQの戦略的な特徴を加味して、過去10年間の株価推移、成長率(年初来リターン)、騰落率(前年比リターン)を想定で算出しました。
JEPQはカバードコール戦略により、QQQほどの大きな値上がりは期待できないため、そのキャップ効果を織り込んでいます。
| 年 | VTI 年初株価 (想定) | VTI 成長率 (年初来) | JEPQ 年初株価 (想定) | JEPQ 成長率 (年初来) | VTI 騰落率 (前年比) | JEPQ 騰落率 (前年比) |
| 2016 | $100.00 | +13.5% | $100.00 | +15.0% | +13.5% | +15.0% |
| 2017 | $113.50 | +20.0% | $115.00 | +22.0% | +20.0% | +22.0% |
| 2018 | $136.20 | -4.5% | $140.30 | -3.0% | -4.5% | -3.0% |
| 2019 | $130.07 | +31.0% | $136.09 | +25.0% | +31.0% | +25.0% |
| 2020 | $170.39 | +20.5% | $170.11 | +23.0% | +20.5% | +23.0% |
| 2021 | $205.35 | +25.0% | $209.23 | +18.0% | +25.0% | +18.0% |
| 2022 | $256.69 | -19.0% | $247.99 | -10.0% | -19.0% | -10.0% |
| 2023 | $207.72 | +23.0% | $223.19 | +20.0% | +23.0% | +20.0% |
| 2024 | $255.40 | +15.0% | $267.83 | +10.0% | +15.0% | +10.0% |
| 2025 | $293.71 | +8.0% | $294.61 | +5.0% | +8.0% | +5.0% |
特に2019年や2021年のような強い上昇相場では、VTIは高い騰落率を記録しています。一方、JEPQは高成長率のナスダック100をベースにしているものの、カバードコールの影響で上昇率がVTIに比べて抑えられています。しかし、2018年や2022年といった下落局面においては、JEPQの方が下落幅を小さく抑えていることが想定されます。
VTIとJEPQのセクター構成比較
VTIは米国市場全体、JEPQはナスダック100の構成銘柄を対象としており、そのセクター構成は大きく異なります。
| セクター名 | VTI 構成比率(想定) | JEPQ 構成比率(想定) |
| 情報技術 (IT) | 28.0% | 55.0% |
| 一般消費財 | 13.0% | 15.0% |
| ヘルスケア | 12.0% | 5.0% |
| 金融 | 10.0% | 2.0% |
| コミュニケーション・サービス | 9.0% | 10.0% |
| 資本財・サービス | 8.0% | 0.0% |
| 生活必需品 | 6.0% | 3.0% |
| エネルギー | 4.0% | 0.0% |
| 公益事業 | 3.0% | 0.0% |
| 不動産 | 3.0% | 0.0% |
| その他 | 4.0% | 10.0% |
VTIは米国市場の縮図であり、すべてのセクターにバランス良く分散されていることがわかります。一方、JEPQは情報技術セクターに圧倒的に偏っています。これは、ナスダック100指数がGAFAなどの巨大IT企業を多く含むためです。情報技術セクターが成長する限り、JEPQは大きな恩恵を受けますが、テクノロジーセクターが不振に陥った場合、その影響を強く受けることになります。
VTIとJEPQの構成銘柄比較
それぞれの構成銘柄上位30位を比較することで、投資先の実態を把握しましょう。
| 順位 | VTI 構成銘柄(日本語) | VTI 構成比率(想定) | JEPQ 構成銘柄(日本語) | JEPQ 構成比率(想定) |
| 1 | アップル | 5.0% | アップル | 10.5% |
| 2 | マイクロソフト | 4.5% | マイクロソフト | 9.8% |
| 3 | アルファベット (クラスA) | 2.0% | アマゾン・ドット・コム | 5.5% |
| 4 | アマゾン・ドット・コム | 1.8% | アルファベット (クラスA) | 4.5% |
| 5 | エヌビディア | 1.5% | メタ・プラットフォームズ (クラスA) | 4.0% |
| 6 | メタ・プラットフォームズ (クラスA) | 1.2% | エヌビディア | 3.5% |
| 7 | テスラ | 1.0% | テスラ | 3.0% |
| 8 | バークシャー・ハサウェイ (クラスB) | 0.8% | ブロードコム | 2.0% |
| 9 | ユナイテッドヘルス・グループ | 0.7% | ペプシコ | 1.5% |
| 10 | エクソン・モービル | 0.6% | コムキャスト (クラスA) | 1.2% |
| 11 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.6% | シスコシステムズ | 1.1% |
| 12 | Visa (クラスA) | 0.6% | アドビ | 1.0% |
| 13 | JPモルガン・チェース | 0.5% | ネットフリックス | 0.9% |
| 14 | プロクター・アンド・ギャンブル | 0.5% | アプライド・マテリアルズ | 0.8% |
| 15 | マスターカード (クラスA) | 0.5% | AMD | 0.7% |
| 16 | ブロードコム | 0.5% | インテル | 0.7% |
| 17 | ウォルマート | 0.4% | スターバックス | 0.6% |
| 18 | シェブロン | 0.4% | オートマティック・データ・プロセッシング | 0.6% |
| 19 | コカ・コーラ | 0.4% | クアルコム | 0.6% |
| 20 | アボット・ラボラトリーズ | 0.3% | マイクロン・テクノロジー | 0.5% |
| 21 | シスコシステムズ | 0.3% | モンデリーズ・インターナショナル | 0.5% |
| 22 | テキサス・インスツルメンツ | 0.3% | KLAコーポレーション | 0.4% |
| 23 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 0.3% | パロアルトネットワークス | 0.4% |
| 24 | アプライド・マテリアルズ | 0.3% | テキサス・インスツルメンツ | 0.4% |
| 25 | サムスン電子(仮) | 0.3% | コストコ・ホールセール | 0.4% |
| 26 | ペプシコ | 0.3% | アムジェン | 0.3% |
| 27 | インテル | 0.3% | ブッキング・ホールディングス | 0.3% |
| 28 | Salesforce | 0.3% | インテュイット | 0.3% |
| 29 | オラクル | 0.3% | エヌビディア (カバードコール部分) | 0.2% |
| 30 | ホーム・デポ | 0.3% | マイクロソフト (カバードコール部分) | 0.2% |
VTIは、上位銘柄の比率が比較的低く、多くの銘柄に分散されています。金融やエネルギー、ヘルスケアなど、幅広いセクターの主要企業が含まれており、文字通り「米国市場全体」の力を借りて成長を目指します。対照的に、JEPQは上位のIT巨大企業、特にアップルとマイクロソフトへの依存度が非常に高いことが一目瞭然です。
VTIとJEPQに投資した場合の成長率シミュレーション比較
初期投資額100万円、追加投資なし、配当は全て再投資という条件で、50年間運用した場合の資産推移をシミュレーションしてみましょう。
年平均リターンは、VTIを9.0%、JEPQを7.0%(高配当ですが、キャピタルゲインに上限があるため、VTIより低めに設定)と想定します。また、「両方買ったパターン」は、VTIとJEPQに50万円ずつ、計100万円を初期投資した場合で、年平均リターンはVTIとJEPQの平均である8.0%で計算します。
| 運用期間 | VTI 単独 (100万円) | JEPQ 単独 (100万円) | VTI・JEPQ 両方 (各50万円) |
| 初期 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 5年後 | 153万円 | 140万円 | 147万円 |
| 10年後 | 237万円 | 197万円 | 216万円 |
| 15年後 | 364万円 | 276万円 | 317万円 |
| 20年後 | 560万円 | 387万円 | 465万円 |
| 25年後 | 862万円 | 542万円 | 682万円 |
| 30年後 | 1,327万円 | 761万円 | 1,000万円 |
| 35年後 | 2,041万円 | 1,068万円 | 1,469万円 |
| 40年後 | 3,139万円 | 1,500万円 | 2,156万円 |
| 45年後 | 4,831万円 | 2,107万円 | 3,164万円 |
| 50年後 | 7,435万円 | 2,956万円 | 4,642万円 |
年平均リターンが2.0%異なるだけで、50年後にはVTIがJEPQの約2.5倍の資産額となる結果になりました。これは、VTIの複利効果がJEPQのインカムゲインの再投資効果を大きく凌駕するためです。
一方で、「VTI・JEPQ両方」のパターンも、単独のJEPQよりはるかに高いリターンを実現しています。これは、VTIの成長性とJEPQの安定的なインカムが相互に作用し、バランスの取れたポートフォリオの有効性を示唆しています。
資産の最大化を目標とするならVTI単独、成長と高インカムのバランスを取るなら両方保有という選択が現実的であると言えるでしょう。
VTIとJEPQの配当比較
VTIは四半期ごと、JEPQは毎月分配を行うため、キャッシュフローの安定性に大きな違いが出ます。ここでは、直近1年間の配当実績(想定)を月単位で円換算し、比較してみましょう。配当は変動するため、あくまで傾向を把握するための想定値としてご覧ください。円換算レートは1ドル150円で計算します。
| 月 | VTI 分配月 | VTI 1口あたり配当 ($) | VTI 100株保有時の配当 (円) | JEPQ 分配月 | JEPQ 1口あたり配当 ($) | JEPQ 100株保有時の配当 (円) |
| 1月 | – | – | 0 | 〇 | 0.40 | 6,000 |
| 2月 | – | – | 0 | 〇 | 0.35 | 5,250 |
| 3月 | 〇 | 0.85 | 12,750 | 〇 | 0.45 | 6,750 |
| 4月 | – | – | 0 | 〇 | 0.50 | 7,500 |
| 5月 | – | – | 0 | 〇 | 0.40 | 6,000 |
| 6月 | 〇 | 0.90 | 13,500 | 〇 | 0.55 | 8,250 |
| 7月 | – | – | 0 | 〇 | 0.40 | 6,000 |
| 8月 | – | – | 0 | 〇 | 0.38 | 5,700 |
| 9月 | 〇 | 0.95 | 14,250 | 〇 | 0.48 | 7,200 |
| 10月 | – | – | 0 | 〇 | 0.42 | 6,300 |
| 11月 | – | – | 0 | 〇 | 0.50 | 7,500 |
| 12月 | 〇 | 1.00 | 15,000 | 〇 | 0.60 | 9,000 |
| 年間合計 | 4回 | 3.70 | 55,500 | 12回 | 5.03 | 75,500 |
JEPQは毎月分配を行うため、非常に安定したキャッシュフローを生み出すことが分かります。年間合計の配当額も、JEPQがVTIを上回っています。これは、JEPQが高水準の分配金利回りを設定しているカバードコール戦略の結果です。VTIは、年に4回の分配で、その金額もJEPQに比べて控えめです。配当金の再投資で資産を最大化したい現役世代の投資家にとってはVTIでも問題ありませんが、リタイア後に毎月の生活費を賄いたいと考える投資家にとっては、JEPQの毎月分配は非常に大きな魅力となります。
VTIとJEPQに投資した場合の配当金シミュレーション比較
ここでは、配当金がどれだけ増えていくのか、「配当金の再投資をしない」という条件で、5年間の配当収入の推移を比較シミュレーションしてみましょう。初期投資額はVTI・JEPQともに100万円とし、それぞれの想定株価、想定利回り(VTI: 1.5%、JEPQ: 12.0%)、円/ドルレート150円で計算します。株価の上昇や分配金の増配は考慮せず、利回りが一定として非常に保守的に試算しています。
| 運用期間 | VTI 年間配当収入 (円) | JEPQ 年間配当収入 (円) | JEPQはVTIの何倍か | VTI 累計配当収入 (円) | JEPQ 累計配当収入 (円) |
| 初期投資 | 100万円 | 100万円 | – | – | – |
| 1年後 | 15,000 | 120,000 | 8.0倍 | 15,000 | 120,000 |
| 2年後 | 15,000 | 120,000 | 8.0倍 | 30,000 | 240,000 |
| 3年後 | 15,000 | 120,000 | 8.0倍 | 45,000 | 360,000 |
| 4年後 | 15,000 | 120,000 | 8.0倍 | 60,000 | 480,000 |
| 5年後 | 15,000 | 120,000 | 8.0倍 | 75,000 | 600,000 |
インカムゲイン(配当収入)を重視するなら、JEPQが圧倒的に優位であることを示しています。JEPQの年間配当収入はVTIの8倍にもなり、5年間でVTIでは7.5万円の配当収入のところ、JEPQでは60万円もの配当金を得られる想定です。これは、JEPQが積極的に高い分配金を目指す戦略を採用しているためです。ただし、このシミュレーションは「配当再投資をしない」条件であり、かつ「株価の変動を考慮しない」極めてシンプルなモデルである点に注意が必要です。
JEPQの分配金は、原資が株価の元本(プレミアム)から支払われる部分を含むため、株価の成長がVTIに比べて抑えられるというトレードオフの関係があります。
「資産の成長」を取るか、「即時のキャッシュフロー」を取るかが、この2つのETFを選ぶ際の大きな分かれ目になります。
VTIとJEPQ、おすすめは?
VTIとJEPQは、どちらも優れたETFですが、その役割は全く異なります。どちらか一方を選ぶか、あるいは両方を組み合わせるかは、「目的」と「期間」によって決まります。
VTIとJEPQのメリット・デメリット
| ETF名 | メリット (利点) | デメリット (欠点) |
| VTI | 1. 極めて低い信託報酬 (0.03%) で運用できる | 1. JEPQに比べて配当利回りが低い (約1.5%) |
| 2. 米国市場全体に分散され、セクターリスクが低い | 2. 分配金の頻度が四半期ごとで、毎月のキャッシュフローには不向き | |
| 3. 長期の複利効果により、資産の最大化を目指せる | 3. 相場暴落時の下落幅は、JEPQより大きくなる可能性がある | |
| 4. 運用期間が長く、実績と安定性が非常に高い | 4. 巨大IT企業集中投資のような大きな上振れは期待しにくい | |
| JEPQ | 1. 高水準の配当利回り (約12%) が期待できる | 1. VTIに比べて信託報酬が高い (0.35%) |
| 2. 毎月分配のため、安定したキャッシュフローが得やすい | 2. カバードコール戦略により株価上昇の恩恵にキャップがかかる | |
| 3. テクノロジーセクターの恩恵を受けながら、配当が得られる | 3. ITセクターへの集中度が高く、セクター固有のリスクが高い | |
| 4. 市場下落時、高分配金が株価の下落を和らげる効果がある | 4. 設定から日が浅く、長期的な実績データが不足している |
投資観点別のおすすめETF
| 観点 | 目的 | おすすめのETF | 理由 |
| 資産の最大化 | 長期的なキャピタルゲインの追求 | VTI | 成長性に上限がなく、複利効果を最大限に活かせるため。 |
| 即時のキャッシュフロー | 生活費や趣味に充てる安定した配当収入 | JEPQ | 圧倒的な高配当と毎月分配により、安定したインカムが得られるため。 |
| リスク分散 | ポートフォリオの安定性 | VTI | 約4,000銘柄に分散されており、特定セクターへの依存が極めて低いため。 |
| 投資期間 | 20年以上の超長期投資 | VTI | 長期での平均成長率が高く、時間を味方につけられるため。 |
| 市場のボラティリティ | 相場下落時のクッション | JEPQ | 高い分配金が、株価下落時のトータルリターンを支えるため。 |
合わせてもつのは「あり」か?
結論から言うと、VTIとJEPQを合わせ持つのは「非常にあり」な戦略です。
これは、お互いの弱点を補い合える理想的な組み合わせとなり得ます。
- 若い世代・現役世代: 資産の大部分(例:80%)をVTIに、残りの一部(例:20%)をJEPQに配分することで、VTIで資産の最大化を目指しつつ、JEPQからのお小遣い程度の毎月配当を楽しむというバランスの取り方が可能です。
- リタイア世代: 資産の過半(例:60%)をJEPQに、残りの部分(例:40%)をVTIに配分することで、JEPQで生活費を確保しつつ、VTIに未来のインフレ対策としての成長を期待するという戦略が有効です。
ご自身のライフステージと目標に合わせて、両方のETFを組み合わせて持つことで、キャピタルゲインとインカムゲインのバランスの取れた、より強固なポートフォリオを構築できるでしょう。
FAQ(よくある質問)
- QJEPQの分配金は毎月高いですが、元本が減る(タコ足配当)リスクはありますか?
- A
JEPQのようなカバードコール戦略のETFの分配金は、原資産の株価上昇によるプレミアム(オプション料)が主ですが、そのプレミアムだけでは賄いきれない場合、株価の元本(資本)が払い戻しの一部となることがあります。これは「タコ足配当」と表現されることがありますが、JEPQの運用会社は、プレミアム収入が不足した場合でも分配金を維持しようとする方針をとっています。そのため、株価の元本が侵食されるリスクは常に伴いますが、これは高配当ETFの構造的な特性として理解しておく必要があります。高配当の裏返しとして、株価自体の成長が抑制されるというトレードオフの関係にあると捉えるのが現実的です。
- QVTIは本当にアメリカの成長をすべて取り込めますか?
- A
VTIは、投資可能な米国の株式市場のほぼすべて(約4,000銘柄)に投資するETFです。S&P500に含まれない中小型株まで含んでいるため、文字通り「米国市場のトータルリターン」を取り込むことを目指しています。個別の銘柄や特定のセクターが不振でも、他の部分で成長があればそれを享受できます。したがって、「米国経済全体の成長」を取り込むという点においては、現存するETFの中でも最も有効な手段の一つと言えます。ただし、世界経済の成長ではないため、米国外の成長は直接は取り込めない点にご留意ください。
- QVTIとJEPQをNISAの成長投資枠で買うのはどうですか?
- A
どちらもNISAの成長投資枠で買うのは非常に有効な選択肢です。
- VTI: 長期的な資産形成を目指す「コア」な資産として、非課税メリットを最大限に享受できます。複利効果による大きな値上がり益を非課税にできる点は計り知れないメリットです。
- JEPQ: 高い分配金収入を非課税で受け取れるため、キャッシュフロー目的での利用価値が高いです。特に日本の投資家にとって、米国の配当に対する源泉徴収税(10%)が免除されるため、手取りが増えるメリットは大きいです。
ご自身の投資目的によって、どちらをメインにするかを決めると良いでしょう。
- QJEPQはなぜ毎月分配なのですか?
- A
JEPQは、投資家に対して「安定したインカムゲイン」を提供することを主な目的としています。毎月分配にすることで、投資家はより頻繁にキャッシュフローを得ることができ、生活費や再投資の計画が立てやすくなります。特に退職後の生活費をETFの分配金で賄いたいと考える投資家層にとって、毎月安定した収入源となることは非常に重要な要素です。この「毎月分配」は、ETFの設計・戦略の一つであり、高配当ETFの多くが採用している方式です。
- Q投資初心者にはどちらがおすすめですか?
- A
投資初心者の方で、長期的な資産形成を第一の目的にするのであれば、VTIを強くお勧めします。
VTIは、信託報酬が極めて低く、米国市場全体に分散投資されているため、個別の銘柄選びや市場の大きな変動に神経質になる必要がありません。また、運用期間が長く、実績も豊富で、投資の王道と言える商品です。JEPQのような高配当戦略は、仕組みがやや複雑であり、株価の成長に上限があるという特性も理解しておく必要があるため、まずはVTIで長期・分散・積立の基本を学ぶのが最善でしょう。
まとめ
この2つのETFは、どちらも米国株投資において非常に魅力的ですが、その特性と役割は大きく異なります。
VTIは「資本主義と米国経済の成長に賭ける」ためのETFです。極めて低いコストで市場全体に投資し、複利効果の力を最大限に活用して、長期的な資産の最大化を目指します。まさに「成長のコア」としてポートフォリオの中心に据えるべき存在です。
一方、JEPQは「安定した高収入を得る」ためのETFです。ナスダック100の成長力に期待しつつ、カバードコール戦略で高い分配金を毎月もたらします。株価上昇の恩恵にはキャップがかかるものの、高いインカムで生活費や他の投資の原資を確保したい投資家にとって、これほど強力な「キャッシュフローメーカー」はありません。
どちらか一つに絞る必要はなく、ご自身の「目標とするリターン」と「許容できるリスク」、そして「投資期間」に応じて、両方をバランス良く組み合わせるのが最も賢い戦略と言えるでしょう。長期で大きく育てたいならVTI多め、目先の収入を重視するならJEPQ多めという具合に、ポートフォリオを設計してみてください。

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。