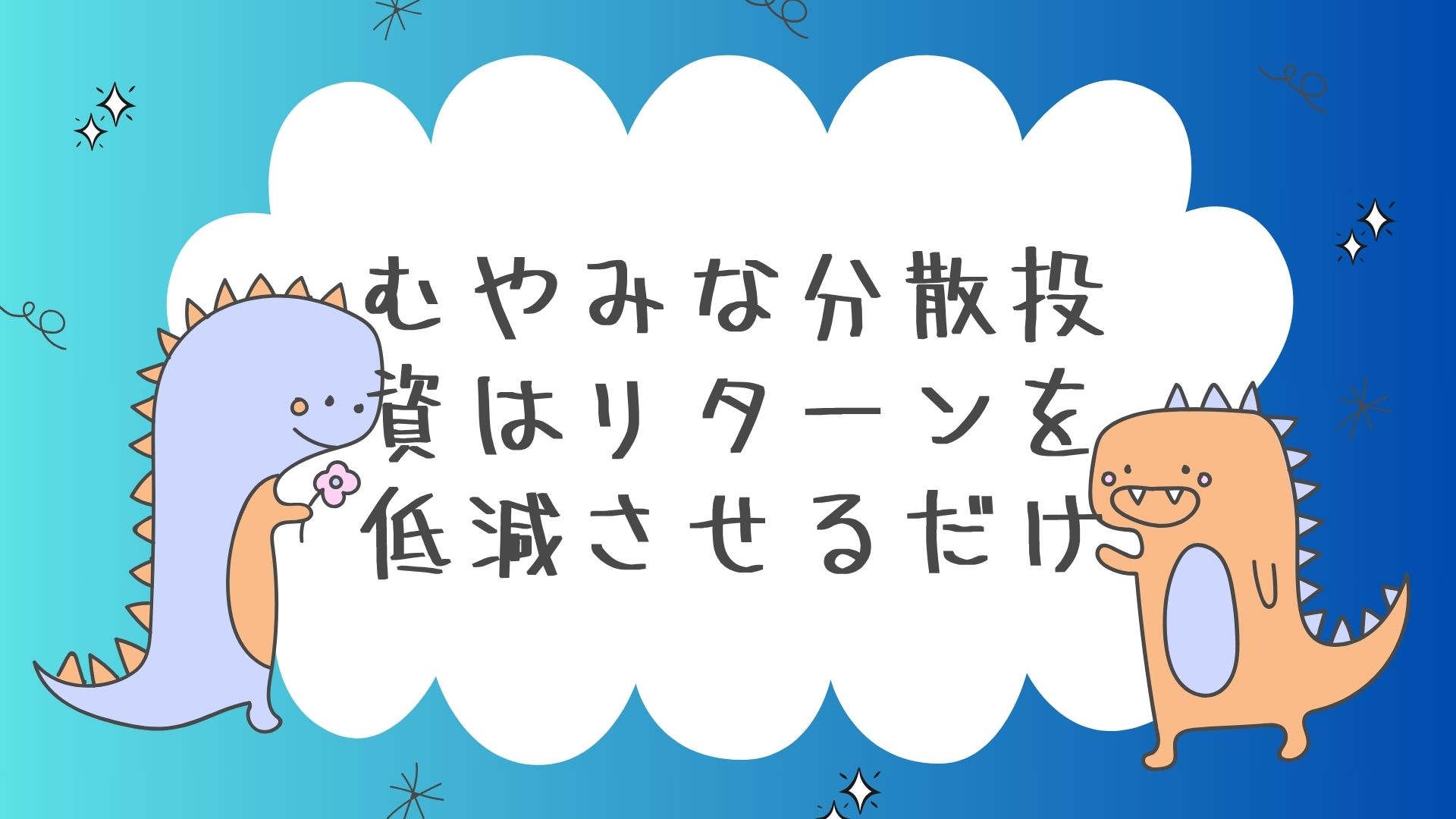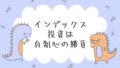分散は10銘柄くらいで十分
「卵は一つのカゴに盛るな」——。投資の世界に足を踏み入れたことがある人なら、一度は耳にしたことがあるであろう、この有名な格言。資産を一つの投資先に集中させるのではなく、複数の投資先に分けてリスクを管理する「分散投資」の重要性を説いた言葉ですね。
しかし、この「分散」という言葉、実は多くの人がその本質を誤解しているかもしれません。「たくさん分ければ分けるほど良い」という、ある種の思考停止に陥ってはいないでしょうか?
「リスクを減らすためには、30銘柄、いや50銘柄は必要だ!」
「インデックスファンドみたいに、数百銘柄に分散するのが最強!」
そんな声が聞こえてきそうですが、もし私が「いや、実は10銘柄もあれば、分散の効果はほとんど得られるんですよ」と言ったら、あなたはどう思いますか?「そんなバカな話があるか!」と怒られてしまうかもしれませんね。
しかし、これは決してテキトーなことを言っているわけではありません。金融の世界には、この「10銘柄分散」の有効性を裏付ける、数々の理論やデータが存在するのです。
なぜ多くの銘柄は必要ないのか?
「分散すればするほどリスクが減る」——。これは、半分ホントで、半分ウソです。この謎を解き明かす鍵は、「リスク」という言葉を2つの種類に分解することにあります。
リスクには2種類ある!「消せるリスク」と「消せないリスク」
投資におけるリスクは、大きく分けて以下の2つに分類できます。
| リスクの種類 | 内容 |
| 個別リスク(非システマティック・リスク) | 特定の企業や業界に固有のリスク。例えば、企業の不祥事、新製品の失敗、経営陣の交代など。 |
| 市場リスク(システマティック・リスク) | 市場全体に関わるリスク。例えば、景気の悪化、金利の変動、政治的な混乱、大規模な自然災害など。 |
重要なのは、分散投資で消せるのは「個別リスク」だけだという点です。どんなに多くの銘柄に分散しても、「市場リスク」から逃れることはできません。例えば、世界的な金融危機が起きて市場全体が暴落した場合、いくら分散していても資産の減少は避けられませんよね。これが市場リスクの恐ろしさです。
では、分散投資の目的である「個別リスク」は、一体何銘柄くらいに分散すれば、十分に低減できるのでしょうか?
驚くべき事実!たった10銘柄でリスクの90%は消える
具体的には、ある研究では以下のようなデータが示されています。
| 銘柄数 | ポートフォリオのリスク(個別リスクの割合) |
| 1銘柄 | 100% |
| 2銘柄 | 46% |
| 4銘柄 | 23% |
| 8銘柄 | 13% |
| 10銘柄 | 約11% |
| 16銘柄 | 8% |
| 32銘柄 | 5% |
| 500銘柄 | ほぼ0% |
(出典:Meir Statman, “How Many Stocks Make a Diversified Portfolio?” Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1987. などを参考に作成)
この表を見ると、銘柄数を1から10に増やすだけで、個別リスクは劇的に(約90%も!)減少していることがわかります。しかし、10銘柄からさらに銘柄数を増やしても、リスクの低減効果は非常に緩やかになります。20銘柄、30銘柄、あるいは100銘柄に増やしたところで、得られる追加的なリスク低減効果は、ほんのわずかなのです。
つまり、「分散はたくさんすればするほど良い」というのは幻想であり、効率的にリスクを管理するという観点では、10銘柄程度で十分と言えるのです。これを「十分な分散」と呼びます。
なぜウォーレン・バフェットは銘柄を絞るのか?
「10銘柄で十分なのはわかった。でも、それって本当に儲かるの?」
そう思われた方も多いでしょう。リスクを抑えることばかりに気を取られて、リターンがおろそかになっては本末転倒です。しかし、ご安心ください。実は、銘柄数をあえて絞ること(集中投資)こそが、市場平均を上回るリターン、いわゆる「アルファ(α)」を生み出すための鍵となるのです。
「無知」を守るための分散投資
世界で最も成功した投資家、ウォーレン・バフェット氏は、分散投資についてこう語っています。
“Diversification is a protection against ignorance. It makes very little sense for those who know what they’re doing.”
(分散とは、無知に対する防御策だ。自分が何をやっているか分かっている者にとっては、ほとんど意味がない。)
これは非常に示唆に富んだ言葉です。バフェット氏は、分散投資そのものを否定しているわけではありません。彼は、自分の投資判断に自信が持てない、つまり「無知」な投資家にとって、分散は有効な手段だと認めています。インデックスファンドのように、市場全体に広く分散投資をすることは、少なくとも市場で大負けすることを防いでくれますからね。
しかし、もしあなたが市場平均を上回るリターンを目指すのであれば、話は別です。市場と同じようなポートフォリオを組んでいては、得られるリターンも市場平均と同じになるのは当然のこと。そこから抜け出すためには、市場とは異なる、自分自身が選び抜いた少数の優良銘柄に、ある程度資金を集中させる必要があるのです。
バフェットのポートフォリオは驚くほど「集中」している
実際に、バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオを見てみると、その集中度合いに驚かされます。2024年時点のデータを見ると、彼らのポートフォリオの上位10銘柄だけで、全体の約90%を占めているのです。
| 順位 | 銘柄名 | ポートフォリオに占める割合(概算) |
| 1 | Apple (AAPL) | 約43% |
| 2 | Bank of America (BAC) | 約10% |
| 3 | American Express (AXP) | 約9% |
| 4 | Coca-Cola (KO) | 約7% |
| 5 | Chevron (CVX) | 約6% |
| 6 | Occidental Petroleum (OXY) | 約4% |
| 7 | Kraft Heinz (KHC) | 約3% |
| 8 | Moody’s (MCO) | 約2% |
| 9 | HP (HPQ) | 約1% |
| 10 | Citigroup (C) | 約1% |
| 上位10銘柄合計 | 約86% |
(※2024年第1四半期のForm 13Fを参考に作成。割合は変動します)
これを見てどう思いますか?「分散が大事」と教えられてきた私たちにとって、1銘柄(アップル)だけでポートフォリオの40%以上を占めるというのは、にわかには信じがたいかもしれません。しかし、これこそが、バフェット氏が長年にわたり市場平均を大きく上回り続けてきた秘密なのです。
彼は、自分が徹底的に分析し、「これだ!」と確信した数少ない企業に、大きな資金を投じる。そうすることで、その企業の成長の恩恵を最大限に享受し、莫大なリターンを生み出してきたのです。
もちろん、これは誰にでも真似できることではありません。一つの銘柄に大きく賭けるには、その企業の本質的な価値を深く理解し、長期的な成長を信じ抜くための、圧倒的な知識と分析力、そして精神的な強さが不可欠です。
しかし、ここから私たちが学ぶべき重要な教訓は、「やみくもな分散は、リターンを希薄化させるだけ」という事実です。100銘柄、200銘柄と分散すれば、確かに個別企業が倒産するリスクはほぼゼロに近づくでしょう。しかし、その中には、素晴らしい成長を遂げる「未来のスター銘柄」もあれば、鳴かず飛ばずの「平凡な銘柄」も含まれています。
結果として、ポートフォリオ全体のリターンは、良くも悪くも「平均」に収斂していきます。それは「安心」かもしれませんが、大きな資産を築くための「破壊力」には欠けるのです。
究極の集中投資「FANG+」
「10銘柄への集中投資が、大きなリターンを生む可能性があることはわかった。まさにその思想を体現したような、エキサイティングな投資対象があるのを知っていますか?」
その名も「FANG+(ファングプラス)」。
FANG+は、「10銘柄集中の哲学」を、いわば究極の形で商品化したような指数です。これは、単なる投資信託の名前ではありません。現代社会を動かす、超巨大テクノロジー企業10銘柄だけに資金を投じる、超攻撃的な投資戦略の象徴なのです。
FANG+とは何か
FANG+は、ニューヨーク証券取引所(NYSE)が算出・公表している株価指数で、以下の特徴を持っています。
- 構成銘柄はたったの10社:次世代テクノロジーを基盤に、現代社会に絶大な影響力を持つ、米国上場のテクノロジー企業や、その関連企業で構成されます。
- 均等加重(Equal Weight):これが非常に面白い点ですが、選ばれた10銘柄に、原則として10%ずつ均等に投資します。バフェットのポートフォリオのように特定の銘柄に比重が偏るのではなく、選ばれし10社に平等に期待をかけるスタイルです。
- 定期的な銘柄入れ替え:時代の変化に合わせて、四半期ごとに構成銘柄の見直しが行われます。これにより、常にその時代をリードする「旬」な企業群に投資し続けることを目指します。
驚異のパフォーマンスと、その裏に潜むリスク
では、この超集中投資戦略は、過去にどれほどのリターンを生み出してきたのでしょうか。S&P500(米国を代表する500社)やNASDAQ100(米国のハイテク企業を中心とした100社)といった、より分散された指数と比較してみましょう。
過去のデータを見れば一目瞭然ですが、FANG+のリターンは、S&P500やNASDAQ100を圧倒してきました。これは、構成銘柄である巨大テック企業が、この10年で驚異的な成長を遂げたことの証左です。まさに、集中投資の「破壊力」が遺憾なく発揮された結果と言えるでしょう。
しかし、忘れてはならないのが、これは「両刃の剣」であるということです。
高いリターンは、高いリスクと表裏一体。FANG+には、その輝かしいパフォーマンスの裏に、無視できないリスクが潜んでいます。
| FANG+の魅力(メリット) | FANG+の危険性(デメリット) |
| 圧倒的な成長性:世界を変えるイノベーション企業の成長の恩恵を直接受けられる可能性がある。 | 極端なボラティリティ(価格変動):上昇も大きいが、下落も激しい。市場の調整局面ではS&P500などを大きく下回る暴落を経験する可能性がある。 |
| シンプルで分かりやすい:「最強の10社」に投資するという、明確で力強いコンセプト。 | セクターの偏り:テクノロジーセクターに極端に集中しているため、同セクターへの逆風(例:規制強化、金利上昇)の影響をまともに受ける。 |
| 時代の変化に対応:定期的な銘柄入れ替えにより、常に最先端の企業群への投資を維持しようとする。 | 高い信託報酬:一般的なインデックスファンドに比べ、手数料が高めに設定されていることが多い。長期ではこのコストがリターンを圧迫する。 |
FANG+への投資は、ジェットコースターの最前列に座るようなものです。息をのむような急上昇のスリルを味わえるかもしれませんが、同時に、恐ろしいほどの急降下も覚悟しなければなりません。この「剣」を上手く使いこなせるのは、その激しい値動きに耐えられる精神力と、ポートフォリオ全体でリスクを管理できる、経験豊富な投資家に限られるかもしれません。
「10銘柄ポートフォリオ」をどうやって選ぶのか?
「10銘柄で十分なこと、集中投資の破壊力、そしてその究極形であるFANG+の存在もわかった。じゃあ、自分自身でマイ FANG+を作るにはどうすればいいんだ?」
おそらく、今あなたの頭の中は、この疑問でいっぱいでしょう。ここが最も難しく、そして最も面白い部分です。闇雲に10銘柄を選んでも、それはただのギャンブルになってしまいます。成功の確率を高めるためには、明確な戦略と規律に基づいた銘柄選定が不可欠です。
鉄則1:相関性の低いセクターに分散させる
「10銘柄に絞る」と言っても、例えばFANG+のようにハイテク株ばかり10銘柄集めてしまっては、分散の意味がありません(もちろん、それを理解した上でハイリスク・ハイリターンを狙う戦略はアリですが)。
より安定したポートフォリオを目指すなら、異なるビジネスモデルを持ち、異なる経済環境で強みを発揮する、相関性の低い複数のセクターにまたがって銘柄を選ぶことが重要です。
例えば、以下のようにセクターを分散させることを考えてみましょう。
| セクター分類例 | 具体的な業種のイメージ |
| 生活必需品セクター | 食品、飲料、家庭用品など。景気に左右されにくいディフェンシブな性格。 |
| ヘルスケアセクター | 製薬、医療機器、バイオテクノロジーなど。高齢化社会で安定的な需要が見込める。 |
| 情報技術(IT)セクター | ソフトウェア、半導体、クラウドなど。高い成長性が期待できるが、景気変動の影響も受けやすい。 |
| 金融セクター | 銀行、保険、証券など。金利の動向に業績が左右されやすい。 |
| 資本財・サービスセクター | 航空宇宙、防衛、建設機械など。景気拡大期に強い。 |
| エネルギーセクター | 石油、天然ガスなど。資源価格の変動が直接的に業績に影響する。 |
このように、値動きの傾向が異なるセクターを組み合わせることで、あるセクターが不調な時でも、他のセクターが好調であれば、ポートフォリオ全体の値動きを安定させることができます。これは、いわばポートフォリオ内での「守備」と「攻撃」のバランスを取る作業です。
鉄則2:「ビジネスの濠」を持つ企業を選ぶ
10銘柄という少数精鋭で戦う以上、一社一社のクオリティが極めて重要になります。私が銘柄選定で最も重視するのは、その企業が「経済的な濠(Economic Moat)」を持っているかどうかです。
「濠」とは、城が敵の攻撃から身を守るために周囲に巡らせた堀のこと。ビジネスにおける「濠」とは、競合他社が簡単に真似できない、持続的な競争優位性のことを指します。
バフェット氏が好んで使うこの概念には、いくつかの種類があります。
| 経済的な濠の種類 | 内容と具体例 |
| 無形資産 | ブランド、特許、許認可など。コカ・コーラの強力なブランドや、製薬会社の特許がこれにあたる。 |
| スイッチング・コスト | 顧客が他社製品に乗り換える際に発生する手間やコスト。マイクロソフトのWindows OSや、銀行のメインバンクなどが典型例。 |
| ネットワーク効果 | 利用者が増えれば増えるほど、その製品やサービスの価値が高まる効果。VISAやMastercardなどの決済ネットワーク、FacebookなどのSNSが該当する。 |
| コスト優位性 | 他社よりも低いコストで製品やサービスを提供できる能力。ウォルマートの巨大な規模を活かした調達力や、サウスウエスト航空の効率的なオペレーションなど。 |
なぜ「濠」が重要なのでしょうか? それは、「濠」を持つ企業は、長期にわたって高い収益性を維持し、安定したキャッシュフローを生み出すことができるからです。このような企業は、景気の荒波にもまれながらも、簡単には沈まない強靭な体質を持っています。
10銘柄しか持たないのですから、一つ一つの企業が、嵐の中でも頼りになる「不沈艦」であってほしいですよね。そのためにも、この「濠」の存在を徹底的に見極めることが、集中投資を成功させるための生命線となるのです。
鉄則3:徹底的に「理解できる」ビジネスに投資する
最後の鉄則は、非常にシンプルですが、多くの人が見落としがちなことです。それは、「自分がそのビジネスモデルを、心の底から理解できる企業にのみ投資する」ということです。
バフェット氏は、ハイテクバブルの最盛期に、周囲から「時代遅れだ」と批判されながらも、自分が理解できないという理由でIT関連株への投資を頑なに見送りました。結果として、その後のバブル崩壊を尻目に、彼の資産は守られました。
なぜ「理解」がそれほどまでに重要なのでしょうか?
理由は2つあります。
- 暴落時の精神的な支えになるから:どんな優良企業でも、株価は市場全体のパニックに巻き込まれて暴落することがあります。その時、あなたがその企業のビジネスの本質的な強さを理解していれば、「これは絶好の買い増しチャンスだ」と冷静に判断し、行動することができます。しかし、理解が曖昧なまま投資していると、不安に駆られて狼狽売りしてしまうのが関の山です。
- 長期的な成長ストーリーを描けるから:企業の価値は、将来にわたって生み出すキャッシュフローの総和です。その企業の製品やサービスが、5年後、10年後も社会に必要とされ、競争力を維持できているかを自分なりにストーリーとして描けなければ、長期的な視点で投資を続けることはできません。
「友達に勧められたから」「アナリストの評価が高いから」といった理由だけで、大切な資金を投じるのは絶対にやめましょう。あなたが、その企業のビジネスモデルを、小学生にでも説明できるくらい、シンプルに、そして情熱を持って語れるか。それが、投資すべきか否かの一つの試金石になります。
まとめ
- 分散投資の目的は「個別リスク」を消すこと:分散で消せるリスクには限界があり、市場全体のリスクからは逃れられない。
- リスク低減効果は10銘柄でほぼ十分:学術的なデータが示すように、銘柄数を10以上に増やしても、リスクの低減効果はわずかしか得られない。
- 過度な分散はリターンを平凡にする:市場平均を上回るリターンを目指すなら、やみくもな分散はむしろ足かせになる。
- 成功者は「集中投資」を実践している:ウォーレン・バフェットのように、選び抜いた少数の優良銘柄に資金を集中させることが、大きな富を築く鍵となる。
- FANG+は「超」集中投資の実例:時代の寵児10銘柄に集中する戦略は、圧倒的なリターンと同時に、極めて高いリスクを伴う「両刃の剣」である。
- 「賢い10銘柄」の選び方:成功のためには、「セクターの分散」「経済的な濠」「ビジネスの理解」という3つの鉄則を守ることが不可欠。
もちろん、この記事を読んだからといって、明日からすぐにあなたの資産が倍になるわけではありません。集中投資は、大きなリターンをもたらす可能性がある一方で、銘柄選定を間違えれば、大きな損失につながるリスクもはらんでいます。
しかし、大切なのは、「常識」を疑い、自分自身の頭で考え、学ぶことをやめない姿勢です。
「たくさんの銘柄に分散しておけば、とりあえず安心だ」
そんな思考停止から一歩踏み出し、一社一社のビジネスと真剣に向き合い、自分だけの「ドリームチーム」を作り上げていく。そのプロセスは、時に困難で、時に苦しいかもしれません。しかし、その先には、単なる資産の増加だけではない、知的な興奮と、自分自身の成長という、何物にも代えがたい喜びが待っているはずです。

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。